※現代・転生パロディです。
※捏造を含みます。
※鶴丸国永短編「神様の涙を君は見たことがあるか」、鶯丸短編「あなたの紡ぐ文字が何よりも刃」と同じ世界設定です。
※上記の短編の鶴丸、鶯丸がいた本丸と今回の燭台切光忠がいた本丸は同一本丸ですが、主は別人です。
※上記の短編を未読でも大丈夫ですが、一応シリーズ作品になっています。
※成人男性と女子高生が不純行為をしている描写や不道徳的な描写がありますが、これを推奨する意図はありません。
※主人公の年齢設定があります。
チェーン展開しているカフェの副店長になってかれこれ数年。気付けば二十八歳になっていたけれど、今のところ結婚とかそういう話はない。恋人もいない。むしろ恋人がいたことすらない。それをすでに結婚した元同級生たちが笑っているのはなんとなく知っている。子どもがいる子もいるし、国際結婚をして海外へ移住した子もいた。SNSで幸せそうな顔で笑っている写真をたくさん見た。みんな、充実した人生を送っているんだなあ。何をもって充実とするのかは人それぞれだけれど、私の瞳には元同級生たちは充実しているように映ってしまうのだ。それと同時に思う。ああ、私はなんて平凡すぎて不幸に思える人生を送っているのだろう、と。
楽しみといえば最近通い始めたスポーツジムくらいなものだ。あまり運動をしないせいで体力が落ちてきたので通い始めたのだけど、これが結構面白い。筋トレなんかまったく興味もなかったし、そもそも体を動かすことがあまり好きではなかったのだけど、通い始めたらいろんなマシンを試したくなるのだ。ジムの設備担当の人が新しいマシンを見つけるとすぐに設置してくれているそうだ。はじめは見たことのないマシンにおどおどしていたけれど、優しいインストラクターのお姉さんに教えてもらっていろんなものを使えるようになった。毎日通う元気はないので毎週水曜日に行く、と決めてからは水曜日が楽しみになっている。汗を流してシャワーを浴びて帰る。それだけなのに私のとってはとんでもなく充実しているように思えてならない。まあ、子どものころからの人見知りが治っていなくて、ジムで友達なんかは作れていないのだけど。でもここはそういう場所じゃないからいいのだ。運動不足を解消するための場所。体力をつけるための場所。そう自分に言い聞かせて他の人が目に入らないようにしつつマシンに向かい続けている。
お気に入り、というかいろいろ使ってみて一番いいと感じてずっと使っているのがトレッドミルだ。ジムにあるマシンの中だと古典的で単純なマシンなのだけど、結局走り込みが一番いい有酸素運動だと思っている。はじめはすぐにバテていたけどだいぶ長時間持続して走れるようになってきた。短時間とはいえ運動をちゃんとしはじめたからなのか、寝付きも良くなったしすっきり起きられるようになった。平凡すぎる人生に少しの光。ああ、なんてささやかな喜びなのだろうか。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「この度はご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした」
ささやかな喜びはその瞬間を潤してくれても、私の人生すべてを潤してくれるわけじゃあない。店のドアが閉まるまで頭を下げ続ける。私の隣で半泣きになっているアルバイトの女子高生が鼻をすする音が耳障りで仕方ない。ドアが乱暴に閉まった音が店内に響き渡る。ゆっくりと頭を上げると同時にアルバイトの女子高生も頭を上げた。半泣きのまま私の顔を見て「さん、すみません、謝ってもらっちゃって」と言う。それに若干顔を引きつらせて「前にも同じことがあったよね。気を付けてね」と声をかけて業務に戻った。
彼女は前にも同じミスをしてお客様を怒らせていたのだ。内容もひどいもので、お客様が注文したものと全く違う商品をテーブルに運び、お客様から指摘を受けると「でももう作ってしまったので……」などと言い放ったのだ。一人目のお客様は本社へクレームを入れてきたそうなのだが、今回はその場でお客様が激昂。彼女を怒鳴りつけて「責任者を呼びなさいよ!」とものすごい剣幕で彼女に詰め寄った。店長が会議で休みだったため、必然的に副店長である私が出て行くこととなる。ひとしきり彼女への教育がどうなっているのか、もう二度と来ない、ご近所さんに言いふらす、などと怒鳴りつけられ誠心誠意謝罪をして今に至る。どう考えてもこちらの不手際だった。
彼女は前回本社からクレーム内容を伝えられた際に店長からしこたま説教されていたはず。同じミスをしてどうする。内心そう思いつつ本社から届いた書類をまとめる業務を再開するため、フロアを任せてスタッフルームへ引っ込む。スタッフルームのドアを閉めた数秒後、ドアの向こう側から笑い声が聞こえてきた。先ほどまで半泣きになっていた女子高生、そして彼女と仲がいい男子大学生のアルバイトの声だ。「やばくない? あの客めっちゃ怒ってたよね?」と笑いながら言うその声にイラッとした。続けて男子大学生が「いいじゃん、副店長が謝ったんだし。大丈夫っしょ」と同じく笑いながら言うその声にもイラッとした。この二人は最近付き合い始めたらしい。先ほどのクレームの話はすぐに切り上げて、次のデートはどこに行こうとかそんな呑気な話をはじめた。
大きく一つため息を吐くと、その二人に「そこ、邪魔なんだけど」と言い放つ声。きりっと胃が痛むのを感じる。すぐにスタッフルームのドアがノックされたので「どうぞ」と返事をすると、社員としてシフトに入っている主婦が入ってきた。
「副店長、どうして彼女をもっとちゃんと怒らないんですか! 前にも同じことがありましたよね?!」
あの子はクレームが多い、それなのに店長も副店長もちゃんと怒らない、業務中におしゃべりが多くて困る、辞めさせてほしい。彼女が言うことは至極当然のことだしすべて正しい。けれど、彼女はほぼ毎日そんなふうに私を責め立ててくる。本人に言えばいいのに、私にじゃなく。店長にも一切何も言わないのはどうしてなのだろう。彼女は二年前に結婚して一年前に子どもを産んだばかりの主婦でシフトにはあまり入れない。子どもの面倒を見るために休みが多いし、急にシフト通りに出勤できなくなることも多い。それは仕方のないことだし、仕事より家族を大切にするのは当たり前のことだ。それでも社員として彼女が雇われているのは、店長が彼女のことを気に入っているからなのだ。彼女は結婚する前からこの店でアルバイトとして働いており、当時から店長とはひどく仲が良かった。店長による本社への猛プッシュにより彼女は社員として採用され、シフトを組んでいるのが店長なのだから割と思い通りに出勤できるというわけだ。そのため店長にはいい顔だけを見せているのだ。不満はすべて副店長である私に向けてくる。
「副店長は独身だから怒り方が分からないのかもしれないですけど、ちゃんと怒ってくれないと困ります!」
これが彼女の口癖のようなものだ。”あなたは独身だから”。それを言われるたびに内心苦笑いをこぼしてしまう。それと同時にこう思う。私が休みの日、彼女がその日の責任者として出勤しているにも関わらず、クレーム処理もろくにしなければお客様への謝罪も一言もしない。そればかりか次の日出勤してきた私にすべて押し付けて逃げてしまうくせに。そんなあなたには何を言われてもね、と。性格が悪いと思う。けれど、こんなに毎日責められているとどうしても黒い部分が出てしまう。
「それになんでクレームがあったあとなのにスタッフルームにいるんですか?! フロアにいてくれないと困るんですけど?!」
それは社員である店長もあなたも誰も書類を一切読まないし整理しないからですけど。新メニューのこと、セールの内容、新しいシステムの導入、本社への報告の変更点。そういうことをすべて確認して、伝えて、まとめているのは誰ですか。私なんですけど。忙しい時間帯はフロアにいるし、忙しそうなときにもフロアに出て行っていますけど。そもそもフロアには社員であるあなたがいるから最悪何かあったとしてもまずあなたが対応すればいいんじゃないですか。そう思いつつ声には出さない。代わりに「では書類のまとめ作業をお願いできますか」と無表情で聞く。すると彼女はイライラした声色で「そんなのやったことないからできません!」と言い放ってスタッフルームから出て行った。笑ってしまう。なんで自信満々にそんなことを言えるのだろう。ため息がこぼれる。私が悪いのか、何もかも。ため息がこぼれてこぼれて、こぼれ切ったら乾いた笑いがもれた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
閉店時間を一時間すぎたころ。本社へのクレーム報告のメールを送信し終わり、着替えてからスタッフルームを出る。戸締りがしっかりされているか確認していると、バックヤードから物音が聞こえた。まさか泥棒?! 一瞬動きが止まってしまったけどなんとか自分を落ち着かせる。何かあればすぐに警察を呼ばなくては。売上金は金庫に入れてあるし、他に盗られるようなものはない。金庫は私の背後にあるスタッフルームの奥。バックヤードからはどう行こうとしても私と鉢合わせることになる。まずは本当に人がいるか確認しなければ。
物音を立てないようにそうっとバックヤードのドアに近寄る。ごそごそとやはり人がいるらしい物音が聞こえてきた。ゾッとしながらもドアの真ん前に立つと、物音と一緒に声が聞こえてきた。嬌声。女の子の喘ぎ声だった。あまりに驚いて完全にフリーズしてしまう。この声、あの女子高生のアルバイトに違いない。甘ったるい声で聞いていて吐き気がするようなことを喘ぎながら言っている。「気持ちいい、もっとして」と。バックヤードの奥のほうにいるらしい。声はそこそこ離れたところから聞こえてくる。女子高生の喘ぎ声に体が固まったままでいると、またしても聞き覚えのある声が聞こえてくる。「そんなに大きい声出すと、さんに聞こえちゃうよ」。店長の声だった。今日は会議でシフトに入っていない。わざわざこんなことのために店にいつの間にか来ていたようだ。
店長は既婚だ。四十代で正直少しくたびれた感じの、おじさんと言われて頷けるような人だ。そんな人が、十代の、未成年の、女子高生と、職場で、淫らな行為を、している。しかも私がまだいると知っているのに。店長、奥さんのことを世界で一番愛しているなんてのろけていたよね? 女子高生はアルバイトの男子大学生と付き合い始めたんじゃなかったの? 吐き気がする。気持ち悪い。店長も、女子高生も、気持ち悪い。「好きだよ」、気持ち悪い、「あたしも」、気持ち悪い! 恋愛って気持ち悪いものなんだ。いや、この人たちが気持ち悪いだけ?
気持ち悪すぎて一歩も動けずにいると、気持ち悪い大きな喘ぎ声が聞こえてからごそごそと物音がした。事が終わったらしい。まずい、このままじゃ鉢合わせる。吐きそうになりながらゆっくりスタッフルームに戻る。そうっとドアを閉めたと同時にバックヤードのドアが開いた音がした。足音がこちらに近付いてくる。けど、足音は一つしか聞こえてこない。どうやら一人は裏口から出て行ったようだ。たまに裏口のドアの戸締りができていないのはこのせいだったのか。そのせいで何度私があの社員の主婦に嫌味を言われていたと思うの? イライラする。でも、それよりも気持ち悪さが強い。
こんこん、とドアがノックされた。びくっと肩が震える。「はい」となんとか絞り出した声で返事をすると、「さん、僕だよ」と言いながら店長が入ってきた。気持ち悪い。何食わぬ顔、というのはこういうことなのだろう。店長はにこにこと笑って「こんなに遅くまで」と呆れたように言った。クレームの件はすでに本社に伝わっていたそうで、事実確認のため店に来たのだという。「さんなら残ってるだろうと思ってね」と言いながら私の隣の席に座った。
無理やりにこやかにクレームの報告、報告メールの確認をしてもらう。店長はにこにこ笑ったまま「いつもごめんね」と言ってネクタイを少し緩めた。そこから本社であった会議の話になり、店長の話を黙って聞く。大事な内容はメモをしながら相槌を打っていると、途中で話が脱線していくのが分かる。おしゃべりが好きな人なのだ。真面目な話をしていても脱線してどうでもいい話にいつの間にかすりかわっている。今日もそのパターンだ。そう思って我慢して聞いていると、店長が突然「ねえ、さんさ」と少し小声で言う。
「いま、彼氏いないんでしょ?」
「え……いないですけど……」
「いたことあるの?」
「……ないですけど」
「うっそ、じゃあ処女なんだ?」
「……それ、セクハラですよ」
苦笑いをこぼしておく。店長はへらへら笑いながら「ごめんごめん! そんなつもりじゃなかったんだけど!」と言う。苦笑いをこぼし続けていると店長はへらへら笑ったまま「どんな男がタイプ?」などと恋愛に関する質問を振ってくる。帰りたい。気持ち悪い。いろいろ言いたいことはあったけれど、相手は店長、つまりは上司だ。何も言えないままやんわりかわしつつ店長が飽きるのを待つ。いつもならこうやって曖昧に答えているうちに飽きてくるのに、なぜだか今日は粘る。何度も何度も似たような質問をしてくる。気持ち悪い。用事があるからと帰ってしまおうか。でも店長のことだから何の用事か聞いてくる。それは困る。嘘をつくのは得意じゃないから。
「さんってさあ、きれいな肌してるよねえ」
「……そんなことないですよ」
「そんなことあるよ〜だってほら、すべすべだもん」
ぞわっとした。左手を触られた。たぶん、あの女子高生を触ったその手で。「やめてください」と手を引っ込めると、店長はにやにやと嫌らしい顔で笑う。「え、なに、照れたの? 男に触られて照れた?」と言いながら顔をぐいぐい近付けてくる。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い。
「さん、僕と付き合わない? 正直すっごくタイプなんだよね」
「店長には奥さんがいらっしゃるじゃないですか、馬鹿なこと言わないでください」
「じゃあさ、一回だけ。一回だけやらせてよ」
「ふざけないでください!」
立ち上がる。机に置いていた鞄を掴んでそのままドアへ向かおうとすると、腕を掴まれた。ぐいっと引っ張られてロッカーに体をぶつけられる。肩をそのままつかまれ、体を固定されてしまう。大人の男性の力だ。敵うわけがない。店長はにやにやと嫌らしい顔で笑ったまま「かわいい〜、緊張してる?」と顔を覗き込んできた。気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い!
「いいじゃん一回くらい。若いうちに遊んどいたほうがいいよ? それに処女、捨てたいでしょ?」
「結構です! 警察に通報します!」
「さんさあ、人間としても女としても、つまんないから彼氏できたことないんでしょ?」
つらつらと言われる。顔は平凡、体型も平凡。職場では業務以外の話はほぼしないし、食事会にも不参加なことが多い。着てくる洋服もいつも似たような感じ、化粧もいつも同じ。お客様に何か褒められても定型文しか返さず、また怒られても定型文しか返さない。世間話を振られても特別リアクションがあるわけでもなく、こちらから話しかけることもない。大きく喜んだり、大きく悲しんだり、大きく怒ったりもしない。顔がかわいくて胸が大きいあの女子高生の子のほうが、よっぽど女の魅力がある。いつも服装や化粧にこだわり、何かしてもらうと大きなリアクションをしてくれるあの主婦のほうが、よっぽど女の魅力がある。でも、私にはどれもない。
「そういう子って、男としてはつまんないんだよね」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
いつの間にか振り出していたらしい雨の中、走って逃げた。店長の足を思い切り踏みつけて、店の鍵を投げつけて、ドアを勢いよく閉めて逃げた。気持ち悪い、あいつに触られた場所が、何かが這っているような感覚がして気持ち悪い! 途中、ドブに向かって吐いた。それでもまだ気持ち悪い。触られた。女子高生の子と、淫らなことをした手で、触られた。それがあまりにも気持ち悪くて。言っていることも理解できなくて気持ち悪くて。気持ち悪くて、気持ち悪くて、たまらない。
通っているジムが見えてきてようやく少しだけ心が落ち着いた。自分の知っているものが視界に入ったおかげだろうか。それでも心臓がばくばくとうるさい。電柱に手をついて呼吸をする。こんなにびしょ濡れでは電車にも乗れないしタクシーにも乗れない。一人暮らしだから頼れる家族もいない。友達の家も一番近い子でもここから電車で五駅はある。ため息が止まらない。どうしたものか。
夏が通り過ぎた季節、雨を頭から被ったままでい続けたせいで少し肌寒くなってきた。迷惑を承知で電車に乗って帰るしかないか。そう思いつつぐっと込み上げてきたものを飲み込んだ瞬間だった。
「君、大丈夫? そんなびしょ濡れで……」
そこで言葉が止まった。低い男の人の声だ。そうっと視線を持ち上げると、ジムの出入り口の屋根の下に背の高いスーツの男性がいるのが見えた。口を開けたまま固まっている。何かに驚いているようだけれど、何に驚いているのかは皆目見当もつかない。私に話しかけたのかすら分からない。けれど、雨の音で聞こえづらいからなのかかなり大きな声だったし、辺りには私しかいない。たぶん私に話しかけたのだろうとは思う。固まったままのその人に、へらりと苦笑いを向けた。
「あの、お気になさらないでください。傘を忘れてしまっただけなので」
「…………とりあえず屋根の下においで。風邪を引いてしまうから」
優しい声だと思った。子どもをなだめるような、そんな何一つ含みのない優しい声。表情も穏やかで悪意などどこにも感じられない。そうだとしても、あんなことがあった直後だ。恐怖心がまだ少し残っていて、男性の隣に行くことは避けたかった。それにジムの前にいるその男性は、あの男なんかよりもずいぶん背が高く体格もしっかりしている。今度こそ何かあったら逃げられない。ぐっと唇を噛んでから「いえ、もう帰りますので」と小さく頭を下げる。そのまま小走りでジムを通り過ぎようとした、のだけど。「待って!」とその人の声が響き、それに驚いてしまって足が滑る。そのまま転んでしまってから左足首に激痛が走った。
「痛っ……」
「ごめん、僕が急に呼び止めたから!」
慌てた様子でその人は私に駆け寄ってくる。それがひどく、怖くて、唇を噛んでしまう。「足首、捻っちゃったのかな」と言いながら私の足に手を伸ばしてくるその人に、気付いたら大きな声で「触らないで!」と叫んでいた。その人はひどく驚いた顔をして手を止めた。「あ……ごめん」と言った顔は、なぜだか、ひどく傷ついているように見えてしまって、はっと正気に戻った。
「い、いえ、こちらこそすみません……心配してくれたのに」
「ううん、僕が悪いんだ。見知らぬ男が触ろうとしてきたら怖いよね。本当にごめん」
その人は「雨の当たらない場所に移動させたいから、少し足と肩に触れても大丈夫かな?」と不安そうに笑って聞いてきた。抱えようとしてくれているらしい。その人はジャケットを脱ぐと私の肩にかけ、「いいかな?」ともう一度聞いてくれた。痛くて立てそうにない。小さく頷くと、その人は少しだけほっとしたように「ごめん、すぐ離れるから」と言ってから私の肩を掴み、足の下に腕を入れた。そのまま立ち上がってジムの屋根の下へ小走りすると、言った通りすぐに下ろしてくれた。そうして入口に置いたままだったらしい鞄からハンカチを取り出すと、私に渡してくれる。「悪いので」と断ったのだけど「いいから」と言って手を引っ込めようとしない。押し負けて受け取ると、またほっとしたような顔をした。
その人は「ちょっと待ってて」と言い残してジムへ入っていく。鞄もジャケットもハンカチも置いたまま。しばらく待っていると、その人と一緒に見知ったインストラクターのお姉さんが出てきた。私の顔を見るなり「あ!」とお姉さんが声をあげる。「さん! どうしたんですか?!」と私の前にしゃがみ込むと、持ってきてくれたらしいタオルで頭を拭いてくれた。詳しいことは話さず、傘を忘れただけだと話す。お姉さんは少し困ったように笑って「天気予報見なきゃだめですよ〜」とおどけて言う。
「今日車なんで……と言いたいところなんですけど、私今日ラストまでなんですよね……」
「えっ、そんな、いいですいいです! 申し訳なさすぎます!」
「でもほら、さん、足首ぱんぱんに腫れちゃってますよ」
「……本当だ」
どうりで痛いわけだ。左足首は見たことがないくらいぱんぱんに腫れている。これは病院行きのレベルだろう。お姉さんも「たぶん松葉杖付かなきゃだめなレベルだね」と苦笑いを浮かべている。困った。シフトももう出ている分は出ないとまた主婦の人に文句を言われる。……思い出さないようにしていたけど、店長にも、頭を下げなきゃいけない。あんな人に、頭なんか下げたくないのに。幸いにも明日は休みだ。病院で診てもらって、様子を見て大丈夫そうだったら出勤すればいい。そう心を落ち着かせる。
黙り込んだ私の顔をじっと見ていた男性が「良ければなんだけど」と声をかけてくれた。
「僕が原因だし、家まで送っていくよ」
「えっ……いや、そんな、申し訳ないので」
「それは僕の台詞だよ。本当にごめんね。あと、知り合いの病院がすぐ近くなんだ。今なら診てもらえると思うから先に病院に行こう」
お姉さんはにこにこと笑って「長船さんにならお任せできますしね。お願いしてもいいですか?」と勝手に話を進める。おさふねさん、というらしいその人は「嫌かな」と不安そうな表情を見せる。じいっと見つめられて、あ、と気が付いた。少し長い前髪に隠れていた右目。その色が、左目と少しだけ違っていた。妖しく光る紅い月のような色。左目の光を閉じこめたような金色とは違う、美しい色をしていた。
瞳に見惚れていた間に、いつの間にか頷いてしまっていたらしい。「車を回してくるね」と言って視界から美しい色が消えていく。はっとして「あ、」と声をかけてももう遅かった。その背中は駐車場の奥のほうへ消えて行ってしまう。
「イケメンでしょ、長船さん。うちの常連さんなんですけど、さんとは来る曜日が違うから今まで知らなかったんですね」
「……きれいな瞳の色をした方ですね。両目の色が違う人、はじめて見ました」
「……? 長船さんってオッドアイなんですか?」
「えっ? どう見ても両目の色が違うじゃないですか」
「そうでしたっけ?」
お姉さんは首を傾げて「どうだったかなあ」と呟いている。あんなにはっきり色が違うのにどうして印象に残っていないの? 前髪で隠れているからあまり見えないとか? 不思議に思っていると、ジムの中からお姉さんを呼ぶ声が聞こえてくる。仕事を抜け出してタオルを持ってきてくれたようで、焦りつつそれに返事をして「じゃあ私はこれで!」と中へ戻っていった。
一台の黒い大きな車がすぐ近くに停車する。運転席から降りてきたその人はまたほっとした顔をしていた。「ああ、そうだ、忘れてたね」と少し照れたように笑うと「長船光忠です」と手を伸ばしてくる。握手を求められている。少しだけ、抵抗がある。でも、なぜだか、ちゃんとその手を握った自分がいた。
「です」
「さん、ね。ごめんね、車に乗せるからまた、」
「あっ」
「うん?」
「こ、こんなびしょ濡れで乗れません……やっぱり、」
長船さんは私の言葉に少しだけきょとんとしてから、ぷっと吹き出した。ぼそりと呟いた言葉が「相変わらずだなあ」と聞こえた気がしたけど、意味が分からなかったから聞き間違いだったかもしれない。長船さんは「失礼するね」と言ってから先ほどと同じようにまた私を抱え上げた。そのまま車のほうへ歩いていくものだから驚いてしまう。タオルで拭いたとはいえびしょ濡れなことに変わりはない。あまり車に詳しくないからよく分からないけど長船さんの車、高級車っぽいし、さすがに申し訳なさすぎる。そう思って「あの、」と話しかけるのだけど長船さんは「ちょっと頭下げられる?」と言うだけで私の話は聞かないつもりみたいだ。助手席のドアを片手で開けると、少しだけ身を屈めた。もう今の時点で長船さんのスーツを濡らしてしまっているのに、これ以上は本当に申し訳ない。そう思って声をかけるけど長船さんは穏やかにほほえむだけだ。また子どもをなだめるような優しい声で「頭、下げられる?」と聞かれる。そんなふうに聞かれると従うしかなくて大人しく頭を少し下げると、ゆっくり助手席に体が降ろされた。
申し訳なさを抱えつつ助手席で小さくなっている。長船さんはそんな私に気付いていないのか、それとも気付いていないふりをしているのかは分からない。けれど、ずっと穏やかに話を続けてくれている。車は静かに走り続けていて、長船さんがひどく丁寧に運転をしてくれていることがよく分かった。
長船さんは近くの会社に勤めている会社員で、あのジムへは週四回から週六回ほど通っているのだという。私が通っている水曜日は唯一会社の用事で行けない日なのだそうだ。だから一度も見たことがなかったのだ。水曜日に通っていることを話したら長船さんはなんだか妙な顔をして「だからか……」とだけ呟いていた。照れたような、安心したような、残念がるような。なんと表現すればいいのか分からない表情だった。
しばらくして長船さんの知り合いがいるという病院に到着した。事前に電話をしておいてくれたらしく、入口にいる看護師さんが車椅子を用意してくれていた。入口のすぐ近くに車が停まって、また抱えられて車椅子に座らされる。車はそのままそこに置いておいていいと言われているらしく、長船さんは車のロックをしてから私と一緒に病院に入った。
看護師さんがドアをノックすると、「どうぞ」と中から男性の声が聞こえた。「やあ、急に悪いね」と長船さんが声をかけると「これっきりですよ」とお医者さんが顔を上げる。私の顔を見た途端、ぴたり、と固まってしまった。知り合い、じゃない。はじめて会う人だ。どうしてそんな顔をされるのか分からず私まで固まってしまう。
「小狐くん、左足なんだけど」
「…………ああ、捻挫、だったか。失礼。私は三条小狐といいます。一応医院長をしております」
「です、夜分にすみません」
深々と頭を下げる。三条先生はなんだか複雑そうな顔をしつつ「では、足を」と言って、丁寧な手つきで診てくれた。念のためということでレントゲンを撮ってもらった。結果は骨に異常なしということだったが全治二週間、絶対安静とのことだった。松葉杖も、とのことで、仕事は休むようにとも言われてしまった。
「あの、痛み止めなどを打っていただくことはできませんか。どうしても仕事を休むことは避けたくて……」
「デスクワーク程度のお仕事なら無理に休めとは言いませんが……ご職業は?」
「……飲食店の接客です」
「休んでください。診断書を書きましょう」
「で、でも」
「診断書を見せても休ませてくれないようなら私が直接ご説明に伺いましょう。連絡先を、」
「小狐くん、どうどう」
長船さんが苦笑いで三条先生を止める。三条先生は不満そうな顔ではあったけれど一旦落ち着いてくれたようだった。長船さんは私に視線を向けて「僕が原因なんだから職場には僕が説明するよ」と言ってくれたけど、さすがにそこまでしてもらうのは気が引ける。丁重に断るとなぜだかしょんぼりした顔をされてしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あの、長船さん……本当に、すみません……」
「いや……僕こそかっこ悪いところを見せちゃったね、ごめん……」
長船さんに病院へ連れて行ってもらった次の日、結局長船さんが「迷惑をかけてしまっているから」と半ば強引に私の職場へ説明するために同行することになった。電話で済まそうとしていたのだけど、出たのが運悪く社員の主婦で事情を説明すると「そんなこと電話で言われても! 仮病かもしれないじゃないですか!」と言われたのだ。キリキリと痛む胃を抑えつつ店に向かおうと準備をしていたとき、連絡先を交換していた長船さんから連絡が来たという経緯だ。
そうして店へ入ると待ち構えていた社員の主婦は長船さんを一目で気に入ったようで、私の話などそっちのけで長船さんにばかり話しかけ始めた。野次馬をしに来たらしい女子高生の子も長船さんを気に入って私のことは無視。店長だけ苛立った様子で私を睨み付けていた。「休みたいってさあ、シフト決まっちゃってるの。分かる?」と店長はシフト表を突き付けてくる。それに続けて「その怪我だって本当なの? 休みたいからって嘘ついてるんじゃないの?」とまくし立ててくる。言い返そうにも、あの日のことを思い出して怖くなってしまって。ぐっと押し黙りかけたとき、長船さんが「それはひどいんじゃないですか」と間に入ってくれた。そこから店長と長船さんはいくつか言い合いをして、長船さんが「僕が原因なので彼女を責めないでください」と言ったとき。店長が馬鹿にしたように笑って「へえ、そいつに処女もらってもらうんだ? 僕からは逃げたのにね。足踏みつけて鍵投げてきてさあ」と言ってため息を吐く。意味不明な難癖だ。昨日、私に逃げられたことを相当恨んでいるらしい。また恐怖心が顔を出す。その瞬間だった。長船さんが壁を思い切り殴ってからものすごい目つきで店長を睨み付け、「ねえ、それ、どういう意味?」と低い声で言った。
そこからは想像を絶する修羅場だった。その場にいた女子高生は「は? どういうこと? あたしのこと好きって言ったじゃん?!」とかわいらしい笑顔はどこへやら、と言った様子で店長につかみかかる。主婦の人も「はあ?! 旦那と別れたら私と結婚してくれるって言ってたよね?!」と詰め寄る。騒ぎを聞き付けたアルバイトの男子大学生は女子高生に「は?! こんなおっさんと浮気してたのかよ?!」と怒鳴り、店長は私に「このクソ女が! お前のせいでめちゃくちゃじゃねーか!」と逆切れ。それに長船さんがついに切れてしまい、激しい言い合いとなってしまった。
最終的にその場で女子高生と男子大学生はバイトを辞め、主婦も帰っていった。私は店長から「お前なんかクビだ!」と言われ返す言葉を失っていると、長船さんが「こっちから願い下げだよ」と言い返し、私の手を引っ張ってその場を後にした。そうして今に至る。
「本当にごめん……僕のせいでクビに……」
「い、いえ、あんなところ辞めてやるって思っていたので……」
とはいえ困った。店長はああいう人だからたぶん私は本当にクビになるだろう。新社会人からずっと務めた会社だったけど、正直ブラックなところがあったし退職金は期待できない。ついでに今住んでいるアパートは私が勤めていた会社のグループが使う社員寮だ。引越しもしなければいけないというわけで。次の仕事が決まるまで貯金でどうにかするしかない中ではかなり大打撃だ。今後の生活をどうするかを考えているうちに眉間にしわが寄っていたらしい。長船さんは「あの、何か困っていることがあるなら」と言ってくれた。ただ長船さんがいくらいい人だからといって、まだ出会って二日しか経っていない、冷たい言い方をすると赤の他人だ。なんでもかんでもお願いするわけにもいかず、「いえ、大丈夫です」とだけ言っておく。
「……あの、もしかしてなんだけど、社員寮に入ってたりする?」
「えっ、な、なんで分かったんですか……?」
「あそこの親会社、取引先なんだ。お店と寮の防犯システム一緒だろう?」
「え、そ、そうですけど……」
「その警備会社で働いてるから、この辺りの企業のことは一通り分かるんだ」
うちの親会社が契約している警備会社って、かなり大きい会社だったような……? この辺りのお店やマンションはもちろん、かなりの国内シェアを占めていたはず。そんなすごいところに勤めている人だったなんて。余計に恐縮してしまった。
長船さんは気まずそうな顔をして何かを考えている。社員寮を追い出される私を思って何かを考えているのだろうけど、これ以上お世話になるのはやはり避けたい。なんといって切り抜けようか考えていたのだけど、私より先に長船さんが思いついてしまったようだった。
「さん、料理とかは得意?」
「え? 人並みにはできますけど……」
「掃除は嫌い?」
「そんなことはないですが……えっと?」
「家政婦さん、やらない?」
「家政婦さん……?」
「うん。住み込みで。有休も使い放題で前のところよりお給料も出すよ」
「それは好条件ですけど……というか、え、出すよ、って……?」
「僕の家で住み込みの家政婦さん、やってみない?」
長船さんはにこりと笑ってそう言ったが、私はというと口を開けて固まってしまった。長船さんはたしかにいい人だ。はじめて会った私を病院に連れて行ってくれたり、家まで送ってくれたりしたし、職場に出向いて事の経緯を丁寧に説明してくれた。いい人なんだけど、これはさすがにいい人すぎやしないだろうか。今までこんな人に出会ったことがなくて、なんと返せばいいのか困ってしまう。いや、それよりも。こんなにいい人だと思っているはずなのに、心のどこかで長船さんを疑っている自分がいる。そのことが何よりも不思議で情けない。こんなにも良くしてもらっているのに。
長船さんは「一人暮らしなんだけど、残業が多かったりいろいろあって家事が疎かになっちゃってね」と照れくさそうに笑う。なんでも長船さんは一人暮らしなのに来客が多かったり我が家同然に訪問してくる人が多かったりして大変なのだという。その人柄のせいなのか知り合いにはよく頼られているようだ。
「みんないい人ばかりだからきっと仲良くできると思うよ」
一番不思議なのは怖いはずなのに、疑ってしまっているはずなのに、その声にひどく心が落ち着くことだった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
これでもかというほど顔を空に向ける。それでもてっぺんが見えないほどの高さのマンションに唖然としてしまう。大都会の一等地にあるそのマンションは恐らく四十階以上の高さで、高層マンションと呼んでいいものだろう。そうっと入口に視線を移すとタッチパネル式の集合インターホンが置かれている。ずっと突っ立っているわけにも行かないので、ちょん、と指で触れてみると「open」と「knock」と画面に浮かび上がった。「open」は入居者用のボタンだろうから、来客である私は「knock」のほうだ。「knock」をタッチすると数字キーが浮かび上がり、右下に再び「knock」と表示された。メモに書かれている通りに「3-804」と打ち込み「knock」を押す。しばらくしてから「いらっしゃい、どうぞ」とあの落ち着く声が聞こえてドアが開いた。
エレベーターで三十八階まで上がると、すぐにその人を見つけた。わざわざエレベーター前で待ってくれていたらしい。ぺこぺこ頭を下げながら近寄ると、なぜだかへにゃりと笑われた。
「迎えに行けなくてごめんね。荷物はもう届いてるから先にご飯にしようか」
長船さんはそう言ってさりげなく私が持っていたバッグを持とうとする。さっとバッグを後ろに隠して「自分で持ちます」と苦笑いを向けると、長船さんは照れくさそうに笑って「失礼しました」と頭をかいた。たぶん松葉杖をついているから気を遣ってくれたのだろう。でも長船さんの優しさに甘えてばかりではいられない。結局、長船さんの家に住み込みで家政婦として働かせてもらうことにはなってしまったのだけど。
私が会社をクビになったのは、長船さんと店長たちが言い争い修羅場となった日からわずか二日後のことだった。店長はあることないことをでっち上げて本社に報告してクビにするように進言したらしかった。退職金はもちろん出なかった。社員寮からも一週間以内に出て行くように言われた。新卒から働いた会社との別れはあまりにも乱暴であっさりとしていて、怒りよりも悲しさと喪失感だけが私に残っていた。長船さんはあの日以来毎日電話をくれた。会社を本当にクビになったことを話したら私の代わりに怒ってくれた。社員寮から追い出されることを話したら今すぐにでも迎えに行くと言ってくれた。悲しさと喪失感だけがあることを話したら優しい声で穏やかに励ましてくれた。すべて嘘ではないと思う。けれど、なぜだか私の心の奥底には恐怖と疑心が残っていた。長船さんは嘘をついているんじゃないか。本当は私のことを煩わしいと思っているんじゃないか。そんな不安にも似た感情がどこかに引っかかって取れないままだ。その気持ちを抱えたまま、社員寮から出て行けと言われた五日後、私はこうして長船さんの家に来ている。
長船さんは部屋の鍵の開け方を教えてから「あの、ものすごく申し訳ないんだけど」と苦笑いをこぼす。不思議に思いつつ「なんですか」と聞いてみると、ガチャリとドアを開けた。玄関には長船さんの靴、ではないであろう靴が二足並んでいる。それを見つめる私に長船さんは頬を軽くかきながら「少し前に来客があって」と申し訳なさそうに言った。なんでもよく来る人だそうで、追い返すわけにもいかないから同席でいいか、とのことだった。この家の主は長船さんなのだから気にする必要なんかないのに。長船さんは二足の靴を端に寄せると「いい子たちだから安心して」と言いつつ、自分の靴を揃えた。
リビングに入ると「お」と低い声が部屋に小さく響いた。眼鏡をかけた男の子と色黒の男の子。声をあげたのは眼鏡をかけた男の子だった。二人とも制服を着ているので恐らく高校生だろう。小さく会釈しつつ挨拶をすると二人も会釈を返してくれる。眼鏡の子はにかっと豪快に笑って「その人が例の家政婦さんか?」と長船さんに声をかけた。
「あ、えっと、です。よろしくお願いします」
「いや、別に俺たちゃ住人でも何でもないんだが……よろしくな、さん。俺は織田薬研だ。こっちは伊達広光」
「無口だけど悪い奴じゃないぜ」と織田くんは伊達くんの肩をばしばし叩く。伊達くんはじろりと織田くんを睨んで「やめろ」と低い声で言ったのち再び黙った。長船さんは困ったように笑ってそれを見ていた。なんでも伊達くんは長船さんが勤める会社の社長の息子さんなのだという。長船さんが勤め始めたころから社長夫婦と仲が良く、気付けば息子さんの面倒をよく見るようになったと語った。そういう縁があって伊達くんは高校生になった今でも長船さんの家をしきりに訪れるそうだ。織田くんは伊達くんと同じ高校に通っており、気付いたらくっついてやって来るようになったらしい。他にもこの部屋には隣に住んでいる人や、小説家だという人、同じ会社に勤めている同僚などなど、様々な人が遊びに来るのだという。それにしても友人が小説家から高校生までいるとは、長船さんの顔の広さには驚いてしまう。
織田くんの隣が空いていたのでそこに座らせてもらう。長船さんは「もう少しでできるよ」と言ってキッチンに消えてしまって、高校生二人と二十八歳の無職などという異様な組み合わせが生まれてしまった。無言でいるのもどうかと思ったので何か話そうにも、とんと言葉が出てこない。高校生相手に怖気づいてしまっている自分を情けなく思っていると、じいっと視線を感じた。織田くんが頬杖をついたまま私の顔を観察していた。ばちっと目が合うと織田くんはにかっと笑って「不思議なもんだな」と呟いた。それがどういう意味なのかは分からなかったが、黙りこくられるよりは全然安心した。織田くんと伊達くんは高校二年生なのだといい、よく学校帰りに長船さんの家に寄るのだという。なんでも「家より落ち着く」のだそうで、長船さんも怒らず迎えてくれると嬉しそうに言った。
はじめは緊張したけれど、不思議と楽しくおしゃべりができていた。伊達くんはあまり話してくれなかったが話を聞いていることはよく分かった。織田くんの言う通り「無口だけど悪い奴じゃない」、そのままだった。織田くんは剣道部に入っていて、大会が近付いてきているから毎日練習で忙しいと苦笑いした。
「柄でもないんだが、結構試合前に緊張したりしてな。和らげる方法を探してるんだ」
「あ、それなら。両手をこうして……」
子どものころからの癖がある。緊張したり何か考え事をしたり願い事をしたりするときの癖だ。親指を外に出したまま拳を握り、親指が上に向くように両拳を合わせる。親指の爪を鼻先につけて目を瞑る。友人や両親からは「なにそれ」とよく笑われているのだけど、これをやると不思議と心が落ち着いて冷静になれるのだ。何か力をもらえている気がして大人になった今でもたまにやってしまう。
それを説明していると、織田くんが黙りこくっていることに気が付く。織田くんの顔を見るとなんだか驚いたような顔をしていた。口が開いたままぼけっと私を見ている。何か変なことを言ってしまったのだろうか。不安に思いつつ呼びかけてみる。はっとした様子で織田くんは「ああ、いや」と苦笑いをこぼす。私の手の真似をして、親指の爪を鼻先につけると「本当だ、落ち着く」と、ひどく静かな声で言った。
「さん」
「うん?」
「それ、今度光忠のやつにも教えてやってくれ。ああ見えて存外怖がりなところがあってな」
その表情はどこか、遠くを見ているように見えた。およそ高校生の子がするようなものではない。あまりにも優しく、悲しく、どこかに罪悪感があるような顔だった。
長船さんが作ってくれたご飯を四人で食べたあと、織田くんと伊達くんは帰っていった。長船さんが送っていこうとしたのだけど、二人ともそれを断っていた。それに苦笑いをしつつも長船さんは「いい子たちだったでしょ」と自慢げに言う。まるで自分の子どものような口ぶりに少し笑ってしまった。
長船さんの家はマンションの一室だと思えないほど広かった。大きな窓があるリビングはもちろん、キッチンに寝室、書斎。トイレやお風呂まで高級ホテルを思わせる贅沢空間だ。家事を疎かにしてしまう、なんて言っていたけれどどこもきれいに掃除されていて若干プレッシャーを感じる。こんなにきれいに掃除、できるだろうか。そんな不安が顔に出ていたのか長船さんは焦ったように「別に適当で大丈夫だよ」と言ってはくれた。けれど、ここまで良くしてもらっているのだから頑張る以外の選択肢はない。少しの不安を抱えつつも「仕事が見つかるまで、よろしくお願いします。長船さん」と頭を下げた。長船さんはそれに少し黙ってから、苦笑いをこぼして「こちらこそよろしく。光忠でいいよ」と言って同じようにお辞儀をしてくれた。
長船さん、改め光忠さんが私の部屋にと用意してくれたのは光忠さんの寝室の隣にある部屋だった。中には棚や机、ベッドなどが置かれている。どれも私が持ち込んだものではない。私が持ち込んだものは段ボール二箱に収まった私物だけ。光忠さんのほうを見たら照れくさそうに笑って「よかったら使って」と言われた。どうやら私が引っ越し準備をしていた数日のうちに購入したらしい。
「あの、光忠さん」
「うん?」
「どうしてここまでしてくれるんですか。この怪我はたしかに光忠さんが関わってはいますけど……ここまでしてもらうことでは……」
たしかにこの捻挫は光忠さんに声をかけられて驚いたときに滑って転んだことが原因だ。でも、それは私が転んでしまったから、が大元の原因であって光忠さんが何か悪いことをしたわけじゃない。それなのに光忠さんはやたらと私を気にかけてくれる。これくらいのことで誰彼構わず気にかけていたら身が持たないに違いない。ちょっとぶつかっただけの人とか、ちょっと迷惑をかけてしまった人とか、誰にでも親切にしなきゃいけなくなってしまう。たしかに私は困っているしこんなふうにしてもらって助かってはいるけれど、光忠さんにほとんどメリットなどない。それなのに、どうして。光忠さんは私のそんな疑問に少しだけ沈黙してから、優しく笑う。ゆっくり瞬きしたその瞳は、やはり色が違う二色の瞳だった。
「きっとそのうち、分かるよ」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
驚いたのは光忠さんがとても料理上手で、世話焼きな人だったことだけじゃない。光忠さんは私の好みをなぜだかよく知っていて、なぜだか私の性格までもよく知っていた。
「おはよう」
「…………あ、あの、光忠さん……」
「目玉焼き二つでいい?」
「あ、はい……じゃなくて、あの」
「なに?」
「私、家政婦なんですよね……?」
「うん? そうだよ?」
「……この二日間、何もさせてもらえてないんですけど……」
光忠さんは早起きだ。仕事がある、ないに関わらずいつも朝五時には起きている。起きてからお風呂に入り、朝食を作り、掃除をし、洗濯を干す。光忠さんはそれを私が起きてくるまでにほとんど終わらせてしまうのだ。私は朝起きることが苦手で、どう頑張っても六時すぎにしか起きられない。そんな私を咎めることもなければむしろ「もっと寝てていいんだよ」なんて笑って言う。家政婦として居候させてもらっているというのにとんだ失態だ。今日こそは、と思ってなんとか五時半に起きてきたというのに。すでにリビングはおいしそうな匂いで包まれていた。光忠さんはお休みだというのに身なりをきっちり整えて、にこにこと笑ってフライパンを握っている。またしても勝てなかった。私の新生活はまず家主との朝ごはん競争からはじまっていた。
「起きるのが遅くてすみません……」
「えっ、いいんだよ? ちゃん、あと一週間は絶対安静だって言われたこと、忘れてない?」
私の足を見ながら光忠さんがそう言う。昨日前に連れて行ってもらった病院で診てくれた先生がなんとここまで診に来てくれた。光忠さんは苦笑いしつつ「心配性な先生なんだ」と言っていたけれど、訪問診療なんてあんな大きな病院でもやるんだなと驚いてしまった。三条先生は「あと一週間は大人しくしているように」と言っただけだったので順調に回復していると思ってよさそうだった。腫れはだいぶ引いたものの痛みは残っている。松葉杖もまだしばらく貸してくれるとのことだったので、有難く使わせてもらっている。まだ心配してくれているようで、未だに掃除すらさせてもらえていない状態だ。昨日は光忠さんが仕事で家にいなかったので、こっそり少しだけ掃除をしたのだけど帰ってきた光忠さんに怒られてしまう始末だった。家政婦として来たはずが、お世話をされているだけになっている。再び自分に情けなさを覚えつつ光忠さんが作ってくれた朝食を有難くいただいた。
この二日間で光忠さんのことを少しだけ理解した。一つ目、光忠さんはひどく心配性である。私が少しでも痛がる素振りを見せるとすぐに飛んできて必死な顔で心配してくれる。何か私が運ぼうとするだけで飛んできて荷物を奪うし、洗濯物を取り込もうとするだけでものすごく焦る。二つ目、光忠さんはものすごく世話焼きである。私の部屋の掃除を率先して手伝ってくれたり、少しでも困っているとすぐに助けてくれる。自分のことはそっちのけで私の面倒ばかりを見てくれるものだから少しだけ困ってしまう。三つ目、光忠さんは、とても優しい。恐らくだけど、はじめて会ったときに私が「触らないで」と叫んでしまったのを覚えている。一度たりとも私に触れたことがない。少しでも触れそうになったらすぐに謝ってくる。食器を下げるときに手が当たってしまっただけで必死に謝ってくる。光忠さんは優しい人だ。優しい人だけど、前に織田くんが言っていたように、少し怖がりな人なんだと思ってしまった。
「人に甘えることも大事だよ」
優しい声には相変わらず心が落ち着く。柔らかに光る瞳の金と紅。右側だけ少し伸びた前髪はその紅を隠すためのものなのかもしれない。それでも、きれいだと思ってしまう。ふと聞いてしまう。瞳の色は遺伝なのか、と。光忠さんは驚いたような顔をして固まった。聞いてはいけない話だったのだろうか。内心焦っていると、光忠さんはゆっくりと口を開いた。「僕の瞳、何色に見える?」と。光を閉じこめたような金色をした左目。妖しく光る紅い月の色のような右目。どちらも美しい色をしていて、どちらも同じように私にはきらきらと光って見えている。そう伝えると光忠さんは口元を右手で覆った。気分が悪くなったのかと思って声をかけたけれど、その顔がほんの少しだけ赤くなっていることに気が付いた。光忠さんは恥ずかしそうに笑って「ありがとう」と言って、小さく笑うだけだった。
光忠さんへの恐怖心と疑心は次第にほどかれていき、消えたかと思っていた。けれどときたまにあの日のいろいろなことを思い出してしまって不安に変わることがある。光忠さんが怖いのではない。光忠さんを疑っているのではない。男性に恐怖し、男性を疑っているのだ。そう思ったらこんなに良くしてくれている光忠さんに申し訳なさを覚えてしまう。ときたまに光忠さんの大きな手を見たとき、大きな体を見たとき。私は自分の知らない間に怖いと感じてしまっているのだ。光忠さんがそれに気付いていないことを祈りながら日々を過ごした。
光忠さんの大きな背中をこっそりと見つめる。洗濯物を干している背中は恐らくどんな女性にも頼もしく見えるのだろう。それにしても、女性にモテて困るほどだろうに、どうして私なんかを家政婦として迎え入れてくれたのだろう。恋人がいる感じはないし結婚なんかもちろんしていないだろう。女っ気がない。あまりにもなさすぎてこちらが困惑してしまうほどに。大企業に勤め、容姿端麗でスタイルが良く、誰にでも好かれる人柄。世の女性が放っておくわけがないのに。
洗濯を畳むことくらいなら座っていてもできる。そう光忠さんに言ったら苦笑いしながら「じゃあ一緒に」と言って私が座っているソファに洗濯物を置いた。光忠さんも同じようにソファに座って二人で洗濯物を畳み始める。光忠さんの家に来てはじめての仕事だ。丁寧に畳んでいたら小さく笑った声が聞こえてきた。「ごめん、あまりにも真剣な顔をしているから」と笑いをこらえながら言われて少し恥ずかしくなってしまった。そんなささいなやりとりが、なぜだかとても、穏やかな日常として私に馴染んでいるように思えて、私まで恥ずかしくなる。
自分が不幸だとは思わない。本当に目も当てられないほど不幸な人はこの世の中にたくさんいるはずだ。仕事があって、家があって、友達がいて、理解者がいてくれた私はきっと幸せな人間なのだとすら思う。けれど、あまりにも私の人生は、私が求めるような満ちたものではなかった。何かが足りない。それが恋人なのか何なのかは分からない。あまりにも平凡、あまりにも特徴がない。私の人生はそういうものだった。私じゃない誰かがこの人生の主役になっても成り立つような人生だった。そんなどこにでもありふれていて誰にでもある平凡な人生が、光忠さんと出会ったことで少しだけ変わった。分からないことや不思議なことはたくさんある。それでも、私は前よりも自分の人生を少しだけ好きになっていた。
「明後日に大事な会議があってね。何度想像しても失敗しそうで少しだけ緊張してるんだ」
光忠さんは恥ずかしそうにそう頭をかいた。私より先にタオルを畳み終わったみたいで、私が畳んでいるのを穏やかに見つめている。光忠さんでも緊張することなんかあるんだなあ。そう思ったとき、前に織田くんに言われたことをふと思い出した。
「あの、私の癖なので効くかは分かりませんが……」
「うん?」
「両手をこうして」
織田くんに教えたものと同じポーズ。親指を外に出したまま拳を握り、親指を上に向くように合わせる。その親指の爪を鼻先につけて目を瞑る。子どものころから気が付いたらやっていた癖。それを説明してやって見せる。「これ、すごく落ち着くんですよ」と目を開けた。
「光忠さん……?」
光忠さんはぼろぼろと涙をこぼしながら笑う。「ごめんね」と呟いて涙を手で拭った。そうして私が教えたそのポーズをゆっくりと作ると、ほんの少しだけ嗚咽をもらした。
「うん、すごく、落ち着くね」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
僕たちが所属している相模国七番本丸は時間遡行軍が出現してすぐに作られた、所謂古株本丸の一つだった。まだ政府がこの本丸システムというものを十分に展開できないまま作られたため、備前国は三十番まで、相模国は二十番までの本丸しか存在していなかった。資源も少なく、各本丸の審神者は不安定なシステムの中で霊力をうまく保てない者も多かったと聞く。本丸ができてすぐは政府も審神者も、もちろん僕たち刀剣男士も分からないことだらけで不安要素だらけだった。多くの審神者が死んだ。多くの刀剣男士が刀剣破壊に遭った。それでも時間遡行軍は攻撃をやめなかったし、むしろそんなときだったからこそ執拗に本丸を潰そうと躍起になっていた。
そんな中、僕たちの相模国七番本丸は、まさに破竹の勢いで数々の戦場を制してきた。主はとくに霊力が強いわけではなかった。ただただいつでも冷静で、ただただいつでも僕たちを信じてくれた。ただそれだけだった。それだけなのに、僕たちにとってはそれが何よりも力だったのだ。僕たちの主は審神者になったときすでに七十を超える、最高齢審神者だった。最初はこんなおじいちゃんに、なんて思っていたけれど、それは戦術を練る姿を見てがらりと変わる。あまりにもすごかった。編成、戦略戦術。戦うことは僕たち刀剣のほうが知っているはず。それなのに、僕たちと同じように、主もまた刀のごとく戦った。それをみんな慕い、彼を審神者だと、主だと心から認めていた。
とくに近侍を務めた大倶利伽羅は誰よりも主を慕い、誰よりも主の力になった。あの大倶利伽羅が、と言う審神者もいたのだという。基本的に大倶利伽羅という刀剣男士は馴れ合いを嫌い、一人で行動することの多い一匹狼だ。そんな大倶利伽羅が主である審神者にくっ付いていることが不思議でたまらなかったのだろう。
主はすごかった。鬼神のごとき手腕だった。それでも、人間には寿命というものがある。
当時の本丸は、審神者の親族または審神者の霊力の譲渡を認められた者によって引き継ぐことを許されていた。のちにこれは諍いを生むとの理由で廃止される制度となるが、できたばかりのシステムとまだ少ない本丸、勢いの止まらない時間遡行軍。それらに政府が焦りを見せていることは一目瞭然だった。僕たちの本丸にいる刀剣男士たちは強者ぞろいで、練度が振り切った者も多かった。政府はそんな本丸をなくすことが惜しかったのだろう。それは主も同じだった。本丸を引継ぐに足る存在がいる、と政府の人間に説明したとあとで聞かされたことを覚えている。引継ぎの件を説明されたあと、大倶利伽羅はしばらく部屋から出てこなかった。主がもう少しで死ぬ。それなのに、その死を看取れない。審神者の引継ぎは審神者存命のうちでなければできない。本丸に二人の審神者が同時に存在することもできないので、引継ぎが終わればもう二度と主には会えない。けれど、僕たちには主の記憶が残る。大倶利伽羅はそれを拒んだ。刀解を望みすらした。僕を含む多くの刀剣男士も同じだった。けれど、それらは一切認められずついに引継ぎの日を迎えた。
「本日から相模国七番本丸の審神者に就任しました。どうぞよろしくお願い致します」
僕たちの前に現れたのは、まだ幼い女だった。政府からは主の孫娘であると説明を受けた。たしかに霊力は似ている。けれど、主ではない。鬼神のごとく僕たちとともに戦った主とは何一つ似通わない、戦いなど何も知らない子どもだった。
誰も彼女を主とは呼ばなかった。出陣の命を受けても士気が上がらず、今までのような戦果は出せなかった。内番も主の命ではないと言ってやらない者が多かった。そのうち誰も内番の命を受けなくなり、見てみればすべて彼女が一人でやっているようだった。主とは大広間で一緒に食事をしたけれど、彼女とは食事を共にしなかった。彼女に話しかけられても、彼女が困っていても。誰も彼女を見なかった。もういない、生きているかももう知ることができない、主の姿をみんなが探していた。
大倶利伽羅は彼女が就任したその日以来、ほとんど部屋から出てこなくなった。近侍という位置にはいたが、一切それを大倶利伽羅は認めなかった。僕も正直なところ、戦いも知らないような子どもを主だと呼ぶことはできなかった。彼女の霊力がなければ僕たちは今頃もうここにはいない。そうだとしても、彼女を主だと、思えなかった。僕が、僕たちが慕った主は、僕たちと同じように刀のように鋭く頑丈で、血にまみれてもそれを振り払う気概のある、鬼神だったから。彼女はそれとは真逆すぎて受け入れることができなかった。どこを見ても柔らかく華奢で、血など浴びたことのない、無垢な瞳。僕たちに触れればきれいさっぱり斬れてしまいそうな、脆い人間。僕の瞳には彼女はそんなふうに映っていた。
誰も彼女を主だと認めないまま、一年という時間が経った。僕たちの主が亡くなったと聞かされたとき、誰もが唇を噛んで、内心怒りを覚えていた。どうして僕たちは主の最期を看取ることができなかったのか。主と認めたのはあの人だったのに。そんな怒りが渦巻いて、余計に誰も彼女を見なくなった。いないかのように扱われても、彼女は僕たちに笑顔で話しかけ、僕たちのことを気にかけ続けていた。
「なあ、みんなしてやめねえか、こういうことは」
彼女がいないときに、薬研藤四郎がみんなを集めてそう言った。粟田口の短刀たちが口々に「やめなよ薬研」と止めていたが薬研くんは話し続けた。
「大将だってこんなことを望んじゃいないだろう。何か考えがあって孫娘を引っ張り出して審神者なんかにしたんだろうよ」
「……どういう意味だ」
「大将は孫娘を宝物だって言ってたんだよ」
薬研くんは主に聞いたことがあるのだという。「大将にとっての宝ってなんだ?」と。主はそれに迷わず「孫だな」と答えて笑っていたと言った。そんな孫娘を危険な審神者にし、自らの本丸を引き継がせた。薬研くんはそれに疑問を覚え続けていたのだという。
「孫娘だから主であると認めろと?」
「そうじゃねえよ。主だと認める認めないは個人の自由だが、さすがに無視はないだろって話だよ」
「主以外の人間と口を利くつもりはない」
大倶利伽羅の言葉に薬研くんは少しだけ眉間にしわを寄せた。しん、と大広間が静かになってしまう。そんな中に能天気な声が響く。鶴丸国永は立ち上がって薬研くんの隣に立ってその肩を軽く叩いた。
「別にみんな仲良しこよしと意見を揃える必要はないさ。各々好きにすればいいだろ、薬研」
「……そうだな、勝手にしろ」
鶴さんは苦笑いをこぼして「怒んなよ」と薬研くんの肩から手を離した。広間全体を睨み付けるようにこちらを見て薬研くんは「大将が見たら悲しむだろうよ」と言い残し、広間から出て行った。そんな薬研くんを見送ってから鶴さんはため息をつき、「参ったな」と苦笑いをこぼした。「最悪な空気だぜ」と辺りを見渡す。誰もが一様に俯き、言葉をなくしている。
「そういう鶴さんは? 彼女を主だと認めてるの?」
「受け入れられてないって感じだな。無視するほどではないさ。……光坊は冷たいほうだよな、意外だぜ」
「……そうだね、自分でも不思議だよ。どうしても主と呼べないんだ」
恐らくこの場で最も大人な対応をしているのは薬研くんだろう。そう頭では分かっている。それでも彼女の姿を見るだけで、彼女の声を聴くだけで、もう主はいないのだと思い知らされる。彼女が嫌いなのではない。彼女が審神者である、という事実が受け入れられないのだ。人間というのはこんな複雑な感情を抱きながら生きているのか。そう苦笑いをこぼしてしまうほど言い表しがたい感情だ。
そんなことがあったあと、誰も彼女を主とは認められずにはいたけれど、無視をしない刀剣男士が少しだけ増えた。主とは呼ばないままではあった。それでも彼女はそれを嬉しそうな顔をしていた。その様子を僕は、遠くから見ていた。僕や大倶利伽羅は未だ、彼女という審神者の存在を受け入れられず、言葉を交わすことも避けている。薬研くんは不満そうだったけれど、もうあれ以来その不満を言うことはしなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
誰も審神者を主と認めない、そんな本丸は、異質な空気に包まれたまま二年目を迎える。冬のある日だった。その日は近侍である大倶利伽羅と僕、そしてへし切長谷部の三人で彼女の部屋の前で夜番をしていた。なぜ三振りもいるのかというと、ここ最近本丸への直接襲撃が多く発生しているとの政府からの通達があったのだ。中でも相模国はその被害が備前国よりも多く、警戒せよとのことだった。彼女は「夜番はなくていい」と言ったが、いくら主と認めていなくてもこの本丸の審神者を殺されれば本丸はなくなる。主が作り上げた本丸がすべてきれいになくなり、また一からやり直しになるのだ。主が彼女に本丸を継がせたことが無駄になる。主を未だ慕っている僕たちにとって、阻止しなければいけないことだった。大倶利伽羅と僕は未だに彼女と口すら利いていなかったが、長谷部くんは少しだけ違っていた。主であるとは認めていないようだけれど、会話くらいはするようになっていた。「そそっかしくて見てられん」と前に言っていたことを思い出す。あの長谷部くんが、とはじめは驚いた。けれど、逆に長谷部くんだからこそそうなったのかもしれない。主命主命とうるさく主に仕事を要求し、大倶利伽羅に負けないくらい主を慕っていた。大倶利伽羅と違ったのはそれが単純な信頼であったことだろう。信頼した主が残していった彼女を、長谷部くんは少しだけ信じてみることにしたらしかった。この場において宙ぶらりんなのは僕だけ、というわけだった。なんとなく、なぜだか。そんな前置きがなければ自分の感情を説明できない。
そんなときだった。爆発音が激しく本丸中に響き渡る。本丸の西側に火の手が見えた。ついに時間遡行軍の襲撃がこの本丸にも来たのだ。彼女の部屋に飛び込むと音で起きた彼女が驚いた顔をして僕たち三振りを見上げている。夜番をしていることは彼女には言っていない。僕たちがここにいることに驚いている様子だった。
「どうして……」
「ここにいては危険だ。早急に本丸から脱出、一時避難を」
「で、でも、私がいなくちゃ、霊力が」
「本丸には霊力が満ちている。しばらくは霊力も持つだろうし、ここの刀剣は強者揃い。そう簡単には、」
長谷部くんが言葉を切る。その視線の先に、すでに時間遡行軍が迫っていた。大倶利伽羅が素早く斬りかかり間合いを取る。長谷部くんに彼女を任せて僕も前に出たが、部屋の外にはすでに多くの時間遡行軍が待ち構えていた。この短時間のうちにここまで来たということか? 西側のほうの爆発音は陽動、かと思ったがそれにしては他の刀剣男士の到着がない。政府からの報告で聞いた本丸急襲はごく小規模での急襲だと聞いている。だが、あまりにも報告とは様子が違う。しばらくすると本丸の至るところで刀を交えている音が聞こえてくる。恐らく、今まで報告のあった急襲とは違う。今まであった急襲はどれも審神者を狙ったもの。だが、この急襲は恐らく、本丸自体を潰す目的で行われているものに違いない。時間遡行軍は集められるだけの同志を集めてここを襲ってきている。そうなると話は変わる。いくら強者揃いの本丸であっても、数の力は圧倒的不利だ。政府からの援軍を待とうにも通信がとれる状態ではない。
彼女を囲んで敵を斬り続ける。斬っても斬っても現れる時間遡行軍は、恐らく僕たちを他の刀剣男士と合流しないようにしているに違いない。恐らく他の刀剣男士たちもそんなふうに合流を阻止されている可能性が高いだろう。ここは僕と大倶利伽羅で道を開き、足の速い長谷部くんにそれぞれ分断されているところに加勢に行ってもらうべきか。……いや、これだけの数だ。長谷部くん一人で行かせるには少し無理がある。長谷部くんは練度が振り切っているし戦場には慣れている。それでも、この数を相手にしながら一人でそれぞれの場所へ加勢は厳しい。そうなると大倶利伽羅を残して僕も長谷部くんに……いや、恐らくそれが一番悪手だ。この場において最も優先すべきは審神者の安全。ここから二人以上を出すことはできない。斬りかかってくる時間遡行軍から彼女を守りながら、ちらりと横目で彼女を見る。怯えていることだろう。戦いなど知らない、刀など握ったことのない、血濡れていないその手は震えていることだろう。そう思った。そう、思っていたのに。
彼女は静かに目を瞑っていた。握りしめた拳。それを合わせ、親指の爪を鼻先にあてて、静かに目を瞑っていた。
「これをするとな、落ち着くんだよ。考え事をしたり祈り事をするときは必ずこうするんだ、俺は」
「へえ、変わってるね」
「俺の宝物にこっそり教えたら真似してるらしいんだ。はは、かわいいもんだな、子どもってのは」
主との会話を思い出した。そのとき、主が言った”宝物”というのは、主の子どものことだと勝手に思っていた。違った。君だったのか、薬研くんの言う通り。君が、主の宝物だったのか。主の癖だった。それは何なのかと僕が聞いたら「みんなには内緒だからな」と言って教えてくれたのだ。緊張したとき、考え事をするとき、祈り事をするとき。主はそういうときにそれをすると頭と心が落ち着くのだと言っていた。戦術に迷ったとき、焦りで頭が混乱したとき。彼女のその姿は、きれいに主と重なっていた。
「大倶利伽羅様、へし切長谷部様。この場から離れて他の刀剣男士様と合流し、時間遡行軍の侵入口を探してください」
「何を言っている。ここの護りを手薄にするな。そもそも燭台切だけを残すなど、」
「どうして?」
「燭台切?」
「どうして、そうしたほうがいいと思うの?」
はじめてだった。彼女に言葉を投げかけたのは。長谷部くんだけではなく大倶利伽羅も驚いた顔をしている。彼女さえも僕の顔を驚いた様子で見上げていた。それでも彼女は瞳をこちらにまっすぐ向け、口を開く。
「大倶利伽羅様のことは皆様が信用しています。大倶利伽羅様がいるだけで士気が上がります。へし切長谷部様は大倶利伽羅様との出陣も多かったため連携がとりやすいと思います。そして何よりも素早さがずば抜けており、大倶利伽羅様の道を切り開く力があります」
「けど、君が死んだら何もかも意味がなくなるよ。審神者の護りはどうするの? 何かいい策でもあるのかな」
「燭台切光忠様、あなたがいます」
「僕一振りしかいないじゃないか」
「あなた一人いれば、私は死にません。私はあなたが強いことを誰よりも知っています」
迷いのない瞳だった。まっすぐに僕の瞳を見つめる、闇夜を切り裂く鋭い光。僕の言葉を待たずに彼女は大倶利伽羅と長谷部くんに指示を出し始める。ここを出てまず粟田口の部屋に向かうようにと。粟田口の部屋は大部屋で、一期一振以外の粟田口はそこに集まっている。今は夜。短刀と脇差と合流することが何より必須だ。粟田口の部屋から大広間は距離が近い。大広間には恐らく戦いながら合流したであろう刀剣男士たちがいるはずだから、そこと合流し侵入口を探し出し、まずはそこを潰す。侵入口を潰したのちに本丸内にいる時間遡行軍を殲滅する。淡々と落ち着いた声で彼女はそう言った。大倶利伽羅はそれを黙って聞いていたが、彼女が話し終わってようやく口を開いた。
「あんたを主と認めてはいない」
「…………はい」
「あんたが光忠と心中するつもりなのならその策には乗らない」
「いいえ、私は一人も死なせません」
僕たちのことを刀として数えていない。主と同じように、僕たちのことを、人間として彼女は見ていた。
「ここにいる人はみんな、おじいちゃんが私に残してくれた大切な宝物だから、必ず守ります」
飛び掛かろうとした短刀を斬り落とす。一斉に短刀、脇差、打刀が斬りかかってくるのを斬り捨てようとした大倶利伽羅を押しのけて斬った。「おい」と大倶利伽羅が困惑した声を上げている。体が勝手に動いた。口が、勝手に動いた。
「行け!!」
その瞬間に再び短刀たちが斬りかかる。彼女の腕を引っ張って自分に引き寄せ、短刀を斬り捨てる。大倶利伽羅と長谷部くんはそれを驚いた顔で見つめているだけで走り出さない。さすがに腹が立ってもう一度「行けって言っただろ!」と怒鳴ってしまう。はっとした長谷部くんが「行くぞ」と大倶利伽羅に声をかける。大倶利伽羅は一瞬迷った顔をしたけれど、唇を噛んでから長谷部くんについていった。
彼女と二人きりになったのはこれがはじめてかもしれない。二人きり、とはいっても周りは敵に囲まれているのだけど。彼女の肩を支えて呼吸を整える。囲んでいる敵は短刀三振り、脇差三振り、打刀二振り。いつの間にか太刀二振りもやってきている。状況は分かりやすく劣勢。彼女の部屋に出入り口は一つしかない。そこは後から来たらしい太刀二振りが塞いでいるため、今はこの状況を打破するというよりは耐えることに集中すべきだろう。今は大倶利伽羅たちを信じてここを護るしか僕にはできない。
あの二人ならば、と僕も思った。主ならそうするだろうと思った。けれどここに残るのは僕一人。主を護るのであれば話は別だっただろう。けれど、ここに残った僕は、彼女を主とは認めず口すら利かない、そんな刀剣男士だった。そんな僕だけを残す策など彼女は取らない。いや、取れないだろうと思っていた。僕のことを信じる要素がどこにもないから。それなのに、彼女は迷うことなく選択した。恐らく主が選んだであろう選択を。僕のことを強いと、彼女は認めていた。
気が付いた。僕がどうして彼女を主と認められないのか。相模国七番本丸の刀剣男士たちは強い、強者揃いだと自分で思う。けれどその強さは単純な練度や鍛錬で培われた力だけのものではない。主を護りたい、主の役に立ちたいと思う力こそが僕たちを強くした。それは見て分かるものでもなければ言って分かるものでもない。僕たちを”刀剣男士”として見る人間には分かり得ないものだった。主は僕たちに人としての強さを教えてくれた。主は長い年月をかけて僕たちにそれを教え、僕たちのそれを認めてくれた。けど、彼女は違う。僕たちの弱いときを知らない。強い僕たちを見たら大半の人は言うだろう。”人間じゃないから特別な力があるのだ”、と。僕たちは人間じゃない。そうだとしても、強いとか弱いとか、そういうのは人間と何一つ変わらない。主が教えてくれた。そんなこと、彼女が知るわけもない。だから僕は彼女を主だと認めるのが嫌だったのだ。僕たちを最初から強いものだと見ている人間と同じだろうからと。でも、彼女はそうじゃなかった。誰にも口を利いてもらえなかった。食事も一緒に取らなかったし、命令を無視されることだって多かった。それなのに彼女は僕たちをちゃんと見ていた。一人の人間を見るように、僕たちをちゃんと見ていたのだ。そうでなければみんなが大倶利伽羅を信頼しているなんて分からない。誰も口に出さないから、そんなのちゃんと見ていなければ分からないはずなのだ。
「燭台切光忠様! 敵は恐らく東側から侵入してきているはずです! 東側には、」
「ああ、分かっているよ。あそこは歌仙くんや山姥切くん、本丸初期からいる強者ばかりだ」
「はい! 恐らく侵入口はそのうち制圧されます! その証拠にこちらへ来る敵が少し減っているように、」
「もういいから!」
「え……?」
「理由はいいから! 指示を出してよ、主!」
太刀を二振り斬り捨てる。増援が来ないことに焦りを感じているのか、短刀と脇差、打刀は少し様子を見ている。彼女の肩を抱いたまま間合いを取り、刀を構え続ける。彼女はもしかしたら泣いていたかもしれない。視線を向ける余裕はなかった。でも、そんな気がした。
はじめて呼んだそれに、不思議と違和感はなかった。
「走ってください! この部屋から出るなら今しかありません! でも外ではなく別の部屋に移るようにしてください!」
ここは東側にある部屋。もたもたしていると増援がやってきてまた振り出しに戻る可能性がある。恐らく本丸内に侵入した敵は他の刀剣男士たちが食い止めていて、こちらに増援できない状態に違いない。まずはこの部屋から出て体勢を立て直し、できることなら他の刀剣男士と合流したい。ただ外に出るとその分隙が生まれてしまう。その上太刀である僕は索敵が得意ではない。主を護りながら戦うには、こちらの目が届きやすい室内にいるほうが良いと判断したのだろう。敵に背を向けるのは格好悪い、が、そうも言っていられない状況だ。
「オーケー、任せてくれ」
いつも、主に頼み事をされたときと、同じ返事をしていた。
小さな体を抱き上げ、目の前にいた脇差を一振り斬ってから出口に向かって走る。追いかけてくる敵を止まらず斬りながら廊下に出ると、倒れた棚や花瓶が散乱していた。索敵は得意ではない。どこに誰がいるのかほとんど分からない。そんな僕の耳元で彼女が言った。「厨房へ」と。言われたままに走り続けると、ようやく仲間が聞こえた。粟田口の面々だ。薬研くんは僕たちを見るなり驚いた顔をして「そりゃ、どういう状況だ?」と少しだけ笑った。
「見ての通り、主の護衛だよ」
「……そうかい、そりゃご苦労だったな」
薬研くんは豪快に笑うと、傷だらけの体を再び動かして言った。「主に傷一つ付けさせるんじゃねえぞ!」と。その一声で粟田口の面々は一つになったようだった。大倶利伽羅と長谷部は一旦粟田口の部屋で彼らと合流することに成功したのだという。そのまま大広間まで固まって行き、そこで獅子王や小狐丸たちと合流したのち、東側に侵入口があると見てそちらに行ったと前田藤四郎は話した。短刀や脇差を中心にして本丸内にいる敵を殲滅してから自分たちも向かうつもりだと言った。
全員が刀を構え直す。未だに時間遡行軍が優勢、こちらは相変わらず劣勢のままだ。それでも、誰も劣勢だとは感じていなかった。<
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「つらくはなかったの」
手入れをされながらそんなことを聞いてしまった。彼女、いや、主はきょとんとした顔をして僕を見ている。そりゃそうだ。つらくはなかったのか、って、僕が聞いてどうする。彼女を主だと認めなかったのも、無視をしたのも僕だというのに。刀解されてもおかしくない状況だった。それなのに、内番を一人でやったり付き添いなしで会議に行ったり。主は強い人間だ。つらくもなんともなかったのかもしれない。
そう思っていたのだけど。きょとん、と見開かれた瞳から、ぼろぼろと涙がこぼれていった。泣いていた。泣き顔なんて見たことがない。主は、ただの子どものように、ぼろぼろと泣いた。それに慌ててしまう僕に泣きながら笑顔を見せた。
「つらくなんかなかったです」
強がりだった。でも、つらかったと言ったら僕たちが気にするからと、気を遣ったのだろう。唇を噛む。こんなに弱い子を僕はないがしろにしていたのだ。戦術本を読み漁り、自分の祖父が残した戦績表を何度も見返し、僕たちの戦いを見続けた。彼女も必死に戦っていた。本当は泣き虫で、おしゃべりな、ふつうの子なのに。
体に血が付いていたけれど、気が付いたらその小さな体を抱き寄せていた。背中をさすって「ごめんね」と謝る。不甲斐なかった。あんなにも好きだった主が残してくれた宝物に気付けないなんて。彼女がいつでも僕たちを見ていてくれたことに気付けないなんて。それほどまでに僕たちは、主がいなくなった事実を受け止められていなかったのだ。屁理屈ばかり並べて彼女を認めなかった。彼女はそんな僕たちのすべてを受け止めてくれていたのに。どっちが子どもだ。
主はわんわん泣いたけれど、それを煩わしいとは思わなかった。弱い、けど、強い。それが本当の強さ。いつかに主が言っていたのを思い出す。こういう子のことを主は言っていたのかもしれない。
僕が彼女を主だと認めたわけではない。もう主はどこにもいない。彼女がこの本丸の、新しい主になった。僕も主も新たに歩んでいく。ただそれだけのことだった。
本丸急襲が終息し、一人一人の手入れをされながら全員が主と話をした。今までのこと、主のこと。いろいろなことをたくさん、時間をかけて。主は誰一人に対しても恨み言を言わなかった。それどころか全員に謝罪して回った。謝るのは僕たちだというのに。最後に手入れを受けた大倶利伽羅は、出てきてからも終始無言を貫いていたけれど前みたいな刺々しさはないように思えた。
全員の手入れが終わり、大広間に集められた。主も大広間に入ると全員が腰を下ろす。何の話をするのかと思ったら突然、主はその場で頭を下げた。
「私のような人間に審神者が務まるとは思っていません。皆様の主になろうなどとも思っていません。ですが、祖父が遺したこの本丸を守るため、お力をお貸しください」
そう言って頭を下げたまま黙る。突然のそれに全員言葉が出なかった。誰もが黙りこくってしまい、静かな空間が広がってしまう。彼女の手が小さく震えているのが見えた。何か言わなくては。でも、僕が言ったところで。そんな気持ちがあって何を言えばいいのかまとまらないままだ。
「あんたが」
静かな声。俯いたままの大倶利伽羅の声だった。
「あんたが頭を上げて、自分がここの審神者で俺たちの主だと言えば、俺はあんたを主と呼ぶ」
大広間が再び静寂に包まれる。大倶利伽羅は俯いたまま黙り、彼女は未だに顔を上げないままでいる。あまりに静かすぎる空間に耐えられなかったのか、鶴さんが「あー」と気まずそうな声を上げた。「俺も伽羅坊に賛成だな」と言った声に、次々と賛同の声が上がった。
その声に引っ張られるようにして、主がゆっくりと顔を上げた。涙でぐちゃぐちゃになった顔を少し拭ってから小さく息を吸う。鼻をすすってまっすぐ僕たちを見つめると、きゅっと拳を握った。
「私は、この本丸の審神者に、皆様の主に、なりたいです」
控えめな宣言。けど、彼女らしいといえば彼女らしいものだった。
こうして、彼女は僕たちの主になった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「え、僕が近侍?」
近侍である大倶利伽羅とともに僕の部屋を訪れた主に言われたのは意外な話だった。近侍を大倶利伽羅から僕に変えたい。ただただ驚きしかなく困惑していると、大倶利伽羅が大きくため息をついた。
「驚くことでもないだろう」
短い一言だったけれど、大倶利伽羅が珍しく僕を褒めていることだけは分かった。嬉しい、嬉しいのだけど、今までずっと大倶利伽羅が近侍をしていたので自分がやるなんて想像もしたことがない。うちの本丸の近侍といえば大倶利伽羅、というふうに完全にはまってしまっている。正直なところ部隊長すらあまりやったことがない自分に勤めるのだろうか。若干に不安を覚えつつ「選んでくれることは嬉しいんだけど……」と頬をかいてしまう。
「光忠さんさえ良ければ、ぜひお願いしたいです」
「う、うーん……そう言われちゃうと断りづらいなあ」
「すみません……」
「なんであんたが謝るんだ」
呆れた顔をして大倶利伽羅がまたため息を吐く。
「僕なんかでいいの?」
「えっ」
「えっ?」
「かっこよくて、強くて、頼りになるすごい人だからお願いしているんです。僕なんか、って変ですよ」
大倶利伽羅のため息が大きくなる。そんなに手放しに褒められると誰だって照れてしまうだろうに、大倶利伽羅は相変わらず呆れた顔で僕を見ていた。「お願いします」と頭を下げられたので慌てて頭を上げてもらう。真剣な眼差しに、負けた。
「やるからには格好よく決めないとね」
彼女は嬉しそうに「今日の夕飯後に発表しましょう」と言った。大倶利伽羅は「ようやくあんたの面倒を見なくて済む」と呟く。主はそれに対して少しへこんだような顔をしたけれど、大倶利伽羅がほんの少しだけ笑ったのを見て主も小さく笑った。
夕飯のあとに近侍が変更になったことを聞かされたみんなの反応は「なんか変な感じする」だった。この本丸はずっと大倶利伽羅が近侍だったから、あまりにその印象が強いのだ。それでも不満を言う人がいなくてほっとした。僕たちの本丸はこうして新しくなっていく。主が変わり、近侍が変わり、みんなの雰囲気が変わる。前よりも少し柔らかな雰囲気が流れる本丸を、僕は案外気に入っていた。それは恐らくみんなも同じだろう。
大倶利伽羅から諸々の引継ぎを受け、部屋も近侍部屋が主の近くなので移動することになる。大倶利伽羅は僕が使っていた部屋に移ることになった。主や他の人も手伝ってくれたおかげでそう大変な作業ではなかった。主の部屋がすぐ隣にある、というのは少し身が引き締まる思いだ。主からも仕事のことなどいくつか教えてもらい、余計に身が引き締まった。
「あのとき、光忠さんが私を”主”と呼んでくれたから、本当に主になれたんだと思います」
主は笑って僕の顔を見る。そうして「ありがとうございました」と小さく頭を下げた。僕も同じように頭を下げる。僕たちを見捨てずにいてくれたこと、僕たちを見限らずにいてくれたこと。どちらかというと僕たちのほうこそ”ありがとう”なのに。主は惜しげもなくこうして僕たちに感謝と謝罪をする。血を知らない。きっと無垢なのだろうと思う。それでも主は、僕たちと同じように戦ってくれる。刀を握れなくても、どんなに力がなくても。全力で戦っているのだ。だから僕はあのとき”主”と呼んだ。ただそれだけだから、別に僕は何もしていないのに。
「今までの分、たくさん話そう、主」
「はい」
「ごめんね、ありがとう、よろしくね」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
僕が主と恋仲になったのは、僕が近侍になってから三年目の冬だった。先に想いを告げてきたのは、主だった。政府へ出向いた帰り道、二人でいつも通り並んで歩いていたとき、突然言われた。突然の告白に固まってしまった僕を見て主は少し笑っていた。そのあとすぐに「想いを閉じ込めておくことがつらかったんです。困らせてしまってすみません」と言って頭を下げた。
僕は人間じゃない。刀と一緒になっても、主は幸せになれない。政府が刀剣男士と審神者の色恋を禁止しているわけではない。祝言を挙げた本丸もあると聞いていたし、それを否定するわけでもない。でも、そうだとしても。主は僕と一緒になって幸せになれるのだろうか。そんな疑問があった。
そう考えている時点で、ああ、僕は彼女に恋をしているのだ、と気が付いた。まっすぐ見つめてくれる瞳。どこまでも混じりけがなく澄んだ心。誰にでも伸ばす優しい手。そんな彼女に僕は恋をしていた。
「僕は君に幸せになってほしいよ」
主としてではなく、審神者としてでもなく。一人の人間として幸せになってほしかった。誰かと結婚して、かわいい子どもを生んで、二人で年を取って。でも、本丸にいる限り、僕たちの主でいる限り、それはむずかしいのかもしれない。結婚してから審神者になった人もいると聞いたけれど、審神者になってから結婚したという人は全員刀剣男士との結婚だった。それを幸せだと言う人ももちろんいる。けど、主はどうなのだろうか。悲しいときは泣き、楽しいときは笑う。怖いのに強がるし、痛いのに見ないふりをする。ちょっと強いふりをしているだけの、ふつうの女の子だ。ふつうの幸せがほしいと言ってもおかしくない。それなのに、僕を選んでもいいのか。僕は彼女しか知らない。彼女しか好きになったことがない。だから、僕にはその答えが出せなかった。
「光忠さんが幸せになることが私の幸せです」
「僕が?」
「はい。だから、光忠さんがどうしたら幸せになれるか、教えてください」
どこまでもまっすぐで、どこまでも混じりけがない。彼女の言葉はひどく僕の心を落ち着かせ、彼女の声は僕の心をとらえて離さない。
「僕も好きだよ、君のことが」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
主と想いが通じ合ってから一年後、祝言を挙げた。本丸のみんなが祝福してくれて、主は嬉しそうだった。それが僕も嬉しくてなぜだか少し泣いてしまった。祝言を挙げたことを政府に伝えたら意外にも祝福してくれたし、今後も期待していると声をかけられた。
本丸を引き継ぐ制度はその年に廃止された。やはり僕たちの本丸同様、刀剣男士が拒絶してしまう場合が多かったと聞いた。何人かの審神者が命を落とし、他の者は皆耐えられずに辞めたそうだ。以降本丸は審神者が引退、もしくは死去するまでを一区切りとし、審神者が交代する際にはすべての刀剣男士が一度刀解されることとなった。主は祖父である前審神者から本丸を引き継いで正常に本丸を運営した唯一の審神者となった。
僕たちの本丸が終わりを迎えたのは、僕と主が祝言を挙げてから五十年後だった。主は体が痩せ細り、ろくに何も喉を通らなくなった。水を飲むのもやっとの状態だったのに、いつだって僕の前ではにこにこと笑っていた。寝たきりになった彼女の死期が刻一刻と迫っていき、ついに、はらはらと雪が降るその日に、僕たちは主の死期を悟った。審神者が審神者として寿命を終えて本丸内で死ぬとき、刀剣男士にはそれがいつなのかはっきりと分かる。なぜなのかは分かっていないそうだがどの本丸も変わりはないのだそうだ。そしてそのとき、審神者は自分一人では死ねない。老死だとしても病死だとしても、時間遡行軍による死でない限りは一人では死ねない。放っておくと悪霊となってしまい永遠に苦しみ続けるのだと聞いたことがある。審神者は刀でしか死ねない。だから命が消えるその瞬間、誰かが刀で斬らなければいけない。そう、主が教えてくれた。それを聞いたときから僕が彼女を斬ろうと決めていた。
訪れたその日は大雪が降った翌日、きれいに空が晴れた日だった。本丸の庭には積もった雪がきらきらと光り眩しいほどで、冬の寒さなど思わせないほど生命力に満ちているように思えた。それでも、主は死ぬ。彼女はもうほとんど息もできていなかった。しわくちゃの顔にしわくちゃの手、冷たい肌、かすれた声。それでも、僕が愛した彼女であることに間違いはなく、僕の愛が消えることもない。愛している、ずっと。どんな彼女でも、どんなときでも、僕は彼女を愛している。ここで終わってしまう愛だとしても、僕は、彼女を愛している。時間が来る。最期に彼女が口を開いた。ほとんど声は出ていない。けれど、僕には届いた。僕には聞こえた。「愛しています」と。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あの、光忠さん、どうしたんですか……?」
「君が幸せになることが、僕の幸せだよ」
「え……?」
「君に幸せになってほしい」
「えっと、光忠さん?」
「君のことが好きだ、ずっと、ずっと、愛している」
光忠さんは涙で顔がぐしゃぐしゃになるのも構わずに泣いた。あまりにも悲痛なその言葉のどれもこれも身に覚えはない。けれど、聞いていないといけない気がして、ただただ光忠さんの言葉に耳を傾け続けた。光忠さんはまっすぐな瞳を私に向け続けてくれたけれど、やはりその言葉のどれにも思い当たる節はなかった。
光忠さんは泣き止むとすぐに恥ずかしそうな顔をして「ごめん、さっきお酒飲んじゃって」と頭をかいた。なるほど、少しほろ酔いだったようだ。苦笑いしつつ「びっくりしました」と言ったら「本当にごめんね」と申し訳なさそうな顔をされた。畳み終わった洗濯物を抱えて立ち上がると、光忠さんはにこりと笑う。「でも」と言った顔はひどく優しかった。
「君のことが好きだっていうのは、本当だよ」
とてつもなく懐かしい体温をしていた。私の両手を大きな手が包み込み、ほんの少しだけ強く握りしめられる。男の人にこんなふうにしてもらったことなんかない。それなのに、どうしてなのだろう。光忠さんのそれを嫌だと思わなかったし怖いとも思わなかった。懐かしくて、悲しくて、優しくて、つらくて。たくさんの感情が混ざり合ってぐちゃぐちゃになっている。でもそれが大切なものに思えて仕方ない。不思議でたまらない。光忠さんは、私にとってなんだというのだろうか。
「ごめんね、変なこと言って」
「い、いえ……」
「たくさん話をしよう。君のことを知りたいし、僕のことを知ってほしいんだ」
涙があまりにも美しく頬を流れていく。光忠さんの金色と紅色の瞳からこぼれ落ちる涙。それをぼんやり眺めていると、まるで色が流れ落ちたように、右目がきらきらと金色に輝いた。夢かと思うようなその光景に瞬きを忘れてしまう。あまりにも美しくて切ないきらめき。また一つ涙がこぼれ落ちたとき、ゆっくりと瞬きをした。
つらく、寂しく、愛しい日々だった。大好きなおじいちゃんが遺してくれた宝物。それが、みんなだった。あの本丸にはおじいちゃんの愛がこびり付いて取れない染みのように遺っていた。一目で決めた。私が必ず守ろうと。政府の人に私が継がなければ本丸は一度解体されると言われた。おじいちゃんは自分の死期を察していた。だから、大切な宝物を私に引き継がせようと、政府に取り合ってくれたと後で聞かされた。すぐに了承したし、迷いはなかった。おじいちゃんが愛したものを残したかった。けれど、それは私のエゴだったことをすぐに突き付けられる。誰も私を審神者だと、主だと言わなかった。悲しかった。寂しかった。けれど、当然だとも思った。私はこの本丸にいるみんなのことを知らない。どうやっておじいちゃんと過ごしていたのか。どうやって強くなったのか。何も知らなかった。戦績表をすべて見た。映像で残っていた分の戦いはすべて見た。おじいちゃんが遺していった戦術書をすべて読んだ。それでも、私はみんなのことを、知らないままだった。いくら知ろうとしてもいくら見つめ続けても、私は時間を共有できない。おじいちゃんの代わりにはなれないのだ。それを実感したとき、つらくて、悲しくて、寂しい、そんな気持ちをみんなが抱えていることに気が付いた。私はなんて無責任なことをしたのだろうか。自分を責めた。それでも、おじいちゃんが宝物だと言ったものを、自分から捨てることができなかった。
はじめて”主”と呼ばれたその瞬間、私にとってその声の主は、特別な存在になっていたのかもしれない。優しい声だった。大きな手だった。おじいちゃんの宝物じゃない。そのときはじめて、”私の”宝物になった気がした。燭台切光忠。私にとってはじめての刀剣男士であり、はじめて愛した男性だった。
「みつ、たださん」
「うん?」
「光忠さん」
「うん、どうしたの?」
「光忠さん……光忠さんですよね?」
「……主……?」
「燭台切光忠様、ですよね?」
苦しいほど強い力で抱きしめてくれた。頭が痛い。何かで糸を切られたような感覚がして、思わず大きく呼吸をしてしまう。光忠さんは何度も何度も私の背中をさすって「そうだよ」と繰り返した。
「ずっと待ってた。君が僕たちを待ってくれていたように、ずっと、ずっと」
泣いて、笑って、また泣いて。光忠さんは私が知っている光忠さんよりも、ころころと表情を変えるようになっている気がする。震える声は私のどこかにこびり付いて取れない染みのように遺る、優しい声となんら変わりはなかった。
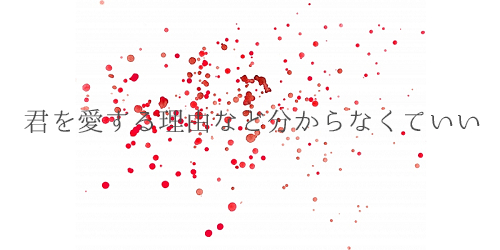
material by suisaisozai