※現代・転生パロディです。
※鶴丸国永短編「神様の涙を君は見たことがあるか」、鶯丸短編「あなたの紡ぐ文字が何よりも刃」等と同じ世界設定です。
※上記短編の本丸と今回の膝丸がいた本丸は同一本丸ですが、主は別人です。
※男主人公です。メインページにて男主人公名を入力していない方は入力をお願いします。
※同性愛要素を含みます。
※刀剣破壊、微妙に闇落ち表現があります。苦手な方はお気を付けください。
※鶯丸短編「あなたの紡ぐ文字が何よりも刃」の夢主が出てきます。セリフがあります。
※鶯谷=上記短編の鶯丸のペンネームです。
※髭切が既婚者の設定です。子どもがおり、名前はありませんがセリフが少しあります。
※上記二作と違い、膝丸視点で話が進みます。
※これまでのシリーズとは違い、ハッピーエンドではありません。
朝の通勤ラッシュは未だに慣れない。吊り革をつかんだ手は汗ばむし、体のあちこちに他人が触れるし、理不尽に女性に睨まれることもある。今日も今日とてため息をつき、居心地の悪い思いをしつつ電車に揺られている。
自宅の最寄り駅から約二十分ほど電車で揺られ、職場の最寄り駅で降りる。そこから歩いて約五分ほどで勤務している出版社に到着する。セキュリティゲート前に立っている警備員はもう顔見知りだ。笑顔で挨拶をされたのでこちらも挨拶を返す。社員証を出してゲートにかざして中へ入ると、ちょうどやってきた部下にも挨拶をされた。最近どこか晴れやかな表情をするようになった部下は片手に茶封筒を抱えている。分厚いそれは担当している作家の原稿だろう。彼女が担当する作家はうちの出版社で一番人気で、本の売れ行きはここ最近ずっと絶好調だ。少し前までは原稿を締め切りギリギリまでにしか渡してくれないと嘆いていたが、それも解消されたらしい。彼女の晴れやかな表情とそれが何か関連しているのかは知る由もない。俺はただの上司なのだから。
部下とともに部署へ入るとその場にいた全員が挨拶をしてきた。それに返してから自分の席につく。席についてすぐに部下の一人が書類に判子を求めてきた。次に行われるイベントの確認書類だ。各書店にも仮通達が終わっているようで、あとは俺の判子さえあればいいとのことだった。目を通して昼までに渡すと返事をすると、部下はほっとしたように席へ戻って行った。
「膝丸さん、内線十番です」
部下の声に返事をしてから電話を取る。「膝丸です」と言うと電話の向こうから相変わらずのん気な声で「髭切だよ~」と聞こえてきた。
「兄さん……今度は何をした……」
『内線かけただけでひどくないかな?』
髭切、と名乗ったのは俺の兄である髭切友である。名字が違うのは複雑な事情、まあ、簡単に言えば異父兄弟というやつだ。母と兄さんの父が離婚した際、父親に親権が渡ったのだという。そのため兄さんの名字は髭切のままとなり、数年が経ってから母が再婚した。そこで産まれたのが俺だった。膝丸緑として十五年間、計り知れないほどの愛情を注がれて育ったと自負している。そんなある日、突然現れたのが髭切友だった。その半年前、母の元夫が事故で亡くなったそうだ。母の元夫は再婚をしていなかった。髭切友は家族を失い、産みの親である母の元を訪れたのであった。俺の両親は髭切友を家族として迎え入れることを決め、俺にも紹介をしてくれた。しかし、髭切友は決して「膝丸」になろうとはしなかった。母がどれだけ説得しても彼は「髭切」の名を捨てようとはしなかった。家族なのに名字が違う俺たちははじめこそおよそ「兄弟」とは呼べない仲だった。俺たち、というよりは、俺個人の問題だったかもしれないが。兄さんはしつこく俺に構った。勉強を教えてくれたり遊びに連れて行ってくれたり。はじめは俺に懐いてほしくてそういうふうにしていたのだと思っていた。けれど、途中からどうやらそうではないと気が付いた。髭切友という人間は、もともとそういう人間性を持った人間だったのだ。誰にでもそういうふうに人懐こく接する。それに気が付いた瞬間、なぜだかすんなり髭切友を兄であると受け入れられた自分がいた。
ただ不思議なことに兄さんは俺のことを決して下の名前では呼ばない。必ず「膝丸」と名字を呼ぶ。いくら両親に注意されてもそれをやめないのだ。マイペースな兄さんらしい。もうすっかり慣れてしまった。
『悪いんだけど、今日うちの子のお迎え頼めるかな』
「……」
『今日は帰りが遅くなりそうでね』
「兄さん、プライベートな内容は内線でかけるなとあれほど……」
『じゃあ頼んだよ~』
ぷつっと切れた電話に大きなため息が漏れこぼれた。
兄さんは五年前に学生時代から交際していた女性と結婚をした。マイペースで人に合わせることを知らない兄さんには少し勿体ない気もするほど家庭的でいい女性だ。ただ、子どものころから体が弱いらしく、出産はかなり危険な状態が続いた。無事に産まれた子どもは女の子で、顔は母親似、中身は父親似だった。元気にすくすくと育ち、今は幼稚園に通っている。奥さんは今は体調を崩して検査入院をしているが、異常はないらしい。入院も兄さんが奥さんを言い包めた結果の処置だったようだ。奥さんが入院しているため今は子どもと二人なのだが、いかんせん、兄さんに家庭的な一面は一切ない。奥さんが不安そうなので仕方なく俺がたまに面倒を見に行っているのだが。それがいけなかったのか、先ほどのように割とこき使われることも多い。
受話器を置いてからもう一度ため息をこぼしていると、近くにいた部下に「髭切さんですか?」と苦笑いをされた。それに頷くと「仲が良いですね」と他の部下からも笑われてしまった。少し気恥ずかしい気持ちになりつつも、兄さんとの関係をそう言われることは素直にうれしい。「まあな」と苦笑いをこぼしながら返す。すると今度は「膝丸さん、外線二番、長尾様です」と声をかけられ、また電話を取った。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あら、お久しぶりですね」
「いつも兄夫婦がお世話になっています」
幼稚園の先生に頭を下げつつ挨拶をする。ちょうど出てきた髭切家の大切な娘は俺を見るなり「パパは?」と明るく笑って首を傾げた。仕事で遅くなる代わりに自分が来たことを伝えると、ぱあっと余計に明るい笑顔を見せて「今日はハンバーグがいい!」と俺の手を握った。兄さんは基本的に料理ができない。そのため俺が面倒を見に行かない日はピザや寿司などの出前を取って食事を済ませることが多い。娘はそれがかなり不満らしく、俺が来る日はこうして食べたいものをリクエストしてはご機嫌になる。そういう姿を見ると本当に子どもはかわいいものだと思うし、いつか自分も結婚をして子どもがほしいとも思う。
こんなことになるなら車で出勤したというのに。内心兄さんへ若干の不満を漏らしつつ、しっかり小さな手を握って電車に乗る。奥さんが家にいるときは決まった時間に出る送迎バスに娘が乗って、バス停まで奥さんが迎えに行くのだが。奥さんが入院している今、送迎バスの時間に父である兄さんは仕事で間に合わず、こうして幼稚園まで迎えに行く日々が続いている。兄さんは普段から車通勤をすることが多いのだが、俺は兄さんから子どもの迎えを頼まれたときしか車通勤をしない。こういうイレギュラーのときは小さな娘さんには悪いが、電車で家に帰ることになってしまうのだ。
電車の中で無邪気に話す声を聞く。子どもが特別好きというわけではないが、兄さんの子どもということもありかわいいものだ。一生懸命に今日あったことを話すそれに相槌を打っていると、あっという間に駅に到着した。駅から兄さんの家までは距離がある。タクシーで家までは向かうことが常だ。タクシーに乗っているとき、携帯電話に着信があった。画面を見ると兄さんからだったので、娘に電話を渡すと喜んで通話ボタンを押した。
「パパ!」
『おやおや、僕は弟にかけたんだけどな~。パパだよ~』
「パパだよ!」
「ああ、そうだな。……もしもし、どうした?」
『今から帰るけど、もう駅は出たかな~と思って』
「ついさっきタクシーに乗ったところだ」
『ありゃ、ちょっと遅かったね。ごめんごめん』
全く気持ちのこもっていないその謝罪にため息を漏らしつつ、「今日はハンバーグだそうだ」と告げると兄さんは「了解~」と言ってから電話を切った。
髭切家につくと、渡されている合鍵を使って中に入る。奥さんが入院してからは掃除があまりされていないらしい。そこそこ散らかったその部屋にため息が漏れつつも中へ入る。もう一人で着替えられるらしい娘は幼稚園の制服を脱ぎ散らかしつつ自分の着替えを引っ張り出した。俺はその横で鞄をソファに置き、背広を脱いでネクタイをほどく。軽く腕まくりをしてからキッチンに入り手を洗わせてもらう。出前ばかり取っているためか、多少の洗い物は残されているがキッチンだけはきれいなままである。とりあえず冷蔵庫の中を覗くと、前に買っておいた食材がまだ残っている。食材は揃っているので買いに出かけなくて良さそうだ。
「ひざまる! できた!」
「ん、ああ、上手に着替えられたな。偉いぞ」
父の真似をして俺のことを膝丸と呼ぶことには若干苦笑いだ。嫌な気がしないのが不思議だが。着替えられたついでに「着替えができて偉いな。もう立派なお姉さんだ。なら片付けもできるか?」とけしかけてみる。予想通り「できる!」と元気に返事をしてから自分のおもちゃを片付け始めた。これでつまらないとぐずりだすことはないだろう。安心してハンバーグ作りに取り掛かることができる。
兄さんが帰ってきたのはちょうどハンバーグが焼き終わったときだった。すっかり自分のおもちゃを片付け終えた娘がいち早く反応して玄関に出迎えに行くと、そちらのほうからうれしそうな「ただいま~」という声がした。それに笑いつつハンバーグをひっくり返す。兄さんはリビングに入ってくるなり「いやあおいしそうなにおいだ」と言った。
「悪かったね、急で」
「いや、大丈夫だ。それより何かあったのか?」
「ちょっとね」
恐らく接待か何かだろう。兄さんが苦手とする業務内容であったことは表情を見ればなんとなく分かる。同じ会社に勤めている俺たちだが、大きな会社のまったく違う部署にいるので何をしているのかはちゃんとは把握していない。ただ、月に二、三度ほど兄さんは接待をしなければいけないらしい。兄さんはそういうのを苦手としているらしく、接待がある日はなんとなく顔が疲れている気がする。娘もそれを敏感に察したようで、兄さんに「パパいい子いい子!」と労いの言葉をかけている。
「いやあ疲れも吹っ飛ぶね~」
「ならよかった。兄さん、悪いが作り終わったら今日はもう帰るから片付けは任せるぞ」
「珍しいね、食べていかないのかい?」
「書類に目を通しておきたくてな」
焼き終わったハンバーグを皿に移す。作っておいたソースをかけて野菜を添え、炊いておいたご飯をよそう。喜びつつ取りに来た娘に「落とすなよ」と注意を促しつつ皿を渡すと、しっかりとテーブルまで運んでくれた。箸やらお茶やらを用意してからソファに置いたネクタイを結び、背広を着ていると「帰っちゃうの?」と寂しそうな声で聞かれた。それに少し後ろ髪を引かれる思いになりつつ「また来る」と返しながら頭を撫でてやる。「絶対だよ」と笑った顔は、どこか兄さんに似ているように思えた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
髭切家を出てまたタクシーを捕まえ、駅に到着した。次の電車は何分後だろうかと時刻表を見上げていると、視界の隅っこで何かが動いたのが見えた。何気なくそちらに目をやると、駅と直結している商業施設の入り口付近でうずくまっている人がいた。学生服を着ているので男子高校生だろう。今時の子は遅くまで遊び歩いているのをよく見るので友人と待ち合わせでもしているのだろうか。小さくまるまって座り込む姿はどこか不審にも見える。けれども、まあ、赤の他人である自分が関わる理由はない。
そちらから目を逸らし時刻表の確認を終えてから、ICカードのチャージをして改札へ向かう。そのとき、また先ほどの男子高校生が視界に入った。先ほどと違い顔を上げている。長い前髪から覗く瞳はどこか揺れていて、恐ろしいほど白い肌がところどころ黒ずんだ紫色になっている。それが恐らく打撲痕であることはすぐに分かった。見た目に似合わず血の気の多い学生なのだろうか。けれど、なぜだか俺は彼がそんな人間ではないと確信に近い推測を持っていた。
「こんなところでどうした。風邪をひくぞ」
自分でも驚いた。自分で知らない間にその男子高校生に近付き、声をかけていたのだ。目を丸くして顔を上げた男子高校生の前髪が左右に流れる。影を落としていた顔が光の下にさらされると、思っていたより広範囲に及ぶ痛々しい打撲痕が露わになった。
それよりも驚いたのが、彼が、驚くほど女顔だったことだ。制服を着ていなければ男だとは誰も思わないだろう。大きいアーモンド形の瞳、長い睫毛がその瞳の形をより良く整えているように思える。打撲痕をないものとすれば白くて光を放つような肌はおよそ男のものとは思えない。少し長めのぼさぼさの黒髪は、櫛でとかせば恐らく艶のあるきれいな髪になるだろう。
大きな瞳がどこか危うげに下を向く。きゅっと膝を抱えて丸くなった体が痩せていると気が付いたのは、制服がずいぶんぶかぶかなせいだ。
「電車賃がないのなら貸すが」
「…………いえ」
「怪我をしているようだが、交番に行くか?」
「…………いえ」
口数は少ないが、重傷というわけではないらしい。彼の前にしゃがみもう一度声をかける。「困っているなら力になるが」と言ってみると彼は押し黙ってしまった。その様子から、誰かに救いを求めたいという様子は見てとれた。微かに震える指先。爪は伸び切ってところどころ割れてしまっている。着ている制服もよく見ればところどころ破れていたり汚れていたりしており、彼が平穏な生活を送っていないことは明らかだった。
「誰か人を待っているのか?」
「…………いえ」
一向に話そうとはしない。彼は顔を俯かせたまま体を小さくして静かに呼吸をするのみだ。コートもマフラーも何も持っていないらしいが、今は冬だ。そろそろ初雪が降るだろうと言われているほど冷え込んできている。駅の中とはいえ暖房が効いているわけではないし、こんな恰好では風邪をひいてしまうかもしれない。何より駅も終電が終わればシャッターが下ろされてしまう。こんなところにうずくまっていると駅員から追い出されてしまうだろう。そうなると外に放り出されることになるし、深夜になればもっと冷え込んでくる。そんなことになれば補導員に保護してもらえるかもしれないが、恐らく彼はそれを望まないに違いない。
「このままここにいると警察や補導員を呼ばれるかもしれないが、それでいいのか?」
「……」
「それか俺のお節介に付き合うか、どちらのほうがいい?」
苦笑いをしてみる。彼は俯かせていた瞳をこちらに向けて、どこか怪訝そうな顔をした。それはそうだろう。見ず知らずの男からこんなにもしつこく声をかけられるなんていい気はしないはずだ。そうとは分かっているのだが。なぜだろうか、彼のことを放っていけない自分がいた。
「俺は膝丸だ。ここから五つ先の駅の近くに住んでいる」
「……、です」
「か。家に帰れないのなら寝る場所くらいは提供できるが、どうする?」
「……お願いします」
「なら移動しながら軽く話は聞かせてもらうぞ」
「…………はい」
手を伸ばす。震える手がこちらに伸びると、恐る恐る俺の手をつかんだ。その手は驚くほど冷たくて、男とは思えないほどに小さかった。
鞄はもちろん、携帯電話や財布なども持っていなかったに電車賃を貸し、俺の家の最寄り駅へ向かう。立ち上がったは男にしては少し身長が低く、体はかなり華奢だ。俺の少し後ろをついて歩くその足はほんの少し庇うような歩き方をしている。顔だけではなく体のあちこちを怪我しているようだ。それにため息をつきつつホームへの階段を上がりきる。電車が来るまであと十分ほど。それまでホームにあるベンチに座って話を聞くことにした。
は高校三年生の受験生だった。どこかで見たことのある制服だと思っていたが、通っているのはこの近くにある男子校。兄さんが通っていた母校だった。家は高校の近くにあり、両親と三人暮らしだという。家族関係がうまくいっておらず、所謂虐待を受けていた。顔の痣は父親から殴られたもの、庇っている右脚は母親に蹴られたものだとは淡々と語った。家にあるものを触ったり使ったりすると暴力を振るわれるのだそうで、爪が長いのはそのせいだった。制服がぼろぼろなのは学校でも同級生たちからいじめを受けているからだとさも当然のように言う。教師には相談したが、昨今はいじめがあるといろいろ世間の目が気になることもあり、聞かなかったふりをされたとは言った。
「死んでしまおうとしても、怖くて、できなくて」
長い黒髪の隙間から見える瞳が不安げに光っている。はそれきり口を閉じて、じっと何かに耐えている様子だった。
の話から恐らく心配はないのだが、このままを家に泊めて朝家まで送って行ったとして、両親が警察に言えば誘拐犯ということになったりするのだろうか。ぼんやりと頭の中でそんなことを考える。ふつうの大人であればこういうとき、どういう行動をとるのだろうか。恐らく警察に連れて行くとか、家に送り届けるとか、そういうのがふつうの大人が取る選択だと思う。だが、どうしても俺にはそれが正しい選択だとは思えなかった。頭では分かっているのだが、どうしてもそうしたくなかったのだ。
「好きな食べ物はあるか」
「え」
「好きな食べ物はあるかと聞いている」
「…………ハンバーグ」
「ふっ」
思わず笑ってしまった。幼稚園の子と同じ食べ物が出てくるとは夢にも思わなかったが、がそんな理由を知る由もない。不思議そうな顔をしつつもなんだか恥ずかしそうに視線を逸らされてしまった。それに謝罪しつつ理由を一応説明してみる。はその話をぼんやりと聞いていた。
やってきた電車に乗り込む。を一番隅に座らせてからその隣に腰を下ろした。人はまばらだがどうもは人の目を気にしているらしい。怪我をしているし、暮らしている環境から臆病になっているのだろうか。話を聞こうにも電車の中だと人目が気になって恐らくあまり話をしてくれない気がしたので、あえて電車の中は何も聞かずに世間話をした。あまり話をするのは得意ではないのだが、はただただ黙って静かに話を聞いてくれている。退屈しているのかもしれないと少し焦ったが、不思議と柔らかく見える表情に安心した。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「適当に座っていてくれ。食事の準備をする」
はきょろきょろとまるで警戒するように部屋を見渡す。俺の言葉に静かに頷いたものの、ソファに座る様子はない。他人を警戒するとあんなふうになるのだろうか。少し同情するような気持ちになりつつ、「ソファに座っていろ」と声をかける。は俺の声に肩をびくつかせたものの、大人しくソファに腰を下ろした。その様子に少しほっとする。
冷蔵庫を開けてハンバーグを作るための食材を取り出す。家族以外の人に料理を作るのははじめてだが、口に合うだろうか。少し心配があったがなんとなく大丈夫に思えるのは自賛がすぎる気がする。咳払いしてから手を洗い、気を取り直して夕飯の支度にとりかかった。
ソファに座った今にも崩れそうな背中をちらりと見る。は俯いたままぴくりとも動かない。自分の家にいるときも、あんなふうにしていたのかもしれない。どこまでに話を聞いていいのか分からないが、ここまでお節介を焼いてしまったのだ、それなりには話を聞いても怒りは買わないだろう。
「あ、あの」
驚いた。ここまで自分から話すことのなかったが俺に声をかけたのだ。ゆっくりとこちらを振り返った顔は、とても怯えているように見えた。
「どうした」
「……ご、ご迷惑を、おかけして、すみません」
たどたどしく紡がれた言葉はこっちが痛くなるほど震えている。小さく頭を下げたはそのまま動かなくなる。はっとして「気にするな」と返したが、それでもは頭を下げたままだ。
「ところで家はどこなんだ? 明日家まで送って行く」
「……駅で大丈夫です」
「そう言って家に帰らないつもりだろう。家が嫌なら他に頼れる親戚はいないのか?」
「……いない、です。僕は、その、養子なので」
「…………そうか。すまない」
複雑な家庭環境にもほどがある。若干頭を抱えつつも、がぽつぽつと話し始めたのを静かに聞く。なんでも生まれてすぐには両親を亡くし、児童養護施設に入ったそうだ。そこで今の家族である人たちに養子として選ばれ、数年は幸せに暮らしていたという。しかし、幸せだったのはほんの数年。が引き取られてからその短い数年の間に、その家には変なことがたくさん起こったのだという。まずは暮らしていた家が放火の被害に遭った。全焼は免れたものの、家はほぼ焼け落ちてしまい結局新しい家へ引っ越したそうだ。その次は母方の祖父母の死去。元気だった二人がぷつりと糸が切れたように亡くなり、母親はそのせいか精神を病んだそうだ。その次は父親が勤めていた会社の倒産。そのころから二人の喧嘩が絶えなくなり、毎日家の中は怒鳴り声で満ちていたとは言った。そんなある日、その怒鳴り声の矛先がに向いた。「お前が来てからこの家はおかしくなった」、「疫病神め」、「あんたなんか引き取らなきゃよかった」。かつては優しかった両親はを罵倒したという。最初は声だけだったそれは日に日にエスカレートしていき、ついには暴力になった。食事も満足に与えてもらえなくなり、家の中では居場所がなくなっていった。ぼろぼろになっていくのことをクラスメイトは気味悪がり、仲の良かった人も寄り付かなくなったという。最初は触れないように避けていた人たちは、やがて両親と同じようにを厄介者として扱うようになった。そうしていじめにまで至った、というわけだった。
けれど、どれほど暴力を振るわれたとしても自分を引き取ってくれた人たちに間違いはない。は遠いどこかを見るような目をしてそう言った。だから憎むことができない、と。
「その人たちのことがまだ好きなのか?」
「……好き、かは、分からないけど……嫌いにはなれないです」
そう呟いた。の瞳は、見ているこちらが悲しくなるほどの暗い闇を放っていた。その瞳にこんなにも胸が痛くなるのは、同情しているからなのだろうか。そうだとすれば、どうにか助けてやりたいと思うのも、その感情からなのだろう。
「本棚の横にある箪笥の左側、上から二番目」
「え」
「いいから開けろ」
「は、はい」
恐る恐るソファから立ち上がり、俺が言った引き出しを開ける。は俺のほうを見て「あの」と困惑した様子だ。「奥にある鍵を出せ」と言えばすぐにそれを見つけ出して「これですか」と首を傾げた。その仕草がやはり女性らしく見え、なんだかちくりと胸の奥が痛んだ。
「この家の鍵だ」
「……えっと」
「お前にやる」
「え?!」
お、と思った。はじめて大きな声を出した。それに少し笑っているとは焦った様子で「もらえません!」と鍵を引き出しにしまってしまう。フライパンに油を引きながら「やると言ったらやる」と返すが、は「もらえないです!」引き出しを閉めた。この姿がの本来の性格なのかもしれない。余計に笑ってしまうとは恥ずかしそうに俯いてしまった。
「今までどう生活していたのかは知らないが、休める場所くらいあったほうがいいぞ」
「で、でも」
「基本的に仕事で家にいることは少ない。それでもいいなら好きに休みに来ればいい」
「……でも」
「大人に甘えるくらい、罰は当たらないと思うぞ」
きゅっと唇を噛んだ。はふらふらと視線を泳がせて、最終的にまた下に向けてしまう。しばらく黙ってから視線を持ち上げると「すみません」と言った。
「どうしてそこまでしてくれるんですか」
「え」
「今日会ったばかりの、変な子どもに、どうしてそこまでしてくれるんですか」
「…………さあ、どうしてだろうな」
はなんだか間抜けな顔をした。驚愕、という二文字が似合うような表情を見て、実は表情豊かなやつなのだと思った。
「あ、そういえば。すまない、気が利かなかったな。風呂、廊下を出て左にあるから使ってくれ。服は……俺のだと大きいだろうが、洗面所に乾いたものがあるから適当に着てくれ。洗面所の引き出しの一番下に新品の下着もあるから好きなのを着ろ」
は俺の言葉に何かを言いかけたが、押し黙ってから少し考える。そうしてしばらく間を置いてから「すみません」と言って頭を下げた。そこはふつう、ありがとう、というところなのだろうが。気付かれないように少し笑ってから「分からないことがあれば聞いてくれ」とだけ声をかけておいた。はもう一度頭を下げて、風呂へ向かった。
風呂から上がったら爪切りを出してやろう。髪が伸び放題だから切ってやりたいところだが、そういうのは不慣れだ。本当であれば散髪に連れて行きたいところだが、恐らく金がかかるとなるとは遠慮するに違いない。仕方ないので意外とそういうのが得意な兄さんに頼んでみようか。
いろいろなことを考えつつ、やはり考えてしまう。いくら虐待を受けているからとはいえ、未成年者を勝手に保護して家に連れ帰ったというのは、誘拐になったりするのだろうか。騙したわけではないし、何か危害を加えたわけでもないが。そうなればご両親に連絡くらい入れておいたほうがいいのだろうが、連絡を入れれば世間体やらなんやらを気にして連れ戻しに来るかもしれない。そうなればは余計にひどい仕打ちを受けるだろう。そう思うと自分がどうしればいいのか分からなくなる。俺が親戚や既婚者であれば、あちらと交渉して引き取れたかもしれないが。血縁もない独身の男には厳しい話に違いない。……待て、俺は、もし引き取れる立場だったとしたら、を引き取ろうとしたのか? 会ったばかりの、ぼろぼろの少年。それだけしかまだ分からないというのに。
うだうだと考えているうちにハンバーグが出来上がる。昨日の残り物のポテトサラダを取り出して盛り付けつつ、白飯をレンジで温める。電気ケトルのスイッチを入れてからインスタントの吸い物を取り出す。ちょうどそのとき、風呂場の扉が開いた音が聞こえた。ハンバーグやポテトサラダを盛りつけた皿をテーブルに置いていると、がリビングへ入ってきた。
「ちょうどできているぞ」
「……すみません」
「ああ、その前に」
引き出しから爪切りを取り出す。それを手渡すと、は恐る恐るではあったが受け取ってくれた。けれど、結局爪切りを使う手があまりにも不器用に見えたので、また爪切りを返してもらって切ってやった。
爪を切り終わってから席につかせ、手を合わせる。も戸惑いつつも手を合わせて二人で「いただきます」と言う。髭切家で作ったものより小さくなったが、焼き加減はあちらよりも上手くいったか。そう自画自賛しつつ箸を進めるが、が一向に手を付けない。「どうした」と聞くとは「あ、いえ」と言いつつ、どこか震える箸をハンバーグに伸ばした。一口サイズにしてからそれを箸でつかみ、ゆっくりと口に運ぶ。口に合うだろうか。少しそわそわしながらその様子を見ていると、がゆっくりとハンバーグを噛みしめた。
「大丈夫か、口に合うか?」
「……」
「あまり人にふるまうことがないから自分好みの味になってしまっていてな、口に合わなければ残してくれ」
「……い」
「なんだ?」
「おい、しい」
そう、ぽろぽろと、は泣いた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
食事を終えて歯を磨いてからは座ったまま眠ってしまった。その寝顔はどこにでもいるふつうの子どものようにかわいらしく、幼く見えた。
それにしてもやはりずいぶんとかわいらしい容姿をしている。声も男にしては少し高いし、よく見なければ男だとは分からない。風呂に入ってきれいになった黒髪は思った通り艶がある。長い睫毛はきれいに上を向いており、唇は風呂に入ったおかげなのか美しい赤に染まっている。本当に、女のようだ。
俺はあまりそういう話を信じないが、前世というものが本当にあるのなら、きっとは女だったに違いない。それもとびきり美しい女だっただろう。けれど、今世は男に生まれてきて正解だった。こんな環境でもし女だったら、どんなひどい目に遭っていたのだろう。そう考えるとぞっとした。
起こさないようにを抱き上げると、思っていた以上に軽くて驚いた。本当に男子高校生とは思えない。ろくに食事を与えられていなかったとは言っていたが、自分で調達すらできない環境だったのだろうか。恐らく小遣いももらえていないだろうし、保護者の許可なしでアルバイトもできないだろう。そうなれば完全に保護者としての役割を果たしていないのだし、離縁することも難しくなさそうだが。けれど、もし離縁が成立したとして、は一体どこへ帰ることになるのだろうか。児童養護施設に戻るのだろうか。けれど、大抵の児童養護施設は十八歳未満までが入所の対象となっている。高校三年生のは帰る家をすぐに失くすことになるのではないだろうか。
その〝帰る家〟を、ここだと、思ってくれるのであれば。そこまで考えてため息をつく。本当に、何を考えているんだ、俺は。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
翌朝、目が覚めるとはもう、どこにもいなかった。洗わないままシンクに置いておいた食器がすべて洗われていたり、貸した服が洗濯機に入っていたり。律儀な子どもだと少し笑みがこぼれた。ただ、何の言葉もないその別れに、ひどく体が冷える寂しさを覚えた。この感覚、どこかで。一体どこでだっただろうか。けれど、いつかに、同じような寂しさを覚えたことがあった気がする。
いつも通り出勤すると、いつも通りの業務がはじまる。今月発売された新刊の売れ行きの報告を受け、会議の日程を確認され、諸々の書類を手渡される。淡々と進んで行く時間の中で、俺だけがなぜか昨日の夜で立ち止まったままになっている。は今、どこで何をしているのだろうか。高校はそろそろ冬休みに入る。そうなれば、ますます、はどこへ帰るのだろう。いつ雪が降ってもおかしくないほど寒いこの空の下で。は拠り所を見つけられているのだろうか。寂し気に揺れる瞳の色が脳裏にこびりついて取れないまま。ぼんやり仕事をこなしていると、昼休憩を知らせるベルが鳴った。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あ、膝丸さん! ちょうどよかった!」
マンションの入り口で大家に声をかけられた。どうやら俺を待っていたらしく、急ぎ足で駆け寄ってきたかと思えば腕を掴んできた。困惑しつつも大家に「もうずっと電話したんですよ!」と怒られてしまい、そういえば今日はあまり携帯を見ていなかったと反省する。「すみません」と謝ると大家は「いいから早く早く!」と歩き始める。そのまま引きずられるように管理事務所に入ると、「あ」と不安そうな声が聞こえた。
「この子、ずーっと膝丸さんの部屋のドアの前に座り込んでてね! お隣さんが声をかけても反応しなかったし不審者だって私に連絡してきたんですよ!」
俺の反応を待たないままに大家は「でも若い女の子だし、怪しい子なのか膝丸さんの知り合いか分からなくてね」と苦笑いをこぼす。その言葉に思わず笑ってしまう。女の子、って。どう見ても男子生徒用の制服を着ているにも関わらず、そう勘違いされてしまうのか、この子は。笑う俺を大家が不思議そうな顔で見ている。
「知り合いの子です。あと、女の子じゃなくて男の子ですよ」
驚く大家は置いておいて、なんだか不安げに座っているのほうを見る。は小さく会釈したが言葉は発さない。恐らく知らない人にたくさん関わって怯えているのだろう。
大家とお隣さんに騒がせたことを謝罪したのち、を連れて部屋へ入る。が着ている制服は昨日洗い終わったときと同じようにきれいなままだ。今日は学校へは行かなかったのだろうか。それでいい。そう思う自分がいた。
昨日と同じようにをソファに座らせ、電気ケトルのスイッチを入れる。はなんだか気まずそうに背中を丸めていたが、食器棚からコップを出す俺の背中に「あの」と声をかけた。
「本当に、甘えても、いいんですか」
そう、恐々と不安そうに、そして何より恥ずかしそうに。白い肌がほんのり赤みを帯びているのに気が付く。無性にそれがうれしくて、俺までなぜだか恥ずかしい気持ちになってしまった。一つ咳払いをしてから「そろそろ冬休みだろう」と聞くと、は小さく頷いてから「明日終業式です」と言った。完全に不登校というわけではなく、ちょこちょこは行っているらしい。
「なら冬休みの間、うちに泊まるか?」
「え」
「ただ家の人に一応友達の家に泊まる、くらいは伝えたほうが、」
「それは、あの、大丈夫、です」
「どうして分かる?」
「…………もう、一週間、家に帰ってないけど、何もない、から」
「一週間?!」
思わず大声を出してしまった。びくっとの肩が震えたので謝っておく。一週間もの長い間、家に帰らずにいただと? 鞄も持っていなければ携帯電話や財布を持っている様子もない子どもが、一体どうやって過ごしていたというのか。それを詳しく聞くとは淡々と説明してくれた。ある日は公園で野宿をし、ある日は高校の中で息を潜めて過ごし、ある日は廃墟となった建物の中で過ごしたという。そんなふうに一つの場所に居つくことはせず、点々といろんなところで過ごしてきたのだそうだ。それでも家の人間が捜索願を出している様子はなく、家の前を通ってみたらしいが一切何の変化もなかったそうだ。そもそも家にいたときも身を潜めて過ごしていたそうで、家にいようが外にいようが関係がないとは小さく笑った。
「でも、さすがに、その……冬休みの間ずっとは、めい、」
「迷惑じゃない。泊める代わりに働いてもらうつもりだぞ」
「働く……?」
「料理ができないなら洗濯や洗い物なんかの掃除をしてもらおうと思っているが、どうだ?」
沸いたお湯を茶っぱを入れたポットに注ぎつつの様子を窺う。は呆然としたままこちらを見ている。口を開けたまま固まってしまったの前にコップを置くと、ようやくはっとした様子でが喋った。
「そ、そんなことで、いいんですか」
「社会人からすれば掃除はなかなか体力を使う大仕事だぞ」
「でも、」
「二択だ。泊まるか泊まらないか。どうする?」
引き出しを開けて、昨日が受け取らなかった鍵を取り出す。それを先ほど置いたコップの隣に置いてもう一度「どうする?」と顔を覗き込む。はじっと鍵を見つめて押し黙って考え始めた。簡単に選んでくれればいいのに。そう思いつつ顔をじっと眺める。何度見てもきれいな顔をしている。大きな瞳、長い睫毛、白い肌、赤い唇、艶のある黒髪。女に生まれていたら、たぶん、下心を抱いていたほど好みだ。……何を考えているんだ、俺は。なんだか悪いことをしてしまったような気がして思わずから目をそらしてしまった。
「お願いします」
「え」
「と、泊めてください」
赤い顔。じっと俺の瞳の中を覗き込むような瞳が、たしかに俺を頼っていた。それが、恐ろしいほど、うれしくて。
「そうと決まれば行くぞ」
「え、どこに、ですか?」
「買い物だ。やっぱり俺の服だと大きすぎただろう」
そう笑うと、はじめて、どこか楽し気に笑ってくれた。警戒心のない、緩んだような顔。どこか懐かしさを覚える顔に俺までほっとした。
そのあとを洋服屋や日用品を扱う店に連れ回した。は家から持ってきたらしい財布を出そうとしてきたがすべて遮った。何かを買うたびレジの前だというのに頭を下げる姿には少し参ってしまったものだ。服屋で店員にどんなものがいいか聞いた際、女性もののコーナーの方へ連れていかれてしまったのは予想通りだった。はどうやら女に間違えられることには慣れている様子で、淡々と「男です」と店員に告げている姿に笑ってしまった。洋服を数着買ってから諸々の日用品を揃え、最後に食材を買ってまた家に帰る。は何度も何度も「すみません」と俺に頭を下げたが、それがどうも心地が悪い。
「泊める条件を一つ追加しよう」
「えっ」
「〝すみません〟、禁止だ」
「え、でも、」
「代わりに〝ありがとう〟をくれるとうれしい」
はぽかん、としつつも「はい」と頷く。たった一日でずいぶん信頼してくれたものだ。それに喜びつつ買ってきたものを、用に空けた箪笥に仕舞っていく。それを手伝うの横顔はどこかうれしそうだ。
それを境にはよく笑うようになった。禁止した通り〝すみません〟と言う頻度がぐっと減り、代わりに何度も〝ありがとう〟と言うようになった。表情も活き活きしてきて、次第に顔色も良くなってきた。あまり家事はできないようだったが、積極的に聞いてきたり説明書を読んだりして一日で家電用品の使い方は覚えた。説明書を熱心に読んでいる姿を見て、どうやら本が好きなのだと気が付いた。書斎に仕事用に買った本や担当した作家の本なんかがたくさんある。自由に読んでいいと言えば分かりやすく顔が明るくなった。その日に書斎から持って行ったのはなかなか難しい専門書だったが、はとくに苦労することなく読んでいた。恐らく賢い子なのだろう。兄さんの母校でもあるあの男子校は偏差値がそこそこ高いことで有名だったが今も健在のようだ。
そういえば、と気が付いた。泊めると簡単に言ったものの、我が家にはベッドが一つしかない。予備の掛け布団と枕はあるが。どうしようかと悩んでいるとが自分からソファを借りられればいい、と言い始めた。昨日はをベッドに寝かせたあと俺はソファで寝たのだが、うちのソファはどちらかというと硬めなので寝ることには向いていない。さすがに毎日となるときついものがあるに違いないだろう。今日はもう遅いので明日敷布団を買うか。
「あの、本当に僕、ソファで大丈夫です」
「いや、そのうち腰を悪くするから却下だ」
「で、でも」
「明日敷布団を買ってくるから、今日は仕方ないから二人で寝よう」
は「でも」と不満そうな声をあげる。それが面白くて「何か不満か?」と笑って言うと焦った様子で「い、いえ!」と首を振った。薄く笑ってから腕時計を見ると、もうずいぶん時間が経っていた。夕飯の支度をすると言えばは手伝うと申し出た。
どうやら包丁は使い慣れていないらしかったので、簡単な作業を任せることにした。二人で並んで台所に立つのははじめてのことだ。当たり前だ、ついこの前会ったばかりなのだから。それなのに。どこか懐かしくて、当たり前の光景のように思えるのはどうしてなのだろうか。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
――どうして?
遠くの方から声が聞こえる。聞き慣れているような、はじめて聞くような。誰の声だっただろうか。ゆっくりと目を開ける。広がっていたのは荒らされた和室だった。見覚えのない部屋だ。一体ここはどこだろう。辺りを見渡しながら前へ進もうとしたとき、何かを踏んでしまった感覚があった。驚いて足元に目をやる。そこには、美しい女が、血まみれで息絶えていた。
――どうして、手に入れようとしないの?
姿なき声が和室の中に響く。俺のすぐ後ろにいるような。むしろすごく遠くにいるような。不思議な感覚に襲われながらも息絶えている女をもう一度見下ろす。美しい。長い髪で顔が隠れているというのに、その女がとても美しいことを俺は〝知っていた〟。
――触れてもいいんだよ。
声に誘われるように息絶えた女の前にしゃがみ込む。震える手を伸ばして長い髪に触れる。艶のある黒髪をさらりと避けて顔を光の下に出す。その顔は。
――どうしてもだめだと言うなら。
その顔は、と、瓜二つで。瓜二つというよりむしろ本人のようで。震える指に誰かの指が重なる。耳元でもっと触れろと囁かれる。美しい女だ。陶器のように美しい肌に触れてみたい。そう、思うのに。触れてはいけないと自分の中で誰かが言うのだ。
――ここで終わらせてしまおうか。
ひんやりと冷たい感覚が首筋を這う。震える間もなく、そこで意識が途絶えた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「膝丸さん、あの、時間」
ゆるく体を揺さぶられて目が覚めた。勢いよく起き上がると「わっ」と声がした。時計の針はいつも起きる時間より三十分ほど過ぎたころ。寝坊、ではないが俺からすれば立派な寝坊だ。ため息をつきつつ視線を正面に戻すと、驚いた顔のままが固まっていた。
「ああ、すまない、起こしてくれてありがとう」
「い、いえ」
は苦笑いをこぼす。なんだか夢見が悪かった気がする。そのせいで目覚めが悪かったのだろうか。急いでベッドから降りると、自分がひどく汗をかいていることに気が付く。暖房を利かせ過ぎただろうか。それとも、悪い夢のせいなのだろうか。
急いで朝食の準備をしてからに先に食べるように言って自分はシャワーを浴びることにする。服を洗濯機に放り込んで風呂場へ入ると、ひやりと体が一気に冷えた。その瞬間、夢の最後に感じた首筋の冷たい感覚を思い出してしまう。ぞっとする。恐らくあれは刀のようなもので首を斬りつけられた感覚だった。そんな経験がないので良そうに過ぎないが。気味の悪い夢だ。それに、あの息絶えていた女。どうしてと同じ顔をしていたのだろうか。夢は何かの暗示だとよく言うが、夢占いでもしてもらった方がいいかもしれない。
風呂から上がるとが食べ終わった自分の食器を洗い始めているところだった。どこか覚束ない手つきに笑いつつ椅子に座ると、が「ごちそうさまでした」と言いながらお茶を持ってきてくれた。
「あの、大丈夫ですか」
「ん? 何がだ?」
「顔色があまり良くないので……」
風呂から上がったばかりだというのにそんなふうに見えているのか。少し驚きつつ「大丈夫だ」と返したが、は不安そうな表情のままだった。
あんな夢を見たのは環境が少し変わったからに違いない。一人暮らしだったこの家にがやってきて、一緒の布団で眠ったからだろう。男相手におかしいかもしれないが内心少し緊張していたのかもしれない。そんな変態じみたこと、本人には口が裂けても言えないが。に出会ってから自分が妙なことを考える瞬間ができてしまって、そういう癖を持っていたのか不安になってしまう。それほどの顔が好みだというのだろうか。……また妙なことを考えてしまった。
「膝丸さん、あの」
「なんだ?」
「……い、いつも、その、どれくらいに帰って来るんですか?」
「残業がなければ早くて八時ごろには帰って来るが……何があるのか?」
「あ、いえ、そういうわけでは」
なんでもないです、と言っては食器洗いに戻って行った。なんでもない、というような顔ではなかった気がしたが。の考えていることをすべて察するのはまだ難しい。いつか話したくなったら話してくれるだろう。そう思ってそれ以上は何も聞かなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あれ、膝丸さん、なんだかご機嫌ですね」
「……そうか?」
「何かいいことでもあったんですか?」
微笑ましそうに笑う部下は書類を手渡しながら「あといつもより顔色が良いです」と付け足した。いつもそんなに顔色が悪い印象なのだろうか、俺は。食生活を見直す決意をしつつ「とくに変わったことはない」と嘘をついておく。変わったことがないわけではないが、誰彼構わず話せるような内容ではない。男子高校生を家に泊めているなどそう簡単には説明ができない。部下は楽し気に疑うような視線のままではあったが、俺がこれ以上話さないことを悟ったのか深追いはしてこなかった。
「……ああ、そうだ」
「なんですか?」
「帰りの時間を訊ねてくるのに何か理由があると思うか?」
「はい?」
「そのままの意味だ」
「んー……ふつうに考えたら何か用事があるとか……あ、あとは早く帰ってきてほしいからとかですかね?」
ばさっ、と音を立てて書類が机の上に散らばる。部下が驚いた顔をして「え、どうしたんですか?」と急いで書類を拾い始めた。
早く帰ってきてほしいから、か。の顔を思い出すと、自信過剰かもしれないがなんとなくしっくりきた。そうとなれば少しでも早く帰るように努力した方がいいのだろう。そんなことを考えていると、部下が「あ、もしかして」と俺の顔を覗き込んできた。
「膝丸さん、彼女できました?」
は、と俺が声を上げる前に近くにいた別の部下が「えー!」と声を上げた。女性というものはこういう話題が好きだ。あっという間に部署内はその話でもちきりになってしまった。男の部下までも話に加わっているのだからどうしようもない。
「まさかあの膝丸さんに彼女ができるなんてね!」
「おい、聞こえているぞ」
「すみませ~ん」
けらけら笑う女性の部下は「だって膝丸さん、女の子に興味ないじゃないですか」と言ってくる。興味がない、か。九割くらいは当たっているので強くは否定しなかったが、一応恋人ができたわけではないとは訂正しておく。その否定をどうやら誰も信じていないようだったがなんとか話が広がるのは止められたようだ。全員が真面目に仕事に戻ったのを確認して、一つ息を吐く。
恋人が一人もいなかったわけではない。学生時代に数人そういうものができたこともちゃんとあった。けれど、どういうわけか、相手の女性にそこまで興味を持てないまま短期間で別れた記憶しかない。人並みに性欲はあるし、付き合った女性とそういう行為をしたこともある。けれど、その行為に熱はなかった。人としてか男としてか、何かが欠落しているのだろうと自分では思っている。相手の女性たちには悪いことをしたとは思うが、そういう理由で別れを選択してきた。女性を愛せない。そう、兄さんに相談したことがあった。すると兄さんはにっこりと笑って「じゃあ、男は?」と言ってきた。そのときは「余計に無理だろう!」と言ったのだが。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「お、おかえり、なさい」
八時ぴったり。玄関の戸を開けてがいたことに少し驚いてしまった。鍵を開けた音に反応してリビングから出てきたのかと思ったが、どうやらそうではないようだった。足音が聞こえなかったし、が立ち上がるような動作をしているのが少し見えた。は恐らく玄関に座って俺の帰りを待っていたのだろう。その様子を想像したら笑ってしまった。は俺が笑った意味が分からず首を傾げている。「な、なにか?」と不安そうな顔をしたので「ああ、いや」と笑いつつ首を振る。それでも不安そうな顔をしているの頭を撫でると、ほんの少し顔を赤くした。
「早く帰れるように努力するから、明日からはリビングで待っていろ」
ほんの少しだけ赤くなっていた顔が真っ赤に染まる。は恥ずかしそうに「すみません」と呟くと、俯いてしまった。その姿が妙にかわいくて余計に笑うとはもっと顔を赤くした。
靴を脱いでリビングに向かいながら、ふと、夢に出てきた美しい女を思い出す。あの女も顔が赤くなるときっとこんなふうなのだろう。白い肌が赤く色づくその様は女性を心から愛したことのない俺ですらそそられるものに違いない。いや、別にあの美しい女でなくとも。…………疲れているのだろう。今日は夕飯を食べたら早々に寝てしまおう。
「あ」
「ど、どうしました?」
「すまない、敷布団を買ってこようと思っていたんだが忘れていた」
残業もなかったし、今日の業務も早く終わらせられたので帰りに寄ろうと思っていたのに。電車に乗っている途中で忘れてしまっていた。「今からでも買いに行くか」と腕時計を見ながら呟く。掛け布団などをクリーニングしてもらう店があるのだが、あそこは確か夜八時半まで営業していたはずだ。今から車で行けばぎりぎりになるが間に合う。店主とは親しくしているし、多少は許してくれるだろう。リビングに向かっていた足を玄関のほうへ戻し、「今から行ってくる」とに告げて靴を履こうとする。は「あ、でも」と引き留めてきたが、二日連続で男と一緒の布団というのは可哀想だ。靴を履いてからのほうを振り返り「すぐに戻る」と声をかけた瞬間だった。が顔を上げて、俺の服をほんの少しだけ握った。
「あ、あの、実は」
「どうした?」
「その……よ、夜が、苦手で、一人で寝るのが、少し、怖く、て」
「……そうなのか?」
「膝丸さんさえ、その、良ければ、昨日と同じように、いっしょに、ね、寝て、もらえませんか」
語尾に近付くにつれ小さくなっていく声と離れていく指。それに思わず固まっているとは「す、すみません、気持ち悪い、ですよね」と苦笑いをこぼす。目にかかった黒髪を細い指で払う。はまた「すみません」と呟いてから顔を上げて「忘れてください」と言った。
「がそれでいいのなら俺は構わない」
「……き、気持ち悪くないんですか」
「どうしてだ?」
「どうして、って……」
履いた靴をもう一度脱ぐ。靴を揃えて先ほどと同じようにリビングへ向かうと、も急いでついてきた。今日は何が食べたいか聞くとは困惑したまま「なんでも」と言った。
「あ、あの、膝丸さん」
「なんだ?」
「本当に良いんですか?」
「逆に聞くが、はいいのか?」
「僕、ですか」
「俺の体が大きいから必然的には窮屈になるだろう?」
「ぼ、僕は別に、あの、大丈夫、です」
「遠慮しなくていいぞ。おじさん臭いとか狭いとか好きに言ってくれ」
「そっそんなことないです! むしろ落ち着くので……あ」
白に戻っていた肌が再び赤くなる。は「すみません」と今にも消え入りそうな声で言った。それを笑ってやりながらリビングに入り、鞄をソファに置く。は赤い顔のままリビングの隅っこで動かなくなる。恥ずかしさでどうしようもなくなっているようだ。そんな反応をされるほうが、こちらも照れてしまうのだが。咳払いをしてから「ならよかった」と返すと、は余計に恥ずかしそうな顔をしてしまった。
「ちょうどよかったよ」
「……え?」
「最近夢見が悪いんだ。人が傍にいてくれると安心する」
が少しだけ顔を上げた。冷蔵庫から取り出した野菜を洗いながら「問題ないな」と追い打ちをかけると、まだ少し恥ずかしそうではあったが「ありがとうございます」と言ってくれた。
はたしかに男だ。けれど、なぜなのか、俺の瞳は一向にのことを男だとは認識しないらしい。恥ずかしがる顔がかわいいなどと思ってしまう。俺が変なのかの顔が俺の好みすぎるのか、それともが変なのか。まあ、恐らく十中八九俺が変なのだろう。妙な気さえ起こさなければ問題はない。そう自分の中で完結させると、ひりひりと心臓の奥が熱くなった気がした。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あ、膝丸さん! こっちです!」
出社後、昼休憩のときに時間をくれと部下に頼まれた。了承すると近くのカフェに来るように言われたので、時間通りカフェに入るとすぐに声をかけられる。そちらのほうを見ると部下と、その部下が担当している人気作家の姿があった。聞いていないぞ、先生が来るなど。内心そう思いつつできるだけにこやかに二人の席に近付く。
「鶯谷先生もご一緒でしたか」
「ああ、いつも世話になっている」
「それはこちらのセリフです。いつもありがとうございます。先生は原稿の仕上がりが早くて本当に感謝しています」
「まあそれはつい最近からのことだがな」
鶯谷先生は穏やかに笑うと「コーヒーでいいか」と言いながら店員を呼んだ。それを部下が「メニューを膝丸さんに渡してください」とたしなめたが、そのままコーヒーを頼んでもらった。
コーヒーが来るまでの間、一番最近に発売となった先生の新作の話になる。最新作は今までの先生の作品とは一味違う、最初から最後までハッピーなラブストーリーだった。はじめは先生のファンからどんな反応をされるか心配だったが、今作も話題を呼びいつも通りの売り上げを記録している。すでに映画化の話が持ち上がっており、担当している彼女は相変わらず慌ただしい日々を送っている。先生はまだ若く容姿端麗ということもあり非常に女性ファンが多いのだが、そのファンたちからは「恋人ができたに違いない」という反応が多いのだという。女性の勘というのは鋭いものだ。直接聞いたわけではないが。
俺のコーヒーが届くとほぼ同時に鶯谷先生が「それで本題だが」と急に口を開いた。
「彼女に長期休暇を与えてやってほしい」
「……と、言いますと?」
「え、ちょ、うぐいすま……鶯谷先生、何言ってるんですか?!」
「所謂ハネムーンだ」
「……はい?」
「彼女と結婚することにした。指輪もここにある」
「ちょっ、えっ、な、なんでそれ今……!」
知らなかったらしい。椅子から立ち上がって驚いている部下の左手を無理やりつかむと、鶯谷先生はこれまた無理やり指輪をその薬指にはめた。一体俺は何を見せられているんだ。唖然としながら二人を見ていると、なんともムードのないプロポーズ劇がはじまってしまった。いや、プロポーズをする前に指輪をはめさせていたし、つまり断らせるつもりはないということなのだろうが。俺がぼんやりしている間に部下が「ふ、不束者ですが」とその手を握る。すると、周りにいた客や店員から拍手が起こった。
「と、いうわけだ」
「……は、はあ」
「な、なんでここでするんですか!」
「祝ってくれる人は多いほうがいい」
「そういうことではなくてですね?!」
「長期休暇は与えてもらえそうか?」
「再来月であれば大丈夫ですが……」
「再来月、か。まあ少し遠いがそれで手を打とう」
「さっきから鶯丸さんはなんで上から目線なんですか!」
鶯谷先生は愉快そうに笑いながら彼女に向かって「そこのコンビニで買い物をして来てくれ」と突然頼む。水を差すのもどうかと思ったので俺が行こうとしたのだが、「個人的に話がある」と言われてしまった。渋々ではあったが彼女が席を立ち、「膝丸さんに変なこと吹き込まないでくださいよ?!」と念を押してから一旦店を出ていった。
「あの、個人的な話とは一体、」
「膝丸くん」
「はい?」
「君は前世で自分が何だったか、覚えているか?」
「…………はい?」
鶯谷先生はコーヒーを一口飲んで笑う。「そうか、覚えていないか」と呟く口ぶりは、まるで自分は知っているかのようだ。はじめて会ったときから感じていたが、この人は作家の中でもかなりの変わり者だ。未だに何を考えているのかよく分からない。
「質問の意図は分かりかねますが……自分は前世というものをそもそも信じていないので」
「君、兄弟はいるか?」
「は? ……兄が一人いますが……?」
「名前は?」
「……いろいろ複雑な事情があって名字が違うんですが、兄は髭切友といいます」
「髭切、か」
そうかそうか、と鶯谷先生は頷く。まるで兄さんのことを知っているような反応だ。兄さんはたしかに俺と同じ会社にはいるが、鶯谷先生はもちろん作家と会う機会などない。企画書やその他諸々の書類に名前が載ることも非常に稀で、勤務している人間でも関わる部署にいなければ知らない社員だ。そんな兄さんのことをなぜ鶯谷先生が知っているのか。もしくは知ろうとしているのか。
鶯谷先生は兄さんのことをいろいろ聞いてきたが、どれも世間話程度のものだ。どんな人なのか、いくつ年が離れているのか、結婚しているのか、最近会っているのか。とくに聞かれてまずいことはない。ふつうに答えていると鶯谷先生は最後に、こちらをまるで貫くような鋭い視線を向けて口を開いた。
「兄が怖いと思ったことはあるか?」
「……兄さんを、怖いと」
「夢に兄が出てくることはあるか?」
「…………夢、に」
答えられない。得体の知れない何かが身体の中を蠢いている感覚を覚えた。兄さんを、怖いと思ったこと? 兄さんは非常に優しく、人懐こく、多少わがままではあるが基本的には尊敬する兄だ。はじめ受け入れられなかったことが今となっては笑い話になるほど、兄さんは俺にとって優しい兄だ。殴られたこともなければ怒られたこともない。怖いなどと思う要素はない、はずなのに。どうしてなのだろう。今、兄さんのことを、〝非常に怖いもの〟と思ってしまうのは。どうして、あの日見た夢に出てきた声が、兄さんのものだったように思ってしまうのだろう。
「君には好きな人間がいるだろう。欲しくてたまらない相手が」
「……欲しくてたまらない、相手」
「欲しいのなら欲しいと言えばいい。あのときもそうだった」
「あのとき、とは」
「君も、彼女もな」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あれ、膝丸さんは?」
「ついさっき帰ったぞ」
「……はあ、なんであんなこと膝丸さんの前で、」
「君は知らないだろうが」
「相変わらず話聞いてくれませんよね、鶯丸さん」
「彼は刀剣男士だ」
「……え」
彼女が困惑するのも仕方ない。膝丸の存在が見つかったのは彼女の次の代、つまりあの本丸における六代目審神者以降からなのだから。それを説明すると彼女は「ぜんぜん気が付かなかった……」と呟いた。なるほど、元審神者と元刀剣男士であっても、出会っていなければ分からないのか。新しい情報はあとで連絡するとして、今はこちらの問題だ。
髭切。たしかに膝丸が口にしたその名前。まさか赤の他人というわけはないだろう。しかも彼の兄としてまた共にいるのだから余計に。膝丸の話だと同じ会社に勤めており、すでに結婚して子どもまでいるとのことだった。それなら髭切には前世の記憶、つまり刀剣男士としての記憶はないのだろうか。彼は恐らく審神者に恋をしていたはずだ。そう、恋を。
「……妙なことにならなければいいが」
「え、何がですか?」
「いや、恐らく俺の杞憂だ」
俺の見立てが間違っていた可能性もある。この時代で結婚をして子どもがいるのであれば、元々彼女に恋をしていたわけではなかったのだろう。もしくは、記憶自体がなく別の女性と幸せになったか。そうであれば今世はあの二人は幸せになれることだろう。欲望に忠実でさえあれば。
「生真面目というか、堅物なのは今も変わらず、か」
「膝丸さん、刀剣男士のときもそうだったんですか?」
「まあな。今より余計にだ」
「うわー……ちょっとは柔らかくなってくれててよかった……」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「お、おかえりなさい」
リビングに入るとソファに座ったが立ち上がってうれしそうな顔をした。それにぼんやりしたまま「ただいま」と返事をすると、ははにかんだ。
欲しいもの。欲しいのなら欲しいと言えばいい。昼に鶯谷先生が言った言葉がぐるぐると頭の中で回り続けている。欲しいものを欲しいと素直に言葉に出すのは子どもっぽい。そう思っているはずなのに、どうしてなのか、やけに気になってたまらない。そして何よりも。欲しくてたまらない相手、鶯谷先生がそう言った瞬間、俺の頭の中には。
「膝丸さん?」
立ったままぼけっとしている俺の顔を覗き込んでが不思議そうな顔をしている。その顔はやはり、あの夢の美しい女そのもので。声も、肌も、髪も、瞳も。まるで宝石のように、あまりにも眩しくきらきらと輝く。頭一つ以上俺より低い身長で、俺の半分くらいしかないのではないかと思うほど小さな体。俺にはもう、あの美しい女にしか、見えないのだ。
「俺は君が」
「……膝丸さん?」
「君が、欲しい」
知らぬ間に飛び出て行った言葉は、いくら引っ込めようと思っても戻っては来ない。言った自分が驚いているのだから、言われたは余計に驚いている。当たり前だ。まるで告白のような言葉を己に向けてきたのが、十は年が離れている男なのだから。は目を丸くしたまま俺の顔を見つめている。その瞳は無垢に輝いており、自分がとんでもなく卑しい人間に思えた。急いで謝ろうと言葉を探すが、それを邪魔するように鶯谷先生の声が頭の中に響く。欲しいのなら欲しいと言えばいい。その言葉を思い出せば思い出すほど、思い知るのだ。俺が欲しいのはこの子だと。
「……あの」
「気持ち悪いだろう。男にそんなことを言われて」
「ひざま、」
「だが抑えられないんだ。極力近寄らないようにするから、許してくれ。自分勝手な大人ですまない」
背広を脱いで鞄といっしょにソファに置く。の近くから離れてキッチンへ向かうと、静けさが部屋を包んだ。言わなければよかった。分かっていたことだが、言わずにはいられなかった。一つため息をこぼしながらシャツの袖をまくり、蛇口をひねる。手を洗ってから蛇口をしめようと手を伸ばしたとき、背中に小さな手が触れたのが分かった。
「……居候をしている身だからと思っているのか」
「そ、うではなくて」
「可哀想とでも思ったか。独り身の俺が」
「違います!」
蛇口に伸ばしていた手を引っ込めて、背中に触れている腕をつかむ。身体をそちらに向けると赤い顔をしたと目が合った。
「一目惚れ、で」
「は?」
「声をかけてもらったとき、に、一目惚れ、したんです」
「…………男の俺にか?」
「変、ですか」
答えるより先に体が動いた。つかんだ腕を引っ張って小さな体を腕の中に収める。濡れたままの背中に腕を回すと、小さな体がほんの少しだけ震えたのが分かった。
変なのは俺のほうだ。生まれてこの方、誰かを愛することとはどういうことなのかを知らないままだった。俺を好きだという女性と付き合って何度愛を伝えてもらっても、それを受け入れることはできなかった。それなのに。出会ってたった数日。しかも女性ではない、十は年が離れた同性。そんなを胸が裂けそうなほど、欲しいと叫ぶ心臓がここにある。
「君は、その……女性と付き合ったことは、ないか?」
「……ないです」
「いいのか、はじめての恋人が十も年の離れた男で」
「膝丸さんが欲しいと言ってくれるなら、もらって欲しい、です」
控えめに腕が回された。あまりにもぎこちないその動きがどうしようもなく愛らしくて。きっともこんな気持ちになるのははじめてなのだろうと分かってしまった。思わず腕に力が入ってしまうとが少し苦しそうに「う」と声を出したので慌てて体を離す。
「……夕飯は、何が食べたい?」
「…………ふふ」
「笑うな」
「すみません」
小さく笑った顔のままなに若干気恥ずかしいままだったが、水が流れる音が耳についてようやく思い出す。急いで蛇口をしめると自分の手が濡れたままだったことも思い出した。手拭き用のタオルで先ほどつかんだの腕を拭く。そこだけ服が濡れてしまっているので着替えるように言うとは頷いてキッチンから出ていった。その足音が洋服ダンスの置いてある寝室に消えていくと同時にため息をついてしまう。なにを、しているんだ俺は。いくらが同じ気持ちでいてくれたとはいえ、大人として軽率すぎる言動だった。男同士など、どうあがいても苦しい思いをさせるに違いないのに。本当にを想っているのなら言わないという選択肢が大人として正しいものだっただろう。何が正しくて何が間違いなのかをどう決めているのかは知らないが、きっと俺は間違えているのだ。
頭の片隅で、美しい女がにこりと微笑んだ。触れたくて触れたくてたまらなかった彼女に、触れられた。そんな気がして仕方ない。一度触れてしまえば戻れない。そんな自分に嫌気が差したがもう遅かった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「あ、髭切さん! 例の弟さんじゃないですか?」
目を開ける前に聞こえてきたそんな声に驚いた。女の声? 恐る恐る目を開けると、一人の美しい女が俺を見て笑っていた。その後ろからやってきたのは俺の兄者、髭切でより驚く。兄者は「あ~本当だねえ」となんとも間延びした喋り方をしていたが、とくに違和感はなかった。
美しい女はこの本丸の主である審神者だと言って俺に頭を下げた。「お待ちしておりました」と言った声からは、初対面だというのに喜びが滲んでいるのが分かってしまう。審神者曰く、近侍である兄者に早く俺と再会させたかったのだという。当の兄者は「気長に待つ気でいたけれどね~」と呑気なことを言っていた。
美しい女の小さな手が俺に伸びる。握手、というやつを求められているらしい。主たる人間に求められるのであれば応じなければいけない。恐る恐るその小さな手を握ると、あまりに力弱くてぎょっとしてしまった。
「お名前をお聞かせ願えますか」
「……源氏の重宝、膝丸だ」
「膝丸さん、これからよろしくお願いします」
白い肌。艶のある黒髪。血色のいい赤色をした唇。凛と光る瞳。彼女が俺の新しい主。
「じゃあまずは僕の部隊に入れて修行させようか」
「あ、いいですね。兄弟だとやりやすいと山伏さんが言ってましたし」
「そうと決まれば行こうか、弟丸」
「膝丸だ! 兄者!」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「怪我丸大丈夫かい?」
「膝丸だ……兄者……」
初陣は恐ろしく不甲斐ない結果となった。兄者が率いる部隊はこの本丸における最強部隊だそうで、顕現したばかりの俺がついていける強さではなかった。流石は兄者の部隊。源氏の重宝たる働きをここでもこなしているようだ。内心でそう思いつつも、やはり不甲斐ない結果には落ち込んでしまう。人間の身体というのがこれほどまでに扱いにくいものだとは思わなかった。刀で斬られる痛みをはじめて知ったが、これは慣れられるものではない。俺という刀はこんな痛みを人間に与えていたのか。
複雑なような誇らしいような、妙な気持ちでいると襖が静かに開いた。「髭切さん、どうですか?」と主が顔を覗かせる。
「生きてるよ~」
「いや、あの、それは分かっているのですが」
「主、申し訳ない、不甲斐ない結果をもたらしたこと、身を斬ってお詫びを」
「え?!」
「介錯しようか?」
「兄者……手を煩わせてすまないが、頼めるか」
「ちょ、ちょっと待ってください! 髭切さんも何言ってるんですか!」
「叩くなんてひどいじゃないか」
乱暴に兄者の頭を叩いた主に驚いていると、主が俺の前に座る。咳払いをしてから、その小さな手をこちらにゆっくり伸ばした。そうして俺の頭を軽く叩くとかすかに笑った。
「生きて帰ってきてくれることこそが、何よりも誉です」
「いいですね?」と主の手が俺の髪を撫でる。美しく笑う女だ。まるで、宝石のようだ。
はじめて自分の心臓というものがちゃんと動いていることを知る。どくん、どくん、どくん、とうるさいほどに動いている。うるさいはずなのに煩わしいものではない。人間というのは不思議なものだ。主たる人間を目の前にするだけで、生命をこれほど強く感じられるなんて。生きている。それがこんなにも心地よいものだとは、知らなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「それ、恋ってやつじゃないのかな」
「……は?」
兄者からの返答に口が開いてしまう。こい? 首を傾げていると兄者は楽しそうに笑う。「うんうん、恋に違いない」と一人で勝手に納得しはじめるのでたしなめる。
「僕もねえ、あの子が好きだよ、弟丸」
「膝丸だ」
「うん、そうだね。お前があの子を好きだというのなら、なおのこと、うれしいなあ」
「……どうしてだ?」
「僕の好きな子と僕の好きな弟丸が好き合えば、それは幸せなことだとは思わないかい?」
膝丸だ、といつも通り正そうとしたが、はたと口が止まってしまう。好き合えば? 兄者の言った言葉に固まっていると不意に兄者が手で俺の視界を塞いだ。そのまま「主が君を好きだと言う姿を想像してごらん」と言われる。兄者に言われるがままに得意ではないが頭の中でごちゃごちゃと考える。頭に思い浮かんだ主はやはり美しい女で、何もかもが光り輝いていた。そんな主の赤い唇が開く。俺の名前を呼ぶところを想像すれば自ずと声も思い出される。「膝丸」、「好きです」、そう言葉が紡がれたことを想像、する。
「ほら、やっぱり」
「……なにがだ」
「鏡を見てくるといいよ。いやあ兄も頑張ってしまおうかな」
けらけら笑って兄者は部屋から出ていった。鏡? 部屋に置いてある手鏡を手に取り覗き込む。そこにはまだ見慣れぬ自分の顔、が、赤く染まっている姿が映っていた。それがどういう意味なのかよく分からなかったが、それを見た瞬間に余計に赤くなった。同時に心臓の音がうるさくなり、ふわふわとした変な感覚が襲ってきた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
それ以降、兄者は妙な行動を取るようになった。俺が主に報告をしに執務室を訪れると、何かを話していたのに急に席を外したり。いつも食事のときは近侍である兄者が主の隣に座るのに、なぜだか間違えて俺の席に座っていたり。それどころか何かと理由を付けて本部への同行も俺に任せるようになった。他の刀剣男士たちもその変わりようには驚いていたが、なぜか誰も文句は言わなかった。主は「もう、髭切さんは」と言いつつもそれを窘めることはなく、俺を見て笑うのだった。それがなぜだか、心地よかった。
「あ、膝丸さん。今ちょっといいですか?」
「構わない。また兄者が何かしたか?」
「今度の会議のとき、髭切さんが遠征に出たいと言っていまして……」
「近侍代行か。任された」
またか。そう思いつつ一つ息をつく。兄者の代わりを務めることは構わないのだが、主はそれでいいのだろうか。兄者も近侍の席にいるのだからもう少し責任感を持つべきなのでは。弟として主に謝罪すると、主は少しきょとんとした様子で首を傾げる。
「いえ、とくに気にしていませんよ」
「しかし」
「それに、あの」
「なんだ?」
「…………ひ、膝丸さんといるの、好きなので」
ぶわっと何かが体の中に舞った。心臓の音がうるさく、主がひどく眩しく見える。思わず目をそらしてしまうと、主が「変なこと言ってすみません」と謝ったかと思うと、走って部屋を出ていってしまった。置いてけぼりを喰らってしまった俺は、言葉を出す余裕もなく、ただただ馬鹿のように口をぱくぱくさせるしかできなかった。
こい。兄者がいつかに言ったそれが分かったような気がして。余計に心臓がうるさく、体の中を舞い続ける何かがくすぐったくてたまらなかった。
「初恋丸」
「……膝丸だ、兄者」
「ふふ、そうだったね」
うれしそうに笑う兄者を見たら余計に体の中がくすぐったくて、顔が熱くなるのも止まらない。余計に笑う兄者は俺の前に座ると「楽しみだなあ」と呟く。
「早く顔が見たいなあ」
「……?」
「かわいいだろうねえ」
「兄者、何を言っているのかさっぱりだぞ」
「何って君と主の子どもだよ?」
「子ど……………も?!」
気が早いぞ兄者!!
そう叫んだ声は本丸全体に響き渡ったようで、夕食のときに全員からからかわれた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「頼みって何かな? 珍しいなあ、僕に頼みなんて」
兄さんはコンビニ弁当を広げながら楽しげに笑う。会社で昼食を二人で食べることはそうないのだが、今日は俺から兄さんに声をかけた。兄さんは二つ返事でオーケーしてくれたが、顔を合わせてすぐに言ったのが先ほどのセリフだった。兄さんには俺の考えていることが分かるのだろうか。察しの良さに驚いていると兄さんが顔を覗き込んで「ありゃ、外れたかな?」と言った。
「い、いや、当たっている。兄さんはすごいな」
「いやいや、兄としてこれくらいは普通さ。なんでもこの兄に言ってごらんよ」
「兄さん、人の髪を切るのに慣れているだろう? 髪を切ってほしい人がいるんだが」
「慣れていると言ってもうちの子しか切ったことないよ?」
「それで構わない。頼めるか?」
「ちなみに誰の髪かな?」
「…………うちに来られるか? 紹介したいのだが」
「それならちょうどタイミングが良いね。今日うちの子、お泊り会なんだよ」
兄さんに「頼む」と頭を下げると、けらけら笑って「僕の弟は相変わらず律儀だねえ」と言った。兄さんには、ちゃんと、言わなければと思っていた。男子高校生を居候させていること。あと、その子と、恋人であること。もしかしたら兄さんは俺を気味悪がるかもしれない。同性で、しかも高校生が恋人など変だと言うかもしれない。そうだとしても、兄さんにはちゃんと話しておきたい。なんと切り出そうか考え始めると悩みが止まらなくなりそうで、一旦考えることをやめた。
「弟よ」
「?! な、なんだ?!」
「その子は君の、恋人かな?」
兄さんが微笑む。その顔は今まで見たことがないくらい優しい顔をしていた。いつでも兄さんは優しい顔をしているはずなのだが、本当に見たことがないくらいに。
「…………そう、だ」
「やっとかあ」
「は?」
「いやあ、兄は心配していたよ。また結ばれることがないのかと」
「兄さん?」
「いやあ、よかったよかった。肩の荷が下りたよ」
兄さんの言っていることはよく分からなかったが、とにかく喜んでくれているようだ。ずっと独り身の俺を心配していたのだろうか。少し首を傾げてしまったが、喜んでいるのだから悪いことではない。のことを紹介しても、この喜んだ顔をしてくれれば、一番うれしいのだが。一抹の不安は拭い切れなかったが、とにもかくにも、今はうれしい気持ちが体を満たした。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「おか……おかえり、なさい……?」
「ありゃ」
なんともいえない雰囲気が部屋の中に漂う。知らない人が突然やって来て驚いている。恋人と聞かされていた同居人がどうやら男であると気付いた兄さん。その間にいる俺。しばらくそのまま固まっていたが、一番に動いたのは兄さんだった。
「僕は髭切だよ。君の名前を教えてくれるかな?」
「あ、え、っと」
「、大丈夫だ。この人は俺の兄さんだ」
「お、お兄さん……?」
「そうだよ、兄さ。くんと言うのかな。よろしくね」
兄さんはいつも通りにこにこと笑ってに手を伸ばした。は恐る恐るではあったが「です、よろしくお願いします」と頭を下げてその手を握った。その様子にほっとしつつも、慌てて兄さんに「すまない」と謝る。事情を話すと兄さんはとくに顔色を変えずに「へえ」と話を聞いてくれた。は俺の隣で俯いたまま一言も話さなかった。握られた拳は少し震えているようにも見えた。
「……そういうわけで、その、受け入れがたいと思うが」
「ん~? なにが?」
「いや、なにがって……」
「いいじゃない。君たちがそれでいいのなら。兄は二人が好き合っているのならそれでいいと思うけどなあ」
「ほ、本当か?」
「うん。それにくん、きれいだしね」
ぼそりと兄さんが何かを呟いたが、あまりに小さい声で聞き取れなかった。聞き返しても「いやあなんでもない」と返されたので、それ以上は何も聞かないようにした。は顔を上げてとても驚いた顔をしていたが、兄さんが「弟を頼むよ」と声をかけると、きゅっと唇を噛みしめて小さく頷いた。
そのあとは兄さんの恐ろしいほどの興味が顔を出したらしく、根掘り葉掘り話を聞かれた。兄さんに隠し事ができるわけもなく聞かれるがままに答えていく。も恥ずかしそうではあったが、聞かれたことには素直に答えていた。こんなにも楽しそうな兄さんを見たのは久しぶりかもしれない。子どものように話し続ける兄さんを苦笑いで見ていると、はっと思い出した。
「兄さん、鶯谷先生と知り合いなのか?」
「鶯谷……ああ~、あの人ね」
「どこで知り合ったんだ?」
「ん~……さあ、どこだろうね?」
「はぐらかしたな、兄さん」
「何か言われた?」
「え、ああ、まあ……。兄さんのことをいろいろ聞かれたぞ」
「……ふ~ん。ま、〝特に問題なく〟元気にやってるって次会ったら伝えといてよ」
兄さんは引き出しを開けるとハサミを取り出す。そういえば本来の目的を忘れていた。に本来の目的を話すと自分の髪を持ち上げて「そういえば」と呟いた。ずいぶん長い間切っていなかったせいで伸び放題の髪を兄さんは「これは苦労しそうだ」とわしゃわしゃ触れる。兄さんは美容師だったわけではないが、手先が器用なので違和感がない程度には仕上げてくれるだろう。そうに告げると兄さんは「買いかぶられたものだなあ」とけらけら笑った。
しゃき、しゃき、と心地よい音を立てながらの髪にハサミが入って行く。兄さん曰く「一番似合う髪型が分かったよ」とのことだったので全面的に任せることにした。もこだわりはないらしく、兄さんに身をゆだねるようだ。
「前髪が長いとだめだからね」
そう言って兄さんはの伸びた前髪を切る。瞳を覆うように伸びていた前髪がなくなり、の顔が光の下にさらされる。眉の位置くらいで切られた前髪。の表情がよく分かる。それに、何より、あの夢の美しい女と、同じだ。あの女もそれくらいの髪の長さだった。後ろ髪はもっと長かったけれど、雰囲気はよく似ている。思わず魅入っていると、兄さんが「見惚れ丸」と俺のことらしき名前を呼んだ。
「膝丸だ」
「そんなに見たらくんに穴が開いちゃうよ。ねえ?」
「……すまない」
「い、いえ」
兄さんはにこにこといつも通りの笑顔のまま、の顔を覗き込む。前髪の長さを確認するように手をちょいちょいと動かしてはまたハサミを動かす。それを何度か繰り返し、最後にもう一度だけの顔を覗き込んだ。そうしてぽつりと、まるで独り言のように呟いた。「本当にそっくりだなあ」、と。
「……?」
「はい、おしまい。これでいいんじゃないかな」
「あ、ありがとうございます」
そわそわと前髪を触りながらが頭を下げる。兄さんは「どういたしまして」との頭を恐ろしく自然に撫でてから、くるりと俺のほうを振り返る。思わずびくっと肩が震えたが兄さんは特に何も言わなかった。
「じゃあもう帰るよ」
「え、あ、ああ、すまない、助かった」
「なんのなんの。これくらいかわいい弟とかわいい恋人のためさ。なんてことはないよ」
「うん、このくらい、なんてことはないんだよ」。そう繰り返した兄さんの声色が、妙に心臓に刺さる感覚があった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
主は美しい女だ。それを欲しいと思ってしまうのは人間の男の性のせいなのか、自分だけの特別な感情なのか、俺には分からない。艶のある黒髪を触れたいと思う。陶器のような白い肌に触れたいと思う。血色のいい唇に触れたいと思う。けれど、その身に触れたいと思う気持ちよりも、その美しい心を自分に向けてほしいという気持ちが、強く俺にはあった。主の心は危うく輝くものだった。誰にでも優しく、笑顔で、温かく、一切差別しない。何か一つが解けてしまえば保てない均衡を、主は驚くほど自然に保っていた。叱るべきところは叱り、褒めるべきところは褒める。それらをする姿にわざとらしさは一切なく、どこまでも純粋に相手を思いやってやる行為であると一目で分かる。そんな、主の心が欲しかった。そんな主に触れたかった。
その感情があまりにも温かすぎて失念していたのだ。彼女は主で俺は従者。膝丸という存在は彼女にとっては多くいる刀剣男士のうちの一振りにしかすぎない。毎日休むことなく出陣して行く刀剣男士を見守り、手入れをし、必要な武具を作る。主の毎日はただひたすらに〝審神者としての生活で成り立っていた。ただの一度も〝人間の女としての〟顔は見せなかった。それを悟ったとき、俺は主を裏切ってしまったように錯覚した。ただの従者が主たる審神者に触れたいなどと考えてしまった。その強き心を独り占めしたいなどと思ってしまった。
「そうかなあ。僕はそうは思わないけれど」
兄者は煎餅を頬張りながら呟く。少し間を開け、兄者はこちらから視線を外した。外を眺めつつ口に入れた煎餅を噛み砕き飲み込む。そこからさらに間を少し開けてから、もう一度こちらを見る。
「いいんじゃないの? 審神者と刀剣男士の色恋が禁止されているわけじゃあないんだし」
「……だが、俺は」
「深く考えすぎだって~。主が君を好いていれば問題ないじゃない」
「それでも主と従者である以上、俺はこの感情を良しとはできない」
兄者の眉がぴくりと動いた。食べかけの煎餅を机の上に置き、兄者は大きなため息をこぼす。そのままその場に寝ころぶともう一度ため息をつく。
主は毎日を〝審神者として〟必死に生きていた。儚いその一瞬で終わってしまう一生を、か細い命を注いで生きていたのだ。それが美しいと思った、愛しいと思った。だからこそ、俺が抱いたこの感情は、主を裏切る刃でしかない。触れたいと思ってしまったことも、欲しいと思ってしまったことも、主に知られてはならない。主が朽ち果てるその日まで俺は従者であり続けるべきなのだ。
「それでいいの?」
「ああ、それでいい」
寝ころんだままの兄者は小さな声で「ふうん」と呟いたっきり何も喋らなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
さすがにまずい。さすがにまずいことは百も承知なのだが。切ってしまったタグを左手でぎゅっと握りつぶしてしまったあとではもうどうしようもない。こぼれたため息と襲い掛かる罪悪感をなんとか飲み込み、開けたばかりのものをそっと寝室の箪笥に仕舞った。
が我が家にやってきてそれなりに日が経った。は当初からは想像もできないほど笑うようになり、ときには拗ねたりなんかもするようになった。まだぎこちないがいろんな表情を見せてくれるは、未だに不思議ではあるが俺にとって痛いほど愛しい存在になっていた。
「お風呂いただきました」
その声にびくっと肩を震わせるとは不思議そうに首を傾げた。「どうしたんですか?」と聞いてくる無垢な声に良心が痛みつつ「いや、なんでも」と言いつつ振り返る。はその顔を見るなりどこか疑うような眼差しを向けてきたが、追究はしてこなかった。それをいいことに「俺も風呂に入る」と言っていそいそと逃げるように寝室を出た。
風呂に入りながら項垂れてしまう。ここ最近、ずっと同じことを考えている自分がいるのだ。は、本当に、これで幸せになれるのだろうか。このことばかりが俺を悩ませる。どんなに愛していたとしても俺は男だ。アラサーで独り身の、どこにでもいるふつうの男。アラサーというのも独り身というのも大きな問題ではない。男、その一点。それだけが俺を迷わせるのだ。もしもが女だったら。もしも俺が女だったら。そんなふうなもしも話を考える時間が増えてしまった。男同士では結婚はできないし、兄さんはああ言ってくれたけれど後ろ指をさされることもあるだろう。それがを傷付けてしまうのではないかと、ふとした瞬間に怖くなる。を大事だと思うほど、好きだと強く思うほどに、その恐怖は膨れ上がっていく。膨れ上がったそれをぷすりと針で刺し、少しずつ中身を出してなんとか萎ませる。それを繰り返しながら日々を過ごしている。
情けない気持ちになりながら風呂から上がり、身体を拭く。何度目か分からないため息を振り払うように一つ咳をしてから髪を拭く。服を着て先ほどまで考えていたものはすべてなかったことにするよう心掛けながら洗面所を後にした。明日は休日なのでゆっくりできる。夕飯はもう食べたあとなのでと映画でも観てのんびりするか。そう、楽しいことだけを考えればいい。今はそれだけにしておこう。嫌でもちゃんと考えなければいけないときが来るのだから。そう自分を納得させてからリビングのドアを開ける。「映画でも、」と言葉を発しかけてがいないことに気が付く。いつも風呂から上がったらリビングのソファで座って待っているのに珍しいこともあるものだ。トイレにでも行っているのだろう。そう思ってソファに座ってテレビをつける。ニュース番組を観つつコーヒーを淹れていると、かすかではあるが物音が聞こえた。か? 音は寝室からしたようだったので、一旦コーヒーを置いてリビングを出る。すぐ近くの寝室のドアをノックせずに開けると、「あ」との驚いたような声が聞こえた。
「どう……した…………」
「…………すみません」
寝室の箪笥の一番下。先ほど俺が隠すようにしまい込んだものを、が見つけてしまったようだった。ネイビーのワンピース。当たり前だが、女物だ。今日の仕事帰りに何気なく寄った服屋で購入したものだ。サイズはMで、俺がそういう趣味を持っていたとしても着られるサイズではない。つまり、いや、当たり前なのだが、自分ではなくが着ることを前提に、買ったもので。買ったときはどうかしていたのだろう。帰ってタグを切ったあとで正気に戻って箪笥にしまい込んだ、というわけだったのだが。はなぜだかそれを見つけてしまったようだった。
「…………出来心で」
「で、できごころで」
「すまない、本当に申し訳ない、が」
「……」
「ど、どうして、着ているんだ……?」
「えっと……出来心で……」
「すみません」とが顔を赤くして俯く。細い腕と脚。本当に女かと見間違うほどに華奢な体に、買ったワンピースは驚くほど良く似合っていた。はワンピースを見つけたときは俺の昔の恋人のものなのかと思ったと言った。けれど、近くのゴミ箱にワンピースのものであるタグが捨ててあるのを見つけ、自分に買ってきたものだと気付いたらしい。その見事な推理に内心恥ずかしくなりつつ、男であるに女物の服を買ってきたことを詫びる。もし俺がの立場なら呆れるだろうし、たぶん、少し引っかかるものがあるからだ。そんな俺の謝罪をは少し笑って「いえ」とおかしそうに言う。
「膝丸さん、真面目そうなのにちょっと変態なんだなって、面白かったです」
「…………変態、なのか、俺は」
俺の反応が余計には面白かったようで、けらけらと笑った。恐らく今まで見た中で一番明るい笑顔だ。変態だと言われたことは若干衝撃的だったが、が笑ってくれるのならそれでもいいかと俺も笑って返した。
今日一日そのままでいてほしいと頼んだがさすがに断られた。は俺を寝室から追い出して「気が向いたらまた着ます」と言ってドアを閉めた。中から着替えているらしい音が聞こえてきて、少し残念な気もしたががより心を開いたように思えてうれしい気持ちが強い。またいつか気が向いてくれる日を楽しみにしよう。そう少し笑いながらリビングに戻った。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
十二月三十日。街中がいよいよ迫ってきた新しい年に色めき立つ中、いつも通り家路を急ぐ。今日が仕事納めだったので足取りも軽い。白い息が消えていくのを横目に見ながら駅へ向かって歩いていると、後ろで高校生のカップルが談笑しながら同じく駅へ向かって歩いている。付き合い始めたばかりらしい二人はとても楽し気に話しながら笑い合っている。そんな声を聞いていると、の顔が自然と頭に浮かんだ。もこんなふうに、同年代の女の子と付き合って、ふつうに幸せになれる道があったかもしれないのに。その道を閉ざしているのは紛れもなく俺で、をつなぎ止めようと大人げもなく必死になっているのも俺で。ちゃんとした大人であればをこんなふうに閉じ込めたりしないのだろうか。好きになってしまっても、気持ちを伝えずに身を引いたのだろうか。自分が欲しいからと手に入れた俺は、ひどくわがままな子どもなのではないだろうか。好きだと気持ちを伝えて、受け入れてもらえて、好きだと言ってもらえたのに。俺は未だ、に触れられずにいた。
兄さんに誘われて会社帰りに少しだけ、という約束のもとバーで待ち合わせていた。兄さんの奥さんも無事に退院をして娘のことは任せてきたとのことだった。バーのドアを開ければすぐに兄さんが俺に気付いて手を振った。
「すまない、遅くなった」
「そんなに待ってないよ。それより急に呼び出してごめんね」
兄さんはマスターに適当にカクテルを頼むと、先に飲んでいたものを一口飲む。二人とも仕事納めだったこともあり、とりあえず仕事の話をしはじめた。どうやら今日は部下がいくつかミスをしたらしく、兄さんはうんざりしたように「今日は厄日だったんだよ~」と頬杖をつく。その愚痴を聞きつつ、兄さんが適当に頼んだカクテルを受け取る。甘ったるいものだったが飲めなくはない。兄さんの話に相槌を打ちながら飲めば、すぐに飲み干してしまった。マスターに別のものを頼んでいると兄さんは急に話すのをやめる。「どうした?」と首を傾げると「ねえ」と兄さんが笑った。
「その後、どうだい。幸せにやってるかな」
言葉に詰まった。幸せに。そう言われると「もちろんだ」と言いたい自分と、そうではない自分がいる。は本当にこのまま俺がつかんだままでいていいのだろうか。そんな思いが顔を出すのだ。今日までそれを考えなかったことにして誤魔化してきていたが、第三者に面と向かって聞かれると、どうにも上手くいかない。
兄さんなら理解をしてくれているし、のことも気に入ってくれていたようだった。そう思って縋るように今の心境をぽつぽつと話した。同性であることでを苦しめる未来があるのではないか。はもっと幸せな道を選ぶことができるのではないか。俺はを幸せにしていけるのか。情けない気持ちも兄さんにであれば包み隠さず話すことができる。ずっとあった胸のつかえがとれたかのように途切れることなくすべて兄さんに話し終えると、喉の奥だけはすっきりしていた。俺の話を聞き終えた兄さんは腕組みをしたまままっすぐ俺を見つめる。にこにこしていた顔はいつの間にかあまり見ない、無表情に変わってしまっていた。
「……お前は、いつまで経ってもそうなんだねえ」
「どういうことだ?」
「たまには欲張っていいと思うけどなあ」
「……いや、だが、それではの人生を俺がめちゃくちゃにしてしまうだろう」
「じゃあさ」
腕組みしていた兄さんの腕が解ける。そうして右手が俺のほうへすうっと伸び、その人差し指が喉に触れた。
「生まれ変わったら、またあの子と出会いたい?」
兄さんが紡いだ言葉はとても甘美な夢だった。生まれ変わってはその容姿の通り美しい女になって、俺はに恋をして、二人はとても当たり前のふつうの幸せを手に入れる。同性だとか、家庭環境だとか、そんなものは何も考えなくてもいい幸せを。そんな、夢。
「そうだな、また出会って必ず愛するだろうな」
「……そっかあ。じゃあ、また、頑張ってしまおうかな」
「何をだ?」
「それはお楽しみだよ」
兄さんは楽しそうに笑う。昔から兄さんの考えていることはよく分からないことが多かった。今日も昔と変わらず、その瞳の奥の色を読むことはできなかった。だが、何かを孕んでいることだけは分かってしまうのはなぜなのだろうか。兄さんは何を考え、何をしようとしているのだろうか。それを知っている気がしている自分が最も不可解だった。それがどんなことにしても、幼いころから良くしてくれた兄さんが考えていることなのだから、任せておこう。そう思いながらカクテルを飲み干した。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
十二月三十一日、大晦日。夜の十一時を回ると目に見えてはそわそわしはじめた。それなりに新年が待ち遠しい気持ちはあるらしい。それを微笑ましく思いながら、俺はどこか薄暗い気持ちを引きずったままだった。冬休みが終わればを家に帰さなくてはいけない。はまた学校へ行っていじめられるだろう。両親に暴力を受けるだろう。何の血のつながりのない俺はそれをどうすることもしれやれない。恋人だとしても。むしろ恋人だからこそ何もできない。と恋人関係であると知られればが余計につらい目に遭うかもしれない。そう思うと、俺は身動きが取れなくなっていくのだ。
「膝丸さん、来年の抱負はありますか」
「抱負か……仕事を効率的に終わらせられるようにすることだな」
「今でも十分な気がしますけど……膝丸さんらしいですね」
「は何かあるのか?」
「僕は一日一日を大切に生きていく、です」
屈託のない笑み。人間の汚いところを見て身に染みて知ってもなお、この子はこんなふうに笑うのだ。それがひどく美しく眩しいものに思えた。こんなにも美しくて眩しい子を俺が独り占めしようとしている。同性の俺が。それが、どうしてか、許すことができない自分が、いて。
ずるずると暗いほうへ引きずられる感覚に陥っていると、突然現実に引き戻される。チャイムが鳴った音だ。も驚いたようで「こんな時間に誰でしょうか」と首を傾げる。もうそろそろ年が明けるという時間に来る来訪者。なんとなく予想はついた。ドアモニターを見れば思った通りの人物が笑って手を振っていた。
「兄さん、こんな時間にどうした?」
『差し入れ持ってきたよ~』
「はあ……開けるからちょっと待ってくれ」
家族はどうした、兄さん。少し呆れつつも兄さんらしいか、と苦笑いをこぼす。奥さんも俺と同じように送り出したに違いない。娘のほうはぐずったかもしれないが、娘がちょっとぐずるくらいで動じる兄さんではない。鍵を開けドアを開けると「あけおめ」と兄さんが笑っている。まだ年が明ける少し前だ。「気が早いぞ」と苦笑いをすると兄さんは「ありゃ、本当だねえ」と腕時計を見た。さすがに玄関で帰すわけにもいかず、リビングに連れて行くとが笑って「こんばんは」と兄さんを迎え入れてくれた。「二人きりのところをごめんね」と兄さんが言うとはどこか恥ずかしそうに「いえいえ」と返した。
「で、差し入れってなんだ? 何も持っていないじゃないか」
「ねえ、くんは膝丸と幸せになれる自信はあるかな?」
「え」
「兄さん?!」
「正直に言ってごらん」
「何を、」
「腰抜け丸は黙ってて」
まっすぐな兄さんの瞳はを貫くように見つめ続ける。は少しそれにたじろいだように見えたが、視線を逸らした理由はそれだけではないようだった。そうしてしばらく黙ってから、は恐る恐る口を開いた。「不安がないとは言えません」、と。
「将来どうなるのかが不安になることもあります。膝丸さんには僕なんかじゃなくてきれいな女の人が絶対似合うだろうと思っています」
「うんうん」
「……僕、が、女だったらよかったのに、といつも、思います」
衝撃を受けた。は今までそんなこと、一言も言わなかった。そんなことを考えていると感じたこともなかった。ただただ無邪気に笑って隣にいたから気付かなかった。悩んでいるのは俺ばかりだと思い込んでいる自分にはじめて気が付いた。恐らく。恐らくだが、あの日、俺が女物のワンピースを買って帰ったことが、の中にあったものをより色づけてしまったのだろう。苦しい思いをしていたに違いない。俺はそれに気付くことなく一人で悩んでいる気になっていたのだ。
「……どうして君たちはそうやって、いつもいつも、苦しんでいるの?」
静かな声だった。いつも明るく、どこか子どものような兄さんの声ではない。遠いどこかにいるような、まるで人間ではないような声をしていた。
「好き同士ならそれでいいんじゃない?」
「……そう、かも、しれないが」
「僕は悲しいよ。本当に」
その瞬間だった。目に前をまるで閃光のようなものが見えた。一瞬しか見えなかったそれの残像を追って視線をそちらに向けると驚いた顔のがいた。その身を、真っ赤に染めて。
「ひげ、きり、さん……?」
「主と従者の次は御曹司と女中、その次は兄と妹、その次は既婚者同士、その次は教師と生徒。それで次は男同士?もう呆れて言葉も出ないよ」
床を染める赤色にただただ言葉を失う。一体、いま、何が起こった? 恐る恐る兄さんのほうを見ると、その手には、きらりと光る、刃があった。日本刀。両手にあるそれのうちの片方、鞘に納まっているもの。それが驚くほど俺の心臓をとらえて離さない。どこかで見たことが?
「ねえ、君たちは一体いつになれば幸せに結ばれてくれるの?」
「どう、いう、」
「来世では幸せになるんだよ」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「なん、て、ことを……! 兄者……! 気でも狂ったか?!」
遠征から戻ると、本丸は異様な空気に包まれていた。薄暗く不浄が渦巻く空気。嫌な予感がした。時間遡行軍の急襲はこの本丸では過去に何度かあったと聞いていたし、警戒は全刀剣男士がしているつもりだった。主本人も常に結界を張ってすぐに何かあれば察知できるようにしていた。それなのに、一体何が。そんな疑問を抱えたまま本丸に踏み込み、主の部屋で見た光景は、到底信じがたいものだった。きらりと光る刃。見飽きたと言えるほど見慣れたそれは、まさしく、髭切だった。
「見ての通り、怖いくらい冷静だよ」
兄者の足元に転がっている主はもう息をしていなかった。たまりになるほど流れた血を気にせず踏み、兄者は俺に近付く。
「兄は悲しいよ。この目で幸せを見ることができると思っていたのに」
「な、にを……」
「来世では幸せになるんだよ」
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
――昨日未明、都内にあるマンションの一室で少年の遺体が発見されました。亡くなっていたのは都内の高校に通う男子生徒で、マンションの大家が発見したときにはすでに死亡していました。男子生徒の胸から腹にかけて日本刀のようなもので斬りつけられた跡があり、警察は殺人事件と断定し捜査を開始したとのことです。現場のマンション一室は現在空き部屋になっており、どのような経緯で少年がこの部屋で死亡したのかは分かっていません。現場に凶器は残っておらず、犯人に繋がる痕跡も今のところ見つかっていません。
「鶯丸さん、お茶淹れましたよ」
「……」
「ああ、その事件、朝もニュースで観ましたけど……新年から怖いですね」
「君は膝丸くんの連絡先を知っているか?」
「……?」
「君の直属の上司の膝丸くんの連絡先だ」
「…………えーっと? もしかして後藤さんのことですか? 鶯丸さん、もうボケ始まりました?」
「……そうか、そうだったな」
鶯丸は首を傾げる彼女を少し笑ってから窓の外に目をやる。雪がしんしんと降り積もる様は、何か大切なものを隠そうとしているように見える。大晦日の深夜、ちょうど新年を迎えたばかりの時間帯から振り始めた雪。休むことなく降り続けるそれを鶯丸は恐らく何かの予感を連れてきたのだろうと思っていた。あまりにも静かに降る雪が、遠い昔、まるでひっそり姿を隠すように滅んだ本丸の終わりと似ていたからだ。
恐ろしく静かに終わった本丸。死亡及び破壊は六代目審神者、膝丸、そして自害したと見られる髭切。たった一人と二振りだった。たったそれだけの被害で本丸は朽ちてしまったそうだ。
五代目を最後に刀剣男士として件の本丸に顕現していない鶯丸は、件の本丸における二人の危うさを伝え聞いていた。一番記憶の濃い歌仙兼定曰く「危うげな兄弟だとは思っていた」というその兄弟が目の前に現れたとき、鶯丸は何もかもに納得した。たしかに危うげな兄弟だったのだ。特に、兄のほうが。鶯丸が見た髭切はこの時代の髭切ではなかった。今から四つ前の髭切は歌仙兼定が言うような人物像そのままの男だったのだ。
「彼は躊躇がない。彼は恋をしていたのさ、彼女と彼の恋に」
「……なんですか、それ?」
「原稿でも書くか」
「暇つぶしみたいに言わないでください」
鶯丸は思う。恐らくだが、それは彼女と彼の望みであったと。来世こそ、来世こそ、来世こそは。心臓の奥、どんなに開けても開けても届かないずっと奥に、きっとそんな望みがあったのだろうと。彼女と彼は恐ろしいほど恵まれなかった。それを許せなかったのだろう。
どうせ実らない種ならば、水をやったところで仕方がない。咲くことはないのだから。それならば、新しい種をまいたほうがいい。髭切という刀剣男士はどこまでも〝人間味がなく〟、躊躇がなかった。
「まさに神のようだな」
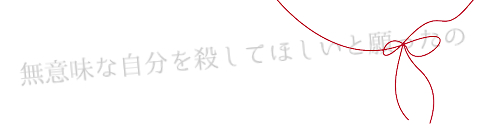
material by irusu