※現代・転生パロディです。
※捏造過多です。
※鶴丸国永短編「神様の涙を君は見たことがあるか」、鶯丸短編「あなたの紡ぐ文字が何よりも刃」等と同じ世界設定です。
※上記の短編の本丸と今回の明石国行いた本丸は同一本丸ですが、主は別人です。
※上記の短編を未読でも大丈夫ですが、一応シリーズ作品になっています。
※作中の明石国行、愛染国俊、蛍丸がひどい環境に置かれていた描写があります。
※鶯谷平介=鶯丸、です。
何もやりたいこともないし、とくに目標もない。けれど、何かをやっていなければろくでもない人間と見られてしまうから、何かはやらなくてはいけない。そういう思いでどうしようか悩んでいた私にとんでもなく良い話が舞い込んできた。芸能界。私みたいな田舎娘には縁のない世界だと思っていたけれど、たまたま遊びに行った東京で声をかけられた。まだ小さい事務所のスタッフだという男の人は気弱な感じだったが、悪い人ではなさそうだった。将来の目標もなければやりたいことも思い浮かばない。そんな私が魅惑の世界を選択することは、そこまで不自然なことではなかったと思う。
何の覚悟もなく何の信念もなくはじめた女優業。デビューしばかりのころはそれなりに仕事をもらえていたものの、やはり新人という肩書きがなくなるとそれもなくなる。私がぼんやりしている間に所属事務所はやる気のある子を新しくスカウトし、その子を売り出し始めた。やる気に満ち溢れ努力を惜しまないその子は着実に実力をつけ、映画に出演したりCMに出演したりと女優業を謳歌しているようだ。一応先輩である私は、というと。
「あのねえ、くん。もうデビューして何年? 新人じゃないんだから、もう少しやる気出さないとこのまま消えてっちゃうよ」
こんなふうに社長に怒られるばかり。周囲から数人売れていったり大きな事務所へ移籍したりしていく中で、気が付けば事務所で一番芸歴の長い女優になっていた。仕事は一ヶ月のうちに何か一つでも入ればいいほう。ほとんどアルバイトで生活を維持している状態だ。田舎に住んでいる両親も私のことは心配してくれているが、生活はどうにかできているし大丈夫だと伝えている。一つ困っていることがあるとすれば。
「言いにくいんだけど、とある事務所から仕事も用意するから君がほしいと持ち掛けられていてね」
「……アダルトビデオですよね、それ」
「まあ、うん、そうだね」
これである。新人時代、いくつか人気のあるドラマに出演した。知名度は低いけれど、そのドラマを観ていた人が私の顔を見て「あのドラマの〇〇役の人だ」と分かる場合はちょこちょこある。ファンレターをもらったこともあるし、街中で握手を求められたこともある。知名度が低くても女優として一応名前は残っているのだ。そういうビデオに出演、なんてことになったらたぶん「あの女優の!」なんて書かれるに決まってる。まあ、そういうビデオに出演するつもりはさらさらないのだけれど。
「それが嫌ならもう少し頑張ってもらわないと困るよ」
次のオーディション。社長がそう呟いて指を立てる。次のオーディション、というのは来月にある映画の出演オーディションのことだろう。それに一応行かせてもらえることになっているのだ。その映画というのが大人気作家である鶯谷平介先生の小説を映画化したもので、まだ撮影が始まる前だというのに注目度が非常に高い。
主演の二人はすでに決定しており、脇を固める俳優陣もすでに数人発表されている。主演は最近俳優業をはじめたばかりの人気モデル、亀甲貞宗。若い女性から圧倒的支持のあるモデルだったが、本人たっての希望で俳優業にも挑戦。当初は彼の父親が資産家ということもあり、コネではないかと叩かれることも多かった。けれど初出演を果たしたドラマでの体当たりの演技が評価され、ついに初主演映画が決まったのだ。もう一人の主演は明石国行。亀甲貞宗と同じく注目の若手俳優だ。若い女性からの支持はもちろん、バラエティ番組などで飛び出すどこか庶民的なトークは主婦層にも大ウケだという。かくいう私も明石国行のファンだ。イケメンなことはもちろん、どこからか漂うゆるい雰囲気が大好きだ。出ているドラマは必ずチェックするし、雑誌もすべて買っている。そんな大好きな俳優が出演する映画のオーディションだ。いつもよりは気合が入っている、つもり、なのだけど。
「役をもらえなかったら、辞めてもらうから」
「……え」
「くんには本当に感謝しているよ。こんなに小さな事務所のスカウトを受けてくれて、当時は仕事をいくつかとってきてくれたしね。でも、最近の姿勢を放っておくわけにはいかない。そういう仕事もしたくないというのなら、辞めてもらうしかないよ」
「じゃ、そういうことで」と軽く話を切り上げられ、部屋を後にせざるを得なかった。とぼとぼと事務所の廊下を歩く。すれ違ったスタッフの数人に挨拶をする。みんな笑顔で「お疲れ様です」と言ってくれるけれど、陰で私をなんと呼んでいるかはもう筒抜けだ。売れない女優。そんなふうに陰ではこそこそ笑われているのだ。他にやることもないから続けているだけ。撮影は楽しい。だから辞めずにここにいるだけ。努力なんかせず、舞い込んでくる仕事だけを受けて。だって、どうせ。一生懸命やったって、私なんか。
居心地が悪いわけではない。社会経験もないのに今更正社員になれるか、それを考えるほうが居心地が悪い。結局惰性でここに留まろうと考えてしまう。ため息が出る。数時間後にはアルバイトのシフトの時間だ。落ち込んでいる場合ではない。明日も生きるために今日働かないと。明日のための今日。今日の価値なんか、それだけなのだ。
居心地の良い場所に居続けるためにはオーディションに受からなきゃいけない。ここ最近はオーディションの話をもらって受けても落ちてばかりだった。注目作のオーディションなんか大勢の俳優、女優がギラギラと役を狙いに来る。私なんかが敵うわけがない。でも、負けてしまったら、私の人生はどうなってしまうのだろう。そう考えると不安でたまらなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「え?! う、受かった?!」
事務所からの連絡は、先日受けた例の鶯谷平介原作の映画のオーディションに、私が受かったというものだった。スマホを耳に当てたまま固まってしまう。受かった? 私が? あの超注目作のオーディションに? あのオーディションに受からなければ事務所を辞めさせられるということもあって、いつもよりは頑張ったと思う。それでも何か努力したわけじゃないし、特別何かをしたわけじゃない。いつも通り受け取った台本を覚えてそれをただ声に出しただけ。私が受かる要素なんて、どこにもなかった、と思うのだけど。
『なんでも鶯谷先生がくんがいいと言ってくれたそうでね!』
「え、え、う、鶯谷先生が?!」
『しかもオーディションを受けた役じゃなくて!』
「じゃなくて……?」
『物語の終盤、殺される女がいるだろう? 主人公の妻の!』
「あの結構重要な人物ですか? 犯人とも絡みが長いし人気のある人が振り当てられそうな、」
『その役なんだよ!』
「…………は?」
『だから! くんが! その重要な役なの!』
衝撃でスマホを落とすかと思った。マネージャーの声が耳元でうるさいはずなのにそれよりも自分の心臓の音のほうがうるさく聞こえる。私が受けた役は殺されるのは同じだけれど、あまり重要ではない役だった。物語の中盤に殺される女性の何人かの一人。ほとんど死体役みたいなものだ。それがどうして、一番重要な劇中の被害者である女性の役になったのか。まったく理解できなかった。
原作ならびに映画のタイトルは「徒花」。亀甲貞宗演じる崎本刑事と明石国行演じる元医者だった記者の宇藤が二人で連続殺人事件を解決していくというストーリーだ。宇藤が犯人なのだが、殺していく女性にはいくつかの共通点がある。既婚者であること、黒髪であること、年齢が二十七歳であること、過去に手術を受けたことがあること。殺され方は一貫して同じで、睡眠薬で眠らされた女性の頭部をナイフで一刺し。仰向けの状態でまっすぐに寝かされ、頭部周辺に血が丸く広がるその姿が花に見える、と小説では表現されていた。宇藤が医者だったころに手術を担当した女性、鈴子はその手術のおかげで妊娠することもでき、幸せな日々を送っていた。鈴子は退院時、宇藤から告白を受けていたがそれを断る。当時から付き合っていた崎本と結婚が決まっていたのだ。自分が手術をしたおかげで子どもを諦めずに済んだだけではなく命も助かったのに、と宇藤は彼女を憎む。愛と憎しみの中で彼女を思い続ける宇藤は、その憎悪を殺人をすることで鎮めようとする。鈴子に似た女性を見つけ出しては殺し、連続殺人犯となるのだ。彼女の夫である崎本が事件の担当刑事になったことを知り、記者という立場を利用して彼に近付く。一緒に事件を解決するふりをしながら殺人を続け、最後には鈴子を殺す。鈴子の頭部にナイフを刺して花を咲かせたところで彼女からの愛は得られない。宇藤は徒花を咲かせ続けていたのだった。それを思い知らされ自殺しようとした宇藤を、崎本が葛藤の中で止めて逮捕し、物語は終わる。後味の悪い話だが心理描写が美しく、実際にあった事件かのように描かれた作品だ。
その鈴子役が、私。固まったままの私の耳にマネージャーの声が響く。「台本、届いたら連絡するからね! また読み合わせがあるからね!」と言われ、ぼんやりしたまま返事をする。ピッと電話が切れた。それからしばらく、そのまま動けなくなる。今までの女優人生、ドラマや小さな舞台にいくつか出た。主演なんてもちろん一つもない。どれもこれも一話だけのゲストや脇役ばかり。映画、主人公の妻。原作の小説は読んだことがあるけれど、台詞が多かった記憶がある。物語の事件の原因となる、重要な役。そんなの、今まで、ない。たぶんこれが私の女優人生を左右する、大きな役に違いない。
そう分かっているのになぜ「やってやろう!」とか「絶対成功させる!」とか、思えないのだろうか。頑張ろう。いつも通りの、ぼんやりした口調で言うだけの、頑張ろう。それだけしか出てこない。頑張りたいのに頑張り方が分からない。
「……やりたくてはじめた仕事じゃないもんなあ」
最低な言い訳だ。でも、こうやって言い訳をしていないと、どうしようもなく自分が惨めになってしまうのだ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「崎本鈴子役のです。よろしくお願いします」
頭を下げると、ぱちぱちと拍手が聞こえた。そのあとに私の隣に座っていた明石国行さんが立ち上がり、同じように挨拶をする。続けて亀甲貞宗さんが挨拶をし、全員の挨拶が終了した。スタッフさんも含めて全員はじめて会う人なので名前を覚えるのが大変そうだ。
どっきりなんじゃないかとか、やっぱり別の女優さんに変更になるんじゃないかとか、不安は多かったがなんとかここまで来た。分厚い台本を握りしめて一つ息をついてしまう。監督の話を少し聞いてからついに読み合わせがはじまった。ドラマの仕事でもちろん読み合わせをしたことはある。けれど、最近はちょい役が多すぎて読み合わせすら参加していなかったから久しぶりすぎて緊張してしまう。何度か噛んでしまいつつ読み合わせが進んでいく。その中で感じたのは、私以外実力のある俳優が選ばれているという、目に見える事実。読み合わせだけで分かる。私だけ浮いてしまっている。主演の二人はもちろん、脇を固める俳優たち。私なんかとは比べ物にならないほど素晴らしい俳優ばかりだ。途中から台本を持つ手が少し震えてしまう。手が冷えてきてうまく力が入らない。口もちゃんと動いているか分からなくなってきた。噛む回数も増えてしまい、余計に緊張してしまう。
結局、読み合わせは散々な結果になってしまった。監督は厳しい顔をしていたけれど、助監督が明るい人みたいで「まあ最初だから緊張するよね!」と明るく励ましてくれて助かった。落ち着くためにお手洗いに立ち、しばらく鏡の前でため息を繰り返してから部屋に戻ることにした。部屋の近くを通りがかったとき、聞こえてしまった。ぼそぼそと話す女性スタッフと女優の声。「なんであの人があの役なの?」。私もそう思うからこそ苛立ちはなかった。本当、なんで私がこの役なんだろう。私を指名した鶯谷先生は何を思って私を選んだんだろう。ため息が出る。出し切ってから、再び部屋に入った。
「さん」
手招きするように呼んでくれたのは主演の亀甲さんだった。年齢は二つ下だけれど子どものころからモデルをしている彼のほうが芸歴は上だ。何より、俳優としての実力差がありすぎる。気軽に話せるような相手じゃないし、私にとっては雲の上の人だ。いそいそと近寄り頭を下げる。「ご迷惑をおかけするかもしれませんがよろしくお願いします」と言うと、亀甲さんはきょとんとした。そして、「こちらこそ、俳優としてはまだまだ新人ですからいろいろ教えてください」と笑う。なるほど、この笑顔にときめかない女性はいないはずだ。それに何度もぺこぺこしていると、亀甲さんの隣に座っていた明石さんもひょいっと顔を覗かせる。「こっちもどうぞよろしゅう」と少し訛りのある口調はテレビで観たままのゆるい雰囲気だ。それにも頭を下げて「よろしくお願いします」と返すと、明石さんは一瞬だけ考えたような表情をしたように見えた。
「ええ殺されっぷり期待しとりますんで」
そうゆるく笑う。それに助監督が笑うと厳しい顔をしていた監督も笑った。ようやく私も笑えてほんの少しだけ緊張が解けた。
休憩が終わってから部屋に一人の男性が入ってきた。助監督から「ご紹介します、原作者の鶯谷先生です!」と紹介があり、全員が拍手で迎える。鶯谷先生のことは何度か雑誌で見たことがあるけど、実際に会うと写真で見るより若い人に見えた。ぺこぺこと関係者の人が挨拶をする中、鶯谷先生は少しきょろきょろと辺りを見渡す。そうして視線が私のほうへ向く。指名してもらったと聞いているのだし、お礼を言うべきだろうか。それともそんなことにお礼を言うなんていやらしいと思われるだろうか。私が迷っている間に鶯谷先生がこちらに近寄り、私の前で立ち止まった。
「はじめまして。鶯谷平介だ」
「は、はじめ、まして。です、あの、この度は、その……」
「君の演じる鈴子を楽しみにしている」
そう、握手を求められた。落ち着いた声色と表情。緊張が解れ、ほんの少しだけ笑顔を見せられた。「はい」と答えれば鶯谷先生は満足そうに笑った。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
夢を見ているみたいだ。ぼうっとする頭の中に今日言葉を交わした俳優、女優の声、鶯谷先生の声が響く。あんな大物たちと一緒に仕事ができるなんて夢にも思わなかった。
ぽけっとしたまま家路を歩いていると、何やら賑やかな声が聞こえてくる。視線を向けてみると赤い字ででかでかと書かれた「タイムセール」。主婦の方々が吸い込まれるように入って行くスーパーの中は人であふれかえっている。表に置いてあるものも驚愕の安さで、次々とワゴンから商品が消えていく。売れない女優、アルバイト三昧の毎日。そんな私は所謂貧乏生活をしているわけで、それに食いつかずにはいられない。ぼけっとしていた自分はどこへやら、スイッチが入ったように体がサッと動いた。すぐさま緑色のカゴを手に取り、目についた商品をカゴへ次々入れる。安い、安い、どれもこれも安い! こんな穴場があったなんて!! 個数制限もないし、一週間分くらい買っていこう! 主婦の方々をかき分けながら店内をうろつく。そうしてお米のコーナーにたどりついた。
「あ、あと一袋しかない……!」
勢いよく伸ばし、お米の袋をつかむ。これで一週間、いや、二週間は確実に買い物しなくても大丈夫だ!そんなふうに思っていたのだけれど。私が握っている米袋を誰かも握っている。ほぼ同時に手をかけたようだった。しばらくその状態が続くが、私も向こうも譲るつもりはないらしい。話し合いしかないようだ。そうっと顔を上げると、ちょうど向こうも私のほうを向くところだった。
「…………え」
「……あっちゃー」
「え、あ、え? あ、かし、さん……?」
「どうも、さっきぶりです」
帽子に黒縁メガネ姿の明石国行さんだった。左手に持っているカゴには大量の食材。あまりにもスーパーは不釣り合いなスタイルをした人なのに、なぜだか庶民的な姿は変ではない。お互い顔を見合わせたまま固まったまま数秒が経ち、先に口を開いたのは私のほうだった。
「な、なぜ、こんな激安スーパーに……?」
「……まあ、見られたもんはしゃあない。表出ましょか」
その言葉に「え」と固まっているうちに米袋は持っていかれてしまう。表出ましょか、って、え、私、何かまずいものを見てしまったのだろうか。いやまずいというか、確かに人気若手俳優のプライベートをがっつり見てしまったのは確実なのだが。おろおろしている私を振り返ると明石さんは「聞いとりました?」と言う。謝りつつその背中についていくと、小さなため息が聞こえてしまったような気がした。
なぜだか私の分の会計まで済ませた明石さんは、私の買い物袋も持ったまま店の外に出る。そのまま細い路地に入って行くと、人気のないところで立ち止まった。私の買い物袋を手渡しつつ自分の買い物袋をいくつか地面に下ろす。ごそごそと漁って取り出したのはあの米袋だった。「袋」とだけ言われて手を差し出される。会計後に明石さんは「余分に一枚袋もらえませんか」と店員さんにお願いしていた。その袋がどうやら私の買い物袋に入っているらしい。それを探し出して手渡すと、明石さんは米袋をその場で開け、半分あるかどうかくらいの量を袋に移し替えた。
「これで勘弁してもうてええ?」
「えっ」
「自分がスーパーにおったこと、誰にも話さんといてもらえます?」
「え、あ、は、はい……でも、どうして……?」
明石さんはバラエティ番組でのトークで庶民的な面がたまに出る。それが主婦層にウケていることは自覚しているはず。安売りのスーパーにいた、なんて話せばもっとウケそうなのに。隠すようなことなのだろうか。純粋に疑問に思っていると、明石さんはため息をついて少しだけ頭をかく。
「うち、貧乏なんですわ」
「……び、貧乏……? で、でも、明石さんは超人気俳優じゃないですか」
「……借金」
「へっ」
「父親が残してった借金、返さなあかんので」
「……え?!」
「こんな激安スーパー通うとる、なんてバレたらその辺調べられてまうかもしれんので、困るんですわ」
このとーり、と軽い感じに手を合わされた。もちろん広めようだとか話そうだとかは微塵に思っていないが、明石さんはそれなりに真剣な表情をしているように見えた。
「弟が二人、いてましてね」
「は、はい」
「ろくでもない両親に振り回されてきたけど、ようやく、平穏に暮らせとるんですわ」
「はい……」
「誰にも言わへんて、約束してくれます?」
「も、もちろん!」
首をぶんぶん縦に振りながらそう答えた。明石さんのファンだし、そもそも共演者の人を陥れようなんて微塵にも考えない。言われなくとも言いふらすつもりなんてはじめから全くない。けれど、明石さんはかなり警戒しているようだった。私が「絶対に言いません」と言い終わった瞬間、ピロリン、と電子音がかすかに聞こえた。何かと思って明石さんのほうを見ると、明石さんはいつの間にかポケットに左手を入れていた。左手がポケットから出てくると、スマートフォンが握られている。「言質、取らせてもらいましたんで」と言いながらスマホをポケットにまたしまった。どうやら録音していたらしい。明石さんはいそいそと買い物袋を持ち上げて眼鏡をかけ直す。そうして「ほな、また現場で」とだけ言い残して颯爽とその場から去って行った。
正直なところ。ほんの少しだけ明石さんのその行動がショックだった自分がいる。もちろん私は明石さんとは今日が初対面だ。明石さんからすればよく分からない売れていない女優、くらいの認識だっただろう。芸能界はどこから情報が洩れてスキャンダルになるか分からないし、人気俳優なのだから何事にも警戒心は強めに持っていることだろうと思う。そうだとしても、明石さんが微塵にも私の言葉を信用していなかったことは、ショックだった。明石さんは悪くない。けれど、私もふつうに買い物をしていてたまたま明石さんと遭遇してしまったわけだ。明石さんをつけて遭遇したわけじゃない。私も悪いことをしたわけじゃない。それなのに、ため息をつかれ、録音され、置いてけぼり。なんだが少しだけ冷たさを感じてしまった。ミーハー心があったとはいえ、憧れの人だった。一緒に映画に出られて嬉しい気持ちがある。でも、それがすべて一人で浮かれていたんだと、なぜだか落ち込んでしまった。
家に帰って明石さんに買ってもらったスーパーの戦利品を冷蔵庫につめる。これも口止め料として払ってくれたに違いない。よっぽど信用されていないのだ。分けてくれたお米も見ていると悲しい気持ちになってきてしまう。仕方のないことなのだ。そう自分に言い聞かせる。私みたいな売れない女優、ふつうだったらどんな手を使ってでも売れようと努力するだろう。それこそ明石さんの弱みを握っているわけなのだから、それをネタにやりたい放題できなくはない。恐らくそんなことをすればファンの方からはひどいバッシングを受けることは必至だが、その分話題にはなる。過去にそういう扱いを受けたことがあったのかもしれない。警戒心が強いことはいいことだ。彼のような人気俳優は事務所からも耳が痛くなるほど言われているだろうし、当然の言動だったのだ。そう思っていないと明日現場に行くことが憂鬱でたまらなくなってしまう。私が落ち込むことなど、何一つないはずなのに。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「おはようございます」
現場に入るとまず亀甲さんに挨拶をされた。それになぜだかほっとしつつ頭を下げて挨拶を返す。亀甲さんはいつもかけているものではない眼鏡をくいっとあげながら、「良い天気になってよかったですね」と笑顔を見せてくれた。刑事役ということもあって衣装はシンプルなスーツ姿だが、スタイルの良さやその容姿だけで華やかな印象になっている。それに少し見惚れてしまうのは私だけではない。周りにいるスタッフさんや他の女優さんも同じように彼に見惚れていた。
亀甲さんに再度頭を下げつつ着替えに向かう。ケータリングが置かれている机の前を通り過ぎようとしたとき、突然角から顔を覗かせたその人と目が合った。
「あっ……」
「どうも、おはようございます」
にこりと笑われる。何とか笑い返して「おはようございます」と挨拶を返してみると、「約束、守ってくれてます?」と当たり前のように聞かれた。もやっとした気持ちが顔を出しかけたけれどぐっと堪える。「もちろん、」と私が答え終わる前に明石さんは「まあ、できへんやろうけど一応」と言葉を付け足す。それにさらにもやっとしていまい、そうになったけれど堪えた。できへんやろうけど、って、どういう意味? 私みたいにやる気のない人間だからそんなことできないだろうってバカにされた? そう思わないようにぎゅっと拳を握りしめる。とりあえず苦笑いをこぼして、「ご心配なく、大丈夫です」とだけ返した。明石さんはそれに満足したような顔をして「ほな、今日もよろしゅう」と言って監督に挨拶をしに行った。
「彼、掴みどころがなくて面白いよねえ」
「うわっ、き、亀甲さん、びっくりしましたよ……」
「そんなに驚かれるとは思わなかった、すみません」
人懐こい笑顔が優し気だ。もやもやしそうになっていた微妙な気持ちがいっぺんにほどかれる。不思議な雰囲気の人だとテレビ越しに思っていたけれど、実際に会ってみるとより不思議な雰囲気を感じる。話しやすいんだけど、話しかけにくいというか。優しそうなんだけど、奥が底なしに深そうで怖いというか。そういう両極端に見える要素を持っている危うさを感じる。
亀甲さんは明石さんのことを「嘘吐き」と評した。その言い草からあの亀甲さんが共演者の悪口を言うのか、と少しがっかりしてしまったけれど、どうやらそれは早とちりのようで。亀甲さんは自分が俳優をやりたいという思いを抱えたとき、一番に話を聞いてくれたのが明石さんだったと言った。さりげなく悩みがあるのかと聞いて、亀甲さんが話すと一見興味なさそうに聞いていたが的確なアドバイスをくれたと。俳優業をはじめてすぐにコネだと叩かれたときも、興味なさそうにしつつもマスコミや自分のファンの人にさりげなく亀甲さんの誤解を解くように話していたのだという。
「お礼なんて言ったら彼は照れて口を利いてくれなくなるから、知らないふりをしているんだ」
内緒だよ、と亀甲さんは笑う。その言葉に嘘がないことは聞かずとも分かった。頑張っていないように見せかけて努力をしているだとか、知らないふりをしているように見せかけて人一倍物事に関心を持っているだとか。亀甲さんはすらすらと明石さんのことを話し、どこか楽し気な表情をしている。それだけ亀甲さんが明石さんのことを尊敬し、背中を追いかけているのだと分かった。いいなあ。反射的に言いかけた。明石さんも、亀甲さんも、この仕事に全力で打ち込んでいる。この仕事が好きでたまらないのだろうと分かる。明石さんは理由が少し違うかもしれないけれど、そうだとしても。それが羨ましくてならなかった。私なんかが、羨んでいいことじゃないのに。
「女優になったきっかけは?」。私が一番嫌いな質問がこれだ。きっかけなんかない。ただなんとなく、やりたいことがなくてどうしようか考えていたときに、偶然スカウトされたから。誘いがあれば女優じゃなくても乗っていたと思う。タイミング良くスカウトの話があったからそれについていっただけ。子どものころからの夢だったとか、憧れの人がいたからとかそういう理由は何一つない。やりたいことが見つからない中で一番手っ取り早い選択肢としてあがったから。ドラマの仕事も映画の仕事も舞台の仕事も。どんな仕事にだって熱を上げたことはなかった。だってただの仕事だから。周りの人と違って憧れでもなんでもない、ただ都合の良い選択肢を選んだ先にあった仕事だったから。なんて惨めなんだろう。苦笑いをこぼしそうになってぐっと堪える。
「さんは女優の仕事、嫌い?」
「えっ」
「いつも苦しそうに台詞を言うし、挨拶もいつも苦しそうだから」
「……すみません、気をつけます」
「いや、そうじゃないんだ、注意したわけじゃなくてですね。上手なのに、勿体ないなあと……失礼ながら」
「…………じょう、ず?」
「はい。さんの演技、僕は好きです」
「でも、なんとなくすべてさらけ出していないように、思えることもあります」と亀甲さんはなんとも言いづらそうにゆっくり言葉を紡ぐ。なんてきれいな言い方をする人なんだろう。すべてをさらけ出していない、なんて。単純に情熱がないとかやる気がないとか、そうきっぱり言ってくれてもいいのに。けれど亀甲さんの言葉にはやはり優しさが滲んでいて、私を責めているのではなく激励しているものなのだと伝わった。これが演技なのか本心なのかは分からないけれど、そう言われてうれしくないわけはなかった。
「……亀甲さんはどうして俳優業もやろうと思ったんですか?」
「モデルの仕事も好きだけれど、やはり自分の口があって自由に話せて自由に伝えられるのだから、自分のすべてを使って表現をしてみたかったから、かな」
「私にはないんです」
「ない?」
「女優の仕事をはじめた理由が、何もないんです」
亀甲さんは不思議そうな顔をする。「昔に雑誌のインタビューでたしか、夢だったと言っていませんでしたか?」なんて当然のように聞かれたから恥ずかしくなってしまう。なんでそんな昔のインタビュー記事のことを覚えているんだろう。亀甲さんのリサーチ能力に驚きつつ、苦笑いをこぼして「すみません、あれ嘘です」と頭をかく。亀甲さんも苦笑いをこぼして「さんもなかなかの嘘吐きですねえ」と茶化すように言った。
「正直羨ましいです。亀甲さんみたいにやりたいことを全力でやれる人たちが、心の底から」
「全力でやればいいさ、あなたが選んだこの仕事を。失敗したって誰も笑ったりしないし、誰も責めたりしない。ひとまず走れるだけ走ってみて、疲れたら立ち止まってもいいんじゃないかと僕は思うけれど……」
「……あはは、そうですね」
亀甲さんは「後輩が生意気にすみません」と言ったけれど、私なんかより芸能生活の長い彼の言葉は誰がどう見ても正しいアドバイスだ。「いえ、そんなこと!」と返してからお礼を言う。亀甲さんはそれに安心したように息をついた。
全力でやっている人はアドバイスまでも全力でしてくれる。有難いことなのだけれど、自分への劣等感がいっそう強くなってしまった気がした。私はどうしてそんなふうに思えないのだろう。どこかで私なんか、と考えている自分がいる。努力したっていいことなんかない。どうしてそんなふうに自分が思っているのかは分からない。昔に頑張っていたことがあるわけでもないし、何かで挫折したこともない。思い出に残るほど熱中したものはないし、挫折を感じるほど努力したこともないからだ。手を伸ばす先もなければ伸ばしたとしてもその先には恐らく何もない。なぜだか子どものころからそう諦めてしまっている自分がいた。
「しょーもない」
「わっ」
「おや、聞いてたのかな」
「やる気ないならやる気出さんままでええんとちゃいます?」
「…………そう、ですね。すみません」
「……なんで自分いま謝られたん?」
「言葉が足りないからかな」
「あの……?」
「……まあええわ。撮影はじまるで」
気だるそうな背中。ちっともやる気や情熱があるようには見えない。俳優をしている理由だってたぶんテレビで言っているものは嘘だろうと思う。私だけが知っている、のかもしれない。それなのに明石さんへの羨望は変わらなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「……ここ、自分の行きつけなんで店変えてくれません?」
「な、なんでですか……仕方ないじゃないですか、安いんですもん……」
「まあええですけど……」
明石さんは小さくため息をつきつつ買い物かごを手に取る。それに続くように私も買い物かごを手に取って、そこから離れようとした。そのとき、明石さんが「あ」と言った声が聞こえて思わず振り返ってしまう。
「国行遅い!」
「三十分も待たすなよ~」
「阿呆、仕事なんやでしゃーないやろ」
中学生くらいだろうか、男の子が二人明石さんの元へ駆け寄っていた。明石さんはすぐに二人と話し始めたし、傍目にも二人が明石さんに懐いているのがよく分かる。恐らく前に言っていた弟というのがあの子たちなのだろう。あまり三人とも顔が似ていないけれど、雰囲気は仲の良い兄弟と言われて納得するようなものだった。明石さんが持っていた買い物かごを赤毛の男の子が奪い取り、薄い茶髪の男の子は明石さんの手を取って引っ張る。仲睦まじい。まさにそういう雰囲気だ。あの子たちのために仕事をがんばっている、のだろう。そう思うとまた羨ましくなってしまって、そんなことを考えている自分が嫌になってしまった。
目を逸らそうとした瞬間、ふと赤毛の男の子がこちらを見た。目が合った。そう思った瞬間「あー!?」と大声で叫ぶ。指さす先には私しかいなかった。
「国俊、うっさい」
「くにっ……兄貴、あの人!」
「はあ? …………なんやファンなんか、サインもろたろか」
「ちっげーよ! あの人、見覚えねえか?!」
「見覚えも何も仕事仲間や」
そう答えた明石さんに痺れを切らせた様子で赤毛の男の子は「ああ、もう!」と言って私のほうへ駆けてくる。よく状況がつかめないままでいると、私の目の前で男の子が足を止めた。じいっと私の顔を見つめたあとで「やっぱり」と呟いて、なんだか寂しそうに笑う。
男の子は国俊くんといって、思った通り明石さんの弟さんだった。今は高校一年生だそうだ。もう一人の薄い茶髪の子も兄弟で、名前は蛍くん。中学二年生だと国俊くんが紹介してくれる。明石さんの服をぎゅっとつかんで少し隠れている様子から人見知りなのだろうと勝手に判断した。一応私も自己紹介をしたら国俊くんは「なんか慣れねーな」と笑ったけど、その意味はよく分からなかった。
どうして話しかけられたのかよく分からない。国俊くんはなんだか楽しそうにいろいろな話をしてくれるのだけど、その背後で面倒くさそうなオーラを出している明石さんが気になって仕方ない。人懐こい国俊くんにたじたじになってしまう。そんなふうに話を聞きつつ、少し気になった。明石さんは関西訛りなのに、この子は訛りが全くない。明石さんの言葉を思い出した。〝ろくでもない両親に振り回されてきた〟。明石さんにしがみつくようにしている蛍くんや、兄弟なのに方言が違うところ、なんだか必死に私に話をしてくれる国俊くん。なんだか危うい雰囲気はそのせいなのかと、少し、勘ぐってしまった。
「あ! なあなあさん!」
「う、うん?」
「料理得意?!」
「え……そ、それなりには……?」
「うちで飯作ってください!」
「は?」
「はあ?」
ほぼ同じタイミングで私と明石さんがそう言ったのをちょっと嬉しそうに笑う。国俊くんは「いいじゃん、だって国行料理嫌いだし」と少しふくれ面をした。明石さんは「いやそういう問題ちゃうやろ」と呆れ顔をしたのち、私の顔をちらりと見て「お子さまの戯言なんで気にせんといてください」と言う。明石さんは自分にしがみついている蛍くんの頭をぽんぽんと撫でながら「蛍が嫌がっとるやろ」と言った。国俊くんはその言葉に少し、ぎゅっと拳を握ったように見えたけれど、すぐに解いて「大丈夫!」となぜだか私の顔を見て言う。
「さんは怖い人じゃねーよ」
俺が保証する、と言った声にはなぜだか自信があるように聞こえる。初対面なのにどこからその自信が出てくるのだろうか。明石さんは不思議そうに「意味分からへんわ」と頭をかく。いや、その前に私の意思は……? 少し疑問に思いつつも口を挟める雰囲気ではないので黙っておく。
買い物かごを取ってすぐの入口付近は人の邪魔になる。とくに明石さんは気付かれるとまずいので一先ずは一緒に店内へ入ることになってしまった。私が持っていた買い物かごも国俊くんによって回収されたのち、一つは元の山に戻されてしまう。国俊くんは私の手をぎゅっと握って「うち今、米しかない!」ととりあえずあるものを教えてくれたらしかった。このままだと本当に明石さんの家でご飯を作ることになりそうなんだけど、どうすればいいのだろうか。ちらりと明石さんの顔を見たけど、もう興味はないみたいで蛍くんとぽつぽつ会話をしている。いや、あの、本当に私の意思は聞いてくれないんでしょうか。少し困りつつもこんなふうに誰かに何かを求められたことが久しぶりで悪い気はしない。国俊くんがどういう意図をもってこうしたのかは分からないけれど。
「で、何作りはるん?」
「えっ」
「ここまで来たら国俊は言うこと聞かへんので。人助けのつもりで付き合うたってください」
ため息交じり。その言葉に国俊くんはようやく私の手を離した。そのタイミングからして、恐らく私に逃げられないようにしていたらしい。きらきらと目を輝かせる国俊くんは私の顔を見上げて、ニカッと笑った。いかにも元気な少年、という感じだ。高校一年生にしては少し子どもっぽく思えてどことなく違和感があるような、ないような。体格もあまり大きくないし、中学生だと言われても納得する雰囲気だ。一年前はまだ中学生だったのだから当然かもしれないけれど。明石さんは背が高いからそれも違和感に繋がっているのだろうか。けれど、兄弟が背が高いから下の子たちも背が高いなんてことはないので、それは気にしすぎなのかもしれない。
ちらりと少し後ろを歩く明石さんと、まだ明石さんにしがみついたままの蛍くんを見る。蛍くんはかわいらしい顔をしている。中学二年生にしては国俊くんと同じく少し小柄だけど、その容貌がそれにぴったりあてはまっている。かわいい、そういう印象だ。体の全体が細い、華奢な感じがしてやっぱり少し危うい感じもある。中学二年生なんて食べ盛りだろうに。いくら借金を抱えているとはいえ、明石さんは大人気俳優だ。生活費にいくらか回せるくらいのお給料はもらっているだろうに、どうしてこんなにもひもじそうに見えるのだろうか。少し思い出しただけでも明石さんは今のクールのドラマ一本に加え、CMも何社か契約しているし雑誌には引っ張りだこで出ている。バラエティ番組も出ているし、一日にテレビをつけていれば一度は目に入るといっても過言ではない。
もやもやと考えていると明石さんが「うちに必要なもん取ってくるんで」と言って蛍くんと二人でどこかへ行ってしまった。国俊くんと二人きりになってしまって、少しだけ気まずいような気がしなくもない。国俊くんはそんなことを一切思っていないらしく、きょろきょろと店内を見回しながら何が安いのかを見ているようだ。
「なあさん」
「あっ、はい!」
「オムライスにしようぜ」
「え? ……あ、メニューをね?」
「うん」
「あ、たまご」と呟いてかごに卵を入れた。国俊くんは「何入れる?」と笑って私を見上げる。それから少し間を置いて「ごめん」と言って苦笑いを見せた。
「迷惑だったよな、突然。ごめ……すみません」
「へっ、あ、いや、びっくりしはしたけど、迷惑とまでは……」
「さんのこと見てたらさ、懐かしくて」
……懐かしい、とは。私が誰かに似ているのだろうか。それこそ、恐らく一緒に暮らしていないと思われる、お母さん、とか。明石さんの口ぶりからして複雑な家庭だったことは分かるけど、一体何があったのだろう。赤の他人でしかない私が踏み込める範囲じゃないから、考えたってどうしようもないのだけど気になってしまった。国俊くんは目線を落としてなんだか気恥ずかしそうに笑う。「うんと昔に、姉ちゃんみたいな人がいて」と呟いた唇が少し緊張しているように見えたのは、なぜなのだろうか。
国俊くんが教えてくれた「うんと昔にいた姉ちゃんみたいな人」は、あまり料理が上手ではなかったけど、いつも一生懸命ご飯を作ってくれていたそうだ。真面目で努力家で、何をやるにも全力でやる人だったと言った。うんと昔、なんて表現をしたのはなぜかが気にはなったけれど、それよりもその人があまりにも自分と正反対で羨ましく思う気持ちのほうが強い。蛍くんも懐いていて、一緒にいるときはいつもべったりだったそうだ。日常的におうちに来ていたということは明石さんの彼女だったのだろうか。そのあたりは少し聞きづらくて黙っておこうと思ったのだけど、国俊くんがさらりと「国行の好きな人だったんだぜ」と言った。続けて「でも恋人にはならなかったけどな」と寂しそうに言う。国俊くんは俯いた顔をぱっと上げて、へらりと笑う。
「その姉ちゃん、頑張り屋すぎてさ、それでだめになっちまったんだ」
だめに、なった。その言葉の意味が上手く飲み込めない。どういう意味なのか聞こうかと思ったけど、国俊くんの顔を見ているとそんなことは聞けなくて。言葉を探していると国俊くんが「そんなに頑張んなくていいって言えばよかった」と困ったように笑う。さっきまでの元気は薄くなっている。どうにか、元気づけてあげたい、けど。私には関係のない、赤の他人の話。それに首を突っ込んでいいのか分からない。
「だからさ、さんも、無理に頑張んなくていいんだぜ」
ふいっと目を逸らされた。「あと何がいる?」と声をかけられ、ぐっと拳を握ってしまった。頑張んなくていい。今まで誰しもが頑張れ、もっと頑張れ、と励ましをくれた。そう言われるたびに苦しくて、頑張れない自分は変なのだと思うようになった。頑張らなくていいと言われたのははじめてで、なんだか強張っていた体から力が抜けたように思えた。それがいいことなのか悪いことなのかは分からない。分からないけれど、なんだか気持ちが楽になっていた。
買い物かごを国俊くんの手から奪って「こっち」とその手を取って連れて行く。途中で明石さんや蛍くん、そして国俊くんにアレルギーや嫌いなものはないかを確認した。国俊くんは少し戸惑っていたけれど、三人もアレルギーはなく嫌いなものもほとんどないと教えてくれる。家に鰹節があるかを聞いたら「ない。持ってくる!」と笑顔で鰹節を探しに行ってくれた。
国俊くんから家にないものを聞きながら食材をそろえていると、明石さんと蛍くんが戻ってきた。切れた調味料類を取りに行っていたらしい。かごに入れてもらおうと隙間を開けていると、明石さんがそのかごなり持って行ってしまった。「持ちますよ」と声をかけたのだけど、「重たいもん多いんで」とだけ言ってかごを持ったままレジのほうへ進み始める。「もう何もいらんなら会計いきまっせ」と言うので、慌ててかごの中を確認する。買い忘れはなさそうだ。「大丈夫です」と言えば「はいはい」と帰ってきた。さすがに全額出してもらうのは気が引けるので財布を出そうとしたのだけど、明石さんが「いりませんわ」と軽く睨んできたので大人しくしまっておいた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
明石さんたち三兄弟は木造二階建てのアパートの一室で生活していた。とてもきれいとは言えないアパートに少し驚いてしまう。住人の人とはほとんど関わりがないとのことで、誰もここに人気俳優の明石国行が住んでいるとは知らないとのことだった。ぎしぎしと嫌な音を立てる階段をあがって一番端の部屋の扉が開く。「どうぞ」と言われたので「お邪魔します」と恐る恐る足を踏み入れる。狭い玄関に靴がみっちり出たままになっている。その光景に驚きつつ視線を少しあげると、すぐに台所があり、その先に一部屋だけあるのが見えた。人気俳優である明石国行が住んでいるとは思えない部屋だ。三人いるから荷物がその分多いとはいえ、あまりにもごちゃごちゃしている。きれいに畳まれた布団は二セットしかなくて、三人でそれを共有しているのかもしれない。
「男所帯なんで汚くてすんませんね」
「え、あ、いえ!」
「いや、その顔完全に引いとったやろ」
「そういうわけじゃないんですけど……明石さんのイメージではない、といいますか……」
「なんや、高級マンションに住んどる思うてました~とか言うんか」
「ま、まあ……」
明石さんは若干うんざりした顔をして「そういうイメージ、はよ消えてくれへんかな」と呟いた。明石さんが人気俳優である限りそれが消えるのは難しいだろうと思ってしまったけど黙っておいた。靴を脱いで中に入っていくと、ささっと素早く部屋の隅に蛍くんが移動していった。どうやら私と距離を取っているようだ。怖がられている。今まで人に怖がられたことがないので地味にショックだ。
その近くに明石さんが座布団を折りたたみつつ座り、何事もないように寝転ぶ。「ほな、頼んますわ」とだけ言うと静かに目を閉じた。国俊くんも「腹減った!」と言うのでとりあえずは調理に取り掛かることにした。国俊くんが手伝ってくれるというので、狭い台所に二人並んで立つ。あまり料理は得意ではないというので、簡単な作業を任せることにする。半分になっているカボチャを国俊くんに任せることにして、私は野菜スープに取り掛かる。それを見た国俊くんが「え、オムライスは?」と不思議そうな顔をした。オムライスだけでは足りないかと思って副菜とスープを作るつもりだったのだけど、多かっただろうか。それを説明したら国俊くんがきらきらと目を輝かせて「食べる!」と元気いっぱいに言ったので笑ってしまった。
野菜スープはすぐに仕上がるので鍋にかけて弱火で置いておきつつ、カボチャを切り終えた国俊くんにベーコンを切ってもらう。私はオムライスの準備をしながら横目に国俊くんの作業を見てこまめに指示を出した。切り終わったらフライパンに油をひいてもらってカボチャを並べてベーコンを乗せてもらう。蓋をして弱火で蒸し焼きにする。焼き加減を見張ってもらっているうちに、昨日炊いたと思われるご飯の残りをおかかご飯にする。買い足してもらったばかりの醤油も入れて味を調整して、今度はたまご。たまごを溶いてからほんだしやみりんなどの調味料と、安売りになっていたしらすを入れてかき混ぜる。それを見ていた国俊くんが「和風?」と首を傾げた。「そうだよ」と返したらばっとリビングのほうに顔を向けて「蛍!」と声をかけた。蛍くんはぴくっと反応したのち視線だけ国俊くんに向け、「なに?」小さな声で聞き返した。「オムライス、和風だって!」と国俊くんが言ったところで、ああ、そうか、子どもは和風よりもデミグラスとかケチャップのほうがよかったか、なんて反省する。けれど、蛍くんは国俊くんの言葉にかすかではあったけれど表情を明るくさせた、ように見えた。和風、好きなのかな? 不安に思いつつ二人の様子を窺っていると、「蛍は」と目を瞑ったままの明石さんが口を開いた。
「なんでもかんでも和風好きやもんな」
優しい声だ。それに蛍くんは「うん」と呟いて、それきりまた俯いてしまう。けれど、さっきよりも表情は明るくて、なんだかそわそわとしはじめた。それがなんだかかわいくて、笑ってしまう。
国俊くんに頼んでいたカボチャとベーコンのソテーが仕上がったのでそのまま場所を譲ってもらい、オムライス作りに取り掛かる。私も料理が得意というわけではなく、いかに時間をかけず失敗をしないように作るか、しか考えていないので手の込んだものは作れない。この和風オムライスもそれを考えて作っているものだ。割と味が気に入ったのでたまに作っている。たまごもきれいに形を作らず少しとろみの残るスクランブルエッグにしたら、形を整えて固めてご飯に乗せるだけ。その上にネギを散らしたら完成、という実に簡単なレシピだ。こんな簡単なものでいいだろうか、と不安に思っていると、隣から盛大にお腹の音が鳴ったのが聞こえてきた。国俊くんは恥ずかしそうに笑って「早く食べたい」とだけ言って、出来上がったソテーをそそくさと盛りつけて机に置きに行ってしまった。野菜スープも出来上がったのでそれぞれのお椀によそうと次々と国俊くんが持って行ってくれた。三つよそい終わったところで国俊くんが「へ」と首を傾げる。
「さんの分は?」
「えっ、私の?」
「え、うん?」
「……一緒に食べてもいいの?」
「え?! そりゃそうだろ?!」
兄弟水入らずのところを邪魔していいのだろうか。食費も出していないのに。オムライスも三人分しか作らなかったし、野菜スープは明日も飲めるかと思って多めに作ってはあるけれど。のそっと起き上がった明石さんが「アホちゃいます」とため息交じりに呟くと、かざかざとスーパーの袋から何かを取り出す。紙皿だった。それを一枚出しておもむろに自分のオムライスを分けると「とりあえずこれで」と言って、国俊くんのものと思われるお皿の隣に置いた。
「うちは人数分しか皿があらへんので」
「作ってもうたのにこんなんですんませんね」と言いつつ割り箸とスプーンを置いてくれた。あのスーパーは皿が売ってなかった、とぶつぶつ言ってから「はよ座り」と手招きしてくれる。お椀の代わりにコップを貸してもらって野菜スープをそこによそう。小さい机の上いっぱいに置かれたお皿に明石さんは「今日はパーティーかいな」と笑った。明石さんは料理が得意ではなく、国俊くんは苦手、蛍くんはまったくだめとのことで、普段は基本的に一品しか食卓には出てこないそうだ。大体丼ものが多いと呟いた国俊くんは少し不満げだ。たまにスーパーで安くなっている惣菜を買うらしいけれど、どうも味が三人の好みではないとも言った。
「はい。作ってくれはったさんに感謝しつつ」
ぱちん、と手を合わせる。いただきます、と言った声は三つともきれいに重なっていて、なんだか温かかった。大きな口で頬張った蛍くんの反応にどぎまぎしつつ見ていると、ぱちっと目が合ってしまった。怖がられているのだからじっと見てたら逆効果なのに。慌てて逸らそうとしたのだけど、蛍くんが「おいしい」とはにかんでくれたのが嬉しくて目は逸らせなかった。国俊くんも隣でがつがつと食べているし、明石さんは黙ったままだったけど食べてくれているからまずくはなかったのだろう。少しほっとしつつ私もいただくと、いつもより少しだけうまくできた気がした。
さすが食べ盛り。あっという間にきれいになったお皿たちに思わず笑顔がこぼれる。食べ終わってしばらくは話をしてくれていた国俊くんだったけど、お腹がいっぱいになったら眠気が来たのだろう。そのまま机に突っ伏して寝てしまった。つられるように蛍くんも眠ってしまった。お皿を集めていると明石さんが一つ息をつく。少しだけ、隈がある。疲れているのだろう。明日は映画撮影はお昼からだけど、明石さんは朝からスケジュールが埋まっているに違いない。明石さんのお皿も回収して「洗いますね」と声を掛けたら「そこまでやってくれはるん」と小さく笑われた。お皿を持って立ち上がると明石さんものそのそと立ち上がった。「さすがに客人に全部やらすんはあれなんで」と言って私の隣に立つ。タオルを手に取ったので、どうやら洗ったものを拭いてくれるらしかった。
それからしばらく沈黙が続いて、水が流れる音だけが部屋に響く。何か話したほうがいいか迷ったけれど話題も見つからないしどうしようもない。こういうとき明るくどうでもいい話を振れたらいいのに。そんなふうに落ち込んでいると、明石さんが「蛍は」と口を開いた。
「女が怖いんですわ」
「……女が、ですか」
「まあ、なんちゅうか、母親がね。ろくでもない女やったんで」
「……聞いてもいいんですか?」
「誰にも言わん約束を守ってくれるなら?」
試すように笑われる。それに「誰にも言いませんよ」と困り顔をしたら、なんだかバツの悪そうな顔をされてしまった。
明石さんたち三兄弟は、兄弟だけど明石さんだけ血がつながっていないそうだ。父親が同じで母親が違う。明石さんが十歳のときに母親が病気で亡くなり、その一年後に再婚した人が産んだのが国俊くんと蛍くんだった。明石さん曰く父親は元から暴力的な人だったそうで、結婚して三か月ほどで奥さんへの暴力がはじまったといった。子どものころの明石さんも殴られるのは日常茶飯事で、亡くなった母親も暴力に耐えていたと呟いた。新しい母親も毎日繰り返される暴力で気を病んでいき、人が変わったようにヒステリックになったそうだ。まだ幼かった国俊くん、産まれたばかりの蛍くんに危害が加わらないように、明石さんはわざと意地の悪いことを言っていたという。父親の暴力も、次第に暴力へ変わっていった母親の八つ当たりも、すべて明石さんが受けていたようだった。
両親が借金を抱えたのは明石さんが十六歳のときだったそうだ。儲かる商売がある、と言われて父親がはじめた事業はすべて詐欺だったようで、多額の借金だけが手元に残った。両親はより暴力的になり、日々のストレスを子どもたちへの暴力で発散させていたという。そんな毎日を送り続けたある日、父親が突然失踪。今でも生きているのか死んでいるのかは知らないのだという。残ったのはやっぱり借金だけ。母親は余計に気が狂い、毎日泣き叫んでは明石さんを殴った。ときには国俊くんや蛍くんにもそれが向いていき、明石さん一人ではどうしようもなくなっていったと明石さんは言った。
「殺したったら楽になるんかと思いましたけどね」
そう言った顔は、どこか疲れているように見えて。今までこの人はどれだけ頑張ってきたのだろうと、胸が痛くなった。
ある日、母親の手が蛍くんに及び、最悪の方向へ向きかけた。蛍くんのかわいらしい見た目に目を付けた母親が、蛍くんを売ろうとしたのだという。突然蛍くんを連れて出かけようとした母親にどこへ行くのかを聞くと、にっこり笑って言ったのだという。「蛍をね、ほしいっていう人がいるからね、お金にしてくるのよ」と。明石さんはそれは聞いて新しい家族に引き取られていくのかと思ったと苦笑いした。新しい家族の元へ行くのならそれでいいと思ったとも。母親にどんな人にもらわれるのかと聞いたら、やはりにっこり笑ったままとある店の名前を呟いたそうだ。そのお店は少年少女を食い物にしているところだった。明石さんが子どものころ、父親から殴られるたびに「あそこに売り飛ばすぞ!」と言われていたから知っていたのだ。明石さんは蛍くんを取り返そうと母親に飛び掛かったけれど、腹を刃物で刺されたと言って、思い出すようにわき腹をさする。蛍くんを無理やり引っ張って母親がタクシーに乗り込んだのを、明石さんは腹から血をだらだらと流して追いかけたそうだ。走り去るタクシーを必死に。もうタクシーが見えなくなっても、ずっと、這いずりながら。しばらくして体が動かなくなって、死を覚悟したとき、蛍くんがその手を握ったそうだ。蛍くんは走るタクシーの窓から飛び降りて、足を骨折した状態で明石さんの元へ戻ってきた。交番のおまわりさんに救いを求めて、母親と引きはがしてもらって、必死におまわりさんにお願いをして明石さんの元へ戻ってもらったのだろう。明石さんと蛍くんはすぐに救急車で病院に運ばれ、帰ってきた国俊くんは一旦施設に保護されたそうだ。母親は交番の中で明石さんを刺した刃物で自殺しようとしたが、一命は取り留めたのだという。
そのまま施設に入った、のかと思いきや。施設に国俊くんと蛍くんだけを残して明石さんは入らなかったのだという。高校を辞めて、働かせてくれるところならどこにでも働きに出て、とにかくお金を稼いだ。借金を返して、国俊くんと蛍くんを迎えに行って、三人で暮らすために。けれど、明石さんが思っていた以上に借金は多額だった。とてもふつうに働いて返せる額ではなかった。そう悩んでいるところに声をかけたのが、芸能事務所のスカウトだった。悩まなかったと明石さんは言った。すぐに事務所に所属して、いろんなアルバイトも続けながらもらった仕事はすべてこなした。稼いだお金のほとんどは借金返済に充てて、いくらかは貯金して。そんなふうに必死に働いて三年間を過ごし、名の知れた俳優になったときに二人を迎えに行ったのだと語った。
「俳優やろう思うたきっかけがこんなんて、イメージ崩れるやろ」
「クソみたいなイメージやけど」と笑う。明石さんは庶民的な雰囲気が主婦層から人気がある。でも、苦労をしているとかそういうイメージは一切ないし、そういう話を明石さんがしないから誰も知らない。国俊くんたちの通う学校から漏れるのでは、と思ったけれど、どうやら二人は別の名字を名乗っているようだ。国俊くんのものらしきノートには見覚えのない名字が書かれている。「それ、ここの大家の名字ですわ」と笑う。大家さんは唯一このアパートで明石さんのことを知っているのだという。なんでも明石さんが高校を辞めて住み始めたのがこのアパートで、当時からお世話になっているのだとか。人気俳優になったからとはいえ、未成年の明石さんが二人を引き取れたのも大家さんの手助けがあったからだと言った。
「あの、ここまで聞いてしまってからではあるんですけど」
「なんでっしゃろ」
「いいんですか、私なんかに教えちゃっても……」
あまりにも詳しく話してくれるから私が心配になってしまった。私の問いかけに明石さんは少しきょとんとして、すぐに「あー」と言って視線を逸らしてしまう。
「どうせ喋らんやろ」
「へっ」
「まあ、気にせんといてください。人に話したことなかったんで、ついべらべら喋ってしもうただけなんで」
最後のお皿を渡すと、明石さんはそれをささっと拭いてしまってしまう。濡れたタオルを洗濯機に放り込みつつ財布とスマホをポケットに入れると「家どこですか」と聞いてきた。帽子とサングラスを手に取る様子から、送って行こうとしてくれているようだ。記者に撮られるとまずいので「一人で帰りますから」と断ったけれど、「いやさすがに」と窓を見て呟く。もうどっぷりと暗くなった空に苦笑いをこぼす。知らない間にかなり時間が経ってしまっていた。
結局家まで送ってくれるし、「結構家近いやん」とか言われるし。玄関で座り込んでしまう。情報量の多い一日だった。頭が重たい気がするほどに。思わずへたり込んでしまいながら、明石さんの話を思い出す。両親から暴力を受けて、半分だけ血の繋がる兄弟を守って、殺されかけて。あまりにも壮絶すぎて言葉を失う。ああ、自分はなんて、平坦な道を歩んできたのだろうか。それなのにしょうもないことでぐだぐだ悩んで、仕事も全力でできなくて。ばかみたいだ。大きなため息が出ていく。本当に、ばかみたいだ。
映画撮影、明石さんに迷惑をかけないように頑張らなくちゃ。明日は主人公の妻の前に殺された被害者を見つけるシーンからだ。このシーンが終わったら、主演二人のスケジュールの都合で少し間が開いてから、私が演じる鈴子が明石さん演じる宇藤に連れ去られて殺害されるシーンだ。宇藤に連れ去られて監禁され、散々痛めつけられてから他の被害者と同じように睡眠薬で眠らされる。仰向けの状態でまっすぐに寝かしてから頭部をナイフで一刺し。もう息のない鈴子に最後に口付けを落とすが、もう冷え切ったその唇の感触に自分がなんて無駄なことをし続けていたのかを思い知る。この作品のタイトルを彷彿とさせる重要なシーンだ。小説では宇藤の心境を一枚の絵を完成させるように丁寧に描いており、台詞が一つもないのに何もかもが読み取れるようになっていた。けれど、映画では心境を文章として表現することはもちろんできない。明石さんの演技力にすべて委ねられるということになるのだ。映画でもここは一つも台詞がないシーンになっている。鈴子の夫であり宇藤の相棒でもある崎本が来るまで、宇藤が一人で鈴子を見つめて何もかもを悟るシーンなのだ。明石さんはどう演じるのだろうか。それが少し楽しみでもあり、不安でもある。死体役は何回かやったことがあるけれど、殺されるシーンは久しくやっていない。それに、死んでいるとはいえキスシーンなんかいつぶりだろうか。しかも相手が明石さんなんて。いろんな情報が駆け巡っているから忘れかけていたけれど、私は元々明石さんのファンなのだ。そんな明石さんとキスシーンがあるなんて緊張する以外にない。
大きなため息。気持ちがぐしゃぐしゃだ。結局何をどう頑張ればいいのか分からない。自分のためにどうやって頑張ればいいのだろう。人に迷惑をかけないようにと考えたら緊張して失敗するし、自分のためにと思ったら頑張り方が分からない。こんな私なんか、明石さんから見たらしょうもない人間なのだろう。そう思ったら落ち込んでしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「辛気臭い顔になっとんで」
休憩中、ホットコーヒーを受け取ってからじっと動かずにいたら明石さんにそう声をかけられた。先ほどのシーンで顔に血が付いて、次のシーンはその続きなので顔に血糊がついたままだ。それを思わずふき取ろうとしてしまったらしく「あっぶな」と呟いて手を引っ込める。私の隣に座ると辺りを少し見回してから「悪いんですけど」と小声で言う。
「今日暇ですか」
「え?このあとって意味ですか?」
「まあ、はい」
「暇ですけど……?」
「うち行ったってもらえません?」
「えっ……ど、どうしてですか?」
「嫌ならいいですわ」
嫌とは言ってませんけど! 理由を聞いているのにそんな返答をされるとちょっとムッとしてしまう。明石さんはそんな私に気が付いたのか、少し視線を逸らして「いや、すんません」と呟いた。
「蛍が」
「……蛍くんが?」
「あんたのことちょっと気に入ったみたいで」
「えっ、そうなんですか?」
「また来てくれるんかって、自分に聞いてきたもんやから」
なぜか恥ずかしそうに言われた。蛍くん、そんなふうに思ってくれたんだ。ちょっとうれしい。ムッとしたことなんて一瞬で忘れて「明石さんは?」と聞いてみると、「このあと雑誌撮影なんで」と返ってくる。明石さんが仕事で遅い日は国俊くんがなんとか何かを作って食べるか、二人とも明石さんが帰ってくるまでお腹を空かして待っているのだとか。明石さんはちらりと視線をこちらに向けて「ほんまに暇やったらでええです」と言ってまた視線を逸らした。
「明石さんがいいならいいですけど……」
「……ほんならこれ」
「封筒? なんですか?」
「金」
「……いや、それはいいです」
「いや渡します」
「いりません。代わりに国俊くんと蛍くんと三人でご飯食べてもいいですか?」
「…………なんやそれ、変なやっちゃな」
はにかんだ。その顔がいつも雑誌やテレビで観る少し大人な笑みではなくて、なんだか、かわいいなあと思ってしまった。笑って見ていると明石さんがぎろりと睨んできて「なんでしょーか」とわざとらしく笑われた。そんなふうに笑い合っているとメイクさんが明石さんの髪を直しに来たのでお互い慌てて別の会話を始めた。その慌てようがなんだか明石さんらしくなくて余計に笑ってしまう。メイクさんに諸々を直してもらったあと「ありがとうございます」と言ってメイクさんを見送った。先ほどのメイクさんは他のスタッフさんから聞いたのだけど、どうやら明石さんに気があるらしい。明石さんが気が付いているのかは分からないけれどああいう人と付き合って、とかは考えないのだろうか。かわいらしいし、気さくだし、家庭的そうだし。いや、でも考えてみればそうだ。明石さんは人気俳優なのだから女の人にモテるだろうに、どうして。……そこまで考えて蛍くんのことを思い出した。女の人が怖いのだと明石さんが教えてくれたのだった。本当は男子校に通わせてあげたかったらしいのだけど、この辺りだと私立中学しかなかったし交通費もすごくかかってしまって通わせてあげられなかった。そう、家に送ってもらっているときに教えてもらった。
「ああ、これ貸しときますわ」
「お金は受け取りませんよ」
「ちゃいます。はい」
「……鍵ですか?」
「国俊たちにはチャイム鳴らされても出るなって言うてあって。鍵持っとる人しか家には入られへんので」
また辺りをきょろきょろと見回してからこそっと呟く。「母親、出てきたんやわ」と。明石さんを刺したことと虐待していたことから母親は逮捕されたのだという。刑期を終えて出てきたので念のため警戒しているのだという。明石さんが俳優になって活躍していることを知らないはずがないので、必ず接触してくるだろうと明石さんは眉間にしわを寄せて言った。「まあ、そういうことなんで」と言って無理やり鍵を握らせてきた。それから立ち上がると「休憩終わりまっせ」と言って監督と亀甲さんの元へ歩いて行ってしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
無事にその日のシーンを撮り終えて、一週間ほとんど何も仕事がない日々に入る。主演二人のスケジュールが丸一日取れたのが一週間後だったということで、その日に合わせてラストシーンは撮影となったのだ。本来であれば映画撮影が優先されるのだけど、元から入っていたスケジュールだったということで今回は異例のスケジュールとなったらしい。明石さんから預けられた家の鍵をじっと見る。きれいだ。恐らく予備で家に置いてあったものだろう。こんなの、ほいほい渡しちゃだめなものなのに。苦笑いをこぼしつつあのスーパーへ向かう。いつもはどれが一番安いか、お得かを考えて買っている。でも、妙に何を買おうか楽しく考えている自分がいて、ちょっと恥ずかしくなってしまった。
作ったものを国俊くんと蛍くんはぺろっと平らげてくれた。二人とも前に寝てしまったことを気にしていたみたいで、お皿洗いは二人でする、と言うのでお任せしてしまった。蛍くんはまだ少し怯えてはいるけれど、わたしの目をまっすぐ見て「ありがとう」と言ってくれたから、少しは信頼してもらえているのだろうと思えた。明石さんが帰ってくると私を送ると言い出しそうだったから、明石さんを待たずに帰ろうとしたのだけど。国俊くんが「国行におかえりって言ってやってくれよ」と腕をつかんで阻止してきたので帰るに帰れなくて。結局明石さんが帰ってくるまで二人の話を聞いて待つことになってしまった。
明石さんをどうにかして楽させたいと国俊くんは言った。本当は高校に行かずに明石さんのようにすぐに働きに出たかったのに、明石さんが珍しく強い口調でだめだと言ったから仕方なく進学したらしい。だから少しでも楽できるように勉強を頑張ったのだと苦笑いした。一番近い高校が偏差値の高い公立高校で、中学三年生になったばかりのときには担任の先生に「お前じゃ無理だ」と笑われたそうだ。必死に勉強して今はその高校に通えていると、少しだけ自慢げに言う。
「国行は自分のことを全部後回しにするんだ。俺と蛍のことばっかりで、自分を大事にしてくれなくてさ」
それは、なんとなく分かる、かも。苦笑いをこぼしてしまう。数日しかプライベートでまだ関わっていないけれど、話を聞いた感じだと自分のことよりも弟二人、という感じがする。
膝を抱えて座っている蛍くんも「おれも」と呟く。女の人が苦手な蛍くんを気にして、高校は男子高へ行かせるからと言われているのだそうだ。けれど、家から一番近い男子高は私立高校な上に近いと言ってもバスと電車での通学になる。それを手助けするために国俊くんがアルバイトをすると言い出せば「学生の本分は勉強」と言って許可をくれない。日に日に帰宅が遅くなる明石さんを心配しているのだと二人は言った。たしかに、ここ最近の俳優・明石国行は売れっ子俳優の先頭を走っていると言っても過言ではないほどの仕事量だ。目の下に隈があったのもそれのせいだろう。借金というのはいくらあるのだろうか。そこまで働かないと返せないほどの額なのだろうか。気になって国俊くんにその話を聞いてみる。国俊くんは明石さんがその話を私にしていたとは思わなかったようで、少し驚いたのちに「えっと」と困ったように頭をかく。
「ちらっと子どものころに聞いただけだけど、たしか……ご、五億……?」
「……ご、おく……?」
「だったと思う! そのときは!」
はは、と乾いた笑いをこぼす。蛍くんも少し笑いをこぼす中、私だけが口を開けたまま固まってしまった。五億円の借金って、笑える額じゃない、よね?逆に笑ってしまうというレベルになっているのかもしれないけれど、さすがに私には笑えない。それを、まだ未成年の明石さんは抱えたということ?
国俊くんが言うに、明石さんが俳優業で稼げるようになったのでもう半分くらいは返したらしい、とのことだった。かなりハードなスケジュールをこなし、唯一明石さんの事情を知っている事務所社長の厚意もあって、ようやく半分。それでもまだ半分ある。二億五千万。サラリーマンが生涯に稼ぐと言われる額に近いそれは、私にとっては途方もない額すぎて。現実味がない。
「早く返さないとってずっと焦っててさ」
「どうして焦るの……?」
「最近、なんかつけられてるみたい。うまく撒いてるって言ってたけど」
「週刊誌の記者」と国俊くんは呟く。まだこの家にはたどり着いていないらしい。けど、仕事終わりにやたら追いかけられたり、プライベートも張り付いてきたりして面倒くさそうにしていたと笑った。もし週刊誌にすっぱ抜かれたとしても、ファンの人は明石さんを真面目な家族想いな人だと思うだけなんじゃないだろうか。私がそう言うと国俊くんは「それが嫌なんだって」とまた苦笑いをこぼす。
「家族を売り物みたいにして稼ぎたくないんだってさ」
家族想いないい人じゃないか。ただそれだけのことなのにそれは家族のためにならないから、明石さんは一人で踏ん張っているのだ。そう思ったら、ぎゅっと拳を強く握ってしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
明石さんの家にこっそり通うようになって五日目。その日も夕飯の買い物をしたあとで明石さんの家に向かって歩いていた。二人の様子を見ていたら蛍くんは和風のものや味付けが好きみたいだけど、国俊くんは洋風のものが好きみたいだった。だから今日は二人別々のメニューしてみようかな、なんて思いながら。明石さんは五日間連続で遅く帰ってきているのだという。私は用事があったりバイトがあったりしてご飯だけ作って帰ったという日が三日間あったから知らなかったけれど。国俊くん曰く私が作った明石さんの分のご飯を食べたらすぐに寝てしまうのだという。そうして二人が学校へ行くために起きるともういない。朝ごはんのおにぎりだけが机に置いてあるのだという。映画のスケジュールを取るために強行スケジュールになっているのだろう。映画の撮影が終わるまではきっと二人は遅くまで明石さんを待つことになる。そう思うと少し胸が痛んだ。
スーパーの袋を片手にぶら下げて少し俯き加減で歩いていき、明石さんたちが住んでいるアパートが見えてきた。今日も住人の人は誰も外に出ていない。人気のないところだなあと改めて思っていると、大きな音が聞こえた。びっくりして思わず音がしたほうを見ると、アパートの二階。明石さんたちの、部屋だった。
走ってアパートに向かっていくと、国俊くんの大きな声が聞こえてきた。「蛍!」と蛍くんを呼ぶ声。それと同時に部屋から髪の長い女の人が出てきた。蛍くんを引きずるようにしながら階段を駆け下りていく。部屋から出てきた国俊くんは、足を引きずっていた。それを見た瞬間、持っていた自分の荷物もスーパーの袋も全部かなぐり捨てて、走り去ろうとする女の人を追いかけていた。出したことがないくらい大きな声で「蛍くん!」と叫んだら、ぼろぼろと涙をこぼしている蛍くんが私を見た。その表情が恐怖に染まっているのが、離れているのにすぐ分かって。カッと自分の中で何かが溢れ出たのがなんとなく分かった。蛍くんを抱えている分向こうのほうが走る速度が遅い。すぐに追いつけた。その女の人の腕をつかんで引っ張ると、ぎらりと鋭い目つきで睨まれる。よく見たら、蛍くんは少し朦朧としている様子で、顔に怪我をしていた。それですぐにこの人が蛍くんたちの母親なのだと分かった。
連れて行かせちゃだめだ。明石さんが必死に守ってきたものを、壊させちゃいけない。守らなくちゃ。私が、守らなくちゃ。
追いついてきた国俊くんが「さんそいつナイフ持ってる!」と叫ぶ。よく見ると、その人の右手には果物ナイフのようなものがきらりと光っている。怖くない、とは、言えなかった。でも、それでも、この手を離しちゃいけない。
「離しなさい、この子たちは私の息子よ、私がどうしようと勝手じゃない!」
金切り声のような叫びだった。キンキンと耳に痛くてとても聞いていられない。蛍くんはぼろぼろと涙をこぼして、苦しそうな声で、「さん」と、はじめて私の名前を呼んだ。ぐっと握った拳を振りかぶって、人生ではじめて人を殴った。それに驚いたその人はよろついた瞬間にナイフを指から滑らせて落としてしまう。必死にそれを足で蹴飛ばすと、国俊くんが足を引きずりながら拾ってくれた。それでも蛍くんのことを離さそうとしない。母親は肩で息をしながら「国行は一銭も金を寄越さない親不孝なやつだから、蛍を売るのよ!」と言った。虫唾が走るというのは、こういうことなのだろう。もう一度拳をぐっと握って振りかぶったけど、避けられた。その代わりに長い爪のその人の平手が私の右頬に飛んできて、引っかかれた感覚があった。鈍い痛みが頬全体に走って、たらりと血が流れたのが分かってしまう。蛍くんが泣いている。昨日まではぎこちなくではあったけど、笑ってくれていたのに。この涙は紛れもなくこの母親が泣かさせたものだ。それを意に介さず自分の私利私欲のために、家族を売ろうとしている。明石さんがこれまで、二人を笑顔にするために、どれだけ頑張ったかなんて微塵にも考えていない。むしろこの人は一瞬ですべてを壊した。そう思ったらなぜだか涙がこぼれ落ちて、掴みかかるようにその人に飛び掛かっていた。なんとか蛍くんをその人の手から逃して国俊くんに任せる。二人に「逃げなさい!」と叫んだのに、二人ともその場から動こうとしない。その人を押さえているのも限界がある。私より背が高いし、たぶん若いころにやんちゃをしていたみたいだから喧嘩してもたぶん勝てない。だから、早く逃げてくれないとまた捕まってしまう。
「いいから逃げなさい!!」
びくっと国俊くんが肩を震わせる。小さく頷くと、ナイフは持ったまま蛍くんを連れて走っていった。それでいい。二人の背中がだいぶ小さくなったところで力尽きた。緩んだ私の腕からその人が逃げると、「あんたのせいで!!」と殴られた。髪をつかまれて地面に叩き付けられる。そのまま馬乗りになられてどことも分からないくらいめちゃくちゃに殴られる。痛い。人を殴ったのもはじめてだったけど、ここまで殴られたのもはじめてだ。鈍い痛みが顔全体にどすどすと襲い掛かってくる。国俊くんがナイフを持って行ってくれなかったら、今頃何度も刺されて死んでいただろう。そのほうが楽だったかもしれない。そんなふうに思っていると、慌てた足音が聞こえてきた。そうして私に馬乗りになっていた人が蹴り飛ばされると、わんわん泣いた蛍くんが私に抱き着いてきた。
「なに無茶なことしとんねん!」
その人を押さえ込みながら明石さんが私を睨み付ける。見たことがないくらい必死の形相で、額に汗をかいて。それがなんだかおもしろくて笑ってしまった瞬間、意識が途絶えた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
霞んでいく視界。咳が止まらず頭が燃えているのかと思うくらいに熱い。何度も閉じかける瞼を堪えていると、誰かが手を握ってくれているのに気が付いた。そうっと顔を横に向けると、私の手を握って明石国行が座っていた。「起きたん」と優しい声で言う。小さく頷くと明石国行は「主はん、また無茶して倒れはったんやで」と呆れ声で言った。子どものころから体があまり強くなかった。審神者になってから、政府の人も何度も様子を見に来ては「無茶しちゃだめだよ」と言ってくれた。刀剣男士たちもみんな、そう言ってくれた。でもそう言われるたびにもっと頑張らなくちゃって思ってしまって。私が頑張らないと何もかもがだめになってしまう。そう強く思うようになっていた。
病気が見つかったのは一年前だ。薬を飲んでいるけれど、一向に良くならない。どんなに頑張りたくても起き上がれないし、うまく言葉を出せない。ああ、死ぬんだなあ、とぼんやり分かった。もっと頑張ればよかったのだろうか。もっと、もっと、もっと。そうしたらもっと、この人と生きられたのだろうか。
ぽたりと手に冷たいものが落ちたのが分かった。明石国行が私の手を額に当てて「あっつ」と泣いている、ような、笑っているような。よく分からない声で呟いたのが聞こえる。
「こんな、頑張らんでええのに。頑張らんと、のんびり、気ままに、おってくれるだけでよかったのに」
その声を聞いたら、ああ、私、やっぱりこの人のために頑張りたい、そう思った。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
目が覚めたとき、まず視界に入ったのは泣きそうなんだか怒り狂いそうなんだか分からないマネージャーさんの顔だった。ひとしきり心配したという話をしたあとに「今、映画撮影中なの分かってる?!」と激しく怒られた。そうっと右頬を触ってみるとかなり分厚いガーゼが貼られている。ああ、そうか、爪で引っかかれたんだっけ。顔もぼこぼこに殴られたから迷惑かけちゃうなあ。でも後悔はしていなかった。あれは間違いじゃなかった。私はああして正解だったと胸を張って答えられる。
マネージャーさん曰く、私を殴った〝暴力女〟は傷害で現行犯逮捕されたそうだ。足を怪我した〝通りすがりの男子高校生〟は大した怪我ではなくもう家に戻っているらしい。もう一人の男子中学生も、首を絞められた痕があったり暴力を受けた痕はあったけれど、どれも大事には至らなかったそうだ。マネージャーさんはそこまで話してから、誰も病室に近付いていないかちらりと背後を確認する。そうしてこそっと「明石国行さんとはどういう関係なんですか」と困り顔で聞いてきた。警察にはアパートの大家さんが通報してくれたそうなのだけど、私の所属事務所には明石さんが連絡してくれたのだという。なんと答えようか迷ったけれど「たまたま近くを通りがかっただけだと思います」と誤魔化しておいた。マネージャーさんは怪訝そうな顔をしつつ「でも目が覚めたら連絡くださいって言われたんだけど」と言ってスマホの画面を見せてくれる。交換したらしい明石さんの番号が表示されていた。「共演者だから気を遣ってくれてるんですよ」と言えばマネージャーさんは「まあ、それもそうか」とようやく納得してくれた。
マネージャーさんは明石さんに連絡を入れたあと、別で担当している女優の現場に行かないといけないから、と言って病室から出て行った。それを見送ってから、どっと疲れが全身に回った感覚がした。じんじんと痛い、どこだろう。全身が痛いからどこが痛いのかもよく分からなかったけど、じんじんと痛んでいるのは右手だった。はじめて人を殴った。拳を握って、思いっきり振りかぶって。あんなに腹が立ったのは人生ではじめてだったかもしれない。じんじん痛い。痛いのは好きじゃない。けれど、なんでか気持ちはすっきりしている。守れた。ただそれだけで私は十分救われたような気持になっていた。不謹慎な言い方かもしれない。けど、なんだか自分が自分じゃなかったみたいな、不思議な感じがあった。頑張れたじゃん。そう自分に言ってしまう。怖かったのに。ナイフを持っていたし、絶対力では勝てそうもない相手だったのに。迷わず立ち向かえた。怯まなかった。それが、なぜだか、すごく、うれしかった。
明石さんのことを思い出す。明石さんは自分のことを後回しにするけど、国俊くんと蛍くんのことは第一に考えていて、二人のためなら無茶もしてしまう。〝やる気ないならやる気出さんままでええんとちゃいます?〟と言われたことを思い出した。言われたときは嫌味で言われたのかと思って謝ってしまった。やる気のないやつは頑張ったってどうにもならない、とかそういう意味なのかと思ったのだ。でも、たぶんちがうのだ。
一人でじんじんする右手を眺めていたら、突然慌ただしい足音が聞こえてくる。看護師さんが「すみません、病棟では走らないでください!」と注意をした声が聞こえて、そのあとに「すんません」とのんびりした声が聞こえた。ああ、もう誰だか分かった。足音の数で誰と一緒なのかも分かる。それに少し笑いをこぼしていると、思った通りドアをノックされた。返事をしたらこちらも慌ただしくドアが開き、心配そうな顔をした二人と呆れ顔をした一人が病室に入ってきた。
「さん、大丈夫か?!」
「国俊うるさいよ、病院だから静かにしなきゃだめじゃん」
「蛍もさっき入口でうるさくしただろ?!」
「はいはい、二人とも静かにしーや」
後ろ手に病室のドアを閉めながら明石さんがため息交じりに呟く。国俊くんが一番にベッドの横の椅子に腰を下ろす。それに続いて控えめに蛍くんも座った。蛍くんは頬に私と同じようなガーゼを貼られていて、国俊くんは足に包帯を巻いている。怪我はしているけれど聞いていた通り大きな怪我ではなさそうだ。それにほっとしていると国俊くんがなんだか複雑そうな顔をする。
「その……こんなこと言ったら怒られるかもしれないけど……」
「うん?」
「あのときさんが来てくれて、すげー、安心した。こんな怪我させちゃったけど」
「おれも……」
二人は揃って顔を俯かせて罪悪感があるような表情をしている。ぎゅっと服をつかんでから国俊くんが「ごめんなさい」と頭を下げた。蛍くんも一緒に頭を下げながら「ごめんなさい」と言う。それをやめさせようと体を起こそうとしたら明石さんが「そのままでええです」と言って二人の後ろに立った。頭を下げた二人の顔を手で無理やり上げると、「お前らは謝らんでええ」と呟いて、手を離す。それから私の顔をじっと見て、突然頭を下げた。
「うちの事情に巻き込んで怪我させてすみません」
「いえ、あの」
「自分らと関わらんかったらせんかった怪我や。治療費は全額、」
「あの!」
「……なんでしょうか」
明石さんは頭を上げて「治療費受け取ってもらうまで帰らんで」と言いつつ困り顔で頬をかく。国俊くんも蛍くんも、大人がするような深刻そうな顔をして俯いたままだ。笑ってほしいのに。蛍くんも国俊くんも無事だったと笑ってほしいのに。明石さんが十代のときから必死に守ろうとした笑顔を見たいのに。
そのとき、ふと、頭の中で〝頑張らなきゃ〟と誰かの声が聞こえた。誰の声かは分からない。聞いたことのあるような、いつも聞いているような、それでいて聞き馴染のないような。そんな不思議な声だったように思う。
少しだけ開いた窓から穏やかな風が吹き込む。カーテンが揺れて光が部屋に入り込む。ちらちらと視界の隅でそれが光ると、遠くのほうで鳥の鳴き声がした。髪が揺れる。私の伸びた髪が。国俊くんの短い髪が。蛍くんの艶のある髪が。明石さんの前髪が。それを見た瞬間に、なぜだか涙が溢れた。ああ、私、この人たちのために頑張りたい。なぜだろう。なぜか分からないけれど、そんなおこがましいことを思った。
そんな私を見て国俊くんが焦ったように「どこか痛いのか?!」と顔を覗き込む。蛍くんも恐る恐る私の顔を覗き込んで「痛いの?」と聞いてくる。明石さんは少しだけ焦ったように「せやから治療費出すんで」と机に置いてあったティッシュを一枚取って渡してくれた。それを受け取って少し笑いつつ涙を拭う。
「痛くはないです」
「じゃあなんですの」
「こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれないですけど」
「はあ」
「うれしくて」
「……はあ?」
「私にも頑張りたいと思えることがあるんだな、と思って」
国俊くんと蛍くんはよく分からないというような表情で顔を見合わせている。明石さんは少し間抜けな顔をしてから思い出したように視線を逸らしてから「アホちゃいます」と少し笑った。
「頑張りたいと思えることだけ頑張ればいいんですもんね」
頑張りたくないことを頑張ろうと思い込もうとしたって無駄なのだ。私にとっての頑張りたいことは女優の仕事じゃない。自分のために何かすることでもない。全部、考えたって無駄なことだったのだ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「えらいきれいに隠してもうてますけど、アップはきつそうやな」
私の髪を持ち上げるようにして顔を覗き込んだ明石さんはそうため息をつく。一日の入院を経てついにラストシーンの撮影日を迎えた。マネージャーさんから元々怪我をしたと連絡はしてもらってあったけれど、現場に入った私の顔を見た瞬間ほんの少しだけ現場は騒然とした。メイクさんが数人集まってプチ会議をはじめたり、監督と助監督がこそこそと話し合いをはじめたり。その様子にマネージャーさんは胃が痛そうだったけれど、メイクさんたちの尽力があってなんとか監督からオーケーをもらえた。引っかき痕は特殊メイクかと思うほどの濃いメイクで隠してもらい、今まで撮影したシーンと差異が出ないように色もなんとか合わせてもらった。キスシーン以外は明石さんのアップが多いし引きが多いのでなんとかなりそうだ。
明石さんは私の隣に座りつつ話そうかどうしようか悩んでいるようなそぶりを見せた。気が付かないふりをしつつ「なんですか?」と聞いてみる。明石さんは「あー」と少し言いづらそうではあったけれど、口を開いてくれた。
「借金、なんやけど」
「……ここでしていい話ですか?」
「言うといたほうがええかと」
「何があったんですか?」
「…………亀甲が」
「亀甲さんが?」
「肩代わり、してくれましてね」
「……二億五千万ですか?!」
「声が大きいわ!」
ばしっと頭を叩かれた。それをさすりつつ「か、肩代わりって」と驚くしかできない。二億五千万を肩代わりしてくれるって、ちょっと理解が追い付かないのは仕方ないだろう。明石さんは少しためらいつつも、「話したんですわ、亀甲には」と頬杖をつく。私が怪我をしたことも、その怪我の原因も、その原因の根源も、亀甲さんにはスタッフさんたちが知る前に個人的に話したそうだ。そうしたら亀甲さんはけろっとした顔で「二億五千万円? キャッシュでいいのかな?」と言い放ったそうだ。明石さんがその平然さに困惑していると亀甲さんはいつから借金を返し続けているのかとかどこから借りているのかとか、いろいろなことをてきぱきと質問してきた。明石さんが困惑しつつ答えると最終的に「そんな馬鹿みたいなところから借りてたら一生返せないよ」と苦笑いをされたそうだ。亀甲さんは「利子も馬鹿にならないし、一括で返してしまおうか」と再びとんでもないことを言い放ち、自分のスマホでどこかに電話をかけはじめたのだそうだ。そうしてあれよあれよという間に事が進んでいき、亀甲さんはにっこり笑って「払ったよ!」と明石さんに言ったとのことだ。恐る恐る明石さんがいつもお金を返していた金貸しに電話すると「もう返してもらった」との返答だった。
「何が起こっとるんかよう分からへんわ……」
「し、資産家の息子さんとはいえ、次元がちがいますね……」
亀甲さんはけろっとした顔で「お世話になりましたから!」と言ったそうだが、明石さんは慌てて「いや返すから!」と今まで交換していなかった連絡先を速攻で交換したと疲れた顔をして言った。亀甲さんは「いいのに」と言いつつ「のんびりでいいですよ。利子もないですから増えることもないですし」と笑って明石さんの連絡先を眺めていたそうだ。明石さんが恐る恐るそのお金はどこから湧いたのかを聞いたら、亀甲さんがお父さんからもらったお金を学生時代に遊びではじめた投資で膨らませた残りだと言われたという。残りが二億五千万円あるって、どんな世界なのだろうか。
二人で撮影に向かう亀甲さんの背中に手を合わせつつ、「感謝ですね、本当に」と明石さんに笑いかける。「いや、感謝ちゅう言葉で片付けられる次元ちゃうやろ」とため息をつかれた。
「……亀甲から貸す条件を二つ出されましてね」
「条件? なんですか?」
「一つは今まで通り接することで、もう一つは素直になることやそうです」
「……ざっくりしてますね?」
「まあ、せやな」
明石さんはコーヒーを一口飲む。また一つ息を吐くと、そうっと私の顔を見た。
「……あんなことがあっても、また、うち来たってくださいて言うたら怒ります?」
「……ははは」
「嫌やったらええです」
「素直になってくれるんじゃないんですか」
「…………嫌やわあ、あんたみたいな女」
「ひどくないですか?!」
ばしっと明石さんの背中を叩く。「いった」と顔をしかめられたけれど、笑いは治まらなかった。憧れの人だった。ファンだし、尊敬している。でも、以前に感じていた後ろめたさみたいなものはもう微塵もなくなっていた。
「……またうち来てめっちゃおいしいわけやない飯作ってください」
「言い方が変じゃないですか」
「めっちゃおいしいわけやないでしょ、ふつうにおいしいでええですやん」
「じゃあそう言ってくださいよ!」
けらけら笑っていると明石さんはなぜだか顔を赤くさせて「もう嫌やわ」と呟く。その照れっぷりが女の子みたいに見えて私は余計に笑ってしまう。私がくすくす笑っているのをなんだか照れくさそうに横目で見つつ「蛍と国俊が来てほしい言うとっただけなんで」と拗ねたような声で言われた。それが少し子どもみたいでかわいいな、なんて思ってしまった。長身モデルで人気俳優の明石さんのかわいいって。そのギャップに笑ってしまうと明石さんは余計に照れくさそうな顔をしてしまった。この前までこの人と大事なシーンを演じることに緊張しかなかったのに、もうへっちゃらになったように思える。亀甲さんが今から撮影するシーンが終わったら、鈴子が宇藤に殺されるシーンから。その次にキスシーンだ。ホットコーヒーが入った紙コップを両手で持って、一つ息を吐く。
「私、この映画を撮り終わったら、女優を辞めようと思うんです」
「……えらい思いきりますね」
「向いてないですしいまいち情熱を持てなくて」
「何しはるんですか、そのあとは」
「とりあえず就活をします。それまでは今やっているアルバイトで食いつなごうかと」
コーヒーがほんの少しだけ波を立てる。それを見て自分の手が震えていることに気が付いた。なんだ、やっぱり緊張してるんだ。少しだけ情けない。紙コップを持つ両手に力を入れ直す。波が穏やかに凪いでいき、なんとか平穏な水面になった。
「明石さんさえ良ければ、そのあとも、たまに、お邪魔していいですか」
あ、また波が立ってしまった。きゅっと口を閉じて黙り込む私を、明石さんがようやく顔をこちらに向け直して見ている。目をぱちくりさせてぼけっとただただ私の顔を見ているので、少し気まずくなってしまう。思わず明石さんの真似をして「い、嫌やったら、ええです」と先に口を開いてしまった。私のその発言に明石さんはふっと吹き出して「イントネーションおかしいやろ」と口元を手で覆って笑う。
明石さんはポケットからスマホを取り出す。ただ、そのスマホは今まで何度か見たものと違っていた。たぶん前に見たものとは色もちがうし、たぶんメーカーもちがう。不思議に思っていると明石さんは「スマホ出さんかい」と呆れ顔をした。慌てて私も鞄からスマホを出すと「連絡先」とだけ言われたので、ようやく意味を把握した。明石さんは「これはプライべート用なんで、蛍と国俊、あと亀甲くらいにしか教えとりませんわ」と悪戯っぽく笑う。
交換し終わるとすぐにスマホをポケットにしまう。持っていたコーヒーを机の上に置くと、頬杖をついてじっと私の顔を見る。
「あげますわ」
「え、何をですか?」
「前渡した鍵」
そう言われて前に貸してもらった鍵を返しそびれていたことを思い出した。財布の中に入れてあるそれを思い出す。明石さんは「なくさんといてください」と言って、腕を伸ばして一緒に体も伸ばす。「んーっ」となんだか少しおじさんくさい声をもらしつつ伸びをした。そうして、「まあ、好きなときに来たってください」と言ってから立ち上がってふらふらと歩いて行ってしまう。髪をかくその手つきをぼけっと見ていると、ふいにこちらを振り返った。柔らかく笑うと「撮影、見に行きまっせ」と手招きしてくれた。明石さんのコーヒーの隣に私もコーヒーを置いて、慌てて追いかける。よく見ると他のスタッフさんたちももう撮影間近ということもあって辺りにいなかった。明石さんの隣に追いついてから一つ大きく呼吸をする。運動不足だろうか、少し走っただけなのに心臓がどきどきとうるさい。
「まあ、なんもせんでええんで」
「え?」
「さんはなーんもせんと来てくれるだけでええんで、お願いしますわ」
「いろいろと」と言ってから近くにいたスタッフさんに声をかけて明石さんは俳優の顔に戻ってしまった。その背中は今まで私が憧れた俳優・明石国行のもので間違いはない。けれど、私にはその背中に何が背負われているのかが見えていて。明石さんがどれだけ頑張って来たのかとか、どれだけ走り続けてきたのかとか。そういうのを全部知りたいという、おこがましい願望を抱いてしまう。全部知っているわけじゃないのに、この人が頑張ってきたものを私も、踏み込んでいいのならば頑張って守りたいと思ってしまう。頭の中で聞こえた〝頑張らなきゃ〟の声を思い出した。ああ、私、この人のために頑張りたい。いらないって言われても頑張りたい。私にとってその頑張りはきっと、今まで惰性でやってきたどんなそれよりも、意味のあるものだと思うから。
けれども、まあ。たまに気を抜いてしまっても許してくれるとうれしい。きっとそんなことは咎めないであろうゆるゆると気だるげな背中。どきどきとまだうるさい心臓を隠すように息を吐いてから、少し笑ってしまった。
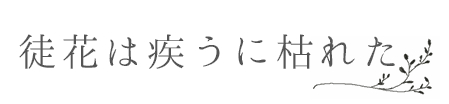
material by phantom