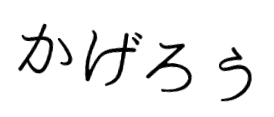
これほどまでに目覚めの悪い朝はない。 目が覚めた瞬間に何もかもが頭をめぐってしまった。 アルコールに弱いことは重々承知している。 けれど、どれだけ激しく酔っても、記憶をなくしたことはただの一度もない。 だから、自分が服を着ていないことも、裸のままわたしに腕枕をしている侑の理由も、何もかも覚えている。
そうっとベッドから抜け出す。 さすがに裸でうろつくのは憚られたので服を探したけど見当たらない。 耳をすませば洗濯機が動いている音が聞こえるので、侑が洗濯してくれたのかもしれない。 困った。 服がない。 どうしようか迷った結果、眠りこけている侑に小声で謝ってからタンスを開けさせもらった。 長袖のパーカーを一着拝借して恐る恐る着る。 さすがに下着を借りるわけにはいかないし、そのままズボンを穿くわけにもいかなかったので下は遠慮しておいた。 部屋を見渡すと掛け時計が目に入る。 朝五時半。 今日は土曜日だから大学はないにしてもバレー部の練習はあるのかもしれない。 起こしたほうがいいのか迷っていると、枕元に置かれている侑のものらしいスマホが鳴った。 起きる! そう思ったら焦ってしまって急いでスマホを持って廊下に逃げてしまった。 静かにドアを閉める。 スマホの画面には治の名前が表示されている。 メッセージアプリの通知はロック画面でも本文が読めるようにされている設定だ。 「九時には帰るでそのつもりで」という文章と最後に怒りマークがつけられている。 治は侑と同じ大学だし、同じバレー部だ。 九時に家に帰ってくるということは部活は休みなのだろうか。 よく分からないけれど九時までは起こさなくて大丈夫なようだ。 それに一人でほっとしていると、「人のスマホ握りしめて何しとんねん」と声が背後から聞こえた。
「……お、はよう、ございます……」
「飯なに食う? インスタントの味噌汁かパンしかないけど」
「おみそ、しるで……これ、治から……」
「ん」
スマホを手渡す。 メッセージをちらりと見てからあくびをこぼした。 そんな侑に「あの、部活とか……」と声をかけたけど、予想通り「オフや」と返事があった。
そうっと視線を下げる。 よかった、ちゃんとスウェットの下だけは穿いてる。 ほっとしていると侑が「ちゅうか、お前それ」とじいっとわたしのことを見ている。 あ、勝手に借りたから怒ってる。 そう思って焦りつつ謝ると「いや、そうやなくて」と怪訝そうな顔をする。 そうするとリビングにそそくさと戻り、タンスの二段目を開ける。 似たようなパーカーを引っ張り出すと「こっち」とわたしに投げた。 これは着ちゃだめなパーカーだったのかな。 ブランドの高いやつとか? あまりその辺りに詳しくないので知らない間に爆弾を踏んでいる気がする。 謝ると侑は「ちゃう」と拗ねたような顔をした。
「それ、治の」
「せやから着替えて」と言ってキッチンのほうへ歩いて行った。 その理由がよく分からなかったけど、とりあえずドアを閉めて廊下でいそいそと着替え直した。 着替え直してから治のパーカーは洗濯に出したほうがいい思って、洗濯機の音を頼りに洗面所を見つけてその前に置いておいた。
リビングに戻ると侑が電気ケトルでお湯を沸かしているところだった。 そうっとベッドのほうを見る。 近くに置いてあるごみ箱の中が見えた。 そこに入っている、恐らく昨日使ったであろうものが見えて内心ほっとした。 記憶はあるんだけど頭がふわふわしてたから、ちゃんと、してたかまでは、覚えてない。 ついでに酔っていたせいもあるのか、はじめてだったのにそこまで痛かった記憶もない。 だから最後までしてないのかな、と淡い期待を持っていたのだけどごみ箱の中のものがそれをぶち壊したというわけだった。 ただ一番最悪の事態、つけずにした、ということはなさそうでほっとしたけど。
「味噌汁だけでええん?」
「う、はい……うん……?」
「なんやその返事。 ふつうにせえや」
けらけら笑う。 高校時代のまんまだ。 上半身裸なところは見ないふりをしておくことにした。 侑から受け取ったインスタントのお味噌汁をすする。 侑はそんなわたしをじいっと見ながらパンを食べている。 無言。 お互い無言で食糧補給を続けた。
わたしはお味噌汁だけ、侑はパン一個だけということもあって二人ともすぐに完食した。 先に食べ終わった侑はわたしが飲み終わるのを待っていたように「ちょおそこ座っとって」と言うと、立ち上がってわたしの隣に立つ。 何をするのかと思って見ていると、突然膝を床につけた。 そのまま手を床について額も床につける。 土下座だ。 あまりに驚愕すぎて固まっているわたしなど置いてけぼりのまま、侑はなんとも美しいフォームで土下座をしている。
「すまん」
「えっ」
「が何も考えられんくらい酔うとんの、分かっとって、手、出した。 すまん」
「なんか飲みもんに入れられたんかもっちゅうのも、分かったのに」と弱弱しい声で呟かれた。 飲み物に何か入れられた。 もしそうだとすればたぶん、あの鬱陶しい男から一度逃げてお手洗いに立ったときだろうか。 そうだとしたらふざけて言っていたホテルに行くという発言もなんだかゾッとした。 侑が来てくれなかったら、あの男にホテルへ連れていかれていたのかもしれない。 そう思ったらつい、へらりと笑ってしまった。
「……謝らんといて。 変な男にされるくらいやったら、相手が侑でよかったわ」
「……嘘吐き」
「え」
「なんなん、お前、ほんまに。 せやったら、なんで」
顔を上げた。 侑の目からぽろっと涙が少しだけ流れたのが見えて、うろたえてしまう。
「なんで、ずっと、北さんのこと、呼んどったん」
全身がびしっと、金縛りにあったように固まる。 そんなの覚えてない。 北さん、なんて、呼んだっけ。 三年も前に失恋した相手の名前なんか。 なんで呼んじゃうんだろう、わたし。 恥ずかしいやつ。
侑は立ち上がると乱暴にわたしの腕をつかむ。 そのまま引っ張られいき、最終的にベッドに投げつられた。 侑が馬乗りになると静かに唇を首筋にあてる。 ぞわっとして「な、なに」と身をよじって抵抗する。 侑は右手でわたしの両手を捕まえると、わたしの頭のすぐ上に押さえつけた。
「なあ、なんで北さんなん。 振り向かへん人、なんでずっと追いかけるん」
苦しそうな顔だった。 侑のそんな顔は見たことがなくて、言葉を失う。 ぎゅうっと掴まれた両手首が少し痛い。 でも、それよりも侑の顔が苦しそうなことのほうが気になった。
「俺じゃあかんのか」
ぽとりと頬に雫が落ちてきた。 侑の表情と、言葉と、涙。 ああ、うん、そうか。 納得した。 わたしが高校時代に侑に感じていた苦手意識。 妙に他の人より優しくされているというか、構われているというか。 あれは全部、好意からくるものだったのだ。
「北さんより俺のほうがのこと好きやで。 せやのに、ちっとも俺んこと見ようとせえへん」
ぐずぐずと泣き始めた。 その様子に慌ててしまって「ご、ごめん」と思わず口走ってしまうと、侑は「そういうん! そういうよう分かってへんのに謝るとこ!」と全力で頬をつねってきた。 そのあとでぱっと手を離してくれた。 少しだけ手首に跡がついているけど、すぐに消えそうだ。 わたしの体をぐいっと引きあげると、侑は隣に座り直した。
「北さんのこと忘れたやろってくらいに連絡して、ちゃんと告って、付き合うて、手繋いで、ちゅーして、えっちしよって思っとったのに」
「……手繋いで、ちゅーして、えっちはしたやん」
「最悪や、ほんまに。 俺めっちゃ最低やん」
「しかもまだ北さんのこと忘れとらんしな!」と睨まれる。 なんとも返事がしがたい。 自分でもまだ忘れてないなんて思わなかったのだから。 侑はそのまま寝転ぶと「ええで、殴っても」とため息を吐く。 ぼさぼさになった髪をちょいちょいと手で直しているようだけど、寝転んでいるからうまく直せていない。 わたしも寝ぐせついてないかな。 そう思って髪を触ると、侑が「ちゃう、もっと右」と指をさす。 寝ぐせの場所を教えてくれているらしい。 右に手をずらすとたしかに髪が跳ねていた。
「……こんなこと言うたら余計にあれやろうけど」
「なんやねん」
「わたし、はじめてやったんやけど」
「…………嘘やん」
「ほんま」
「いやたしかにかなりきつくてよかったけど」
「痛くなかったんは侑が経験豊富やからなんかな」
「アホかお前。 いつから俺が片思いしとると思っとんねん」
「……誰に?」
「お前にやわ。 ふざけんな、ほんまにどつくで」
「……嘘やん」
「嘘ちゃうわ。 お互いビギナー卒業できてよかったやんけ。 最悪やほんまにふざけんなクソ」
やけくそかというほど乾いた笑いをこぼして侑は「ほんまに最悪や」と呟いてため息をこぼした。