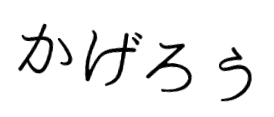
久しぶりに飲んだアルコールが体中に回ってふわふわする。 ふらふらと侑の後ろをついていっているのだけど、途中で手を繋がれていることに気が付いて。 なんで手なんか繋いでるんだろ。 ちゃんと回らない頭では答えは見つけられなかった。
侑は今、治とルームシェアをしているらしい。 あの居酒屋は治のバイト先であり侑のバイト先でもあると言った。 すぐ近くの少し広い部屋を、家賃やら食費やらを折半して暮らしている。 そんな近況報告をぼんやり聞きつつ侑に手を引かれたまま歩いていく。
「なあ、ほんまにアホちゃうん。 こんなくたくたになるまで酔うとか、ほんまに」
何度呆れ声で言われたか分からない。 ぐずぐずと鼻をすすりながらとりあえず「うん」とだけ返し続けている。 侑はひたすらに歩き続けていたけれど、ようやく少しだけ立ち止まった。 マンションの前だ。 オートロックの操作をしている。 何事もなく扉が開くと、侑はすぐそばにあるエレベーターに乗った。 一緒に乗りこみ、また侑の横でぐずぐずと鼻をすする。 侑は階数ボタンを押してからわたしの顔を覗き込むように身を屈める。 「ブッサイクな顔になっとんで」と言いつつ指でわたしの頬を撫でるように涙をすくい取った。
「これに懲りたら合コンなんか行かんことやな」
けっと吐き捨てるように言われる。 高校のときから侑は、むかつくけど真しか言わない。 だから頷くしかできなかった。 だって人数合わせで呼ばれて、どうしてもって頼まれて。 そんな言い訳は一つも口から出て行かなかった。
エレベーターから降りると、侑はまっすぐ歩いてすぐに立ち止まる。 ポケットを探ろうとしてわたしにコートを着せたままだと思い出したらしい。 「左のポケット」とだけ言われたのでポケットに手を入れると、キーケースらしきものが入っていた。 大人しく渡せばすぐに部屋の鍵を取り出してドアを開ける。 「片付いとらんけど」と言ってから散らばっている自分と治のものらしい靴をどけてスペースを作る。 「どーぞ」と言うとようやく手を離した。 ふらふらと玄関に入って靴を脱ごうとする。 情けないことにうまくバランスが取れなくてへたり込んでしまう。 それを見た侑がため息をついて「どんだけ飲まされとんねん……」とまた呆れ声で呟いた。 そうしてわたしの靴を脱がしながら肩をつかむ。 太ももに腕を回すと、ふわっと体が浮いた。 あ、この、感覚。
三年前のまだ少し寒かった春先。 その季節はわたしの中で、蜘蛛の巣が絡みついたようにまとわりついて消えないものになっている。 一生忘れることはないだろう。 あの人の、北さんがわたしに触れた体温も、わたしに向けた微笑みも、言葉も。 何もかもが絡みついて取れないまま。 好きだった。 大好きだった。 そのせいか、未だに彼氏なんかできたことがない。
「今、北さんのこと思い出しとるやろ」
リビングに置かれたベッド二つのうちの片方にわたしをぽいっと捨てるように寝かせてくれる。 鋭く耳に刺さるような声に、「うん」しか返事ができない。 侑は分かりやすく舌打ちをすると「ほんま、なんなん」と苛立った声で呟く。 冷蔵庫を開けたような音。 そのあとに何かを注ぐ音がした。 すぐにベッドのほうに戻ってくると侑はずいっとわたしの前にコップを差し出す。 水を入れてくれたのだ。 腕を伸ばして受け取ろうとするのだけど、うまく焦点が合わない。 ふわふわする頭。 ぼんやりする意識。 体にうまく力が入らず、受け取ったコップが傾いてしまった。 ばしゃっと胸元に水がこぼれると侑が「何しとんねん」とコップを取り上げてくれた。 シーツも少し濡れたかもしれない。 謝らないといけないのに、うまく言葉が出ない。 寝転んだ途端、余計にぼんやりしてきた気がする。
「……嘘やろ。 なあ、なんか飲み物に入れられたんちゃうんか」
侑の言葉がよく理解できなくて何も言葉が返せない。 侑の表情もよく分からないままだ。 分かるのはふわふわする感じが少し気持ちがいいということだけ。
濡れた胸元を拭こうと侑が持ってきてくれたらしいタオルが少しだけ首筋に当たった。 それだけなのに変な声がもれた気がした。 「ちょ、ほんまにやめて、我慢せえや」という声だけ聞こえた。 タオルでごしごしと胸元を拭かれるとぞわぞわして声がもれる。 その感覚が怖くて、なぜだか、口から「きたさん」ともれた。