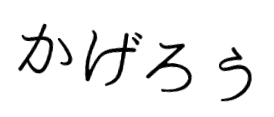
時間というものはあっという間に過ぎていく。 これまで過ごしてきた時間などどこにもなかった幻かのようだ。 悲しいほど目には見えない。 見えるのは、もう終わったのだという光景だけだ。
「卒業おめでとうございます」
「ありがとうな」
二年生がそれぞれ先輩たちに花を渡していく。 わたしも花を渡す係になりそうだったけど、せっかくだから選手同士でやったほうがいいと言ったらカメラ係を任された。 体育館の中央に花を持った三年の先輩たちが並ぶ。 「はい、チーズ」とわたしが言うと面白いくらいみんな同じピースサインをくれた。 三年生だけの写真を撮り終わったあとはみんなで撮らないと。 そう一年生と二年生に声をかける。 一年生の一人がカメラを、と声をかけてくれた。 けれどこれも選手はみんな入らなきゃ、と笑えばお礼を言われた。 監督やコーチも代わろうとしてくれたけど、さすがに監督たちは写真に入っていてくれないと困る。 そう笑って言えばこちらもお礼を言ってくれた。 一年生が部旗を広げているのを見つつ、全員がきれいに収まるポイントを探す。 少し後ろに下がって、しゃがんで、また少し下がって。 そうして、ファインダー越しに、その人の横顔を、忘れないようにじっと見た。 部活用の立派なカメラだから撮りはしない。 撮ったら他の人に見られるし。 自分のデジカメを持ってくればよかった。 そう思いつつファインダーから離れて画面で位置を調整した。
「撮ります。 はい、チーズ」
ぱしゃ。 呆気なくシャッターが切れる。 もう一枚念のために撮っておくと、全員が笑ってお礼を言ってくれた。
おしまいなのだ。 わたしが過ごした二年間は、もうどこにもないようにここで終わる。 続くことはない。 続けたくても続けられない。 続けるためには、あの人がいてくれないといけないから。
侑の言葉は真だった。 間違ったことは一つも言っていない。 だから、わたしが勝手に拗ねたのだ。 未だに口を利くことが少ないままの侑の顔を見る。 尾白さんと話している横顔は穏やかに笑っていた。 その横顔にこっそり「ごめん」ともらしたら、勝手にシャッターを切っていた。
その音に気付いた侑がわたしを見た。 一瞬真顔になったけど、すぐに尾白さんに声をかけてからこちらに向かってくる。 そうしてわたしの真ん前で立ち止まると突然「スマホ」と手を出してきた。
「は?」
「自分のスマホ、出せや」
「……なんで?」
「ええから出せ。 悪いようにはせんから」
それ、悪役の台詞だよ。 内心そう思いつつ若干の罪悪感を抱いていたところこだったので、大人しくポケットからスマホを取り出して侑に渡した。 侑は「これ押したらカメラ?」と画面を見せてくる。 頷くと「治、部活のカメラ持っとって」とわたしからカメラを奪って治に渡す。 治は黙って受け取ると一年生と二年生に「ちょおそこどいて」と声をかけていた。 よく分からないまま立ち尽くしていると、わたしのスマホを持ったまま侑が三年生の輪に入って行く。 何か話をしてから「!」とわたしを呼ぶので大人しく近寄ると、「じゃあまずアランくんからで」と尾白さんを三年生の輪から外した。
「何するん」
「何って、と三年のツーショ撮るんやん。 全部先輩らにあとでそれぞれ送っといて」
は? 困惑しているわたしに侑が「はよせえや」と急かしてくるからおずおずと尾白さんの隣に並ぶ。 そこから怒涛の撮影会がはじまる。 それを見ていた角名が「アイドルのツーショ会みたいっすね」と呟くと体育館が笑いで包まれた。 続々と撮っていき、最後に残ったのは北さんだった。
「こういうんてピースしといたらええんか?」
「や、北さんは主将やし特別なポーズで」
「どういうやつや」
「お姫様抱っことか?」
「はあ?!」
「なんやそれ」
真顔で侑に説明を求める北さんの横で「アホかそんなこと北さんにさせられへんわ!」と久しぶりに大きい声を出す。 それに治が「ええやん、最後くらい」とまさかのフォローを入れてくるものだから、他の部員も乗り気になってきてしまった。 侑からお姫様抱っこがどういうものかを教えてもらった北さんがこちらを向く。 「がええんやったらそれでもええけど」と言うまっすぐな目に、嫌ですとは言えなかった。
ぎゅっと北さんに肩をつかまれる。 太ももの辺りで腕がふらふらしつつ「この辺か」と誰ともなく確認をしている。 角名が「そこだとパンツ丸見えになるんでもうちょっと上っすね」とナイスフォローを入れてくれたおかげでパンツ丸見えは避けられそうだ。 「ここか」と呟いた瞬間にふわっと体が浮いた。
「かっこええ、かっこええで信介!」
「ちょお、こっち向けや、そっぽ向くなや」
「照れとる」
「外野うっさいねん!」
「が怒った〜!」
ゲラゲラ笑いながら侑が何度もわたしのスマホで写真を撮る。 そんな中で北さんだけは真顔で「これで合うとんのか?」とわたしに確認をしてきている。 一応「合うてます……」と振り絞った声で答えると、北さんは「前向かな、写真やでこれ」とあまりにも冷静にツッコむものだから、照れている自分が余計に恥ずかしくなった。
ぱしゃぱしゃと何度も写真を撮られている中で、北さんがわたしの顔をじっと見る。 あまりにもじっと見るから思わず「なんですか」と聞いてしまった。 北さんはほんの少しだけ笑うと、「いや」と呟く。
「ほんまにありがとうな。 のおかげで二年間、楽しかったわ」
おしまい、なのだ。 北さんにとっての三年間。 わたしにとっての二年間。 もう交わることはない。 ここから永遠の平行線のまま、知る由もない人生をそれぞれ歩んでいく。 卒業というものは大方がそうなのだ。 もう、この人の、北さんの声を聴ける日も、滅多になくなる。 北さんがこの先どういう道を歩いていくのかわたしには知る術もない。
わたしは北さんのことが好きだった。 先輩として、主将として、人間として、男の人として。 大好きだった。 マネージャーをしているのは嫌々行った部活見学で、部活の紹介をする北さんに一目惚れしたからだ。 バレーなんて興味なかったしそもそもスポーツは苦手だった。 それでも頑張れたのは北さんがいたから。 今となってはなんて不純な理由なのだろうと呆れてしまう。 今ではみんなを応援する気持ちがちゃんとあるから目を瞑ってほしい。 けれど、わたしは北さんに出会っていなければ確実にバレー部のマネージャーなんてやっていなかった。
ぶわっと、二年間胸の奥にしまい込んだ思いがはち切れたように、涙が流れていった。 でも口からは一つも流れ落ちない。 言っても無駄だと知っている。 北さんはわたしのことをただの後輩としか見ていない。 今言ったところで困らせるだけだ。 北さんは優しい人だから、きっと罪悪感を抱える。 そんなことは望んでいない。
北さんはわたしの顔を見たまままた笑う。 「なんや、子どもみたいやな」という言葉で、ああもう、わたしの恋は叶わないのだと悟った。