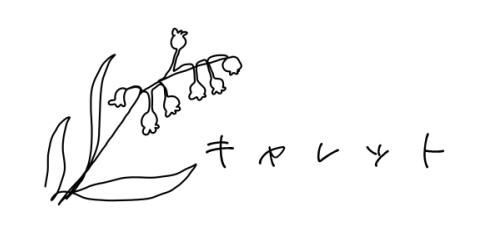はじめて、佐久早くんとキスをしてしまった。離れた瞬間に沸騰しそうなほど熱くなった顔を、佐久早くんがくつくつ笑っていた。そのまま抱きしめてくれたり、また手を握ったりしてくれながら、わたしはなんだか死にそうな思いできゅっと唇を噛んでいたっけ。
一緒のベッドで眠ることになったときはちょっと、もしかして、とどきっとしてしまった。でも、佐久早くんは特に何もする様子がないまま「おやすみ」と言ったっきりだった。なんだか恥ずかしくて佐久早くんに背中を向けたわたしを抱きかかえてどうやらもう眠っているらしい。時折佐久早くんの足が当たったり、もぞもぞとわたしのお腹を撫でるように手が動く。それにびっくりしている間に、深夜になってしまった。
わたしのお腹辺りにある佐久早くんの手を、そうっと触ってみた。ぴくりとも動かない佐久早くんに少し安心しながら、爪のふちをするりと撫でてみた。きれいに整っている。たぶん、こういうところまでちゃんとしていないと落ち着かないのだろう。佐久早くんの性格がよく出ている指先だ。
好きだなあ、なんて再確認していると、佐久早くんがぎゅうっと抱きしめる力を強くしてきた。どうやらまだ小さくなり足りないらしい。どんどん足も絡めてくるし、これ以上近付けないというほど距離が近い。そんな状況に一人で照れていると、「ん」と佐久早くんの眠たそうな声が聞こえた。どうやら起きてしまったらしい。でも、多分わたしは佐久早くんに背中を向けているからどうやら起きていることに気付かれていない。佐久早くんの手に触れていた指先の動きを止めて、なんとなく寝たふりをしてしまう。触ったから起きちゃったのかな。そんなふうに少し反省していると、もぞもぞと佐久早くんが体勢を少し変えたのが分かった。
きっと、中学生の頃の自分に今の状況を説明しても理解できないんだろうな。そう思うと少しおかしい。言葉が一つも理解できなくて黙りこくってしまう自分が容易に想像できた。でも、本当なんだよ。そう言ってもきっと信じないだろうな、なんて。
それにしても、佐久早くんはどうして急にこういう話をする機会を設けようと思ったのだろうか。二年経って突然思い至ったのか、それともずっと気にしていたのか。どちらにせよ、なんだか申し訳ない気持ちになってしまう。どうしてなのだろう。
そんな疑問を頭にぼんやり浮かべたまま、次第に瞼が重くなっていった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
朝、目が覚めてから二人で朝ご飯を食べて、片付けだけでもやらせてほしい、と手を挙げた。ほぼ無理やり片付けをさせてもらいつつ、眠る前に気になっていたあの疑問を口にしてみた。佐久早くんは一瞬目を逸らしてから「別に。くだらない理由だから気にしなくていい」と言った、けど。理由があるのなら知りたい。そんなふうにやんわりお願いしてみたら、少しだけ黙りこくって言葉を探したのち、言いづらそうに口を開いた。
「友達……というか、古森元也って覚えてるか?」
「うん。もちろん覚えてるよ?」
「……なんか話の流れで彼女との話を聞いて」
「うん」
「単純に、いいな、と思っただけ」
もうこれ以上聞くな、と言いたげな顔と声だったから、「そうなんだ」と間抜けな声で返すしかできなかった。のろけ話でも聞いたのだろうか。佐久早くんもそういうの、羨ましいとか思うんだ。ちょっと、意外だった。昨日からずっと意外な一面ばかり見せてくれる気がする。わたしは佐久早くんのことを全然知らないんだなあ。前までのわたしなら、ネガティブに捉えていただろう。でも、今は、それが少し楽しみに思える自分になれていた。
二年間佐久早くんと付き合っているけれど、でも、今日からが恋人のはじまりなのかもしれない。わたしも佐久早くんも、お互いなんだか遠慮しながらお付き合いしていた二年間だった。恋人というよりは、もう少し距離のある関係、というか。人から見ればなんだか不思議な関係だったのかもしれない。千香ちゃんが佐久早くんとの話に驚いていたように。
「じゃあ、あの、改めてよろしくお願いします」
「……こちらこそ」
佐久早くんがくすりと笑った。「なんだこの会話」とおかしそうに呟いたのがなんだか面白くて。わたしも「なんだろうね」と笑ってしまった。そのやり取りがなんだかとても、恋人っぽくて。勝手に嬉しくなってしまった。
お皿を洗い終わって手を洗っていると、佐久早くんが一つ伸びをした。今日は午後から練習があるそうなので、あと一時間くらいでお暇しないと迷惑になってしまう。忘れ物がないように今のうちに荷物の準備をしておこう。そう思って手を拭いてから自分の鞄のほうへ行く。近くに置いてあるものを整頓しながらしまっていると、佐久早くんがじっとこっちを見ているような気がした。思わず振り返ると、やっぱり佐久早くんとしっかり目があってしまった。
「……帰るの?」
「え、あ、うん? 佐久早くん、午後から部活だったよね? わたしも三限があるから」
「ふーん」
ふーん、と言われてしまった。何となく佐久早くんが求めていた答えではないのだろうとは分かる言い方だ。でも、別に変なことを言ったつもりはなかった、けどなあ。少し言葉に迷ってしまう。そんなわたしをじっと見つめて佐久早くんは頬杖をついて黙りこくっていた。
何か機嫌を損ねてしまったのだろうか。そんな不安が少しよぎった。でも、佐久早くんの表情を見ていて、何となく言いたいことが分かった、ような気がした。でも、ちょっと恥ずかしくて自分で言うのは。そんなふうに思って負けじとわたしも黙りこくってみる。さすがに自分で言えるほどのポジティブさはまだ身につけられていない。そう苦笑いをこぼしつつ。
佐久早くんの視線が一旦別のところへ移動した。どこともなく宙を見つめて、静かに瞬きをしている。呼吸の音が聞こえてきそうなほどの静かさ。静寂が似合う人だ。佐久早くんは。そんなふうに一人で勝手に見惚れていると、ちらりと視線がこちらに戻ってきた。
「それ」
佐久早くんが指を差した先には、昨日コンビニで急遽買った化粧品。これが一体どうしたのだろうか。鞄にしまおうとしていた手を止めて「これ?」と見せてみる。佐久早くんは小さく頷いたのち「置いてったら」と言った。
「洗面所の棚、空いてるところあるし。好きに使っていいよ」
ベッドの横にあるカラーボックスも指差して「そこにも何か適当に入れてったら」と言った。佐久早くんの家に、わたしのものを置くスペースがある。なんだかそれが、とても、気恥ずかしいけれど、嬉しくて。
「いいの?」
「いい。というか、そのために空けた」
知らなかった。いつの間にそんな作業をしてくれていたのだろう。あまり部屋をじろじろ見ないようにしていたから気付かなかった。驚きながら「じゃあ、あの、置いていきます」と答えると、佐久早くんが小さく笑って「うん」と優しい声で言った。
戻る / next