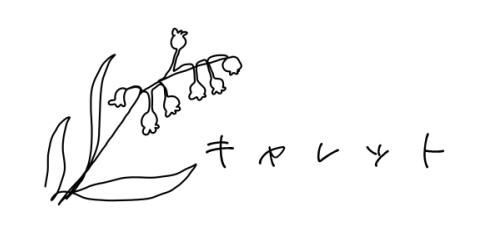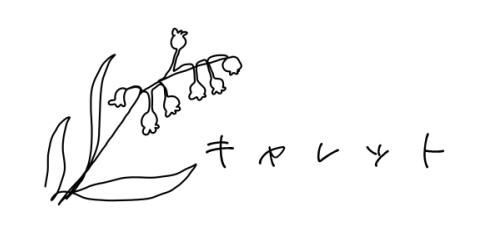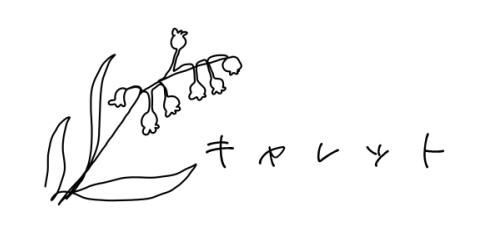 佐久早くんが部屋に戻ってきてから、わたしの隣に座った。ついていたテレビをなぜだか消すと、ちらりとわたしに視線を向ける。もしかして、言っていた〝話したいこと〟、だろうか。そんなふうに思っていたら「高二のとき」と突然口を開くものだから驚いてしまう。
佐久早くんが部屋に戻ってきてから、わたしの隣に座った。ついていたテレビをなぜだか消すと、ちらりとわたしに視線を向ける。もしかして、言っていた〝話したいこと〟、だろうか。そんなふうに思っていたら「高二のとき」と突然口を開くものだから驚いてしまう。
「え、高二のとき……?」
「俺が落とした部室の鍵、拾ってくれただろ」
「あ、う、うん、覚えてるよ」
「そのときからのこと、好きだった」
そんなことを話してくれたのははじめてだった。わたしもその日のことはよく覚えている。それから佐久早くんと話すようになったから。わたしは中学生のときから佐久早くんのことが好きだったけど、佐久早くんはそのときからだったんだ。でも、好きになってもらえる要素なんて、なかったけど。そんなふうに不思議に思った。
「あんなの、普通のやつからしたら〝普通に拾えよ〟って言う場面だろ。そう言われるのが分かってたから諦めて拾おうとしてて。そうしたらが拾ってくれた」
「そう、なんだ?」
「髪の毛に枯れ葉がついてたし、服の袖真っ黒だったし、頬にも少し砂が付いてた」
「えっ?!
そうだったの?!」
「いつもなら汚えなって思うのに、そのときは、なんか、かわいいなって思って」
目を逸らされてしまった。佐久早くんはぼそりと「だから、好きになった」と言った。汚いと思うはずなのに、かわいいと思った。どうしてなのだろう。わたしは微塵にも美人ではないし、特に愛嬌があるわけでもない。ごくごく普通の女子高校生だった。佐久早くんにかわいいなんて思われる要素はなかったはずなのだけれど。
心臓が痛い。さっきから佐久早くん、急にどうしたのだろう。佐久早くんのことが好きだから、どんな話でもこんなふうに喜んでしまう。内容がどうとか、急にどうしてそんなことを言い出したのかとか、全部どうでも良くて。わたしって馬鹿だな、と情けなくなった。
「俺はそのときから、になら何されてもそんなに嫌じゃなくなった」
物に触られたり、体に触られたり。佐久早くんはそう呟いて「そういうやつ、正直俺にとってはあんまりいない」と付け足す。それに加えて「異性は家族以外ではじめて」と言った。
「は俺がそういうふうに気を許せたから自分のことを好きになったと思ってるだろ」
「……う、うん」
「違う。逆。好きになったからそういうのどうでも良くなったんだよ」
佐久早くんの左手が伸びてきた。そうして、まだ濡れたままのわたしの髪を触る。濡れたものを触るのは、あんまり好きじゃない、のに。全然嫌そうな顔をしていない。じっとわたしのことを見つめたまま、すりすりと指の腹でわたしの髪を撫でている。その手付きが、とても、優しくて。心臓が張り裂けそうになってしまう。
「は触られたりするのが好きそうじゃなかったから、これまで何もしなかっただけ」
「……どうして好きそうに見えなかったの?」
「俺が触ろうとするといつもびっくりしてるだろ。手とか」
繋ごうとすると手を引っ込められたから、と佐久早くんが呟く。やっぱり、手を繋ぎ始める前によく手がぶつかっていたのはそのせいだったのだ。繋ぎたいって思ってくれていたんだ。それが嬉しくて、また心臓が痛くなった。
髪から手が離れる。今度はわたしの手に指先が触れる。するりと指を撫でてから指を絡めてきた。きゅっと握られた手がじんわり温かい。わたしが好きな佐久早くんの声と同じ、温かい体温をしている。それが、やっぱり、嬉しくて。
「人に触るのは好きじゃないけど、のことは好きだから触りたい」
顔を覗き込まれる。手は握られたまま。目の前に佐久早くんの顔。お風呂上がりの、なんだかとけてしまいそうな体温。それが全部一気に襲いかかってきて、呼吸が止まりそうだった。
わたしは佐久早くんになら何をされても嫌じゃないし、何を言われても嫌じゃない。佐久早くんが嫌なことをしたくないだけ。それだけを考えていた。
嫌じゃ、ないんだ。佐久早くん。自分でそう内心呟いて一気に恥ずかしくなる。嫌じゃないんだ。わたしに触るの。嫌がられていなかったんだ。こんなに近くにいても。佐久早くんにとって付き合える範囲の人間だから彼女にしてもらえたわけじゃ、なかったんだ。
「俺は好きだから触りたくなったけど、は触りたくなくなったんだろ」
「……えっ」
「何を気にしてんのかは知らないけど、そういうふうに感じる」
なんで、と余計に顔が近くなった。その表情から、なんとなく、理由はもう分かっているように思えた。思わず後退ろうとしたけど、佐久早くんが握ったままを手を引っ張る。逃げ場はない。わたしの、気持ち悪い恋心を、佐久早くんはどう思うだろう。中学のときの、あの必死に手を洗っている佐久早くんの横顔を思い出す。触りたくないはずのものに触れて助けてくれた。あの日の光景がまた頭に浮かんだ。
「……わ、わたし、きれいじゃない、から」
「は?」
「だから、触られたら、嫌かなって……」
佐久早くんが小さく首を傾げた。わけが分からん、というように眉間にしわを寄せている。そのまま「どういう意味?」と聞かれて、しどろもどろ説明した。中学のときの好きになったきっかけも、佐久早くんのことをどう思っていたのかも、全部。手を繋いでいる間もずっと佐久早くんがどう思っているのかが気になってたまらなかったことも。佐久早くんは時折ちょっと首を傾げつつも最後まで聞いてくれた。
話し終わったわたしの手を、佐久早くんがぱっと離した。やっぱり気持ち悪かったかな。少し視線が俯いてしまった瞬間、首の後ろに手が回ってきて、ぐいっと引き寄せられた。声を出す暇もない間に、ぎゅっと、佐久早くんの腕の中に閉じ込められていて。びっくりしすぎて言葉を失う。それと同時に火が出そうなほど顔が熱くなった。
佐久早くんに、抱きしめられている。肩は抱きしめている左手でぎゅっと掴まれていて、腰は右手でそっと支えられている。手、大きい。手を繋いだときにも思ったけど、今もすごく分かる。感じる。体もすごく大きい。すっぽりわたしが隠れてしまっている。全身すべて佐久早くんに支配されているような錯覚に陥るくらい、頭がくらくらしてきた。
はっとする。髪の毛が濡れているから、佐久早くんも濡れてしまうかもしれない。ぽたぽたと水滴が落ちているかもしれないし、生乾きになってきたら変な臭いがするかも。そう思って「あの、髪が濡れてる、から」と声をかける。佐久早くんはじっとしたまま動かず、何も言ってくれない。でも、肩を掴んでいた左手が動いて、濡れたわたしの髪ごと後頭部をしっかり支える。たぶん、それが答えだった。どうでもいい、という、意味の。
嬉しい、本当に嬉しいし、困惑しているのだけど、何より、顔が佐久早くんの肩に埋まっちゃって、呼吸が。ちょっと苦しい。恐る恐る佐久早くんの肩を叩いて「ちょっと、苦しい」と言ったら、バッと勢いよく離れてくれた。
「……ごめん」
「う、ううん……」
そうっと上げた視線の先、佐久早くんの顔が、赤くなっていた。それを見てしまった瞬間に、とっくにもう熱い顔が余計に熱くなる。
とても失礼な言い方をするのだけど、佐久早くんも、なんというか、わたしと同じなんだなあと感じてしまった。こうやって人を抱きしめたら照れるような、とてもとても、普通の人。わたしのことをちゃんと見てくれて、ちゃんと思いを言葉にしようとしてくれる、普通の人。そう思ったら、なんだか体のどこかにずっとあった重たいものが溶けていくような感覚があった。
のほうが潔癖だよな。佐久早くんがいつかに言った言葉だ。あのときは意味が分からなかったけれど、今は少し分かる。あんまり人に触るのが得意じゃない佐久早くんは、わたしを好きになってくれて触ることが嫌じゃないと言ってくれた。嫌だったものがそうじゃなくなるほど心を開いてくれたのだ。でも、わたしは、佐久早くんのことが好きになってからずっと、佐久早くんに嫌われたくない一心で触ることを諦めてきた。徹底的に除菌とか消毒とか、そういうことをしていないと不安だった。洋服でさえ佐久早くんの隣にいても変じゃないものを着なくちゃ、と思っていた。好きだから触ることを諦めてしまっていた。好きになればなるほど、どんどんいろんな扉を閉めてしまって、怖がりになっていたのだ。
わたしはとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。目の前にいる佐久早聖臣という人は、どこにでもいるありふれた、なんてことはない普通の人、だったのかも、しれない。好きな人に触れたいと当たり前に思うような。好きな人ができたら何か変化があるような。とても、普通の人。佐久早くんのことをはじめてそんなふうに思った。
「……中学のときの話は、正直よく覚えてない。のことはもちろん覚えてるけど」
「そ、そっか」
「でも、俺がそういうことをしたのなら、そのときからのことを、気にかけてたんだと思う。じゃなきゃ雑巾なんか拾わないし声もかけない」
ちょっとバツが悪そうな顔をした。でも、わたしにとってはとても、嬉しい言葉だった。なんて言葉にすればいいのか分からずにいると、佐久早くんが「そもそも」と小さくため息をつきつつ呟く。
「確かにあんまり人に触られるのとか好きじゃないけど、汚いからっていうよりは親しくないやつにベタベタされるのが好きじゃないって理由のほうが大きい」
「あ、そ、そうなんだ……?」
「だから、はいい」
優しい声。いつも思う。佐久早くんは瞳も、髪も、声も、体温も。全部、きれいな星空に溶けるような優しいものだなあ、と。瞳や髪は黒色なのだけど、真っ黒な一色ではなくて、どこかにふと別の色が溶け込んでいるような特別な色に見える。声や体温は落ち着いていてあまり起伏はないけれど、いつでも深く遠くまで広がるようにずっとそばにいてくれるような温もりがある。不思議な色と温もりがわたしを染め上げてくれるように、いつも寄り添ってくれる。
わたしはやはり勘違いをしていた。佐久早くんは、とても、普通の人だ。普通にわたしを好きになってくれて、普通にわたしを好きでいてくれて、普通にわたしを大事にしてくれる。何も特別なことなんてない。でも、その普通こそがわたしにとっては何よりも特別なのだけれど。
ああ、わたし、佐久早くんに大事にしてもらってるんだなあ。すんなりそう、心の中で呟くことができた。
「あの、佐久早くん」
「何?」
「……手、触っても、いい?」
「いいよ」
はい、と両手がすんなり差し出された。きれいな手。指先まできれいにされている大きな手は、これまで触ることを何度も躊躇した思い出ばかりだ。そうっと手を伸ばして、佐久早くんの手に触れる。わたしの弱っちい手とは違って少し硬い、かっこいい男の人の手。
ちらりと佐久早くんの顔を見る。じっとわたしの手を見て小さく笑っていた。とても、嫌そうな顔には見えない。それを自覚してなんだか肩の力が抜けた感覚に似たものを感じた。触ってしまった、けど、わたしはいいんだなあ。そんなことを噛みしめて、一人でちょっとだけ、口元が緩みそうになる。
力を抜いていた佐久早くんの手が、突然わたしの手を握った。ちょっと驚いて顔を上げるとしっかり視線が交わってしまう。きれいな瞳。また星空を見上げているような気持ちになっていると、握られている手がより強く握られた。両手でしっかり手を握られると、心臓が高鳴ったのが分かった。すりすりと親指が肌を撫でるのが、くすぐったいけれど、それよりも熱っぽくてたまらない。佐久早くんも、こういう、触り方するんだなあ。そんなふうにどきどきしてしまった。
左手が、そっと頬に触れた。親指の腹が柔らかに頬を撫でる。一瞬で全身に佐久早くんの体温が回って、どこかしこも全部自分のものじゃないみたいな体温に染められてしまった。佐久早くんの親指が唇をなぞると同時に、ほんの少しだけ目を逸らしてしまう。それを「こっち見てろ」と咎められれば、否とは言えなくて。そうっと視線をまた戻したら、佐久早くんが満足げに微笑んだ。
少し佐久早くんの顔が近付いた瞬間、何をするのかが分かった。まだ握られたままの手をぎゅうっと握りしめてしまう。佐久早くんはそれには気付かないふりをしてくれた。でも、赤くなっているであろう顔はそうにもいかなかったみたいで。左手でわたしの頭を撫でると「大丈夫」と内緒話をするみたいに優しい声で言ってくれた。
きっと、忘れられない夜になる。そっと重なった唇が温かかったから。全然怖くなかった。触れられることも触れることも。それが、嬉しかった。
戻る
/
next