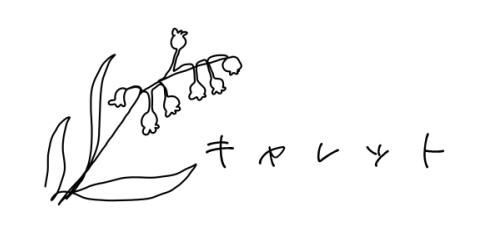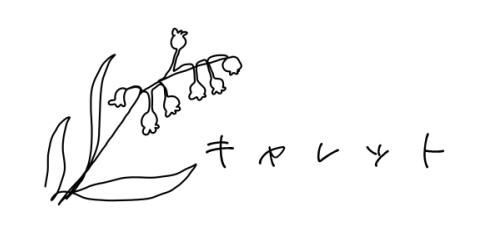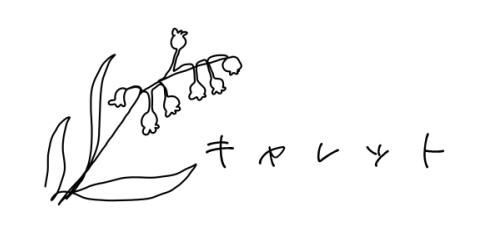 「前着てた花のやつ、もう着ないの」
「前着てた花のやつ、もう着ないの」
フルーツタルトを食べ終わって、片付けようとする佐久早くんをどうにか説得してお皿を洗わせてもらった後のことだった。ソファにおずおずと腰を下ろしたわたしに佐久早くんがそう言った。前着てた、花のやつ。そう言われていまいちピンと来なくて。「花のやつ?」と聞いてみると、佐久早くんの視線が少し下に向いたのが分かった。
「ひらひらのやつ。スカート」
「…………あ、小さい花が描いてあるやつのこと?」
「たぶん。よく着てただろ。前にうちに来たときから見てないけど」
どき、とした。あの花柄のスカートは、佐久早くんの家で映画を観た後に捨ててしまったから。物を大事にしない人だと思われるかもしれない。そう思って「どうして?」と聞いてみる。佐久早くんはじっとわたしのことを見て「いや」と呟き、そっと目を逸らした。
「かわいかったから」
ぽつりとそんなことを言われて、びっくりした。佐久早くんはそういうことを言わない人だとばかり思っていた。これまでもそうだったし、佐久早くんがそういうことを言うなんて思ったこともなくて。それに、そういうことを言う相手がわたしなんて、想像もしたことがなかった。
固まっているわたしに佐久早くんが「おい」と小さな声で言う。ほんのり頬が赤い。照れているのが一目で分かる表情をしている。そういう顔は、あまり、見たことがない。かわいい。そんなふうに思いつつ「あ、はい」とわたしも小さな声で返した。
「あ、あれは……破れちゃってたから、捨てちゃって」
「……そう」
「う、うん」
「…………今度、服見に行く?」
「えっ、あ、う、うん」
佐久早くんはスマホを手に取ると「いつが空いてるの」と聞いてきた。わたしも慌ててスケジュール帳を開く。思わず「うん」って言ってしまったけど、ショッピングなんて佐久早くん、楽しんでくれるのだろうか。わたしは結構優柔不断で買い物に時間がかかるタイプだ。佐久早くんはそういうの迷わないタイプだろうし、イライラさせてしまうかもしれない。
家に帰ったらほしいものと、行くであろうショッピングセンターに入っているお店をチェックしておこう。ホームページを見れば今ある商品が分かるだろうから大体の目星をつけておけば時間短縮になる。佐久早くんとスケジュールを合わせながらさり気なく「行くならどこに行くの?」と聞いてみる。大体選択肢は限られてくる。佐久早くんは少し考えてから、この近くにある中では一番大きいショッピングセンターの名前を口にした。帰ったらお店一覧を全部見よう。好きなお店のホームページをチェックしておかないと。
来週日曜日、午前十時。駅で待ち合わせ。スケジュール帳にそう書き込んでから鞄にしまう。佐久早くんもスマホをカレンダーに登録したみたいだ。わたしとの予定が佐久早くんのスマホのカレンダーに登録されているんだなあ。そう思うと、なんだか胸が痛くなるくらい嬉しかった。
スマホを机に置いた佐久早くんが、まだじっとわたしを見ていた。思わず視線を佐久早くんの顔に向けてしまう。どうしたんだろう。もしかして何かついているのだろうか。そう思っていると、佐久早くんがほんの少しだけ目を細めたのが分かった。その表情にどきっと心臓が音を立てる。その数秒後、佐久早くんの左手が、なぜだかわたしの髪に触れた。
「……さ」
「あ、う、うん?」
「俺に触られるの、嫌い?」
「えっ、ど、どうして……?」
「顔が強張るから」
つん、と頬に佐久早くんの指が触れる。少しだけ冷たい体温。それをひりひりするほど感じてしまって、どきどきして困ってしまう。佐久早くんに触られている。それがどうにも、心臓を騒がしくしてしまう。汗をかいていないだろうか。肌が荒れていないだろうか。乾燥していないだろうか。逆に油分が浮いてきていないだろうか。そんなふうに不安になる。
佐久早くんがぱっと手を離した。じっとわたしの顔を見たまま「嫌いならしない」と呟く。悪いことをした子犬みたいに気まずそうな顔をしているのが分かって、焦った。嫌いなわけがない。佐久早くんにだったら何をされても嫌じゃない、けど。不安なのだ。佐久早くんがわたしに触れて、距離が縮まれば縮まるほど、佐久早くんにとって良くない部分が露呈してしまうんじゃないか、と。わたしは何も持っていない。佐久早くんにとって、何かメリットになるものを、何も。知られれば知られるほどそれが、痛いほど、佐久早くんに伝わってしまうのではないかと怖かった。
ぎ、とソファが音を立てる。佐久早くんが少しわたしに近寄ったのが分かった。肩がぶつかりそうなくらいの距離。近くで見る佐久早くんの顔は、やっぱりかっこよくて、透き通るようなきれいな肌が目に痛いほどで、とても、直視できなかった。
「嫌じゃないならこっち見ろ」
びくっとした。嫌じゃない、けど、とてもじゃないけれど、見られなくて。きゅっと自分の手を握ってしまう。まさか付き合えるなんて思っていなかった佐久早くんが、わたしと付き合っている。それだけでいっぱいいっぱいな二年だった。二年経っても変わらない。佐久早くんがかっこよくて、わたしはもうどうしようもないのだ。名前を見るだけで、喉の奥で名前を呼ぶだけで、佐久早くんに見つめられるだけで、佐久早くんに名前を呼ばれるだけで。とても、とても、幸せな気持ちになれる。そんなどうしようもない単純なやつなのだ。
俯いたままでいるわたしのすぐ近くに佐久早くんがいる。石鹸みたいないい匂いがするし、ほんの少しだけ体温を感じる気がする。それだけで胸がいっぱいなのに、顔なんか見られない。でも、俯いたままだと嫌がっていると思われてしまう。どうしよう。慌てて「嫌じゃないの」とだけ呟く。佐久早くんは「じゃあこっち見ろ」と言うだけ。当たり前だ。嫌じゃないならどうして顔を上げられないのか、なんて佐久早くんに分かるわけがない。
「……俺はのこと、好きだけど」
「あ、ありが、とう」
「がどう思ってるのか、よく分からない」
「えっ」
思わず顔を上げてしまう。ばちっと目が合った佐久早くんは、見たことがないほど、寂しそうな顔をしていた。驚きすぎて言葉が出ない。わたし、こんなに、佐久早くんのことが、好きなのに。伝わらない。佐久早くんはわたしの細かい表情の違いにも気付いてくれていたから、それは伝わっているものだと、勝手に思っていた。
佐久早くんがソファから立ち上がる。「もう暗いから送る」と言われて、はっと時計を見る。午後八時。気付かない間に長居してしまっていた。慌てて立ち上がるけど、それより、佐久早くんの言葉にどう返そうかということだけが頭を回っている。どうしよう、このまま何も言わずに帰っちゃったら、誤解されたままになる。でも、おかしなことに言葉が出ない。
無理やりにでも、言葉を。そう思ってこじ開けた喉から出たのは、震えた情けない声だった。
「さ、佐久早くん」
「うん」
「わたし、佐久早くんのこと、好きだよ」
絞り出したわたしの声に佐久早くんが振り返る。じっとこちらを見つめてから、見たことがない顔をして笑った。「うん」とだけ言った声も聞いたことがない音をしている。作り笑顔だった。たぶん、信じてくれていない。それに余計に心臓が変な音を立てるから何も言えなくなってしまった。
駅まで送ってくれる間、佐久早くんは一言も話さなかった。最近よく繋いでくる手も、指一本触れなかった。佐久早くんの少し後ろをついていくわたしも、何も言えないまま。夜空に溶けるみたいな佐久早くんのきれいな黒髪をだけを見つめて、一人で泣きそうだった。
戻る
/
next