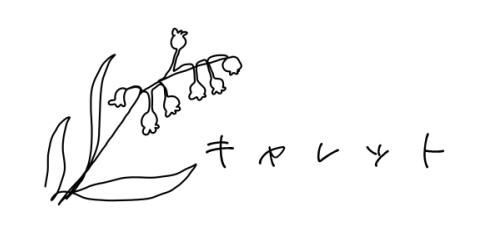二時間前、佐久早くんから連絡があった。今日は佐久早くんと出かける予定があったのだけど、急遽用事ができて大学に行くことになったと言われた。じゃあ今日は中止だね、とわたしが送り返したら「いや、一時間くらい待たせると思うけど、家で待ってて」と返信があった。
家で待ってて、と、いうと。返信できずに固まったままのわたしに追加メッセージが届く。「鍵渡してあるから入れるだろ」と。でも、それなら、待ち合わせ時間をずらせばいいんじゃないかな。そう思っていたらまたしても追加メッセージ。「今日は最終的に俺の家に連れてくつもりだったから」。そう言われると、何とも言いがたくて。結局「分かった」と返信した。
そして、現在。わたしは佐久早くんの家の鍵を握って、ドアの前に立っている。かれこれ五分くらいこうしてドアを見つめているのだけど、どうしても一歩が踏み出せない。当たり前だ。前みたいに佐久早くんが招いてくれているわけでもないし、いくら佐久早くんが待っててと言ったとしても勝手に入るのと感覚は同じ。わたしからすればただの不法侵入にしか思えないのだ。本当に。佐久早くんが入っててと言ったとしても。
そうっと鍵穴に鍵を差し入れる。当たり前だけど、入った。ゆっくり鍵を回せば呆気なくガチャンという音が響く。開いてしまった。一人で大罪を犯してしまったような気持ちになりながら、そっとドアノブを握る。恐る恐る開けたドア。思わず「お邪魔します」と言ってしまいながら、そうっと玄関に入った。
まず何より消毒だ。佐久早くんが実際に見ていないから何とでもできてしまうけど、徹底的に。持ってきていた新しい靴下に履き替えて、使い捨てスリッパを履き、とにかく服はコロコロで徹底的に埃を取って除菌スプレーをかけた。それからなぜだか音を立てないように部屋に入ると、片付いた佐久早くんの部屋が。
「……あれ」
思わずそう声が出た。机の上に、佐久早くんなら必ずすぐ捨てるであろうティッシュゴミが放置されていた。珍しい気がする。いつも外でも出たごみはすぐにごみ箱を探して捨てているのに。よほど急いで家を出たのだろうか。不思議に思いながら恐る恐るごみ箱に入れておく。
どこに座っていいか迷っていると、キッチンに朝食を食べたと思われるごみが残っているのが見えた。それに首を傾げてしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
フローリングの上に座って四十分後、ガチャ、と鍵が開いた音が聞こえて心臓が跳ね上がった。慌てて立ち上がると同時にドアが開いた音。それからまた鍵がかかった音が聞こえてくる。すぐに足音が近付いてきて、リビングのドアが開いた。
「……ただいま」
「お、おかえり。お邪魔してます」
佐久早くんは鞄を肩から下ろしながら「なんで立ってんの」と眉間にしわを寄せる。それからちらりと部屋を見渡して、わたしの鞄がフローリングに置かれているのを見つけたらしい。「ソファ座れ」と言われてしまった。
すぐに手を洗ってうがいをはじめる。ちゃんとしている。やっぱり佐久早くんのそういうところ、好きだなあ。ぼんやりそう思っていると、ハッとした。わたし、消毒とかに気を取られて手洗いうがいをしていない気がする。除菌シートには触っているけど。
反省している間に佐久早くんが戻ってきた。「だから、ソファ」と言われて慌ててソファに座らせてもらった。
「な、なんか、ごめんなさい」
「なんで謝るんだよ……むしろ待たせて悪かった」
「全然、それは本当に大丈夫、本当に」
隣に腰を下ろした佐久早くんが一つ息をついてから、マスクをごみ箱に捨てる。さっきうがいしたときに取ったものだろう。ぼんやりそれを見ていると、「何か飲むか?」とこっちを佐久早くんが見た。「お水で」と答えたら「ん」と短く返事をしてキッチンのほうへ歩いて行く。
そういえば今日はどうして家に呼んでくれるつもりだったのだろう。また映画かな。佐久早くんの背中を見つめて考えていると「氷いる?」と聞かれた。びくっとしてから「あ、大丈夫」と答える。氷を入れると水滴が落ちてしまう。自分の服に落ちるならまだしも、万が一ソファやカーペットに落としたら大変だから。
戻ってきた佐久早くんがコップを机に置いてくれた。お礼を言って一口いただいて、コップをまた机に戻す。それから「今日はどうしたの?」と素直に聞いてみる。別にどこかに出かけたいと言っていたわけじゃないけど、家に呼んでくれたのには理由があるのだろう。そう思って。
「……って」
「うん?」
「甘い物好きだよな?」
「……え、あ、うん? 好き、だけど……?」
ハテナを飛ばしながらそう答えると、佐久早くんはもう一度立ち上がってキッチンのほうへ歩いて行く。何の質問だったんだろう。冷蔵庫を開けて何かを取り出している佐久早くんの背中を見ていると、くるりとこちらを振り返る。その手には明らかにケーキ箱があった。それも、とても見たことのあるケーキ箱だ。
あれは確か、東京駅の近くにできたケーキ屋さんのケーキ箱だ。連日大行列で開店の二時間前から並ばなければ買えないという大人気のフルーツタルトが看板商品。情報番組で嫌というほど見た。食べたいけど二時間前から並ぶとなるとかなり大変だし、そこまで苦労するのもなんだか気乗りしなくて一度もチャレンジしたことはない。
フルーツタルト以外のケーキも結構すぐに完売してしまうと聞いた。佐久早くん、そんなケーキ屋さんのケーキ箱をなぜ持っているのだろう。不思議に思っていると、机の上にそのケーキ箱を静かに置いた。
「……昨日」
「うん?」
「高校のときの先輩がノリで買いに行くからお前も来いって言ってきて」
「それで行ったの? 大変だったでしょ?」
「全く気乗りしなかったし断りたかったし断るつもりだったけど」
「う、うん……?」
「買ってったら」
「うん?」
「……彼女が喜ぶぞって、言われたから」
頭が吹っ飛んだかと思った。驚愕で固まっているわたしに佐久早くんが「別に食べなくていい。柄じゃないことをしたのも分かってる」と少し早口で言った。
大人気のケーキ屋さんだ。人がたくさんいただろう。そういう行列に並ぶのも好きじゃないと聞いたことがある。それなのに。気乗りもしなくて断りたかったのに。彼女が喜ぶと言われて、佐久早くんが、嫌いな行列に並んだ、と、いうこと?
思わず、わたしのため、と言いそうになった口を塞いでおく。違う、自惚れてしまってはいけない。佐久早くんの彼女は一応わたしだけれど、わたしだから佐久早くんがそうしたわけじゃない。彼女という存在にしたのだから、わたしのため、だなんて言ったら恥ずかしい勘違い女になる。たまたまわたしが彼女というポジションにいただけだ。思い上がってはいけない。
そんなことを頭の中で繰り返して、一つ呼吸をしてからようやく「食べていいの?」と言えた。佐久早くんは「うん」と少し恥ずかしそうに答えながらケーキ箱を丁寧に開ける。持ってきてくれたお皿とフォーク。それを受け取る。ケーキ箱の中には、大人気のフルーツタルトが一切れだけ入っていた。人気だから一切れしか買えなかったのだろう。これを半分こだ、と少し嬉しく思っていると、佐久早くんは一切れしかないそれを丸々わたしが受け取ったお皿に載せてきた。
「あ、えっと、フォークで半分にしても大丈夫?」
「は?」
「佐久早くんの分を切り分けないと」
「俺は食べないからいい」
固まってしまった。だって、大行列に並んでやっと買えるってなったら、当然自分の分も買うだろう。それなのに、佐久早くんは本当に、食べたくて並んだんじゃなくて、喜ぶと思ったから並んでくれたのだ。それがあまりにも衝撃的で驚いてしまった。佐久早くんは心底不思議そうに「そんなに驚くことじゃないだろ」と言う。確かに佐久早くんが好んで甘いものを食べている姿は見ない、けれど。なかなか手には入らないものを苦労して手に入れたのだから自分も、ってならないんだなあ。わたしだったら絶対に自分の分も買ってしまう。
ケーキ箱を畳みながら佐久早くんが「食べれば」と言った。慌ててフォークを握り直して「あ、ありがとう」と言ってから「いただきます」とフルーツタルトに視線を落とす。佐久早くんが、喜ぶと思って買ってきてくれたケーキ。今まで見たどんなケーキよりもきれいで、かわいくて、おいしそうに見えてしまう。嬉しい。素直にそう口に出そうか迷ったけれど、舞い上がっていると思われるかもしれないから黙っておくことにした。
そうっとフルーツタルトにフォークを入れる。佐久早くんはそれを隣でじっと見ているだけ。ちょっと緊張する。きらきら光っている苺と生地を一緒に持ち上げると、それだけでふわっと甘いカスタードの匂いを感じた気がした。おいしそう。恐る恐る口に運んでみると、一瞬で口の中が苺とカスタードの匂いでいっぱいになる。この苺、すごくおいしい。テレビの特集で見たときも、とにかく果物にこだわっているからどの果物もおいしいと言っていたっけ。これは確かに、あれだけ行列ができるのも頷ける。カスタードクリームが甘すぎないから果物を邪魔していない。甘すぎないところも人気の理由かも。
そんなふうに思いながら飲み込んで、はっ、とした。無言で食べてしまった。慌てて「おいしい」と言ったら佐久早くんは「ん」とだけ言った。反応が、薄いと思われたかな。慌てて言葉を追加。こういうところがおいしいとか、こんな味だとか。いろんな感想に言葉を尽くしていると、佐久早くんが小さく笑った。
「いいって。顔見てれば分かるから」
いいから食べろ、と笑われるものだから、恥ずかしくて。「はい」とだけ呟いて、ゆっくりフルーツタルトを食べ進める。なんだか今日は、贅沢な一日だ。
わたしは、友達からも表情があまり出ないタイプ、とよく言われる。感情を表に出すことが苦手だと自分でも思っている。嬉しい、楽しい、悲しい、寂しい。そういう感情をどうやって出せばいいのか分からない。言葉にしようにも表情に出そうにもうまくいかない。それが原因で勘違いされてしまったことも過去にある。
でも、佐久早くんは、分かってくれるんだなあ。自分でも気付かないほど些細な違いをくみ取ってくれる。丁寧に毎日を生きている佐久早くんだからそういうこともできてしまうのだろう。わたしも、そうでありたいな。きらきらのフルーツタルトを食べながらこっそり思った。
戻る / next