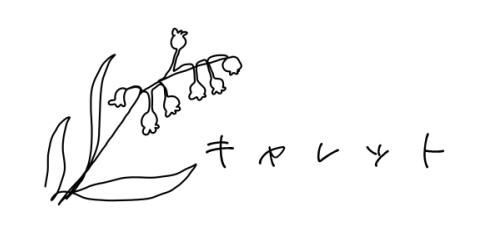「い、家の、鍵……?」
「こうでもしないと伝わらないから」
何が、を教えてくれないと分からないよ、佐久早くん。混乱したまま「もらえないよ」と返そうとするのだけど、佐久早くんは断固拒否。「いいから持ってろ」と言われてしまい、恐る恐る鞄にしまった。
もうすっかり空が暗い。月だけが眩しく光っていて、とてもきれいな夜空が広がっている。困惑した気持ちのままちらりと空を見てから、佐久早くんに「じゃあ、わたしあっちの電車だから、またね」ととりあえず笑顔を向ける。いつもここで解散している。いつも通りの言葉だった。それなのに佐久早くんは、ほんの少しだけ視線を逸らした。それがやけに気になってしまう。何か変なことでもあっただろうか。でも、何も言われない。わたしの気のせいかな。そんなふうに思いながら歩き出そうとした瞬間。佐久早くんの手がまたしてもわたしの手を掴んだ。びっくりして佐久早くんの顔を見上げると、じっと瞳を見つめられる。
「佐久早くん?」
「……」
「うん?」
「俺はお前が好きだ」
ぶわっといろんなところから汗が出たような感覚。びっくりしすぎて固まっていると、佐久早くんがぱっと手を離した。「それだけ」と呟いて、視線を少し下に落とす。
泣きそうだ。わたしは、佐久早くんのその言葉だけで、馬鹿みたいに嬉しい。佐久早くんがその言葉をわたしに向けてくれることが、夢みたいで胸がいっぱいになる。どうして急に言ってくれたのかは分からない。でも、佐久早くんにとって必要なことだったに違いない。それならいいのに。それなら、嬉しいな。佐久早くんにとっての必要なものにわたしの何かが含まれているみたいに思えるから。そんなことをこっそり喜んでしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
家に帰ってから、佐久早くんがくれたキーケースを取り出した。ベッドに座ってぼんやりそれを眺める。佐久早くんの家の鍵。たぶん、世界でわたししか持っていないものだろう。いや、もしかしたらご家族の方は持っているかもしれない。でも、それにしても、わたしが持っていていいんだ。それを目に見えて感じることができて、思わずずっと見つめてしまった。使うときが来るかは置いておくけど、とにかく、佐久早くんがくれた信頼の証。そう思えてならない。
佐久早くんの言葉を思い出している。わたしのほうがよっぽど潔癖。あれは一体どういう意味だったのだろう。良い意味で言ってくれたのか、悪い意味で言われたのか。それすらも分からない。鬱陶しがられているのかと心配したけど、別れ際に好きだと言ってくれた。ということは、良い意味だったのだろうか。潔癖。きれい好きだから付き合いやすいとかそういう意味だろうか。それなら嬉しい。
中学生のとき、佐久早くんに恋をしてしまった薄汚いわたしはもうどこにもいない。消えていなくなっちゃえ、とずっと思っていた。佐久早くんにとっては耐えがたいことだっただろう。汚れた水。汚い雑巾。それにまみれたわたし。見るに堪えない汚いもののオンパレード。それでも声をかけてくれた。助けようとしてくれた。あの光景が忘れられないけれど、同時に、消してしまいたい光景でもある。佐久早くんの嫌そうな顔と必死に手を洗っていた横顔。そのどちらも、今も二人でいるときにたまに思い出す。あんな顔をさせてはいけない。佐久早くんが嫌がることはしたくない。だって、好きな人だから。好きな人のことは困らせたくない。当たり前だ。そんな当たり前の思いがあの日からずっとある。
佐久早くんの家に行ったときに着ていた花柄のスカートはもうクローゼットにない。佐久早くんのきれいな部屋の中で、あの花柄だけがうるさく思えたから。思い返してみればいつも佐久早くんはシンプルな服装だった。ガチャガチャした柄物なんて隣にいたら浮いてしまうほど。花柄のスカートを捨てて、代わりに佐久早くんの服装と雰囲気が合う落ち着いた色のスカートを買った。
きれいな子、になるのは難しい。でも、汚くない子、になるのは難しくない。ちゃんと髪の毛を整えて、ちゃんと化粧をして、シンプルだけど野暮ったくない服を着る。それだけで、汚くない子、にはなれる。ちゃんと日々の生活を送ればいい。余計なものはいらない。佐久早くんのようにいらないものは排除していけばいいのだ。
大丈夫、ちゃんとできてるよ。自分にそう言い聞かせる。大丈夫。佐久早くん、好きって言ってくれた。だから、ちゃんとできている。大丈夫だよ。汚れた水にまみれて廊下で呆然と座り込んだままだったあの日の自分。大丈夫。あなたはいなかったことできるよ。大丈夫だからね。そう安心して小さく息を吐いた。
戻る / next