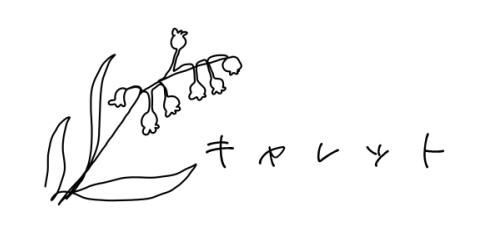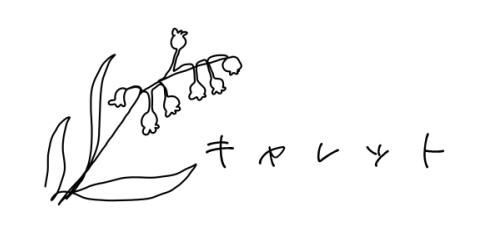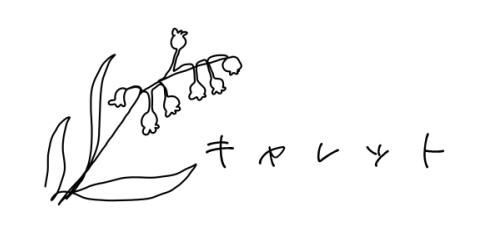 待ち合わせ場所に早めに付いてしまった。腕時計を見たら十五分前。思ったより電車の乗り換えがスムーズにできてしまった。でも、早いに越したことはない。ついた、と連絡をしたら佐久早くんが気にするだろうから連絡はせずに壁にもたれかかった。
待ち合わせ場所に早めに付いてしまった。腕時計を見たら十五分前。思ったより電車の乗り換えがスムーズにできてしまった。でも、早いに越したことはない。ついた、と連絡をしたら佐久早くんが気にするだろうから連絡はせずに壁にもたれかかった。
今日もいい天気になってよかった。今日はたまに二人で行く喫茶店でお茶をしてからその辺をぶらぶらしようという話になっている。ぼうっとしていると、突然横から「あの」という知らない声が耳に入ってきた。わたしじゃないだろうと思いつつ、何気なく視線を向ける。その先にはしっかりわたしの顔を覗き込んでいる男性の姿があった。
「あ、こっち見てくれた」
「……え、わたしですか?」
「そうそう。お姉さんに声をかけました」
人懐こい笑みを浮かべたその人は、わたしと同じように壁にもたれかかると「誰と待ち合わせですか?
友達?」と聞いてくる。暇つぶしの相手にされているのだろうか。嫌というわけではないけど、できれば知らない人と深い話はしたくないなあ。そんなことを思いながら「彼氏です」と答えた。その人は「へえ?」とどこか含みある声色で言った。
「僕あれなんですよ。彼氏がいる女の子に好きになられちゃうみたいで」
「……へ、へえ、そうなんですか」
何の話だろうか。ちょっと苦笑いをこぼしていると「でも本命の子にはフラれちゃうんですよ〜」とその人が言う。それは残念だけど、見知らぬ人に話すのはどうなのだろうか。会話の流れがよく分からないまま適当に相槌を打っておく。暇つぶしなんだろうから、この人が待ち合わせている相手が来たら終わるのだろう。はっきり拒否しづらいしこのまま適当に流しておこう。
よく分からない話を聞かされて、ちょっと相槌のレパートリーがなくなってきた。知らない人の恋愛の話はあんまり興味ないよ〜、と内心困っているのだけど、悪い人じゃなさそうだから言いづらい。
「あ、お姉さん手がきれいですね」
「そうですか?
はじめて言われました」
「嘘、本当に?
こんなにきれいなのになー」
何の声かけもないままその人がわたしの手に触れた。びくっと肩が震えたのを見たその人が笑って「あれ、どきっとしちゃいました?」と笑う。いや、確かにどきっとしはしたけど、笑ってはいそうですって言える感じのものじゃない。ちょっとした恐怖心というかなんというか。
佐久早くんに手を触られたときも怖かったけど、こんな感じじゃなかったな。離してほしくないけど離してほしい、みたいな。そんな気持ち。今はただただ離してほしいとしか思わない。けれど、こういうときにはっきり拒否をすると怖い目に遭うことがある、と聞いたことがある。逆上されたり、余計に執着されたり。そう思うとどうすればいいのか分からなくて、ただただ固まってじっとしているだけになってしまった。
にこにこ笑ったままのその人が、わたしの顔を見て「名前、教えてくださいよ」と言った。ちょっと顔が引きつってしまった。正直、この人と仲良くなりたいと思っていないから教えたくない。教えなかったら「名前くらいいいじゃん」と言われてしまうかもしれないし、機嫌を損ねてしまうかもしれない。知らない人とこんなに会話をした経験があまりないだけに困ってしまう。
佐久早くん、早く来ないかな。ちらりと辺りを見渡すけれど佐久早くんの姿はまだ見えない。佐久早くんは人より背が頭一つ高いからいればすぐに分かる。恐らくまだ電車に乗っているのだろう。まだ約束の時間の十分前だからいなくて当然だ。助けを求められる人が誰もいない。自分でどうにか切り抜けないといけない。一つ息をついて、その人の顔を見た。
「あの、本当にごめんなさい。できれば手を離してほしいんですけど……」
「えーっ、なんで?」
「な、なんで、と言われても……知らない人に触られるの、あまり好きじゃなくて……」
「だから名前教えてよ。友達になろうよ」
引く雰囲気がない。強気な人だ。自分とタイプが違いすぎて余計に対処法が分からなくなっていく。
ざわざわしている喧噪の中で、なんだかひとりぼっちになったような気持ちになる。ひとりぼっちでこの人に対峙しているような感じがして、ちょっと怖い。にこにこ笑っている優しい人に見えるのに、離してほしいと頼んでも手を離してくれない。ちぐはぐな態度に底知れぬ何かを感じて、ちょっと怖気付く。この人、優しい人じゃない。本当は怖い人だ。直感的にそう思った。
そっと自分の手を引っ込めようとするけど、やっぱり強く握られるだけで諦めてくれない。一体わたしの何がよかったのかさっぱり分からない。暇つぶしの相手ならたくさんいるだろうに。気が弱そうに見えたのだろうか。実際そうだから情けないのだけど。
爪を撫でられた。ぞわっとした。緊張とかそういうのではなく、嫌悪感だ。気持ち悪い。人に触られてそう感じたのは生まれて初めて。反対の手をきゅっと握った瞬間に、あ、と思った。
佐久早くんが感じている〝気持ち悪い〟というのは、こういう感じなのだろうか。汚いものに触るときにぞわっと嫌悪感が広がる感覚。思わず身を縮めてしまうような不快感。わたしなら、こんなもの、できる限り感じたくない。やっぱり佐久早くんが嫌がることはしたくないなあ。そんなことを考えた。
「おい」
びくっと肩が震える。わたしの手を握っている人が「あ、彼氏来ちゃった?」と笑う。振り返ると佐久早くんが、眉間にしわを寄せてこっちを睨んでいた。
「誰。何してんの」
「あ、ううん、あの、知らない人で……」
「知らない人ってひど!
まあ彼氏来ちゃったなら仕方ないか〜」
ぱっと手が離れた。ひらひらと手を振ってその人が「またいつか名前教えてね〜」と歩いて行く。その背中を佐久早くんが睨み付けながら「何?
本当に誰?
何された?」と矢継ぎ早に聞いてきた。怒っている、のだろうか。いつもより少し声が低くなっているように聞こえる。怖気付きながら待っている間に声をかけられたことと、離してほしいと言っても離してもらえなかったことを説明した。佐久早くんはもう見えなくなった背中を未だに睨み付けるようにしながら、小さく舌打ちをこぼした。
「遅くなって悪かった。行くぞ」
「えっ、あ、うん」
なんで謝られたんだろう。わたしがそれを否定する前に話が進められてしまったからどうしようもない。佐久早くんについて歩いて行こうとした、ら、佐久早くんの手がわたしのほうに向けられた。手を差し伸べられている、みたいな。何か渡さなきゃいけないものがあっただろうか。少し固まっていると佐久早くんがぼそりと「手」とだけ言った。
「……繋ぐの嫌じゃないんだろ」
「い、嫌ではない、けど」
「じゃあ何。あいつには触らせるのに俺はだめなわけ?」
怒っている。今の言葉でそう確信した。佐久早くんと手を繋ぐのが嫌な、わけじゃない。佐久早くんが嫌なんじゃないかと、無理をしているんじゃないかと、不安なのだ。今だって、この手はさっきあの見知らぬ人が触っていた手だ。佐久早くんが嫌がるには十分な状況だ。ここに来るまでにわたしが何に触れたのかも分からないのに。
いつも持ち歩いているアルコールウェットティッシュで拭いてしまえばまだマシだろうか。そう思って鞄の中に手を入れようとした瞬間、佐久早くんが「それ出すな」と低い声で言った。それ、というのはきっとわたしが出そうとしたもののことだろう。手を止めて、言葉に困ってしまう。だって、それで困るのは佐久早くんなのに。そんなふうに視線を向けると、佐久早くんはなんだか微妙な表情をしていた。怒っているようにも見えるし、困っているようにも見えるし、照れているようにも見える。いろんな感情が入り混ざった顔だ。
佐久早くんはしばらくわたしの顔を見つめていたけど、ふとした瞬間にため息を吐いて目を逸らした。それから、少し考えるように顔を背ける。視線を辺りに漂わせていたと思えば、横目でわたしをじっと見た。
「は俺が潔癖なんだと思ってるだろうけど」
「う、うん?」
「俺よりよっぽど、のほうが潔癖だろ」
そう呟いてから「そもそも俺は別に潔癖じゃない」とため息交じりに呟く。それから、有無を言わさない素早さでわたしの手を握った。それにびっくりしている間に佐久早くんが歩き始めるから、わたしも一緒に歩いて行くしかなくて。
わたしが潔癖?
どうして?
階段の手すりも、エレベーターのボタンも、汚い雑巾も、人が触ったものも、基本的には何でも触れるのに?
そう言われる出来事に思い当たる節もない。これまでの人生、他の人にそんなことは言われたことがない。そういうことを少し気にするようになったのも佐久早くんと知り合ってから。特別きれい好きでもないし、特別こだわりがあるわけでもない、のに。
握られている手を見つめる。大好きな佐久早くんが手を繋いでくれている。それは嬉しい。嬉しいのだけど、少し滲んでいる手汗とか、さっきまでの光景とか、佐久早くんが内心であの嫌な不快感を覚えていないかが気になって仕方なくて、怖い。佐久早くんは今何を考えているのだろう。そう考えると、心が落ち着かない。
佐久早くんのことが好きだ。中学生のときからずっと、憧れだった。嫌なことは嫌だとはっきり言えて、人に嫌われることなんかちっとも気にしていなくて、いつでもきっちりしていて、自分が許せないものはなんであれ許せない。それがたとえ、嫌いな汚いものを触る結果になったとしても。自分の気持ちに正直で、自分のことを尊重していて。とても、まっすぐな人だと、憧れている。
戻る
/
next