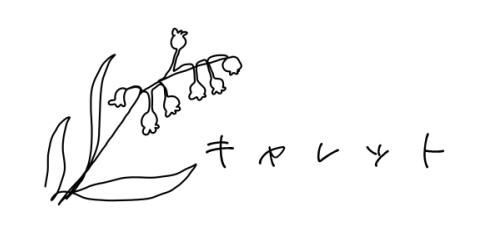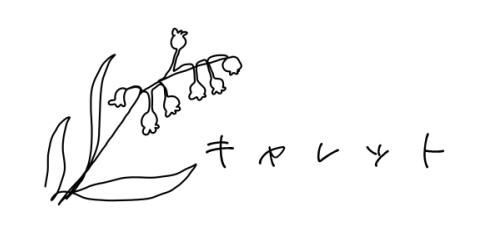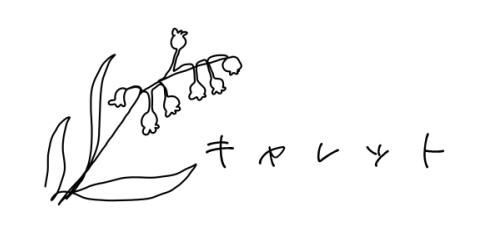 珍しく佐久早くんが映画を観たい、と言ったからてっきり映画館に行くのだと思っていた。お昼ご飯を食べて、電車に乗って、降りた駅で首を傾げる。映画を観るなら別の駅で降りたほうが便利なんじゃないかな。不思議に思ったけれど、佐久早くんがルートは決めてくれているから何も言わずについていき、気付いたときには「お、お邪魔します……」と震えるくらい緊張しながら言っていた。
珍しく佐久早くんが映画を観たい、と言ったからてっきり映画館に行くのだと思っていた。お昼ご飯を食べて、電車に乗って、降りた駅で首を傾げる。映画を観るなら別の駅で降りたほうが便利なんじゃないかな。不思議に思ったけれど、佐久早くんがルートは決めてくれているから何も言わずについていき、気付いたときには「お、お邪魔します……」と震えるくらい緊張しながら言っていた。
佐久早くんの家だった。どう見ても。二年付き合ってはじめて入った。きれいに片付いている玄関には靴が一つも置かれていない。きっとその日履く靴以外はすべて靴箱にしまってあるのだろう。そんなきれいな玄関に少しの間とはいえわたしの靴が置かれてしまう。なんだか申し訳ない。恐る恐る靴を脱ごうとして、はっとした。きれい好きな人は靴下を替えてほしいと言ってくることがあるとテレビで観た。佐久早くんもそういうタイプかもしれない。それにスリッパなしで玄関に上がられたら嫌なのではないだろうか。
いろいろ考えてたら体が動かなくなった。何かして嫌な気持ちにさせたくない。せっかく、こうして佐久早くんと付き合えたのだから、せめて嫌なことはしない人でありたい。どうしようか迷っていると、不思議そうに佐久早くんが「どうした?」と顔を覗き込んできた。それにさえもびっくりしてしまいながら口ごもってしまう。そんな様子のわたしを見て、佐久早くんは首を傾げながらスリッパを一足出してくれた。どうやらこのまま上がっていいらしい。怖々靴を脱ぎ、スリッパを履く。それから自分の靴を揃えてようやく一つ関門を越えた。
佐久早くんの後について恐る恐るリビングに入る。きれいに片付いた部屋。埃の一つも見当たらない。わたしもそれなりに部屋は片付けているけれど、物が結構あるからこんなには片付いていない。絶対佐久早くんに部屋は見られたくないな。そんなことを考えたら余計に緊張してしまった。
中学、高校のときからそうだった。佐久早くんはいつも小さなペンケースに必要最低限のものにしか入れていなかったし、ノートなどの持ち物にも無駄な装飾は一切なかった。シンプルで何もかもが洗練されている。そんなイメージだ。それがそのまま部屋にも反映されているのだろう。無駄なものも華やかな柄物もほとんどない。花柄のスカートを穿いているわたしだけが無駄にガチャガチャしているように思えて恥ずかしく思えた。
お茶を出してくれた。それを受け取りながら、スマートフォンを操作している佐久早くんの横顔を盗み見る。何が観たいか聞いていないけれど、佐久早くんが観たがる映画ってどんなのだろうか。男の人が好きな映画のイメージと、佐久早くんが好きそうなもののイメージがいまいち一致しない。
そう考えて、わたしは中学生の頃から佐久早くんに片思いをして、二年お付き合いしているというのに、佐久早くんの好きなものをあまり知らないな、と気付いた。バレーボールが好きだということくらいしかあまり知らない。佐久早くんが好きじゃないものや嫌いなものはたくさん知っているのに。なんだか情けない。好きな人の好きなものを知らないなんて。一人でそんなふうに苦笑いをこぼしてしまった。
「膝掛けいる?」
「えっ、あ、大丈夫です!
ありがとう」
佐久早くんはスマホを操作しながら「寒くなったら言って」と言ってくれた。優しい。その優しさを噛みしめながら「うん」と返す。動画配信サイトでお目当ての映画を見つけたらしい。テレビが勝手に付くと、映画がはじまった。
はじまって、驚いた。佐久早くんが選んだ映画は動物ものだったのだ。かわいいゴールデンレトリバーが主役で、動物好きの飼い主とともにいろんなところを旅するというもの。他にもたくさん動物が出てくる、所謂ほっこりする感じの映画。
佐久早くんって動物が好きなんだ。なんだかイメージにない。ちょっと驚いたけど、よくよく思えば心当たりがある。この前二人で歩いているときにかわいい子犬を散歩させている人とすれ違った。わたしが思わず「かわいい」と声に出してしまって、飼い主さんが立ち止まってくれたのだ。撫でさせてもらって、佐久早くんに思わず「かわいいね」と言った。佐久早くんは、触りこそしなかったけれど「かわいい」と呟いていた。佐久早くんが相槌じゃなくて「かわいい」という言葉を返してきたのが印象的だったからよく覚えている。
そっか、佐久早くんは動物が好きなんだ。知らなかった。一つ佐久早くんの好きなものを知れて嬉しい。思わずにこにこしてしまいながら映画を観る。わたしも動物好きだよ。一緒だ。そんなふうに一人で勝手に考えてしまう。好きな人の好きなものを、自分も好き。自分が好きなものを、好きな人も好き。それってすごいことだなあと思うのだ。一つ一つ大事にしていきたいな。そう思った。
映画の中に猫が出てきた。佐久早くん、猫も好きかな。そう思って「猫、かわいいね」と声をかけてみた。声をかけてすぐ、映画中に声をかけるなんて良くなかったかな、と反省する。でも、佐久早くんはその点には特に何も言わない。画面に向けていた視線をわたしに向けて、一つ瞬きをした。
「かわいい」
思った通り。やっぱり猫も好きだった。わたしも猫、好きだよ。そうにこにこしてしまう。「ね」とだけ返してまた画面に視線を戻した。
しばらく二人とも黙って映画を観る。当たり前だ。映画は静かに観るもの。おしゃべりしながらではストーリーが頭に入ってこない。二人で静かに並んで座っているのも、はじめは緊張したけれど次第に慣れてきた。どきどきしたままだけど、嫌などきどきじゃない。不思議だ。佐久早くんが淹れてくれたお茶を一口飲んで、コップをテーブルに戻す。それから自分の手を膝の上に戻してから一つ息をつく。
二年かあ。そうふと思った。佐久早くんと付き合い始めてもう二年も経った。夢みたいな二年間だった。佐久早くんがわたしのために時間を作ってくれて、わたしの隣にいてくれる。本当、未だに信じられない。こういう未来が待っていたのなら、中学生だったあの日、汚い水を頭からかぶって良かったな。割と本気でそんなことを思ってしまった。
けれど、佐久早くんはどうしてわたしと付き合ってくれたのだろう。汚い水をかぶっていた汚い上に鈍くさいやつ。汚いかもしれない隙間に手を突っ込めるようなやつ。およそ佐久早くんが好きになってくれる要素なんてなかったはずだ。
付き合うことになったのは高校の卒業式からだ。佐久早くんから言ってくれた。わたしは告白をするつもりはなく、これが佐久早くんを近くで見られる最後だな、なんて思いながら卒業式に参加していた。佐久早くんは絶対にバレーボール選手になるだろうし、遠くから姿を見ることはできるはず。それに、告白したところでフラれて終わるだけ。それなら遠くからどきどきして見ているだけのほうがよっぽど楽しい。そんなふうに思っていたから言おうと思ったことなど一度もない。そんなわたしを呼び止めてくれたときは全く状況が理解できなかったものだ。
思い出に耽っていると、佐久早くんが体勢を変えたのが視界の端っこに見えた。小さく伸びをしている。猫みたいでなんだかかわいい。微笑ましく思っていると、くるりと佐久早くんの顔がこちらを向いたのが分かった。驚いてわたしも佐久早くんの顔を見ると、しっかり目が合ってしまう。なんだろう。嬉しいけど、緊張してしまう。
「どうしたの?」
「……あのさ」
「う、うん」
佐久早くんはそこで言葉を切って、なんと言おうか考えているようだった。何か大事なことなのだろうか。もしかして、別れ話、とか。いや、でも、今日ははじめて家にお邪魔させてもらっているわけだし、そんなことはない、と、思うけど。嫌などきどきを感じながら佐久早くんの顔を見つめて言葉を待つ。
映画は中盤だ。物語の終盤に向かっていく派手な事件が起こっている最中。きっと大事なシーンなのに、佐久早くんもわたしも、画面は見ずにお互いの顔を見ていた。
「……手とか」
「うん?」
「繋ぐの、嫌いなのか?」
とんでもなく恥ずかしそうに、そう聞かれた。手を繋ぐのは嫌いか。どうしてそんなことを聞かれたのだろう。「そんなことはないけど……?」と首を傾げてしまう。むしろ、嫌いなのは佐久早くんのほうなのではないだろうか。人に触ることも、触られることもどちらも。佐久早くんをずっと見てきたから知っているつもりだ。
中学生のとき、クラスメイトだった男の子に貸した消しゴム。「もういらないからやる」と言って受け取りを拒否していた。女の子が勝手に触ったシャーペンを嫌そうな顔をして見ていた。高校に入ってからも、人に肩を叩かれれば嫌そうにするし、勝手に物に触られそうになったら拒否する。だから、手を繋ぐなんて以ての外、だと、思っていたのだけど。
佐久早くんとわたしは、二年付き合ってきて、手を繋いだことがない。そのことをうっかり話してしまった大学の友達からは「信じられない」と言われるけど本当のことだ。だって、佐久早くんがそういうことをするのが好きじゃないから当然のこと。嫌なことをしたいなんて思うわけがない。だから、繋いだこともないし繋ぎたいと言われたこともない。言ったことももちろんないまま。
「……繋ぎたいんだけど」
「えっ」
「嫌ならしない。忘れろ」
あ、と思った。これまで佐久早くんと二人で出かけると、いつもわたしの腕に佐久早くんの手が必ずぶつかる。距離感には十分気を遣っているはずなのに毎回だ。佐久早くんとわたしは身長差がある。手と手がぶつかったことは一度もない。それでもきっと佐久早くんは不愉快だろうから、毎回慌てて離れて謝っていた。あれは、もしかして、わざとだった、のかな?
そう思ったらぶわっと顔が熱くなった。だって毎回なんて変だと思っていたから。そういうことなら説明がついてしまうから。
佐久早くんと手を繋ぐ。一応、繋いでみたいな、とこっそり思ったことは何度もある。佐久早くんの手はとても大きくて、骨っぽくて、かっこいい男の人の手をしている。わたしのぷにぷにの弱っちい手とは全然違うから、触ってみたいなと見るたびに思った。好きな人の手なのだ。触りたいと思うのが普通、だと、わたしは思う。
でも、相手は好きな人だけど何より、佐久早くんだ。人に触られることが好きじゃない。汚いものに触ることはもっと好きじゃない。わたしの脳裏にはいつもあの光景が浮かぶのだ。中学生のとき、汚い水を頭からかぶったわたしを助けてくれたときの佐久早くん。手に何度も何度も石鹸をこすりつけて、とても丁寧に必死に手を洗っていた。汚い上にどうでもいいただのクラスメイト。触りたくなかったものに触ってしまったからだ。その姿に、本物の恋をした。だから。
佐久早くんが気まずそうに視線を逸らした。「嫌ならいいって言ってるだろ」とこぼして。その言葉にハッとする。嫌なわけがない。嫌なのは、本当はそんなことをしたくないのは、佐久早くんのほうなのに。もしかしてわたしが繋ぎたがっているような雰囲気を出してしまったのだろうか。そう思った変な汗をかいてしまう。
「違う、違うよ。あの、嫌とかじゃなくて」
「じゃあ何。嫌じゃないなら今繋ぎたいんだけど」
「いっ、今……?」
じろりと睨まれた。気を遣ってもらっているのはわたしだ。慌てて鞄を開けていつも持ち歩いているものを取り出す。除菌ジェルとアルコールウェットティッシュ。佐久早くんはそれを見て「何してんだよ」と呆れたように呟く。それに曖昧に返答しながら、まずアルコールウェットティッシュで手をきれいに拭いて、それから除菌ジェルを手に塗る。これで、一応、汚いものはついていないはず。ちょっと手がひりひりするけど、ちゃんと消毒できている証だ。ハンドクリームなんて塗ったらぬるぬるして気持ち悪いだろうし、構っていられない。
佐久早くんにきれいになった手を見せる。「こ、これなら大丈夫?」と一応確認を取ると、佐久早くんは一瞬固まってから「まあ……」と曖昧に返答をくれた。合格をもらえたらしい。ほっとしているわたしに佐久早くんが「じゃあ」と言って、手を伸ばしてきた。
はじめて手を握られた。大きな手。わたしの手なんてすぐに握り潰してしまえそうだ。手の平に他のところよりほんの少し硬いところがある。バレーボールをしているからかな。そんなことを考えながら、恐る恐る握り返した。
その瞬間、どくんっ、と心臓がうるさくなる。どうしよう、手汗とかかいたら、佐久早くん嫌だよね。それに除菌したけど手を洗ったわけじゃない。本当は嫌なんじゃないだろうか。手を離して、わたしが帰ったあと、手を必死で洗うんじゃないだろうか。今はものすごく、我慢をしてくれているんじゃ、ないだろうか。そう思ったら嫌な汗が止まらなくて仕方がなかった。
戻る
/
next