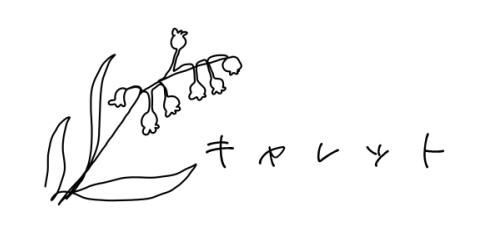佐久早くんはとても背が高い人だった。いつも億劫そうに猫背になっていて、何となくいつもつまらなさそうにしている。無表情だしいつもマスクをしているからそもそも顔がよく見えない。ちょっと怖そうな人。それがはじめて本人を見たときの第一印象。それでも、わたしはなぜだか佐久早くんが気になってたまらないまま。同じ教室にいるだけでなんだかドキドキして毎日困ってしまったことを覚えている。
わたしの恋を決定付けたのは、中学一年生の夏前の出来事だ。そのときのわたしは掃除で使った雑巾と、それを洗った水が入ったバケツを持って廊下を歩いていた。同じ掃除場所を担当していた女の子たちから、まあ、あけすけに言えば押しつけられたもの。わたしはいつも俯いていて暗い生徒だったから仕方がないことだ。
早く洗って帰ろう、と考えていたときのことだった。別のクラスの男子がふざけて廊下で野球をやっていたところに遭遇してしまった。恐る恐るその脇を通ろうと壁に体をくっつけるようにして歩く。でも、投げられた上履きが、すっぽ抜けてしまい。多くの人の予想通り、わたしの顔に思い切り当たった。それにびっくりしてバケツから手を離してしまい、その上に滑って転んでしまい。まあ、それはそれは、汚い水にまみれた汚い鈍くさいやつの出来上がり。そこまでが話の冒頭。
上履きをぶつけてきた男子たちは「まずい」と思ったのだろう。聞き取れないほどの早口で謝ってから、逃げるように走り去っていった。上履きさえも忘れて。手を差し伸べるとか、タオルを持ってきてくれるとか、そういうことはしてくれないんだ。内心そう思ったけど、当たり前だ。誰だって汚いものは触りたくないし、大してかわいいわけじゃない女子なんか助けたくもない。気持ちは分かる。汚い水に濡れた髪を払いながら、とりあえず雑巾を拾おうとした。
そのときだった。どこからともなくぬっと伸びてきた手。それが、落ちている雑巾をつまみ上げた。それから何も言わないままに転がっているバケツの中へ入れ、不機嫌そうな声で「タオル」とだけ小さく言った。顔を上げた先にいたのが、佐久早くんだった。びっくりして言葉を出せないわたしの頭にタオルを被せると「それもういらないからあげる」と言った。それからテキパキとどこにモップがあって、どこに使っていい雑巾があって、と掃除に必要なものの在処を教えてくれる。わたしが呆けつつ「ありがとう」と言うと、何となくバツが悪そうな顔をして「いや」とだけ言って去って行った。その先にある水道で、念入りに手を洗っている姿を、わたしはしばらく眺めていた。
佐久早くんはとてもきれい好きなのか、潔癖症なのか、基本的に人の物には触らないし自分の物を人に触らせない。ずっと見ていたからそれくらい知っている。だから、驚いたのだ。あの佐久早くんが、汚い雑巾を素手で触って、汚いわたしにタオルをくれた。あんなに念入りに手を洗うほど触りたくなかっただろうに。
おかしいと言われるかもしれない。汚いもの扱いされてるんだからときめくも何もないでしょ、と言われてしまうかもしれない。それでもわたしは、丁寧に、必死に、手を洗っている佐久早くんに、正真正銘の恋をしてしまったのだ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
佐久早くんに想いを伝えないまま中学を卒業して、こっそり追いかけて同じ高校に入学した。気持ちを伝えるつもりなんかなかったし、佐久早くんと仲良くなろうと思ったこともなかった。そんなわたしの運命を変えたのは、恐らく高校二年生の春の出来事だったと思う。
部活に向かうために部室棟のそばを歩いていたときだった。わたしの行く先に佐久早くんが不機嫌そうに立っているのを見つけて、内心でちょっとラッキーだな、なんて思った。それにしても何をしているんだろう。不思議に思って様子を観察していると、佐久早くんが足下をじっと見ている。佐久早くんの目の前には下に隙間がある倉庫。なんだろう。そう通り過ぎようとしていた足をゆっくり動かして、そうっと後ろを歩いて様子を窺うと、佐久早くんが足で木の枝をコツコツと蹴っているのが見えた。その動きを見てピンときた。きっと、隙間に何かを落としてしまったのだろう。手で触るのは嫌だし、地面に落ちている木の枝も触りたくない。だから、足で木の枝を動かして取り出せないかを試しているに違いない。
恐る恐る声をかけた。高校に入ってはじめて自分から話しかけた声は上擦っていたかもしれない。「どうしたの」というたった一言だ。緊張して発したその言葉に、佐久早くんが振り返る。「いや」とだけ言われてしまった。でも、中学のときに助けてもらったこともある。何か役に立てるなら、と思って「何か落としたの」と聞いてみた。佐久早くんは少し黙ってから、目を逸らして「部室の鍵」と教えてくれた。何でも鞄から取り出したときに誤って落としてしまったのだという。それが運悪く石ころに当たって隙間に入り込んでしまったのだとか。
何が落ちているか分からない倉庫の隙間。手を入れるの嫌だよね。そう言いながらしゃがんで、地面に手をついた。そんなわたしに佐久早くんが「おい」と慌てているのが分かった。でも、気にせず隙間に手を突っ込んで探ってみると、チャリ、と目的のものらしき感触を見つける。それをつまんで手を引っこ抜くと、思った通り鍵だった。「これですか」と聞いたら佐久早くんは、なんだかびっくりした様子で見つめてから小さく頷いた。持っていたタオルできれいに鍵を拭いてから「はい」と渡したら、佐久早くんはじっとそれを見つめてから受け取ってくれて、それから小さな声で「ありがとう」と言ってくれた。
それからだ。たまに佐久早くんが話しかけてくれるようになった。廊下ですれ違うときも何か声をかけてくれて、教室にいるときも声をかけてくれて。何が起こっているのかよく分からなかったけど、嬉しいことに変わりはない。緊張しながら佐久早くんと話す心臓のドキドキは、何とも言い表せないくすぐったさがある。とても心地よく、どこにも売っていない宝物だなあ、なんて一人で噛みしめていたっけ。
「」
びくっと肩が震えてしまった。慌てて顔を上げると、佐久早くんがいつの間にか真横に立っていて、「遅れてごめん」と呟いている。どぎまぎしながら「全然、待ってないです、大丈夫です」と必死に答えた。
今でも信じられないことだと思う。初恋は実らないとよく言うし、わたしの場合は恋をした相手からしても実らないであろう人だった。彼女になりたいとか彼氏になってほしいとか、そんな欲張りなことは考えたこともなかった人が、今こうして隣に立っている。大学に入学して二年目の夏。わたしの隣には、初恋である佐久早聖臣くんがいる。
「嘘つくな。顔が赤くなってる。日焼け止め塗ってきたのか」
「ぬ、塗りました、大丈夫です、ごめんなさい」
驚くことに、付き合って二年目を迎えている。佐久早くんがちょっと怒っているのは去年の夏に待ち合わせ中にわたしが日焼けをしてしまったことがあるからだ。日差しにいたわたしが悪い。それなのに佐久早くんは今日みたいに心配してくれた。そのあと佐久早くんに日陰に連れて行かれて数分しっかり怒られたっけ。怒られているというのに佐久早くんが怒ってくれていることが嬉しくて、全然嫌じゃなかったなあ。そんなことは佐久早くんにはもちろん秘密のままだ。
じっとわたしの顔を観察して、佐久早くんが小さくため息をつく。とりあえず帰ったら冷やしてしっかり保湿しろ、と言われたのでウンウン頷く。佐久早くんが心配してくれている。夢みたいだ。
二年経っても変わらない。佐久早くんがわたしの隣にいて、わたしのことを呼んで、わたしと歩いている。それがあまりにも非現実的で、話しかけられるたび驚いてしまうのだ。本物だ、と思ってしまうというか。これは夢じゃないんだ、といつも衝撃を受けてしまう。
マスクの位置を直しながら佐久早くんが歩き始めた。慌てて半歩後ろくらいについていく。数秒後、佐久早くんがちらりとわたしに目を向けてから、歩く速度を緩めたのが分かった。歩くスピードが速くてついて来られない、と判断されたのだろう。申し訳なく思いつつも、締め付けられるほどにきゅんとしてしまった。わたしなんかに合わせてくれるんだ。あの佐久早くんが。それだけで今日は胸がいっぱいで仕方がない。
これ以上ゆっくり歩いてもらうのが申し訳なくて、恐る恐る隣を歩く。視線は少し下。人にぶつからないように気を付けながらも、ちらりと盗み見るように佐久早くんを見てしまう。背が高い佐久早くんの視界にはわたしの視線は入らない。だから、いつもこうして盗み見している。どこから見てもかっこいいな、と。
ちょん、とわたしの腕に佐久早くんの手が当たった。慌てて手を引くと、佐久早くんが驚いたようにわたしを見ていた。「ごめんね、近すぎたね」と苦笑いをこぼして謝り、手が触れないくらいの距離を取る。佐久早くんは昔から人に触ったり触られたりすることが嫌いだ。だから、間違ってもわたしから佐久早くんに触らないし、佐久早くんとこうしてぶつかってしまわないように気を付けている。でも、気を付けているはずなのに一度は必ずこうしてぶつかってしまうのだ。そろそろ言葉で拒否されるかもしれない。ちゃんと気を付けよう。そんなふうに改めて自分に言い聞かせて、また前を向いた。
戻る / next