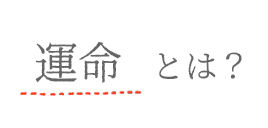
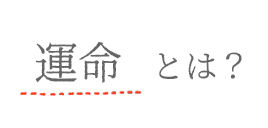
|
とにかく謝れ。
早めに切り出せ。
相手に聞かれる前にな。
木葉さんの言葉が何度も頭の中でリピートしている。 その通りだ。 木葉さんや他の先輩方、尾長に言われたことを守ってなんとかしないと。 そう思って臨んだ二度目の食事。 テーブルについて少ししてから彼女、さんの様子がおかしいことに気が付いた。 どこか上の空というか元気がないというか。 体調が悪いのに無理に来てくれたのだろうか。 そう心配になって聞いてみたら、さんは少しだけ間を開けてから言った。 「……本当に、三十一歳、なんですか?」 その瞬間に全身がピシッと音を立てて動かなくなった。 たぶん瞬きもできていなかっただろう。 そんな俺を見てかさんは「どうなんですか」とさらに質問を続ける。 木葉さんの言葉をまた思い出す。 とにかく謝れ。 早めに切り出せ。 相手に、聞かれる前にな。 この瞬間を持って先輩方のアドバイスはすべて無に返った。 どうして、どこでそう疑問に思ったのだろうか。 見た目だろうか。 さすがに五歳はきつかっただろうか。 先輩たちは「三十一には見えない」と言っていたが、ふだんは実年齢より年上に見られることが多い。 だから見た目で気付かれることはないだろうと思っていたのだが。 ただ、以前木兎さんに言われたことがある。 「赤葦ってなんか落ち着いてて大人みてーなんだけど、喋ってるうちになんかちゃんと後輩だなっつーか、放っとけないタイプだな〜って思う」と。 何か会話の中で年下感が出ていたのだろうか。 大混乱する頭を必死に動かし、ようやく出た言葉は「えっと、どうしてですか」というなんとも情けないものだった。 さんから説明された経緯に頭を抱えそうになった。 偶然に偶然が重なっていた。 あの日のカフェに木葉さんがいたこと。 木葉さんが木兎さんの名前を口にしたこと。 その日に木兎さんの試合中継があったこと。 さんの家のテレビがたまたまそのチャンネルになっていたこと。 さんが木兎さんの名前を覚えていたこと。 そんなこと、あってもいいのか。 いや、そもそも俺が嘘を吐かなければこんなことにはならなかった。 こんなことにならなかった、と思うけど。 こんなことになるまでにも至らなかったかもしれないと、往生際の悪いことを思ってしまう自分がいる。 「……すみません、嘘を吐きました」 さんの顔がちゃんと見られなかった。 今まで話したことはなくても、電車の中で見かけるたびに思っていた。 きっと真面目で誠実な人だろう。 人に嘘を吐いたり騙そうとしたりするような人じゃない。 そういうところに惹かれたのだから、自分で一番分かっていた。 嘘を吐いたり騙されたり、そういうことをされたら怒るのではなくショックを受けるタイプなんじゃないかと。 嘘を吐いたことは事実だ。 けれど、決して悪意があったわけでも騙そうと思っていたわけでもないことだけは信じてほしかった。 気持ち悪いと言われるかもしれないと思ったけど、自分がさんを知っていたことを話した。 電車でよく見かけていたことも、アプリをはじめたのはさんと知り合いたいからだったことも。 きっとさんは内心ドン引きしていただろう。 けれど、黙って話を聞いてくれた。 そうして最後、話し終わってた俺に「年上の女をからかおうというような気持ちはないか」を確認してきた。 それはそうだ。 そう思われて仕方ない。 断じてちがうと必死に否定し、アプリのいいね画面を見せた。 少し必死すぎる気もしたけれどどうにかして誤解は解きたかった。 少しの沈黙があってから、少し冷めてしまった料理を食べようとさんが言ってくれた。 話すことに必死で忘れていた。 謝って、お代は払うと言ったら遠慮された。 嘘を吐かれた上に冷めたご飯を食べる羽目になり割り勘させられる、なんて最悪な休日にしてほしくない。 なんとか説得してお代は払わせてもらうことになり、ほっとした。 「正直に言ってショックでした。 嘘を吐かれていて」 食べ終わってからさんは話し始めた。 アプリで俺と知り合ってからこうして実際に会うことになったとき、すごく勇気を出して会ってくれたのだと。 アプリで男性と知り合うことに後ろめたさがあって、かなり最初は警戒していたとも。 アプリをはじめた経緯からあまり良くない思いをしたことまで、たくさん教えてくれた。 それはこちらも同じだった。 さんのことを知っていたから喜んで食事に誘えたというだけ。 これが見知らぬ女性だったらきっと警戒しただろうし、そもそもこういうアプリを使おうなんて思ったこともなかった。 ネガティブな印象があったし、変な人に引っかかってしまったという話を聞いたこともあったからなおさらだ。 女性の立場からすればよりそうだったと思う。 さんのような人なら余計に。 「でも今は、たとえ人から不誠実だと言われても、赤葦さんと出会えてよかったと思っています」 からん、と氷がグラスにぶつかる音が響いた。 さんは俺の顔をまっすぐに見ていた。 怒ってもいなかった。 悲しんでもいなかった。 ちょっと、照れているような顔をしていた。 「赤葦さんさえよかったら、連絡先を、あの、交換しませんか」 できることならば運命がほしかった。 さんにつながる赤い糸みたいな、そんな少女じみたことを思っていた。 けれど、そんなものはどこにもなくて。 俺とさんは、俺が一方的にさんを好いている、同じ電車に乗ることがあるだけのただの見知らぬ他人。 それだけでしかなかった。 考えに考えて、無理やりさんをこちらに手繰り寄せるようなことをしたと思う。 年齢を誤魔化して近付いてまるではじめて会いました、というような態度を取った。 きっと普段の自分ならしないようなことをやってしまうほど、俺はさんのことが好きだった。 話したこともなければ名前を呼ばれたこともない、彼女の年齢も知らないし、そもそも彼女は俺を知らないのに。 つぎはぎだらけの糸だった。 ところどころ切れかけていて、ほつれていて、とてもきれいとは言えないものだった。 それをつないでくれたのは、紛れもなく俺が恋をしたさんの、あまりにも優しい心だった。 |