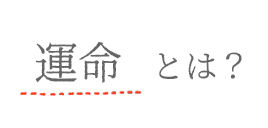
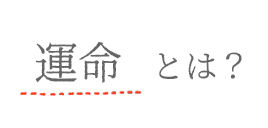
|
何も言い出せないままお店に到着してしまう。
席について二人でメニューを見て、注文をして、また穏やかに会話をする。
真正面から赤葦さんの顔を見た。
嘘を吐いているのだろうか。
何か隠しているのだろうか。
聞かなきゃいけないのに、なんと切り出せばいいのかに迷ってしまう。
なんと言い出そうか迷いに迷っているわたしに気が付いたのだろう。
赤葦さんはふと、話すのをやめた。
そうして心配そうな顔で「どうしました?
気分が優れないとか、そういうことがあれば言ってください」と言ってくれる。
その優しさに胸が痛んだけれど、ここがタイミングだ。
ぎゅっと拳を握る。
「赤葦さん、あの、聞きたいことがあるんですが」 「はい?」 「……本当に、三十一歳、なんですか?」 わたしがそう聞いた瞬間に赤葦さんは、まさにフリーズ、という感じで固まった。 完全に動きが停止している。 わたしが「どうなんですか……?」と追及すると、赤葦さんは完全に動揺したまま「えっと、どうしてですか」と言う。 落ち着いてゆっくりと疑問を説明する。 バレーボール選手の木兎選手の後輩が赤葦という人であること、前回会ったときに遭遇した先輩から木兎という名前が聞こえたこと。 どう見積もっても偶然というにはあまりにも可能性が低すぎること。 赤葦さんにはお兄さんがいないこと、木兎選手の年齢から考えてどうやっても三十一歳にはならないこと。 赤葦さんはわたしの話を聞きながら徐々に視線がわたしから外れていった。 明らかに動揺している。 話し終えてからじっと赤葦さんが話すのを待つ。 その間、赤葦さんは斜め下を見たまま黙り込んで、自分の手を握りしめている。 顔を上げたのは、店員さんが注文したものを持ってきてくれてからだった。 「あの」 「はい」 「……すみません、嘘を吐きました」 赤葦さんが頭を下げる。 そうして「本当は二十六歳です」と言った瞬間、体から力が抜けた。 嘘を、吐かれていた。 悪意があるかはまだ分からない。 けれど、その事実があまりにもショックだった。 赤葦さんがもう一度頭を下げて「すみません」と言った。 独り言を呟くように「どうしてですか」と聞いていた。 わたしの問いかけに赤葦さんは顔を上げた。 とても苦しそうにも見えたし、なんだかものすごく恥ずかしそうに見えた。 その表情の意味がよく分からない。 赤葦さんは「最後まで話を聞いてくれますか」と申し訳なさそうに聞いてきたので、頷いて見せる。 赤葦さんは「すみません、ありがとうございます」と言ってから、ぽつりぽつりと話し始めた。 驚いたのは赤葦さんはアプリを使う前からわたしを知っていたことだった。 赤葦さんが二十四歳のころ。 出勤中の赤葦さんとわたしは同じ車両に乗っていたそうだ。 先に乗っていたのはわたしで、赤葦さんはあとから乗った。 先にわたしが降りるときに赤葦さんはポケットからスマホを取り出す。 そのときいっしょに入っていたイヤホンを落としてしまったそうだ。 まったく覚えていないのだけど、それを拾って渡してくれたのが、わたしだったのだという。 「そのときは優しい女性だと思っただけだったんですが」 それから何度か同じ車両に乗り合わせたのだという。 とはいっても近くにいることは少なく、車両の端と端だとか、同じ座席の反対側だとか。 意識しないと視界に入らないところにいたそうだ。 わたしをなんとなく知っていたからなのか視界に入ってしまって、電車の中でどう過ごしているのかをたまに見てしまったと赤葦さんは恥ずかしそうに言った。 あのおばあちゃんに席を譲っているところ。 妊婦さんに席を譲っているところ。 酔っぱらった女性を介抱しているところ。 ベビーカーに乗った赤ちゃんにこっそり変な顔をしているところ。 恥ずかしいところまで見られていたようで恥ずかしくなってしまう。 「たまに乗り合わせて、そういう姿を見ているうちに、その、恋をしてしまって」 声をかけようといつも思ったと赤葦さんは言った。 けれど、見ず知らずの大男から突然声をかけられたら怖いだろうと思い、勇気が出せなかったとも。 今日こそは、今日こそは、と思っているうちに時間は過ぎて行き、しばらくして帰りの電車でも乗り合わせるようになった。 そうしてわたしがアプリをはじめて少し経ってから優子と電車でその話をしているのを聞いたと言った。 赤葦さんはものすごく申し訳なさそうに「その、すみません、チャンスだと、思って」としどろもどろに呟く。 そのときにわたしが「年下はちょっと」と言ったのが聞こえたそうで、赤葦さんは登録する際に年上にサバを読んだそうだ。 けれど、アプリでやり取りをする際に年齢確認があるはず。 そう言ったら年齢確認をせずに一日に決められた上限いっぱいをわたしとのやり取りに使った、と説明してくれた。 わたしのことを見つけられたのはアイコンに使ったキーホルダーを知っていたからだとも教えてくれた。 優子との会話を聞いてからわたしにいいねをするまでに時間がかかったのは、数多くいる女性からわたしを探すのに苦労したからだと苦笑いした。 おばあちゃんからもらったお礼のお菓子の話で感じた違和感も、ちゃんとそれで説明がついた。 あのとき赤葦さんはわたしと優子がパラソル型のチョコをもらったのを、見ていたのだろう。 聞かなかったけれど分かった。 「すみません。 気持ち悪いことをしていると自覚しています。 ただ、あの、断じて自宅までついて行ったりはしていません。 会話を聞こうとわざと近寄ったりもしていません。 ストーカー行為のようなことは本当にしていません。 その……電車の時間を、わざと、合わせたことは、あります、けど」 赤葦さんは力なくそう言う。 最後にまた「すみません」と言ってから頭を下げ、またゆっくり顔を上げる。 まっすぐにわたしを見ると、もう年上の男性だと思っていたときに感じた余裕みたいなものは消え去っていた。 なんだか必死な顔をして、赤葦さんはきゅっと少し唇を噛んでから口を開く。 「あなたのことが好きです。 すみません、ずっと、好きでした」 運命なんてはじめからどこにもなかった。 赤い糸でつながっているなんてこともなかった。 赤葦さんの手によって作られた運命で、赤葦さんの手によって結ばれた赤い糸だったのだ。 赤葦さんとアプリでつながったのも、会うことになったのも、わたしの理想通りだったのも。 すべては赤葦さんによって作られたものだった。 きっと、本当にはじめからなかったのだと思う。 赤葦さんが落としたイヤホンを拾ったのだって、きっと運命じゃない。 すべては偶然と故意がつないで、つないで、なんとかつながった縁だった。 嘘だった。 年齢も、今までの態度も、嘘でできたものだった。 けれど、そうだとしても。 それはあまりにも、わたしにとっては、かわいい嘘、だった。 「その、えっと、驚いています」 「……そうですよね、すみません」 「あの、確認なんですけど」 「はい」 「年上の女をからかってやろう、みたいな気持ちはないってことですよね?」 「あるわけありません。 本気です。 アプリでもさんにしかいいねしてません」 赤葦さんは焦った様子でスマホを取り出すとあのアプリを開いた。 そうして自分がいいねをした相手が表示されるページをわたしにずいっと見せた。 本当にわたししかいいねしていない。 相手からいいねされた数が見えるのだけど、結構な人数からいいねが来ているのに。 「本当にさんと話すきっかけがほしくて登録しただけです」と言ってから、赤葦さんははっとした様子で「偉そうにすみません」と恥ずかしそうに呟く。 そこから少し沈黙してしまった。 赤葦さんはひたすら申し訳なさそうな顔をしているから、なんとか場を持たせたくて「とりあえず食べませんか」とすっかりぬるくなってしまったであろう料理に目を向ける。 赤葦さんはそれにも謝って「お代は自分が出すので」と言った。 断っても「払います」と言って聞かない。 一先ず「分かりました」と言っておいて、帰るときにまた断ることにした。 二人で大人しめに「いただきます」と言ってから食事をいただく。 ぬるくなっているそれにちょっと笑ってしまうと、赤葦さんは余計に気まずそうな顔をして「すみません……」と言った。 |