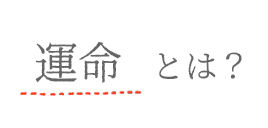
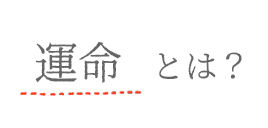
|
赤葦さんから来た連絡には十時発の電車、五号車に乗ったと連絡があった。
もうホームにいたので五号車の乗り場まで移動しておく。
大体十五分ほどで着くはずなのであっという間だろう。
深呼吸。 どうか、赤葦さんに騙されているわけではありませんように。 そればかりを昨日から考えていた。 思い至ったのだ。 たとえ赤葦さんが二十六歳だったとしても、その理由がわたしを騙そうというものでないなら、それでいいと。 悪意がなければいいと思った。 たとえば年上の女性を弄んで楽しんでいる、とかそういうことでなければいい。 何かわたしが思ってもみないような理由があればそれでいい。 そう思うことにした。 そんなことを考えている間に電車がやってきた。 風を呼んでゆっくりと停車する。 五号車がわたしの目の前に滑り込んでくると、すぐに赤葦さんの姿を見つけた。 赤葦さんもわたしを見つけてくれたようで、目があると小さく笑って会釈してくれる。 ドアが開いてわたしが乗り込むと、赤葦さんが立ち上がって「こんにちは」と声をかけてくれた。 それに、笑って、返す。 休日ということもあり電車内は少し混んでいる。 赤葦さんは横長の座席の一番端に座っていたけれど、その席をわたしに譲ると言った。 座っていたのは赤葦さんだし、赤葦さんが立つと身長もあって距離が開いてしまう。 だからわたしが立ちます、と返したのだけど赤葦さんは「いえ、女性を立たせるわけにはいかないので」と照れくさそうに言った。 断り続けたら赤葦さんに恥をかかせる気がしたので、お礼を言って座らせてもらうことにした。 代わりに荷物を持とうと提案したけど、赤葦さんはなんだかうれしそうに笑って「大丈夫ですよ」と言った。 あまり声が響かないように赤葦さんと会話をしていると、近くに立っている女の子がひそひそしているのが見えた。 こちらをちらりと見ている。 うるさかっただろうか。 そう思ってより小声にすると、赤葦さんが少し身を屈めて「すみません、なんでしたか?」と言った。 赤葦さんに聞こえないんじゃ意味ないし、どうしようか。 悩んでいると女の子たちの会話がちょっとだけ聞こえた。 「あの人、めっちゃ背高くない?」と少し、なんというか、黄色い声というような感じで。 それに続けて「あんな彼氏ほしい〜」と聞こえた。 やっぱり赤葦さんって、ふつうに生活していて彼女ができないなんてこと、ないよね? よっぽど職場に女性がいないのだろうか。 けれど学生時代に彼女くらいできていただろうし、どう考えてもモテなかったなんてことはないにちがいない。 モテてモテて困った、とまではいかないにしても、モテなくて困ったという域には入らなかっただろう。 どうしてあのアプリを使ったのだろうか。 電車が停車し、人が乗り込んでくる。 病院の最寄り駅だ。 赤葦さんの話を聞きながら少し視線をドアのほうへ向けると、あ、と思った。 あのおばあちゃんだ。 席はどこも空いていない。 赤葦さんに一言言ってから立ち上がると、おばあちゃんもわたしに気付いてくれた。 「こんにちは。 よかったらどうぞ」 「いいのよ、今日はお友達の家に寄るので一駅だけなんです。 お気になさらないで」 「この先はカーブがありますし、お気にせずよかったら座ってください」 迷惑だったかな? 少し不安に思っているとおばあちゃんは穏やかに笑った「ありがとうね、いつもごめんなさいねえ」と言ってくれた。 お友達の家に持っていくお土産らしき大きな荷物を受け取る。 電車が動き出していたのでおばあちゃんの手を取って席まで誘導すると、赤葦さんがその荷物をさりげなく持ってくれた。 席に座るとおばあちゃんが「ありがとう」とまた言って、自分の荷物を赤葦さんが持っていることに気が付くと「かっこいい彼氏ねえ」と微笑ましそうに言った。 照れながらしどろもどろに返している赤葦さんの横顔。 嘘なんて吐けなさそうな人。 そんな印象なのに。 やっぱりわたしの勘違いなのだろうか。 おばあちゃんの話を聞く横顔がとても、人を騙すような人にも見えなかった。 目的の駅の手前でおばあちゃんが言いにくそうに「今日はお礼できるものを持っていないの」としょんぼりして言う。 お礼してほしくて譲ったわけじゃない。 そう笑って言うのだけど、おばあちゃんはお友達へのお土産を開けようとするものだから少し困ってしまう。 なんとか断って最後に「またお話ししてください」と笑いかけると、おばあちゃんは「ありがとうね、お幸せにね」と手を握ってくれた。 赤葦さんと二人でおばあちゃんを見送ると、ちょうど席が二人分空いた。 二人で座ってから赤葦さんに「すみません、よく会う方なので気になってしまって」と苦笑いをする。 赤葦さんは小さく笑って「いえ、大丈夫ですよ」と言ってくれた。 おばあちゃんの話をしている中で、お礼といっていつもくれるお菓子のことを話した。 スーパーではなく駄菓子屋さんでお菓子を調達しているらしく、いつも少し懐かしいものをくれるのでうれしいと話す。 オレンジやグレープ味の風船ガムやヨーグルト型の入れ物に入ったお菓子。 家に帰って食べると子どものころよりおいしく感じる、と話したら赤葦さんはくすりと笑った。 「分かります。 俺もこの前、先輩がふざけて買ってきたあのチョコを食べたんですけど、なんだかおいしく思えましたよ」 それに笑い返す。 そうですよね、と言って懐かしい駄菓子の話が続いていく。 けれど、ふと、口が止まった。 あのチョコ。 赤葦さんはそう言った。 けれど、わたし、会話の中にチョコレートの話は出していない。 それにおばあちゃんは大体いつもチョコレート以外のお菓子をくれるのだ。 きっと溶けるといけないと思ってのことだろう。 いつかに優子といるときに席を譲ったとき、パラソル型のチョコレートをくれた。 たった一度だけだ、チョコレートをくれたのは。 赤葦さんにはそのことを話していない。 それなのに、赤葦さんは”あの”チョコレートと言った。 ふつうに考えればどれのことか分からなくて聞き返すところだろう。 けれど、思い当たる節があったから自然に聞き流してしまった。 赤葦さんは喋るのを止めて「どうしました?」と首を傾げる。 気のせい、かな。 赤葦さんもきっと何かを勘違いして、そう言っただけ、だよね。 うん、きっとそうだ。 大丈夫、何も変なことはなかった。 赤葦さんは悪い人じゃない。 自分にそう言い聞かせてからにこっと笑う。 「いえ、なんでも」と返したら赤葦さんは優しく笑ってくれた。 |