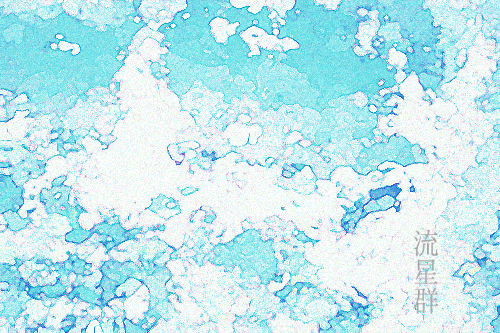
日曜日。 ベンチから見るコートの中は生き生きとした活気の声であふれている。 それを見つめる瞳。 今までなら冷たいものがどこかにあって、どこか他人事のように思えていた。 けれど、今はそうは思わない。 もう死んでいない。 ちゃんとわたしも生きてここにいられている。 そう思うだけで胸がわくわくした。
部内試合は塚本さんのチームの勝利で終わった。 いつものわたしなら落ち込んだと思う。 けれど、悔しさが残っただけで薄暗い感情はどこにもなかった。 そんなことが本当に久しぶりだったからうれしくて、思わず何かを堪えるように天井を見上げながら大きく息を吐いてしまった。 楽しかった。 バレーが楽しいと心から思えたのが本当に久しぶりで。 それだけで無敵になれた気がした。
練習試合は塚本さんが正セッターでわたしが控えセッターになった。 薄暗い気持ちも自分を蔑む気持ちもない。 ただただ目の前で繰り広げられる試合に夢中になれた。 バレーのことだけを考えられたのはいつぶりだろう。 ああ、バレーボールって楽しいな。 わたしはセッターというポジションが好きだな。 続けてきてよかったな。 そればかりが頭に浮かんだ。
出番はなかった。 今までのわたしならほっとしたんだろう。 でもちょっとだけ残念に思っている自分がいて、ちょっと調子に乗りすぎだな、と恥ずかしくなってしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「お疲れ」
体育館から出て部室へ向かおうとしたところを呼び止められた。 赤葦くんがすでに着替え終わった姿で立っていた。 固まっているわたしの後ろから先輩たちがぞろぞろと出てきてしまう。 わたしと赤葦くんを見つけると「あ」という顔をしてからすぐににやにや笑い「今からデート?」と赤葦くんに聞いた。 赤葦くんは待っている間見ていたらしいスマホをポケットにしまいつつ「俺はそのつもりですけど」といつも通りの表情で答える。 それにわたしが慌てている間に先輩たちはけらけら笑って「いってらっしゃ〜い」と先に部室へ歩いて行った。
「で、どこ行きたい?」
「ふつうに聞かないで……!」
「なにが?」
「な、なにがって……」
バレてるじゃん、と呟きかけたけどぐっと堪える。 もともと赤葦くんは隠すことにはあまり乗り気じゃなかった。 今までわたしが付き合わせている形だった。 今回赤葦くんに助けられた立場だからそこに文句は言えなくて。
そんなふうに葛藤していると、目の前で赤葦くんがふっと吹き出した声が聞こえる。 何かと思えば口元を隠しつつ笑って「ころころ表情が変わるから」と言った。 なんとか笑いを堪えて「かわいいな、と思って」と付け加える。
「そ、そういうの言わなくていいから!」
「いや、言うよ」
「いいんだってば!」
「着替えてる間にどこ行きたいか考えといて」
「ここで待ってる」と言って赤葦くんはまたスマホをポケットから出した。 たぶんわたしが決められない可能性があるから候補を探しておいてくれているのだろう。 男子部は今日も早上がりだったのだろうか。 わたしが聞くより先に赤葦くんが「今日は監督の都合で午前終わり」と教えてくれた。 コーチはいるとのことで自主練のために体育館は解放されているのだという。 いつも自主練習に残っているのに、今日はよかったのかな。 少しそう不安になったけど赤葦くんがほんの少し照れながら「木兎さんが今日はいいって」と呟く。 なんでも追い出されるように、木兎先輩をはじめとする先輩たちに体育館からつまみ出されたのだとか。 「ひどくない?」と苦笑いをこぼす。 「なんでだろうね?」と首を傾げたら、赤葦くんは目を丸くして驚いている様子だった。 それにわたしが余計に首を傾げると、ふっとまた吹き出して「いや、ごめん」と言う。 よく分からない。
とりあえず赤葦くんを待たせている状態なので、急いで部室へ向かう。 少し小走りする足はなんだか軽やかだ。 自分はとんでもなく単純な人間かもしれない。 そう思うと少し情けなくもなったけれど、それはそれで悪いことではない気もした。
部室に到着し、ドアをノックしてから中に入ると先についている先輩や他の部員に迎えられる。 笑顔で話しかけられたり赤葦くんとのことをからかわれたり。 恥ずかしい気持ちもあったけれど、どこか晴れ晴れとしていた。 自分のロッカーの前にたどり着き、中から制服を出してジャージを脱ぎ出す。 大会や他校での試合のときはジャージでいいのに、学校での休日練習は制服で登下校しなきゃいけないのって結構面倒だ。 内心そう思いつつ半袖のシャツを脱ぎかけたところで「」と呼ばれた。 振り返ると、水野さんが椅子に座ってわたしをじっと見つつ手招きしてくれていた。
急いで制服のシャツを着つつ返事をして水野さんのところへ行く。 水野さんは手首をさすりつつ「お疲れ」と笑いかけてくれた。 心底どうかしていると思うのだけど、少しどきどきしている自分がいる。 水野さんがいたから梟谷学園に来たのだから仕方ない、と思ってもらいたい。 目指すものの形が違っていたとしてもわたしの憧れであることに変わりはない。 水野さんはわたしの顔を見つめて「よかった」と安心したように笑う。
「赤葦くんが言った通り、わたしはになれないから、はのままでいてね」
「チームのためにもね」と呟いた声は、どこか悔しさが滲んでいるように聞こえた。 水野さんはきっとすごい選手になる。 大学に行ってからも、社会人になってからも。 きっと日本女子バレー界にその名を残す人なのだと思う。 でも、今は違う。 怪我のせいで試合に出られない。 その見惚れるほどすごいトスを出すことはできない。 わたしも悔しい。 けど、もちろん、水野さんのほうが悔しいのだ。
水野さんは手首をさするのをやめる。 「うん、まあ、でも」と照れくさそうな顔をした。 「憧れだって言われたのは、結構、うれしかった」なんて言ってくれるから、わたしまで照れてしまう。 本人に言うつもりはなかったのに、こっちもバレてしまっている。 恥ずかしいけど、なんだか伝わってうれしい気持ちもある。
「これからもずっと、わたしの憧れです」
照れくささは隠しきれなかった。 でも、ちゃんと伝えられた。 それだけで十分でなんだかもう、俄然無敵な気持ちだった。 言えたらこんなにもすっきりするんだ。 知っていたら一年生のときに言っていたかもしれないなあ。 内心そう思いつつ思わず笑ってしまう。 水野さんもつられたように笑うと近くにいた伊藤さんが「なにこの照れくさい空間」と同じように笑った。
水野さんに頭を下げてから自分のロッカーに戻る。 リボンをつけてからジャージの下を脱いでスカートを穿く。 カーディガンだけ羽織ってジャージを畳みつつ鞄をロッカーから出した。 十分にスペースは空いている。 ジャージを中に入れてあった袋に入れてから鞄にしまい、肩に鞄をかけた。 ロッカーを閉めていると伊藤さんがにやにやと笑いつつ「どこ行くの〜?」とわたしの背後に突然やってきていた。 「へっ」と素っ頓狂な声が出ると他の先輩や同輩も悪ノリしてきて「赤葦くんとどこ行くの〜?」と楽しそうにからかってくる。 塚本さんまでその輪にいるものだから余計にあわあわしてしまった。 それを唯一苦笑いで見ていた水野さんが「はいはい、かわいそうだからやめてあげなって」と声をかけてくれたのでなんとか助かった。
水野さんの後押しを受け、ようやく部室から脱出した。 もうこの時点で疲れてしまったけど不快感はない。 むしろ、あんなふうにからかってくれるのはむしろ優しさだろうと思う。 それを思ったらなんで今まで隠していたんだろう、と少しだけ思ってしまった。 風で乱れる髪を押さえつつ小走りで体育館のほうへ戻る。 その間に他の部活の友達に声をかけられたけど、「お疲れ! ごめんまた明日!」とだけ返して足は止めなかった。
赤葦くんのところについたときには少し息が上がっていた。 スマホの画面から顔をあげて「おかえり」と言われたので「た、ただいま」と返したら「そんなに急がなくてよかったのに」と笑われた。 スマホをポケットにしまってから「どこ行く?」と聞いてくれる。 赤葦くんとならどこに行っても楽しい、という意味で、いつもどこでもいいと答えることが多かった。 今回もそれを見越されている気がする。 少し考えてから「じゃあ」と口を開いたら、ほんの少しだけ赤葦くんが驚いたのが分かってしまった。
「う、海……行きたい、です」
「……なんで敬語?」
笑われた。 でも赤葦くんはすぐに「いいね、海」と言ってルートを考え始める。 とりあえず駅に向かうのは決定事項なので、二人で歩き始めることにした。 歩き始めてすぐ、肩から鞄がずり落ちそうになったのでショルダーベルトの位置を直す。 それを横目で見ていた赤葦くんの手が伸びてきて、ショルダーベルトをつかむとそのまま引っ張って行こうとする。 「自分で持つからいいよ」と負けじと掴み返して死守していると赤葦くんは少し不満げに「いいのに」と呟いた。
最寄り駅から電車で一本。 一番近い砂浜はそこだった。 わたしは行ったことがないところだったけど、赤葦くんは子どものころに行ったことがあるそうだ。 思い出すような視線をどこかに向けつつ「小学生のときだったかな」と思い出をめぐっている。 意外とこの横顔が好きだ。 勉強しているときに分からない問題を考えているときより柔らかい。 部活のことで悩んでいるときより抜けている。 不意に懐かしそうな表情をすると、わたしまでなんだか懐かしい気持ちになる。
赤葦くんは小学生のときに行った海のことを思い出したらしい。 ぽつぽつと教えてくれる思い出話を聞いていると駅に到着した。 ICカードを定期入れから出して改札をくぐる。 そのあとで「は海、あんまり行かないの?」と聞かれたので少し考える。 どちらかというと山でキャンプ派の家族なのであまり海に行った記憶はない。 最後に海に行ったのは遠すぎる昔のことで記憶にほとんど残っていなかった。 それを聞いた赤葦くんは「逆に山に家族で行った記憶がない」と笑った。
ホームにやってきた電車に乗り込む。 意外と空いていたので二人並んで椅子に座った。 二人掛けの席が並んでいる電車だったのだけど、こういう席に座るときは必ず窓側を譲ってくれる。 なんとなくそれに気恥ずかしさを覚えるけど、あまりにも自然にそうしてくれるからわたしが変なんじゃないかって思うほどだ。 赤葦くんが通路側に座ったと同時に電車が動き出してから、かすかにスマホのバイブ音が聞こえた。 自分かと思って鞄を探っていると赤葦くんが「俺の」と言ってスマホをポケットから出す。 画面をつけてすぐに赤葦くんが「うわ」と少しだけ嫌そうな顔をした。
「どうしたの?」
「姉貴」
「そ、そんなに嫌がらなくても……」
「さっきホームにいたとき、反対側にいたみたい」
「なんて?」
「隣にいた子彼女でしょ、ってさ」
赤葦くんは未だ嫌そうな表情のまま「めんどくせえ」と珍しく少し崩れた口調になった。 お姉さんと仲が良いのだろう。 わたしのクラスメイトの子がお姉さんと仲があまり良くないと話していたのを思い出す。 連絡も取らなければ家に帰っても話さない、と言っていたっけ。 赤葦くんは映画に行ったときもお姉さんのことを話していたし、普段からたまに話に出てくるから仲は悪くなさそうだとは思っていた。 でも、こんなメールを送ってくるのだから、きっと仲が良いんだ。 そう思うと少しだけほほえましい気持ちになった。
「この前映画から帰った日もうるさくてさ」
「何に?」
「彼女とデートだったんでしょ、って。 彼女いるって言ったことないのに」
なんて返したのか聞いてみたら「だから何って言ったらにやにやしながらどんな子とかいろいろ聞かれた」と苦笑いをこぼした。 仲の良い姉弟だ。 くすっと笑ってしまうと赤葦くんが「いや笑い事じゃないよ」と困ったような顔をする。
「どんな子って言ったの?」
「姉貴が好きな少女漫画の話したの覚えてる?」
「うん」
「そのときにに似てるって言ってたキャラクターのこと言ったらさ」
「うん?」
「あんたそのキャラクターが一番好きって言ってたもんね、って言われた」
「気を悪くしないでほしいんだけど」と苦笑いで前置きしてから、赤葦くんは帰ってから思い出したというそのキャラクターのことを教えてくれた。 その子はヒロインの幼馴染という設定の子で、美人で気の強いヒロインに比べると少し地味で気の弱いキャラクターだったのだという。 ヒロインと最終的に付き合うことになるキャラクターに長年片思いをしていたが、最後までその想いを告げることはなく物語は終わってしまう。 そればかりではなくヒロインが相談をすると後押ししたり、二人が付き合うことになったら笑顔で祝福したりして、当時の赤葦くんはかなりもやもやしたそうだ。 「自分も好きなのになんで敵に塩を送るんだろうって」という言い方が面白くて笑ってしまった。 けれど、最後までヒロインを友達として応援し続けた姿に赤葦くんは惹かれたのだと言った。
「がんばってるから応援したくなるというか、助けたくなるというか。 そういうところが似てる」
「そ、そうかな……?」
自分ではよく分からない。 たしかに赤葦くんには助けられてばかりだけれど。 そんなふうに思っていると赤葦くんは小さく笑って「そうだよ」と優しい声で言った。
top / 流星群