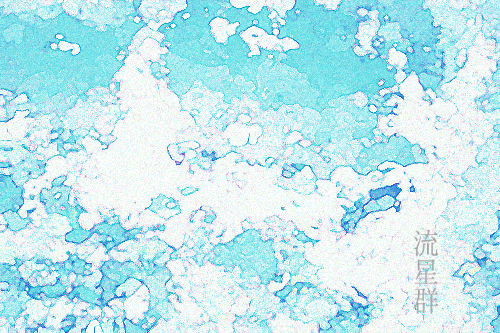
自分の気持ちを言葉にするのは簡単に思えるのにとても難しい。 赤葦くんを前にするといつもそう思う。 何か言わなきゃって思うほど何も言葉が出てこない。 そういうとき、まるで心がなくなったように空っぽなことに気が付く。 何も持っていないわたしのどこを好きになってくれたのだろう。 そう思うとなんだか悲しくて、結局黙ってしまう。 でも、そんなわたしのことがすべて分かっているように赤葦くんが言葉にしてくれる。 甘えているのは分かっているのだけど、そうしてくれることでなんだか心を取り戻せた気がして、いつも頼ってしまうのだ。 わたしの中身は全部赤葦くんが与えてくれたものだなあ。 そう思ってしまうくらい、わたしは赤葦くんに甘えっぱなしなのだ。
駅から出て目の前に海が見えた。 きらきら光る水面がきれいで思わず声が出ると、赤葦くんも穏やかな声で「きれいだね」と言ってくれた。 出てすぐの場所に堤防があって、それに沿って歩いていくと砂浜の入口に行けるようだ。 二人で堤防を辿りながら海を眺める。 心地よい波音が体に馴染むように響いている。 なんだか二人とも聴き入ってしまうように口数が減った。 けれど、気まずさはひとつもない。 会話をしていないのにお互いのことを考えているのが手に取るように分かる。 照れくさいような居心地の良いような、不思議な感覚だった。
日曜日ということもあって人は思っていたよりいた。 それでも静けさを保っている海は、近くで見ると余計に水面を輝かせている。 昨日の星がぜんぶ海に落ちてしまったみたいな光は美しさとほんの少しの切なさを感じさせた。
「俺って頼りない?」
砂浜に続く階段を降りる途中、そんなことを突然聞かれた。 赤葦くんは足元を見たりわたしを見たりしつつなんだか不安げな顔をしている。 そんなこと思ったこともない。 ちょっと驚きつつ「ううん」と首を横に降ったら、赤葦くんは「本当に?」となんだか情けなく笑った。 ちゃんと舗装されていない階段はぼこぼこしていて、注意していないと足を滑らせてしまいそうだ。 わたしも足元を見たり赤葦くんを見たりしながら降りていく。 一段先に降りていた赤葦くんがそれを見て「やっぱり鞄持とうか?」と聞いてくれた。 バランスを取りやすくしようとしてくれているのだろう。 でも、さすがに鞄を持ってもらうのは申し訳ない。 赤葦くんだって部活終わりのそれなりに重たい鞄を持っているし、わたしの鞄だってそれなりに重たい。 言葉を選びつつ断ると、赤葦くんはやっぱりちょっと不満げな顔をして「いいのに」と呟く。 差し出した手を引っ込めようとしたところを、きゅっと握ってみる。 それに驚いた赤葦くんが急いで顔を上げたからか、赤葦くんが足を滑らせた。 わたしが手をつかんでいたから転びはしなかったけど、赤葦くんは「びっくりした」と言ってまた階段を見たりわたしを見たりと忙しない。
「ご、ごめん、鞄は持ってくれなくていいから、手を、つなぎたいな、と思って」
「…………お安い御用です」
「なんで敬語なの」
ちょっと笑う。 赤葦くんは照れくさそうな顔をして「かっこ悪いとこ見られた」と呟いた。 きゅっと握ってくれた手をわたしも握り直してから、二人並んで階段を降りた。
白い砂は意外と柔らかくて少し足を取られる。 二人で苦労しつつ波打ち際まで歩いていき、ようやくちゃんと前を向けた。 波が押し寄せないところに鞄を下ろしてから二人とも座る。 ほんの少し吹いている風に赤葦くんのネクタイがゆらゆらと揺れている。 つないだままの手が、何かを探るように動いた。 赤葦くんはわたしの手を握る力を緩めたり強めたりしながらじっと見つめる。
「なに?」
「いや、小さいなと思って」
「赤葦くんが大きいんだよ」
「そうかな?」
反対の手を見つめてからつないでいる手を見る。 「いや、が小さいだろ」と言うのでわたしも反対の手を出してぴったり合わせてみる。 赤葦くんの指の第一関節の少し下にしか指が届かない。 身長差もあるし当然なのだけどなんだか悔しい。 わたしの手に比べると少しごつごつしていて硬い。 爪の形も指の太さも、関節の出方も違う。 そんなふうに赤葦くんの手を観察していると、赤葦くんが少し笑ったのが見えた。 わたしが視線を赤葦くんに向けたのが分かったみたいで「いや、ごめん」と余計に笑った。
「かわいいなと思って」
「え、なにが……?」
「手が小さいのとか、じっと見てる顔とか?」
「……赤葦くんのつぼって難しいよね」
「そうかな。 意外と簡単だと思うけど」
合わせていた手を離す。 赤葦くんは風でずれたネクタイを直してから膝で頬杖をつく。
「大体ならなんでもかわいいって言うと思うよ」
「……だ、大体、ですか」
「大体です」
ぜんぶ、と言わない辺りがなんだか赤葦くんらしい。 赤葦くんは「限りなくぜんぶに近いから」と笑ってくれた。
ぽつぽつと、久しぶりにちゃんと部活の話をした。 去年の春高予選以来、自分に対しての自信を喪失してしまったけど、それを埋めるために誰かの真似をすることに依存してしまったこと。 それが情けないことだと分かっていたから赤葦くんにも相談しないまま、どんどん首を絞めてしまったこと。 ずっとバレーが苦しかったこと。 そのときは水野さんや塚本さんだけじゃなくて、赤葦くんのことも見るたびネガティブに思ってしまっていたこと。 好きにならなきゃよかった、なんて、ひどいことを思ってしまった瞬間があったこと。 赤葦くんが手を握ってくれているからなのかすんなり話せた。 言葉に詰まらなかった。 何を言っても赤葦くんなら受け止めてくれるんじゃないかと思えた。 また甘えている。 でも、それでよかったのだ。
赤葦くんはじっとわたしの顔を見たまま話を聞いてくれた。 合間に低い声で「うん」とだけ相槌を打って、ただただ静かに。 それにお礼を言ったら優しい声で「なにが?」と言うだけだった。
夢中でバレーの話をした。 水野さんのどこがすごいとか、塚本さんのここを見習いたいとか、赤葦くんに教えてほしいことがあるとか。 たくさん。 赤葦くんの相槌を聞くのも忘れるくらい夢中に。 こんなに楽しくバレーの話ができるなんて思わなかった。 そんなわたしをただただ見つめて静かに話を聞いているだけだった赤葦くんが突然「あのさ」と口を開く。
「なに?」
「キスしたら怒る?」
「…………お、怒る」
「言うと思った」
けらけら笑う。 じゃあなんで聞くの。 そうちょっと視線を逸らして聞いたら「聞かずにしても大丈夫だった?」と逆に聞かれて黙ってしまう。 大丈夫じゃない。 ここ、外だし、他に人いるんだよ。 内心そう返す。 そんなの赤葦くんにはお見通しだったみたいで「室内で人がいないときね」と笑われた。
じいっと見られている。 なんとなく視線がこっちに向いているのが見えていなくても分かった。 そうっと視線を戻したら、赤葦くんがやっぱりわたしのほうをじっと見ていた。
「次の合練来る?」
「……赤葦くんは?」
「行くよ。 のトス、俺も打ってみたいし」
「だめ?」と穏やかに笑う。 思うのだ。 赤葦くんがわたしの大体かわいいと評してくれたのと同じように、わたしも赤葦くんのお願いなら大体なんでも聞いてしまうだろうと。 限りなくぜんぶに近いくらい、大体なんでも。 ……その大体に含まれないのが人前でキスすることくらい、なのかも。 一人でそんなことを考えつつ笑い、「わたしも赤葦くんのトス、打ってみたい」と答えたら「お安い御用です」と言って手を握り直してくれた。 楽しみが一つ増えた。 そう赤葦くんが言うので、他に約束でもしてたかなと首を傾げる。 赤葦くんは笑いながら「のトスを打つことと、とキスすること」と言う。 思わず赤葦くんの膝をつないでないほうの手で叩く。 赤葦くんは「そういうのもかわいい」と言って、余計に笑うのだった。
top / Fin.