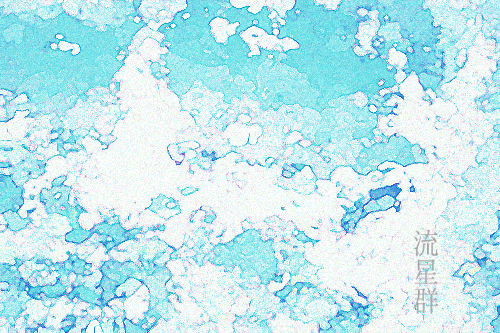
「赤葦くん〜? ちょっと言いすぎじゃない?」
「すみません、もうすぐ終わります」
伊藤さんが赤葦くんの言葉にため息をもらす。 水野さんには、なれない。 赤葦くんの声がまだ耳に残っている。 ついに人から言われてしまった。 それにきっと笑うだろうと思っていたのに、実際に言われてみたら表情は一つも動かないままだ。 変な汗が背中をつたう。 固まったまま動けないわたしの顔を赤葦くんが覗き込んだ。 ほんの少しだけばつが悪いような表情をしていた。
「でも、水野先輩だってにはなれないよ」
「……え?」
「どんなにがんばったってはだし、水野先輩は水野先輩だろ」
「意地悪なこと言ってごめん」と言ってから少しだけ丸めていた背中を伸ばした。 赤葦くんの顔を追うようにわたしも顔を上げると、少しだけ呼吸がしやすくなった気がする。 俯いていたら苦しい。 それをなぜだかすんなり認められた。
「もう一回言うけど」
ずっと認めたくなかった。 わたしはあんなふうになりたいけど、なれないのだ。 それを認めたくなかった。 自分のトスを嫌いになってしまいそうで、認められなかった。 でも、そうじゃなかった。 今まであげてきたトスが頭をめぐる。 わたしがあげてきた無数のトス。 失敗もあった。 ものすごく調子が良くてわたしは最強なんじゃないかって思うくらいのトスもあった。 でも、その中で一番輝いて記憶に残ったままなのが、ぼろ負けした試合のときのトスだったのだ。 調子が悪くていつも通りのトスがあげられなかった。 それでもチームメイトはわたしのトスを求めてくれた。 どんなに下手くそでも、どんなに乱れていても。 チームメイトみんながそのトスを信じて打ってくれた。 そんな状態でもトスを求められる。 それこそが、セッターとして何よりも誇りで何にも代え難いことだった。
「俺はが好きだよ」
少し辺りの人たちが冷やかすというか色めきだったような声をあげた。 いつものわたしだったらそれを恥ずかしがったと思う。 けれど、今は一切気にならなくて。 まっすぐにわたしを見てくれている赤葦くんの瞳が今までで一番力強く見える。 なぜだか指先に熱を柔らかく帯びてきた。 何度こすり合わせても冷たいままだった指先に感覚がある。 鮮明にトスをイメージできる。 その頭の中には、もう水野さんの姿はなかった。
なんだか困ったように笑う伊藤さんはわたしの背中を叩いて、「絶対勝つよ」と顔を覗き込んでくる。 それを見ていた他のチームメイトも「こっからですよね〜」と笑った。 まだ夢から覚めたような感覚のままその会話をぼんやり聞く。 絡まっていた糸がほどけてなくなった。 あまりにもあっさり。
「簡単なことだろ」
笑った。 赤葦くんは審判の人を見て「もう大丈夫です」と告げた。 休憩を含んだかなり長いタイムが終わる。 チームメイトの輪の中に入ったままコートに戻ると、いつも頭をぐちゃぐちゃにしていた何かはなくなっていた。
ホイッスルの音が響いて五秒後、思った通りの位置に鋭いサーブ。 ファーストタッチも思った通りの同輩になり、わたしの頭上に完璧なAパスがあがった。 そう、この子は攻撃力があまり高くないことが悩みで、筋トレをしても筋肉が付かないしスパイクの威力が上がらないといつも嘆いていた。 だからといってレギュラーを諦めたくなくて、攻撃力が伸び悩んでいるのならとレシーブ力を上げたのだ。 特にサーブレシーブは、それだけを見ればレギュラーの誰よりもうまい。 必死に練習している姿を見ていたから知っていた。 ゆっくりと腕を持ち上げる。 重たくない。 指先も冷たくない。 分かる。 一番近い位置にいるのは同輩の控え選手。 後ろ側にいるのは一年生。 サーブレシーブをした同輩はフォローに回るためにすでに体勢を立て直し終わっていた。 ネットから一番離れた位置に恐らく次期主将になる同輩。 その少し前方に伊藤さん。 第一セットの試合運びからすればたぶん伊藤さんにあげた。 きっとわたしじゃない誰かならこうするだろう、と思って。 何の変哲もない、誰にあげたのかさえよく分からない曖昧なトスを、きっとあげただろう。
鋭い音が響いた。 熱を帯び始めた体が呼吸を求める。 ゆっくり大きく息を吸いながら顔を上げる。 それとほぼ同時に伊藤さんが飛びつくように「よっしゃー!」と抱き着いてきた。 あげるべきだと思ってあげたトスは、誰にも負けない全国屈指のエースによってポイントに変わっていた。 ひりひりと痛いくらいに指先が熱い。 もう体は重くなかった。
「もう一本!」
弾ける笑顔が眩しい。 眩しいけれど、憧れのように触れられない場所にあるわけじゃない。 憧れはわたしより高い位置にあったわけじゃなくて、わたしとは別の場所にあったのかもしれない。 なりたかった。 それは変わらない。 けれど、ならなくてもよかったものなのかもしれない。 チームメイトが求めてくれたのは憧れを真似したものじゃなくて、そのままのわたしだった。 そう思えたら表情が綻んで、いつぶりか分からないほど久しぶりに、コートの中で笑えた。
セッターとしてはじめてトスをあげた日のこと。 あげたトスがはじめて点に変わった日のこと。 はじめて頭に描いた放物線を描けた日のこと。 あげてきたトスは数多い。 数えたことなんてない。 星の数ほどあげてきた。 そのトスのいくつが得点に変わり、いくつが失点に変わったのか。 それを考えるとなぜだか苦しくなったことがある。 いや、なったことがあるんじゃなくて、最近はずっと苦しかった。 わたしがあげたトスの何本が成功で何本が失敗だったのか、それが無性に気になっていた。 ああ、でも、そんなもの、どうでもよかったのだ。
「わたし打てる!」
「わたしも!」
「わたしもいけます!」
誰かのお手本に頼らないセットアップは久しぶりで、頭が混乱してしまった。 一瞬止まった指先。 それを一瞬で感じ取ったチームメイトが我先にと手を挙げてくれる。 そんな小さな動き、どうして感じ取れるの? みんなの能力が高いから。 きっとそれもある。 けれど、それよりも恐らく、みんながわたしのことをちゃんと見てくれていたからなんだと、心から思えた。
見ていないけれど誰がどこにいるか分かる。 頭が混乱しているけれど、どこか冷静でいられた。 以前自主練習を一緒にしていた同輩と、「できたらかっこいいよね」くらいの気持ちで練習したことがあるものがある。 それを突然思い出した。 控えにしておくにはもったいないくらい能力のあるスパイカー。 練習で失敗したことはなかった。 今まで感じたことのないくらい自信があふれてきた。 小さく彼女の名前を呼べば、ぜんぶ分かってくれる。 あの日の練習を彼女も覚えていた。 それが、無性に、うれしくてたまらなかった。
彼女にあげることを察した相手チームが壁を作る。 わたしの指先にボールが触れるとほぼ同時にブロッカーたちがタメを作ったのが横目に見えた。 速攻が来ると読んだに違いない。 劣勢の場面なら手堅い攻撃で来ると思ったのだろうと思う。 水野さんがそうだから。 水野さんは手堅い攻撃でも点を取れるから。 それまでのゲーム展開をきっちり計算できているから。 水野さんならそれでもスパイカーの能力を最大限引き出せるトスがあげられるから! それが羨ましかった。 そうなりたかった。 でも、そうなれない。 わたしのプレイスタイルにはないものだから。 アタッカーに頼って、リベロに頼って、チームに頼って、いろんな人から力をもらって得点する。 それがわたしのバレーだから。 わたしがセッターをしていて最も誇りに思うことだから。
指先にボールが触れる。 勢いよく送り出したトスは、ネットの端から端へ素早く飛んだ。 ブロック二人が驚いた顔をしたのが視界の端に見えた。 もう遅い。 ボールと一緒に飛び出した彼女の手によって、相手コートにボールが落ちた。
「なにそれ!? ブロード?! いつの間に練習してたの?!」
ハイタッチをしながら伊藤さんがはしゃいでそう聞いてくる。 「合わせてたことあったっけ? 急にやったの?!」と嬉々とした表情で別の同輩がわたしと彼女の顔を交互に見る。 なんとなく照れくさくて笑って誤魔化そうとしたのだけど、ブロードを打った同輩がけろっとした顔で「一年のときにちょっとだけ」と答えた。 そんなの知らなかった、と伊藤さんや他のメンバーは少しだけ悔しそうな顔をする。 自慢げに「わたしとの得意技なんで」と言った横顔にわたしまで得意げな顔になってしまった。
top / これからも囁いて