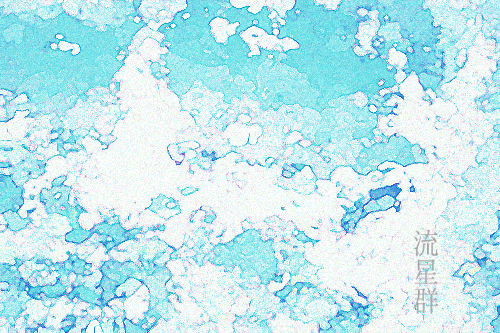
そう約束されていたように、頭上にレシーブがあがる。 それに向かって伸ばす腕が、手が、指が、ぎしぎしと軋むような感覚。 わたしはいつからこんなふうになったのだろうか。 誰がどこにいて、どんな状況で、どんな戦況で、どんなコンディションか。 それらがオールクリアだったとしてもこのトス一つで簡単にひっくり返る。 重たい。 ボールが、空気が、体が。 水野さんなら、どこにあげるんだろうか。
着実に点差を広げられていく。 守備が堅く堅実なトスをあげ続ける塚本さんを中心に、基本に忠実なバレーを繰り広げられている。 こちらのチームは迷いのあるトスをあげ続け、ころころと作戦を変え、攻撃にも守備にも徹することができないままだ。 呼吸が荒い。 上を向いているのがつらい。 チームメイトの背中を見るのも、顔を見るのも、なんだか怖くて。 誰からどう見たって一目瞭然だ。 この圧倒的劣勢を作り出しているのは、セッターであるわたしだ。 わたしがセッターでなければこんなことにはなっていないはず。
「! 大丈夫大丈夫、こっから巻き返そう!」
伊藤さんの声。 優しい人だからわたしのせいにしない。 それが耳に痛くてたまらない。 いっそ責めてくれればいいのに。 あんたのせいで負けそうなんだけど、って。 言ってくれれば諦められるのに、優しくしてくれるから甘えてしまう。 こんなのセッターとして出来損ないにもほどがあるのに、情けないと分かっていても、わたしはやめられないのだ。
ぐるぐると塚本さんが仕掛けてくる攻撃パターンを頭の中で考える。 それをどう対処すればいいかを考えて、頭の中で数えきれないトスをあげた。 でも、どの一つも、憧れには程遠い。 こんなもの、中学のときは感じたことがなかった。 わたしはいつからこんなにも臆病になってしまったのか、笑ってしまうほど分からなかった。
わたしがあげた速くもなく高くもない曖昧なトスを伊藤さんが打つ。 もっとちゃんとしたトスをあげれば絶対に決められる選手なのに、わたしのトスがその威力を殺している。 一年生レギュラーに簡単にレシーブされて、塚本さんの元へボールが美しい放物線を描いて飛んでいく。 それを一片の迷いもないトスが直線を描くように鋭く放たれ、こちらのコートにボールが落ちる音が響いた。
水野さんなら。 水野さんなら、どうしただろう。 今のは伊藤さんにあげずに体勢を立て直すべきだっただろうか。 伊藤さんばかりにトスをあげているから少し休ませたほうがいいだろうか。 けれど、他の選手は少し表情が暗い。 少しの戸惑いも見える。 わたしのトスに不安を覚えている。
わたしがただ焦っているだけの間に一セットを先取される。 小さなため息がどこからか聞こえた。 たったそれだけで、一瞬にしてここが去年の、あのコートかのように錯覚する。 相手チームの応援団たちの歓声。 相手選手たちの喜びの声。 それらを目の前に見ながら、自分のチームの応援団たちのため息を聞いた。 引退する先輩たちの泣き声。 そして、空間を切り裂いたのかと思うほど鮮明に聞こえた。 「やっぱり水野じゃなきゃだめかあ」。 今でも、あの声が忘れられない。
第二セットも最悪な幕開けでスタートした。 相手チームのサービスエースで先制されただけではなく、こちらのコンビミスが続き三点を失う。 まだ点を入れられていない。 なんとかしなくちゃいけない。 こんなとき、水野さんなら。 そう考えている間にもゲームは進んでいき、気付けばこちらは相手のミスで取れた一点だけ。 九点も差が開いていた。
だめ、かあ。 そう俯いたその瞬間だった。
「タイム」
突然響いた声は低いものだった。 驚いて思わず顔をあげる。 誰の声か一瞬分からなかった。 わたしの前で伊藤さんも同じような顔をしてコート外を見つめている。 そちらに視線を持っていくと、赤葦くんがじっとこちらのコートを見ていた。
赤葦くんの隣で男子部の木葉さんが「いやお前監督じゃねーから!」と笑いつつも引かせようとしている。 それでも赤葦くんはもう一度審判をしている女子部の人に向かって「タイムを」と言った。
「うちの監督って赤葦くんだっけ?」
「まーそれでいいんじゃない?」
「集合〜! あとついでに休憩〜!」
けらけら笑いつつ赤葦くんの元へ伊藤さんたちが集まっていく。 塚本さんのチームはどうやら男子部の木兎先輩が監督ポジションをやりたいと言ったらしく、そこにみんな集まっていた。 和やかな空気だ。 こんな中でもわたしだけが置いてけぼり。 そんな気がしてならない。 思い描くようなトスをあげたい。 それだけなのに儘ならない。
恐る恐るチームの輪に入る。 一歩だけ後ろにさがって。 もういつものことだから癖になってしまっているようだった。 俯いたまま水分補給しながら談笑をはじめるチームメイトの声を聞く。 再開したらどうしようか。 サーブが強力なレギュラーの先輩からはじまる。 強いサーブはいつもレフト寄りに打ってくる。 ファーストタッチがオールラウンダーの同輩になるはずだ。 きっとAパスをあげてくれる。 ……ああ、頭の中でもチームメイトに頼りきりになってきた。 だめなセッターだなあ、わたしは。 水野さんと違って。
「」
「あ、は、はい」
「は何が原因で不利になってると思う?」
赤葦くんの静かな声に談笑していたチームメイトが押し黙る。 そんな空気につられてか、相手チームも静かになった。 体育館には外から聞こえる少しの風の音、誰かが咳払いをした声。 それくらいしか聞こえなくなった。
「……わ、わたしが……下手、だから」
「違う」
「え」
「が下手だったら正セッター争いなんてしてないよ」
隣にいた伊藤さんが小声で「分かってんじゃん、赤葦くん」と笑ったのが聞こえた。 その意味が分からなくて言葉を失う。 だって、わたしが下手だから思うようなトスがあげられないのだし、コンビミスをしたり作戦を読まれたりするのに。 わたしさえ、水野さんのように上手ければ問題はないのに。 それ以外に何の原因があるのだろう。
「前にも言ったけど、俺はのあげるトスが好きだったよ」
「あんなかっこ悪いトスの、何がいいのかわたしには分からないよ……」
「チームメイトに頼るのってそんなに悪いことかな」
よく分からない。 また視線が下を向く。 自分のシューズが見えたところで、赤葦くんが小さく息を吐いた。
「俺は試合中しんどくなったら遠慮せずエースに頼るし、なんならいつもチームメイトに頼りっぱなしだけど」
「な、なんだよ赤葦照れんじゃん……!」
「赤葦が優しくなってる……!」
「ちょっと黙っててください」
試合中、しんどくなったら俯いてしまう。 チームメイトの顔を見るのが怖くて、頭の中で鮮明にイメージできるまで黙っていたくて。 こういう場面、水野さんはどうしてたかな、って思い出したくて。 頼ったら自分が出来損ないのセッターだと認めるみたいで、怖くて。
「チームメイトを頼るのは、チームメイトを信じてるからだと俺は思うけど、違う?」
「……でも」
「水野先輩はそうじゃないって言うんだろ」
「……うん」
「ずっと思ってたけど、なんで水野先輩みたいにならなきゃいけないの?」
「ここで聞く……?」
「聞くよ。 ずっと言えなくてモヤモヤしてたから」
今まで赤葦くんに相談していたときのすべて、赤葦くんはバレーに関するアドバイスはたくさんくれた。 けれど、たぶんただの一度もわたしの考え方や憧れに、口を挟んだことはない。 水野さんが憧れだと言えば、不思議そうな顔はしたけど何も言わなかったし、こういうトスがあげたいと言えばアドバイスをくれた。 そこに疑問を持たれていたのは少し驚いた。
「あ、憧れ、だから……」
「憧れて、プレイスタイルを真似し続けたらは水野先輩になれるの?」
「え」
「なれてるの?」
どき、とした。 核心をつかれたような、そんな感じ。 無意識に一番言われたくないことだったんだと思う。 たぶんどこかで気が付いていた。 わたしは、いくら努力をしたって、水野さんにはなれない。 むしろ水野さんを真似しようとすることでプレイが乱れているのだと分かっていた。 でもやめられなかった。 憧れだから。 あんなトスをあげたいと思ってしまった。 あんな試合運びをしたいと思ってしまった。 それがだめだったと言われてしまうのだろうか。
「なれないよ、水野先輩には」
まるで死刑宣告だった。 わたしにとっては十分すぎるほどに。
top / 飛沫に眩む