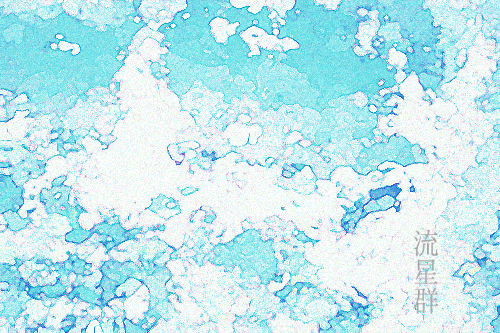
金曜日の記憶がほとんどないまま、土曜日を迎えた。 体育館に向かう足が重い。 朝起きてリビングへ行ったら母親に「あんたどうしたのその顔」と呆れられた。 ほとんど一睡もできなかった。 頭の中で何度も何度もトスをあげたけれど、たったの一球も思い通りのトスはあげられなかった。 想像ですらできないんだ、現実でもできるわけがない。 誰にチームメイトになってもらおうか。 それも答えがほとんど出なかった。 負けると思うけど、わたしのチームに入って一緒に道連れになってください。 なんて言えるわけがない。 先輩やレギュラーの人たちに恥をかかせるわけにはいかないので、同じ立場の同輩と後輩に頼むしかないだろうか。 でもそれだと選んだ人たちの気を悪くするかもしれない。 ぐるぐる頭の中をかき混ぜながら歩いていると、知らない間に体育館についてしまった。
今日は陸上部が梟谷学園を会場にして記録会をするとかで、グラウンド横の体育館は参加者の休憩スペースとして使われている。 そのことからいつもどおり女子バレー部はいつも男子部が使用している体育館を共用することになっている。 ただ、女子部は練習試合を控えていることもあり、男子部監督の厚意で午後は女子部がコートを全面使用させてもらうことになったそうだ。 そのため男子部は午前練で終了になったという。
それを聞いたとき、全面コートを使えるときに試合に向けた最終調整をするだろうと思った。 だから部内試合は午前にやると思ったのに。 体育館に入って集合したときに聞かされた今日のスケジュールは、午前は通常練習をし、午後一番に部内試合というスケジュールだった。 体育館のど真ん中、センターコートを使って部員全員が見る中での試合にする、と。 また知恵熱が出るんじゃないかと思うくらい、ぐるぐるする頭の回転が加速した。
整列した一番前にいる水野さんの背中を見る。 その手にはギプス。 軽いストレッチに参加するだけでほとんど見学に回るとのことだった。 あのギプスをつけているのがわたしなら、何の問題もなかったのに。 ぎゅっと握った拳は冷たくてなんとも頼りなかった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
やっぱり散々な練習内容になってしまった。 午前練習をやっとの思いで乗り越えたところで、待ち構えているのは部内試合という名の公開処刑場。 控えセッターすら降ろされるかもしれない。 それでも構わない。 不満なんかない。 点が取れないセッターはコートにいる資格はない。 そう、わたしなんかでは、務まらないのだ。
母親が持たせてくれたお弁当を食べようにも、一向に食欲がわいてこない。 誰にチームメイトになってくださいとお願いしようか。 トスが乱れたらなんて謝ろうか。 こんなトスをあげたら、あんなトスをあげたら、こういう攻撃をしたら。 頭の中でぐるぐるコートが回るような感覚。 自分はどこにいればいいのだろう。 どこに誰がいて、誰がどこにいて。 だめだ、目が回る。 水野さんならこんなことないだろうに。 一人で凛とコートに立って、誰もが納得するトスをあげて、誰もが驚く試合運びをして。 わたしなんかでは真似できないプレイをたくさんする。
体育館の中で残っている男子部の人たちと先輩たちが談笑しているのが聞こえてきた。 そうっと見てみると赤葦くんもその輪にいる。 見なかったことにしようと視線を逸らしたのだけど、その瞬間に木兎先輩の大きな声が背中にぶつかるくらいの衝撃があった。
「俺らも部内試合見てってもいい?」
危うくお弁当を地面に落とすところだった。 伊藤さんはそれに「いいと思う」と答えてすぐに監督に「男子部の馬鹿どもが見学したいらしいんですけどー!」と大声で聞いていた。 男子部監督と談笑していた監督とコーチも「いいぞー」と軽く答えるから、再びお弁当箱をぎゅっと握り直す。 良くない。 ぜんぜん、良くない。 部員全員に見られるだけで良くないのに、水野さんに見られるのだけで良くないのに。 そのうえ男子部の人まで見るとか、赤葦くんまで見るとか。 ぜんぜん良くない。 公開処刑場に観客が増えただけだ。
正セッター争いのための部内試合。 そうは言っても監督はそこまで重要視しているわけではなさそうだった。 塚本さんが正セッターでわたしが控えセッター。 ほとんどそれが決まっている状態で、部員それぞれの実力を再確認するための試合。 それくらいの認識らしく、割と和やかな雰囲気にはなりそうである。 でも、そうだとしても、わたしにとってはぜんぜん和やかじゃない。 逃げ出したい。 情けない姿を見られるくらいだったらここから飛び出してそのまま部屋にこもってしまいたい。 いかにわたしがだめなセッターかを見られるだけなのだから。
どんどん背中が縮こまっていく感覚がする。 このまま砂粒になってしまえばいいのに。 そんなことを考えているとき、「!」と伊藤さんの声が突然飛んできた。 驚きつつ返事をして振り返る。 伊藤さんが手招きをしているのが見えてしまった。 レギュラー陣と男子部の人がいる輪に入るのは正直勘弁してほしい。 けど、呼ばれているのだから行かないわけにはいかない。 もう逃げるタイミングを失ったのだとそこで悟った。 恐る恐るその輪に入ると伊藤さんに「誰をチームメイトにするか決まった?」と笑顔で聞かれる。 塚本さんはもう決まっているようだ。 それを聞いてからでいい、と思ったのだけど水野さんが「一人ずつ言ってったら? 被るとあれだし」と提案する。 それに塚本さんが頷いてしまったので、わたしも同意せざるを得なかった。 得点板の空いているところに一年生の子が名前を書いていってくれるらしい。 塚本さんがまずレギュラーの三年生の名前を挙げた。 そして、視線がわたしに向く。 誰でもいいよ。 わたしのトスを打ってもいいよって言ってくれる人なら。 誰でもいい、から、選べない、のに。 選ばないといけない場面でそんなことを言えるわけもない。 恐る恐る辺りを見渡して、目配せして様子を窺う。 その結果、比較的いつも穏やかで真面目に練習をしている同輩の名前を挙げた。 ウイングスパイカーの子なのだけど、自主練によく付き合ってもらっていたし速攻が合わせやすい。 レシーブの実力も折り紙付きで実力は申し分ない選手だ。 ただ、選手層の厚いうちの部では控えにも入れていない、わたしと同じ立場にいる。
すぐに名前を挙げる塚本さんと違ってしどろもどろ名前を挙げていくわたし。 この時点でかなり情けないのだけど、このあとにもっと情けない姿をさらすことになると思えば耐えられる。 塚本さんが最後の名前を挙げてわたしが最後の名前を挙げようとしたら、「ちょっと待ったー!」と伊藤さんが声をあげた。
「わたしいなくない?! なんでわたし入れないの?!」
「他のレギュラーは選ばれてるのにね」
「エース、どんまい」
「ひどくない?!」
けらけら笑いつつ若干涙目だ。 塚本さんは冷静に「うちは守備堅めにしたいから」と言い放つと伊藤さんは「守りもできますけど〜?!」と笑った。 それからすぐにわたしの顔を見ると、なんだか、子犬のような目で見てくる。 もちろん、伊藤さんが入ってくれるなら、すごく有難い。 わたしが選んだチームメイトたちはバランスが良いタイプの選手が多く、攻撃力は低めだ。 かといって塚本さんのチームほど守りが堅いわけでもない。 パワータイプのエース選手が入ってチームバランスが整う布陣になっているのだ。
でも、わたしのトスでは伊藤さんはエースになれない。 水野さんのトスと合わさって、伊藤さんはエースになる。 伊藤さんが一人ではエースになれないというわけではない。 でも、最高のトスがあってはじめてアタッカーは生きると、おこがましくも思うのだ。 セッターのエゴだとは分かっているけど思わずにはいられない。 水野さんのトスを見たときからずっとそう思っているのだ。 わたしのトスで女子部のエースを殺すわけにはいかない。 道連れにしちゃいけない人だ。 そう思って別の名前を挙げようとしたのに、伊藤さんが「は選んでくれるでしょ?」と得意げに笑うから、つい、伊藤さんの名前を言ってしまった。 それでも伊藤さんは満足げに笑って「絶対勝つよ」とわたしの背中を軽く叩いた。
top / 揺れ惑うこの手を握ってくれたのは