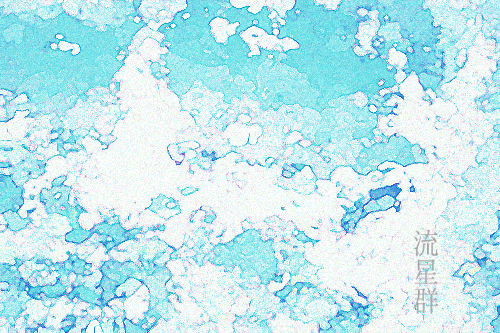
水曜日。 休憩中に顔を洗いに部室外にある水道へ向かう。 気が重い。 塚本さんとはうまく話せないし、先輩は塚本さん派だろうから近寄りにくいし、同輩にも気を遣わせるから関わりづらい。 後輩はもっと気まずいだろうから余計に。 気が重い。 試合形式練習で輪に入ろうとするだけでその場の空気が固まる。 塚本さんのときはそうでもないのに。 みんなわたしのチームに選ばれるのが嫌なのかもしれない。 そう思うと余計に気が重くなった。
水道にはあの角を曲がれば、というときだった。 誰かがいる。 思わず足を止めて息を潜めてしまう。 立ち去ればいいのだけど、話し声が聞こえてきたから立ち止まったままになってしまった。
「水野、本当、つらいだろうね」
「そりゃあそうでしょ……自分の代わりがあんな感じなんだもん」
どきっとした。 立ち去らなきゃ。 いいことなんてない。 ないのに。
「、ぜんぜん分かってないもんね」
ちょきん、と指が切られたような感覚。 びりびりしているのに氷を触っているように感覚がない。 気が付いたら俯いて口が少しだけ開いた。 ゆっくりと呼吸をする。 ほらね、やっぱり。
顔を洗うことなく体育館に戻った。 誰とも言葉を交わさなかった。 話しかけたって、みんな、腫れ物に触るようにするから。 はっきり言ってくれたら諦めがつくかもしれないのに。 そう思ったら今までの自分が滑稽に思えてたまらなかった。
最悪だった。 今までの練習の中で一番最悪だった。 何をしてもだめだった。 もう言葉が出ないほど、だめだった。 練習終わり、いつもなら多少自主練に混ざっていくけど、すぐに部室へ向かった。 誰よりも早く着替えて誰よりも早く部室を出た。 誰の顔も見たくなかった。 誰にも顔を見られたくなかった。 指先がずっと冷たい。
憧れだった。 強くて、眩しくて、必要とされることが。 自分にないものを持っていることに憧れた。 言い難いほど強烈に憧れた。 憧れ、だった、けど。 憧れには届かない。 届かないほど高く遠いところにあるから憧れなのだ。 わたしがどれだけがんばってもそこにはたどり着けない。 それは永遠の憧れのまま、わたしは追いかけ続けるまま。 そうしてまた失敗を繰り返していくだけなのだ。
ああ、怖いなあ。 トスをあげることが怖い。 コートに立つことが怖い。 誰もが求める水野さんのトスをあげられない自分を見られるのが怖い。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
木曜日。 生まれてはじめて知恵熱なんてものが出た。 移動教室中、ふらついていたら赤葦くんが気付いて保健室へ連れて行ってくれた。 測ったらしっかり熱があって、授業を休むことになった。 高熱というわけではないけど大事をとって部活は休みなさいと言われた。 情けない。 どうしてこうもうまくいかないの。 何もかも。 苦しい。 バレーボールが好きなのに、苦しいよ。
いつの間にか授業が終わる時間になっていたらしい。 チャイムの音がかすかに聞こえた。 保健の先生が一言かけてからカーテンを開けた。 気分を聞かれたので「最悪です」と答えたら、なんだか愉快そうに「青春ね」なんて言われる。 青春なんて甘酸っぱい言葉で片付けられてしまった。 内心そう苦笑いをこぼす。 もう一度熱を測るように言われて体温計を受け取る。 高熱でも出てくれていればいいのに。 はあ、と一つため息が出てから体温計の電源を入れた。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「赤葦なんか元気ないな?」
「……いえ、いつも通りですけど」
唐突に木兎さんからそう言われて少し驚いてしまった。 それにつられてきた小見さんからも「なんかな~?」と笑われる。 いつも通りトスをあげているし、会話もしている。 それなのにどこからそんな感じが出ているのだろうか。 ひとまず「何もないです」と返しておく。 木兎さんは「え~?」と納得していない様子だったが、これ以上聞いてくれるなという視線を向ければ何も言わなかった。
「そういえば女子部の」と木葉さんが言った声にやけに反応してしまった気がする。
「二年のセッターの子いるじゃん」
「あー! な! 塚本と正セッター争いしてる!」
「そうそう。 今日練習休みなんだってさ」
「え?! 部内試合って土曜日だろ?」
「伊藤がぼやいてた。 大丈夫かなって」
苦笑い。 木葉さんの言葉に木兎さんは「え、マジか」と一気に興味をそちらに移したようだった。 それと同時にまた俺の顔を見た。
「どうしたの?」
「……休み時間に熱出して保健室行ったんですよ」
「マジか……不運すぎる……」
「正セッター争い目前でとか……」と猿杙さんが心から同情するような声をあげた。 試合が土曜日とはいえ、その前に体調を崩すのはスポーツ選手としては致命的といっても過言ではない。 いろいろ調整したいところもあるだろうし、今回に関してはチームメイトを決めなければいけないという課題まで抱えている。 それに、これは俺だから言えることかもしれないけど、〝あの〟だからこそ、ここで体調不良というのはあまり良くない展開だと思う。
「まあ、一日休んだほうが気も休まるだろ」
「それもそうだな。 あの子、すげーいっつも緊張してるからたまには休息も大事だな」
木兎さんがそう言う木葉さんに「そうなのか?」と不思議そうな顔をする。 試合や大会であれば緊張もするだろうが、いつもと言うからには練習も含まれているのだろう。 木葉さんはけろっとした顔をして「いっつもそわそわしてんじゃん。 練習中もさ」と言葉を付け足した。 木兎さんは相変わらず不思議そうな顔はしているが「へー」と返しただけで追及はしなかった。
木葉さんの言葉はそう間違ってはいない。 ただし「緊張している」というより、怯えている、と言ったほうがたぶん正しい。 そわそわしているのは緊張からではない。 誰にトスをあげればいいのか、どんなトスをあげればいいのか、次はどう動くか。 それを考えるとき、はボールではないものを見る。 隣のコートにいる、水野先輩。 俺がそれに気付いたのは結構早かったと思う。
が水野先輩に抱いている憧れは、呪いだと思った。 水野先輩なら誰にトスをあげるか。 水野先輩ならどんなトスをあげるか。 水野先輩なら次はどう動くか。 その思考にの意志はない。 ただただ、〝水野先輩なら〟。 それだけをは求めていた。 はじめはよっぽど水野先輩が憧れなのだろう、と少し微笑ましくさえ思ったけれど、次第にその微笑ましさは消えた。 呪い。 そんな言葉がしっくりくる。
中学二年のとき、俺が通っていた中学の女バレとのチームが大会で対戦したのを覚えている。 男子部の応援を女子部がしてくれたこともあって、その試合を見ていくことになったのだ。 はバレー選手にしては背が低かったし、突出して何が上手いとか何が武器だとかそういうのは、正直に言えばなかった。 特にその試合では調子がすこぶる悪かったようで活躍という活躍はなかった。 のチームはセッター不足だったらしく、選手交代されることはなかった。 その試合を眺めながら「なんでセッター代えないんだろ」と思ったのを覚えている。 そんなふうに眺めていたとき、肩で息をして俯いていたにチームメイトが声をかけたのだ。 笑って。 距離があったからなんと声をかけたのかまでは分からない。 けれど、同じセッターというポジションだからこそ、分かる。 その声かけのあと、のトスは徐々に安定し、攻撃の息もなんとか合い、なんとか点に繋がっていった。 試合には負けてしまっていたけれどの顔は晴れ晴れとしていた。 チームメイトの人たちもそうだった。
セッターがいないからといって甘やかしているわけではなかった。 純粋にをセッターとして欲して、求めて、頼っている。 トスを求められている。 たったそれだけのことが、セッターにとっては何よりも誇りなのだと、俺はそのときに胸に刻んだのだ。
そんなを知っているからこそ、呪いが絡みついて重たいトスをあげ続ける今の姿は、俺にとっても同じくらい呪いになっている。 水野先輩はすごい人だ。 それは分かる。 けれど、だからって、どうしてはすごくないとなるのだろうか。 苦しそう。 もがいている。 トスをあげるたび笑顔がこぼれるように明るい色をしていたあのときと違う。 海の底から海面に向かって、あがりっこないトスをあげようとしている。 重たい腕、重たい指、重たい呼吸。 の体は呪いで雁字搦めになっているのだ。 それがもどかしい。 もどかしいけれど、うまく伝えられない。 が抱えるトラウマを目の当たりにしてしまっているから。
「って去年の春高予選ちょっとだけ出てたじゃん。 あれがトラウマなのかもな」
top / 偶然だと笑ってよ