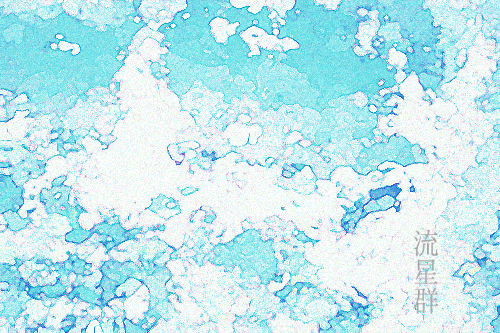
月曜日。 体育館に入るとすぐにいつもと空気がちがうことが分かった。 ざわざわとしていて、三年生の先輩は数人泣いている。 何か良くないことがあったことは明らかだった。 とても話しかけられる雰囲気ではなかったので、近くにいた一年生にこっそり話しかける。 一年生もこっそり耳打ちするように状況を教えてくれた。
日曜日の合同練習が終わったあとのことだったらしい。 いつもどおり伊藤さんと水野さんは一緒に電車に乗って帰っていたそうだ。 つり革を握って二人並んで立っていたそうなのだけど、電車が大きく揺れた際に伊藤さんが水野さんに少し寄り掛かったのだという。 伊藤さんが体を戻しつつ謝ろうと顔をあげたら、水野さんが苦しそうな表情をして右手を押さえてしゃがみ込んだ。 目的の駅ではなかった次の駅で二人で降り、水野さんの家族と監督に電話をしたそうだ。 水野さんの家族が駅に到着するまで、水野さんは右手を押さえてずっと苦しそうにしていた。 日曜日に開いていた緊急病院に行き検査を受けたところ、疲労骨折であることと中度の腱鞘炎であることが判明した。 監督が水野さんを問い詰めたところ、ずっと痛いのを隠していたと話したのだという。
「水野さん、もしかしたらもう今年中は試合に出られないかも、って」
一年生の子はそこで言葉を切って「すみません、準備してきます」とどこか元気のない声で呟いて体育館の外へ出て行った。 今年中は、試合に、出られないかも? ガツン、と頭をハンマーで殴られたような感覚があった。 水野さんが試合に出られないかもしれない? なんで? どうして? 何一つ理解できない。 集まっている三年生の輪に水野さんはいない。 泣いているのは伊藤さんだった。 誰よりも責任感が強く、誰よりも部員思いで、誰よりもバレーボールが好き。 伊藤さんはそういう人だ。 だから主将を満場一致で任せられている。 伊藤さんは、水野さんがこうなったのは自分のせいだと、自分を責めていた。 あのとき水野さんに寄り掛からなかったら。 たとえ痛みを抱えていたとしても、こんなことにはならなかったかもしれない。 そう泣いている伊藤さんを三年生の先輩たちみんなが励ましていた。
どんよりした空気に包まれた体育館に監督とコーチが入って来た。 すぐに部員全員が整列すると、監督からはじめに水野さんの話があがる。 水野さんは三日間は自宅療養したのち学校には登校してくるのだという。 部活も本人が参加を希望したため、手首を使わない練習と見学だけの参加は許可したと言った。 症状は軽くはないが一生バレーができないような絶望的なものではまったくなく、安静にしていれば問題ないと明るい声で言う。
話は続き、今週末に控えた練習試合を含めたレギュラーメンバーの話になる。 正セッターには塚本さんが入ると話があり、控えセッターは誰になるのか。
「控えはでいくからそのつもりで」
どき、と心臓が跳ねる。 よく分からないまま「はい」と返事をした声は、たぶん震えていた。
自分でも知らないうちに思い出していた。 去年の試合。 控えセッターだった三年生の先輩の代わりに入ったわたしが、チームを負かした張本人になった、あの試合。 水野さんの代わりに出たのに水野さんの代わりになんかなれっこないと分かってしまった、あの試合。 指先が冷たい。 指をこすり合わせてもあたたかくならない。 冷たいままだ。
きっと誰もが思っただろう。 「なんで?」と。 一年生は知らないと思うけど、上級生は知っている。 あの試合でわたしが何もできなかったことを。 その以前もそれからも、チームに何一つ貢献できていないことを。 みんなが知っている。 そんなわたしが入るくらいなら、一年生のセッターの子が入ったほうがみんな納得するんじゃないだろうか。
何度も何度も指をこすり合わせているうちに監督の話は終わった。 すぐにレギュラーメンバーとベンチメンバーが呼ばれて集まる。 他の部員は練習の準備をはじめる。 わたしはいつも準備をする側だった。 でも、行かなくちゃいけない。 わたしなんかがあの輪に入らなくちゃいけないのだ。 気が重くてたまらない。 心臓が冷えていく感覚が怖い。 一歩だけ輪から身を引いた状態で、その中に加わった。
「」
「は、はい」
「任せたよ」
伊藤さんがわたしの背中を叩く。 それにうまく答えられないまま、頷くだけになってしまった。 伊藤さんはそれを咎めることはなかったけれど、少し拍子抜けしたような顔をしていた。
練習試合に関する簡単なミーティングがはじまる。 今週末に試合をする学校は毎年各大会で優勝争いをしている強豪校だ。 練習試合をするのは久しぶりのことで、毎年大会でしか顔を合わせない。 監督は今後の大会でも恐らく当たることを前提として、良い勝負をし相手の弱点などを研究するための試合としたいと言った。 突然正セッターを失ったチームが落ち込んでいることは重々承知していると言った上で、「それでも勝ちを諦めるつもりはない」と主将である伊藤さんの顔をまっすぐに見て言う。 正セッターとなった塚本さんに負担が向くことが懸念とし、今度はわたしの顔を見た。 「水野のときのようにぶっ通しで塚本でいくことはしない。 も試合に出す」とはっきり言った。
その言葉に塚本さんが手を挙げた。 塚本さんという人は口数が少なく落ち着いた性格をしていて、こういう場面で自分から手を挙げることは滅多にない。 三年の先輩も驚いている中、塚本さんは静かに口を開く。
「わたしが正セッターでいいんですか」
その言葉に一番驚いたのは、たぶんわたしだったと思う。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「顔、死んでる」
火曜日。 朝練を終えて教室に入ってまず赤葦くんにそう言われた。 女子部の事情はそれなりに耳に入っているらしく、少し気まずそうな顔をして「水野先輩、木曜日から来られるんだっけ?」と聞いてくる。 それに頷くだけで返事をすると「そっか」と小さく笑みをこぼした。
練習中、控えですらない部員たちでやる試合形式練習で、いつも横目に水野さんのトスを見ていた。 それを真似して、作戦を真似して、いつも失敗ばかりだった。 そんなわたしが水野さんという目標を失ったらどうなってしまうのだろう。 ついに誰もトスを打ってくれなくなるのではないか。 そんな不安がぐるぐると渦巻いて仕方ない。
そんな中、塚本さんのあの発言があってわたしの気持ちは正直大荒れだった。 塚本さんはどういうつもりでそう言ったのだろう。 だって控えセッターで入っているのは塚本さんなのだからそのまま正セッターになるのは当然のことだ。 こんなことを言うのは気が引けるけど、水野さんに敵わないとしても実力のある選手であることに間違いはない。 高校でセッターに転向して、何度か試合にも出て勝利を収めている。 それだけで理由は十分なはず。 たとえ、一年前の試合で控えセッターに入ったのが、わたしだったとしても。 チームを負かしたセッターなんてコートには要らないのだ。 だから、わたしという選択肢はそもそもないのに。
「土曜日に部内試合するんだって?」
「……なんで知ってるの?」
「木兎さんがうるさかったから」
塚本さんの意見になぜか耳を傾けた監督が出した答えは「部内試合」だった。 正セッターを決めるための試合。 チームバランスが偏らないようにセッターが自分のチームメイトを一人一人選んでいくというオプション付きの試合だ。 チームメイトは当日に決め、ぶっつけ本番での試合になる。
塚本さんの言い分はこうだった。 〝こんな形で正セッターになっても不満がある部員がいるかもしれない。 のことを推薦している部員がいるのも知っている。 たまたま控えセッターにいたのが自分だからと正セッターにそのまま繰り上がるのは、自分としても納得がいかない。〟 そう迷いなく強い声で言ったのだ。 いつも静かな塚本さんがそんなふうに思っていたなんてもちろん知らなくて、先輩たちはもちろん監督たちも驚いていた。 わたしが引っかかったのは、わたしを推薦している部員、という部分だった。 そんな人、本当にいるのかな。 そんなふうに思いつつも口を挟めるわけがない。 塚本さんの真剣な思いを汲み取り、コーチもレギュラー陣も部内試合に賛成したというわけだった。 最後に監督から「はそれでいいか」と確認されたけど、断れるわけがない。 「はい」とだけ答えた声はどんな声色だったか覚えていない。
「ってさ」
「なに?」
「バレー好き?」
「……え」
「なんか、最近のを見てるとそのあたりが不安になる」
不安になる、って、なんで赤葦くんが? そんな疑問を抱きつつも考えてしまう。 心からバレーを楽しいと思ったのはいつが最後だろう。 中学生のとき。 セッターをやる子がいなかったからとはいえ、正セッターとして試合に出られるのはうれしかった。 わたしのトスで得点が決まるとその瞬間だけ無敵になれた気分だった。 仲間とハイタッチをして喜んで、ときには涙が枯れるほど悔しがって。 楽しかった。 中学三年間はセッターをやっていることはわたしにとって何よりも誇りだった。 そう、誇り、だったんだ。
水野さんに出会って、水野さんに憧れて、水野さんを追いかけ始めたら、今までの自分のトスがどれもこれも間違いだったと思った。 アタッカーに頼りきりのトス。 Aパスに頼りきりの動き。 わたしがセッターとしてコートにいるためには、周りの選手の協力が必要だった。 水野さんはたった一人だったとしてもコートにいるべきセッターだった。 そうなりたかった。 だから、今までの自分が間違いだったと思い知った。 水野さんの背中を追って、追って、追って、何度も失敗した。 挙句の果てにはチームを負かした。 じゃあわたしがやってきたことの中で、一つでも間違いじゃなかったことがある?
「俺はバレーを楽しそうにしてたのトスが好きだったよ」
「……過去形は、ちょっと、カチンとくる」
「でも本当にそうだよ」
「いつのわたしのことを言ってるの」
「正確に答えるなら中学二年の夏かな」
覚えてる? あの試合。 赤葦くんはそう言うと、わたしが返す前に話し始める。 中学二年の夏季大会。 二回戦の試合を、赤葦くんは見ていたと言った。 そんな話を聞いたのははじめてだったし、そう言われて対戦校が赤葦くんが通っていた中学だったことを思い出した。
あの試合はとにかくわたしの調子が悪くて、トスは乱れるわ攻撃パターンはめちゃくちゃだわ速攻は合わないわ、で悲惨だった。 それでも代わって出られるセッターがいなくてわたしは試合に出続けていた。 俯いて、ああしんどいな、って思ったときに顔をあげたときだった。 チームメイトがいた。 劣勢なのに笑っていて、「は仕方ないんだから」と言ってわたしの肩を叩いた。 「わたしたちはにしか頼れないけど、はわたしたちみんなに頼ればいいじゃん」と言ってくれた。 下手くそなわたしのトスを不格好にでも打ってくれた。 疲れて動けないわたしのためにAパスを上げ続けてくれた。 それに、わたしは頼りきりだった。
「……嫌味?」
「俺がそんなこと言うと思う?」
「……思わない、けど」
「じゃあ信じてよ」
笑われた。 あの試合、結果はぼろ負けだった。 わたしに能力がなかったから。 水野さんみたいなトスがあげられていたら。 やっぱりそう考えてしまうのだ。
「暗い顔してる」
「……赤葦くんには分からないよ」
「そうかな」
分からないよ。 赤葦くんにも、水野さんにも、塚本さんにも、誰にも。 こんな惨めな気持ちはわたしにしか分からない。 今までの自分が間違いだった。 今までのトスはわたし一人では打てないトスばかりだった。 一人では戦えない。 一人では、コートに立てない。 わたしなんかでは。
「憂鬱だなあ」
top / 奇跡なんか訪れないのに