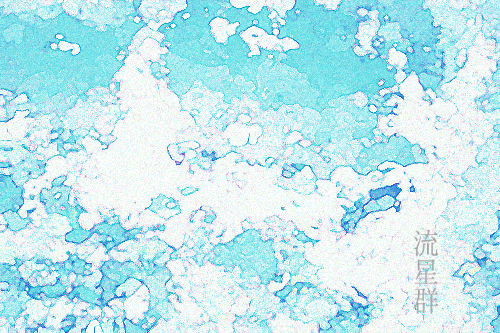
「いや〜悪いね〜、主将二人負かせちゃって〜?」
「ぐあー! 次は勝つからなー!」
試合は一方的な展開となった。 Cチームはチームバランスが非常に良いだけではなく、セッターを務める男子部控えセッターがチームをまとめる能力に長けていた。 木兎先輩曰く「どっちかっていうと守備型」というだけあって手堅い攻撃パターンが多かった。 対するわたしは。
「すみません」
「なんで謝る! でもまあ、はちょっとトスに迷いがあるからもっと自信持ってこっか」
主将の伊藤さんは、本当に優しい人なのだ。 負けたのがどう考えてもわたしのせいだったとしても、そう言わない。 その優しさに救われるところもあるけど、逆に胸の奥がぎゅうっと痛くなる。
Bチームの連携はあまり良くなかったと思う。 伊藤さんと木兎先輩の持つ攻撃力を活かしきれていなかった。 何より、どういうふうに試合を運ぶかをほとんど決めきれないままだった。 わたしが迷って、わたしが決めかねて、わたし一人が立ち止まっている間に試合は終わっていた。 当然、負けという結果を残して。
あの場面に木兎先輩にトスをあげていればよかったのだろうか。 いや、それとも伊藤さん、それとも男子部の先輩、それとも女子部の後輩? パターンが頭の中に浮かんではどれも輪郭をなくすようにぼやける。 わたしがそれを決めて、点を取れなかったら。 ああ、わたしが憧れている、正セッターの水野さんだったら、誰にあげたんだろう。 きっと伊藤さんにあげるんだろうなあ。 ……そんな気持ちであげた伊藤さんへのトスはわずかなズレを生じてしまい、いとも容易くレシーブされた。 これが水野さんだったら。 そう思うとゆっくり扉が閉まるように心が暗くなるのだ。
中学二年生のとき、新人大会の二回戦であたった学校にいた水野さんに、わたしはひどく憧れた。 迷いのないトス、迷いのない眼差し。 考える間もなく弾き出される結論に基づいたトスは、どれもこれも芸術を感じさせるほどに伸びやかでまっすぐだった。 無駄がひとつもない。 どれも洗練されていて、どれにもちゃんと理由があって。 憧れだった。 強く、強く、憧れた。
わたしが通っていた中学のバレー部ではセッターというポジションはあまり人気がなく、セッターをやっていたからという理由でわたしが正セッターをしていた。 小学生のときにセッターになったのだって、アタッカーをやるには身長とパワーがなかったしリベロをやるほどレシーブがうんと上手いわけじゃなかったから。 そんなわたしにとって水野さんは、セッターになるべくしてなったセッターだった。 憧れた。 羨ましかった。 わたしもそんなトスをあげたくて、水野さんのトスを近くで見ていたくて、水野さんのトスを真似したくて。
中学三年生のとき、高校生の大会を見に行って水野さんを探した。 絶対一年生で試合に出ているだろうから目立つ、そう思って。 思った通り水野さんは一年生にして正セッターとして試合に出場していた。 その日からわたしは志望校を梟谷学園一本に絞って毎日勉強した。 わたし立高校だから両親には渋い顔をされたけど、梟谷学園の名前はさすがに知っていたらしくそこまで強く反対はされなかった。 そうして無事、わたしは梟谷学園に入学した、というわけだ。
女子バレー部に入部してからは毎日ふわふわと浮かれていた。 同じチームに水野さんがいる。 それだけでなんだか自分まで強くなれた気がした。 わたしの代は部員が少なく、セッター志望がいなかった。 必然的に水野さんやセッターの先輩たちはわたしを気にかけてくれることが多くなったと思う。 憧れの水野さんに、直接指導してもらえる。 嬉しかった。 浮かれたわたしは憧れの人に近付けた気がしていた。
でも、それが本当に「気がした」だけだったと、すぐに気が付く。 何度か試合に出してもらったことがある。 けれど、どの試合でもわたしは、結果を残すことができなかった。 水野さんのようなトスをあげたいのに、水野さんのような試合運びをしたいのに。 どれもこれも、水野さんの劣化版でしかなかった。
「は水野に似てるよね、トス回しとか」
「そ、そんなことないです、恐れ多いですよ」
「そうかな? 結構似てるからか合わせやすいよ」
伊藤さんがけらけらと笑う。 似てる。 そう言われて少しだけ喜ぶ自分がいた。
「でもはっきり違うとこもちゃんとあるよね」
「え……」
「水野はなまじ自分が上手いから結構一人でどうにかしちゃうタイプなんだけど、は選手に寄り添ってるというか? 頼ってるなーって思うときがあるかな」
一気に心臓が冷えたような感覚。 そう、わたしは絶対に水野さんにはなれない。 自分の能力を信じ、自分のトスを信じ、自分の結論を疑わない。 そういうところがわたしには一つもない。 わたしと水野さんが明らかに違う要素を誰もが知っている。 それだけでもう、十分すぎるほど、わたしにとっては絶望だった。 自分の力を信じられないからアタッカーにあとを任せてしまう。 迷ったトスをあげてもきっと決めてくれる。 わたしが決めなくても、アタッカーが決めてくれればそれでいいのだ。 そう、思ってしまう自分がずっといた。 チームの司令塔であるセッターなのにわたしは自分のトスを信じ切れない。 これが正解だったのか。 水野さんのトスを見なきゃ、正解が分からないのだ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
「難しい顔してる」
「……わたし?」
「以外に誰がいるの?」
知らない間に隣にいた赤葦くんが苦笑いを浮かべる。 目の前では別チームを組み直した先輩たちによる混合試合がはじまっている。 それをぼうっと眺めていただけに、少し驚いてしまった。 赤葦くんは静かに腰を下ろすと膝に頬杖をついてじーっとわたしを見る。 「なに?」と苦笑いで返すと「別に」とだけ返してそっぽを向いてしまった。
赤葦くんとはじめてちゃんと話したのは入学式が終わったときだった。 同じクラスだった赤葦くんとは体育館からクラス別に退場していくときに隣同士だった。 背が高い子だな、と思っていたくらいで話しかける気はなかったのだけど、赤葦くんから声をかけてくれた。 教室に戻るまで二人で会話をしている中でお互いバレー部に入るつもりだということを知り、当然のように会話はずっと続いていった。 聞けば赤葦くんは一つ先輩である木兎先輩にトスをあげるために梟谷学園に来た、という。 それがほとんどわたしと同じ志望理由だったから勝手に親近感を持ってしまい、それなりに人見知りなはずなのにたくさん赤葦くんとしゃべってしまったっけ。
それからふつうに友達として仲良くなり、同じバレー部ということもあって相談し合ったりした。 同じセッターというポジションだったこともあって、わたしはよく赤葦くんに話を聞いてもらう立場だった。 水野さんに憧れていることも赤葦くん以外の人には言っていない。 恥ずかしくて本人はおろか先輩にも同輩にも言えなかったのに、赤葦くんにはすんなり言えたのは今でも不思議だ。 赤葦くんには「内緒にしてね」とお願いしたら、逆に赤葦くんからは木兎先輩を尊敬していることを内緒にしてほしいと頼まれたっけ。 そんなの、言葉にしなくても男子部の人たちにはバレてしまっているだろうに。 ちょっと笑ってしまったけど「分かった」と返事をしたのを覚えている。 そんなふうに試合の反省や改善点を二人で話しているうち、恋人という関係に発展していった。
赤葦くんに部活の相談をしなくなったのはいつからだっただろう。 考えなくてもはっきり分かる。 あれは、前年度の主将たちの引退試合のことだった。
去年、梟谷学園女子バレー部は春高予選を勝ち進んでいた。 その前は予選大会で優勝し、本選に出場していただけに優勝候補筆頭として各チームからかなり警戒されていた。 当時二年生の水野さんが正セッターをしており、控えには三年生のセッターがいた。 そんな中、試合前日に三年生のセッターが右手薬指を骨折。 監督は大慌てで選手登録変更の紙を書いていた。
三年生のセッターの代わりに控えセッターとして名前を書かれたのが、わたしだった。 三年生にはセッターがもう一人いたけれど、その人は高校生になってからセッターに転向した人だった。 現在控えセッターになっている塚本さんもミドルブロッカーからセッターに転向したばかりだったのだ。 そのため経験はわたしのほうが上だと監督が判断した結果だったのだと思う。 未だになぜあのとき自分が控えセッターになったのか、よく分かっていない。
試合で水野さんは徹底的に研究されていたためか、かなり劣勢を強いられていた。 相手チームの分析力と対応力が非常に高く、水野さんの弱点を熟知しているのがよく分かった。 エースに任せるタイミング、ツーアタックのタイミング、速攻のタイミング。 すべてきれいに読まれていたのを今でも覚えている。 今まですべての大会、正セッターとしてずっと出場し続けている疲れもあったかもしれない。 第一セットを取られ、第二セットがはじまってもやはり押されていた。 それを見た監督がわたしを呼んだ。
忘れもしない。 たぶん、あのときほど、周りの音が聞こえなくなったことはなかった。 心臓が自分の中にないと思うほどに静かだった。 選手交代の合図があって、水野さんが憔悴した表情でわたしに向かって歩いてくる。 水野さんの背番号が書かれたナンバーパドルを握る手が、震えていたのを、嫌というほど覚えている。 今でも夢に見るほど、鮮明に。 わたしの指に重ねるようにナンバーパドルを握った水野さんが小さな声で「ごめん、任せた」と言った瞬間、今まで消えていた心臓が激しく脈を打った。
試合はストレート負けで終わった。 ベスト16で梟谷学園女子バレー部は消えた。 ほとんど点が取れなかった。 連携ミスがいくつもあった。 すべて相手チームに読まれて、すべて止められて、すべて阻まれた。 痛いほど分かった。 選手の先輩たちがみんな、わたしのトスを不安がっていると。 そしてわたし自身も自分のトスを不安に思っていると、泣きそうなくらい痛感した。
ホイッスルが鳴り響いた瞬間、相手チームとその応援団の歓声の声が会場中に華やかに広がる。 荒い呼吸と冷えるような心臓。 応援席から聞こえるため息と、三年生たちの泣き声。 そうして、応援席のどこからか聞こえた声。 「やっぱり水野じゃなきゃだめかあ」。
涙も出なかった。 謝罪も、感謝も、何も。 水野さんならどうしただろう。 どんなトスをあげて、誰にあげて、どんな試合運びにしただろう。 それだけを、ただただ考え続けていた。
その試合をすでに本選への出場権を得たあとの男子部も見ていた。 もちろん、赤葦くんも。 赤葦くんが試合後にメールをくれたけれど返信しないまま、その日は一睡もできずに朝を迎えた。
その日以来、わたしが赤葦くんに相談することはなくなった。
「そんなに水野先輩ってすごい人かな」
「……え?」
「そりゃあ上手いしすごいとも思うけどさ、俺はのトスのほうが好きだったよ」
「……ははは、変な冗談言わないでよ」
「冗談じゃないけど」
ちょっと困った顔をした。 どういう意味だろう。 中学時代にベストセッター賞を獲ったことがある人よりわたしがすごいわけがないのに。 チームに甘えて、チームに頼るばかりのセッターなんて、全然すごくない。 震える指先も迷う指先も。 どれもこれも。 何一つとしてわたしには良いところなどない。
さらに苦笑いをこぼすわたしに赤葦くんが何かを言おうとした。 けれど、それは遠くから大声で「赤葦ー!」と叫んだ木兎先輩の声にかき消されてしまう。 赤葦くんは小さくため息をついて「はいはい」と返事してから立ち上がる。 「あとでメールする」とだけ言って、木兎先輩のほうへ歩いて行った。 木兎先輩の近くに到着すると、三年生の先輩に囲まれてなんだか呆れたような顔をしたけれどすぐに小さく笑って自主練習に参加する。 赤葦くんはすごいなあ。 内心ぽつりと呟く。 二年生にして女子部より強豪として有名な男子部の正セッターを務めるだけではなく、副主将を任されている。 セッターとしてももちろんすごい人で、わたしにとっては雲の上の選手だ。
仄暗い気持ちをかき消すように立ち上がる。 一つ息を吐いてから前を向き、いつも一緒に自主練習している同輩の輪に加わった。
top / 波よ凪がないで