※原作で職業などが分かる前に書いたものです。
高校卒業ぶりに再会した瀬見は、少しだけ痩せたように見えた。 ほんの少し伸びた髪。 きれいな指。 汗臭さなど微塵にも感じられない瀬見が大人っぽく見えた気がした。
瀬見の運転する車に乗るの、怖いな。 なんて思っていたのは内緒だ。 高校時代のちょっとおっちょこちょいだったり落ち着きがなかったりする印象がそう思わせていたのだけど。 実際に助手席に乗ってみると瀬見は驚くほど安全運転だった。 聞けば毎日車通勤をしているらしく、車はもう生活に欠かせないものなのだと笑った。 未だに一人で車に乗ることを避けている私が心配することなど、何一つなかったのだ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
瀬見から連絡が来たのは火曜日の夜だった。 その日は仕事が残っていたので先輩たちと残業をしていた。 パソコンをぼけっと見ながらコーヒーを飲んでいたとき、普段滅多に鳴らないスマホが鳴った。 どうせダイレクトメールか何かだろうと思っていたのだが、表示されていたのは「瀬見英太」の四文字。 しかもメールかと思ったのに着信だったのだ。 驚きつつ廊下に出て電話を取ると、「おー出た。 ひさしぶり」と少しだけ舌足らずな声が聞こえて。 恐らくアルコールを飲んだ後なのだとすぐに分かった。 後から聞いた話、天童と山形と偶然会って居酒屋に行ったときだったのだとか。 高校時代の話をしているうちに、「そういえばにだけ会ってないな」という話になり、私に電話をかけて会う約束を取り付ける流れになったのだという。
社会人になってからというもの、残業が多かったりたまに出張があったりしてなかなか人と会えなくなっていた。 大学は県外だったしこちらもめいっぱい授業を入れて生活していたので、白鳥沢バレー部OBでの飲み会などには一度も参加したことがない。 そのたびに幹事をしていた山形からは「またかよ〜」とがっくりされていたっけ。 いつかに「の予定に合わせるから」と言ってくれたこともあった。 でも、そのときはちょうどゼミが忙しかったことに加えて、バイト先の後輩が二人突然飛んでしまったことが重なっていて。 いつになるかも分からないから、と苦笑いをして断ったのだ。 社会人になってからは余計にそうだった。 毎回、大学時代と同じように山形から誘いの連絡をもらいのだけど、大抵残業の予定があったり出張の予定があったため、すべて断っている。 それでも毎回誘ってくれることがうれしくて、山形の家宛てに差し入れを送っている。 飲み会が終わると必ず全員で私の差し入れを囲んでいる写真を送ってくれるのが、余計にうれしかったり。
瀬見からの電話は「お前、最近大丈夫か?」からはじまり、「息抜きにドライブ連れてってやるよ」というところに落ち着いた。 最初は山形からの誘いを断るように「でも忙しくて」と断ろうと思ったのだけど。 言おうとしかけた私を遮るように「って高校のときから無茶するからさ、心配なんだよ」と困ったように笑われてしまって。 そんなことを言われたらなんだか断るのも悪い気がして。 ああ、なんだか、心配をかけていたんだな、とはじめて気付いて。 ここ最近ずっと休日出勤していたのだけど、その予定をなくして瀬見の誘いを受けることにしたのだ。 今度のバレー部の飲み会も有休を使うなりして参加しよう、と心に決めて。 それを瀬見に伝えると突然山形が電話を代わって「お前もっと早くそうしろよ」と笑われた。 「マジでみんな心配してんだからな?!」と怒られているのに、うれしくてたまらなかった。 そのあとに電話を代わった天童にも同じようにちょっとからかわれつつ怒られて「ごめんごめん」と笑いながら謝ったっけ。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
瀬見の車が家の前にやって来たとき、車の中にいたのが瀬見一人だけでちょっと驚いてしまった。 あの話の流れだと山形と天童もいるのかと勝手に思い込んでいたのだ。 「瀬見だけ?」と疑問をそのまま投げかけたら「え、瀬見だけですけど」と首を傾げられた。 思い込みを説明したら瀬見は笑いながら「あーなるほど」と頭をかいた。 相手が瀬見とはいえ、男の人と二人でドライブに行くのははじめてだ。 最初こそ若干緊張して車に乗り込んだのだが、次第に高校時代に戻ったような懐かしい感覚に包まれて。 まるで部活の休憩中のときのようになっていった。
瀬見は自分の話などは一切せず、ただただ私に質問を繰り返して私の話を引き出すような会話を続けている。 「職場どこ?」とか「何時に帰んの?」とか「え、休日出勤してんの?!」とか。 こんなにも自分の話をしたのは社会人になってからでははじめてだった。
「さあ」
「うん?」
「本当に大丈夫か?」
海沿いを走る瀬見の車は驚くほど静かだった。 瀬見の運転が上手いのか道路がきれいに整備されているからなのか、それとも両方なのか。 あまり車に乗らない私には分からなかったけど、瀬見が運転に気を遣っていることだけはよく分かった。
瀬見の問いかけに少しだけ狼狽えてしまう。 電話で言われたときはうれしかっただけなのに変な話だ。 実際目の前で言われるとなんと答えればいいのか分からない。 じっと黙って考えてしまうと、瀬見はけらけら笑って「いいって」と運転席側の窓をほんの少しだけ開けた。
「そういうのって誰かに言った方がさ、結構楽になるだろ」
信号で車が停止する。 ものすごく穏やかなブレーキングが、やっぱり気を遣ってくれているのだと分かってしまうほどだった。 瀬見が少しだけ開けた窓を下まで開けて「すげー海きれい」と指をさした。 運転席側の外を見て「本当だ」ととてつもなくぼんやりとした声が出た。 瀬見がナビを操作して「駐車場あるかな〜」と呟く声を聴きながら、ぼけっと瀬見の横顔と海を眺める。
高校時代、クラスの女の子が瀬見のことを「かっこいい」と言っていたことを思い出す。 そのときは「えーそうかな?」と首を傾げていたけど、ちゃんと見るとたしかにそうかも。 あのときは毎日顔を合わせていたし、かっこ悪いところもたくさん見ていたのでそんなふうに思わなかったのかもしれない。 モテるだろうなあ、と思ってくすっと笑うと瀬見が「え、なに?」と不思議そうな顔をした。 信号が青に変わるとゆっくり車が発進し、見つけたらしい駐車場に向かって走り始める。
「なんで笑ったの?」
「瀬見ってモテるだろうなあと思って」
「え、なんだよ突然」
「実際どうなの? モテるでしょ?」
「そうだったらいいのになあ」
苦笑い。 誤魔化されたような気がしてならない。 とくに恋愛話が好きということもないのでその話はそこでやめておく。 瀬見はナビをちらちら見つつ駐車場を探しているようだ。 まだ海開きはしていないけれど砂浜には子どもたちやおじさんなど、ぽつぽつと人がいる。 瀬見も砂浜を歩くことを思いついたらしい。 今日私、ワンピースにヒールで来ちゃったけど大丈夫かなあ。 若干不安に思いつつも、まあ歩くだけだし、と外を見渡して駐車場を一緒に探すことにした。
少しだけ走った先に駐車場を無事に見つける。 狭めの駐車場だったけど瀬見は難なく車を停めた。 シートベルトを外しながら「あ」と下を見ながら声を出す。 「、ヒールか」と苦笑いをこぼすので「ごめん」と私も苦笑いで返す。 瀬見は「いや、気付かなくてごめん」と言ったのち「やめとくか」とシートベルトをつけようとする。 「大丈夫大丈夫、歩くだけでしょ」とそれを止める。 瀬見は若干躊躇ったけど、「転ぶなよ」と笑ったのち車から降りた。
砂浜に続く石段を降りていく。 あまりきれいな石段じゃなかったのでバランスを両腕で取りながら瀬見の後ろをついていくと、途中で瀬見が振り返った。 すると、とても自然に私の右手を握って「危なっかしい」と小さく笑う。 その顔が優しくてなんだか照れてしまった。
「なんか」
「なに?」
「あれだな、、きれいになったな」
顔が少しだけ赤い。 照れるなら言わなくていいのに。 私まで照れつつ石段を降り終えてから瀬見の手が離れてから、瀬見の横腹を小突いておいた。
砂浜は思ったよりも歩きづらくて苦労した。 靴の中に砂が入って痛いし、転びかけるし。 そのたびに瀬見が笑いながら「やっぱやめとくか」と言うのだけど、久しぶりに見る海をもう少し堪能したくて「大丈夫」と強がりを言ってしまう。 そんなことをしているうち、ついに思いっきり砂に足を取られて転びかけてしまう。 それを瀬見が支えようと私の腹部に腕を回してくれたのだが、足場が悪くて瀬見を巻き込んで転んでしまった。 二人で砂浜に倒れ込んで服が砂まみれになってしまった。 瀬見はしばらく呆然としていたけど、体を起こすのと同時に大笑いしはじめた。 私に手を貸しながらも大笑いを続けていた。
「大丈夫じゃねーだろ」
大笑いしながらわしゃわしゃとまるで犬を撫でるみたいに私の頭を撫でる。
その言葉に、突然、本当に自分でも訳が分からないまま、ぼろぼろと涙が流れていく。 ぎょっとした顔をした瀬見は一瞬だけ手を止めた。 けれど、優しい顔に戻ると同時にまたわしゃわしゃと私の頭を撫でてくれた。
「ごめん」
「なにが?」
「瀬見も転んじゃった」
「いいって、そんなの」
瀬見の手が私の頭を撫でることをやめると、そのまま今度は私を抱き上げた。 べそべそ泣いている私の背中をぽんぽん叩きながら笑って石段の方へ戻っていく。
「、ちゃんと飯食ってる? というかちゃんと寝てんの? 顔色悪すぎて笑えねーからな、本当に」
石段にたどり着く。 瀬見は私を抱きかかえたまま石段を上っていくので、べそべそ泣いたまま「降ろしてよ」と呟く。 「なんで」と笑いながら訊かれたので「重いでしょ」とべそべそ答える。 瀬見はそれに「いや全然」と答えつつまた大笑いした。
石段を上がり切るとようやく地面に足が付いた。 堤防に座ってぼんやり海を眺めていると、少しずつ涙が引いていく。 瀬見は黙って隣に座って、私と同じようにぼんやり海を眺めていた。 びゅうびゅうとほんのり冷たく強い風が吹く。 それに髪が揺れるので手で押さえていると、瀬見が立ち上がって風よけになるように反対側に座り直した。 「あんま意味ねーか」と呟いて、顔を海から私に向ける。
「やっぱり瀬見、モテるでしょ」
「ただモテるだけじゃ意味ないんだよなあ」
その言葉で瀬見に好きな子がいることが分かった。 片思いをしているらしい。 それなら私とドライブをせずに好きな子を誘えばいいのに。 友達想いな、いいやつめ。 心の中でそう笑ってやる。 口にしたところで瀬見は私を小突いて「なんでだよ」と言うのが目に見えている。 瀬見はそういうやつなのだ。 いつだって自分より他人を優先する。 損なやつなのだ。
砂が入った靴を片方脱いで、ひっくり返す。 ぱらぱらと砂粒が風に舞って落ちていく。 手で靴の側面を何回か叩いて、砂粒が落ちなくなるまでそれを続ける。 落ちなくなったら靴を一度置いてから足を手で払う。 ワンピースを着てきてしまったので脚をクロスしてそんなふうな作業をしていると、瀬見がじっとそれを見ているのに気が付いた。
「なに?」
「ん? いや」
「なんか言いたそうじゃん。 気になるんだけど」
砂を払い終わったので靴を履く。 そうしてもう片方も同じように靴を脱いで砂を払いつつ瀬見の顔を見る。 瀬見は視線をあっちこっちに向けつつ「あー」とか「んー」とか唸りつつ何かを言い渋っている。 「なによ」と笑いつつちょっと足で瀬見の靴を蹴ってやると、ちらりとこちらに視線を向ける。
「いや、なんつーか」
「なんつーか?」
「そういうの、似合うなあ、と、思って」
「……そういうの?」
「その服」
危うく靴を落としかけた。 瀬見、今日、どうしちゃったんだろうか。 高校時代にそんなことを言われた記憶はない。 髪を切っていったときに「似合うじゃん」と言われたことはあるけど、こんな感じじゃなかった。 こんなふうに女の子扱いされるような言い方ははじめてだ。 やっぱり数年ぶりだからなのだろうか。 私が変わったのか、瀬見が変わったのか。 それとも何も変わっていないのか、二人とも変わったのか。
「なに、どうしたの。 照れるんだけど」
笑って誤魔化す。 瀬見は黙って私を見たまま穏やかな顔をしている。 誤魔化せなかったらしい。 じっと見られるといよいよ本当に照れてきて、視線を逸らしてしまった。
ザアザアと海が凪ぐ音と風の音だけが私たちの周りに響く。 片方の靴を履くのも忘れて瀬見の視線から逃げるように黙りこくる。 瀬見も黙ったまま私の顔を見つめ続けているみたいだった。 そんな時間にどぎまぎしていると、車に乗っている途中で見かけた子どもたちがこっちのほうまで歩いてきたみたいで、無邪気な笑い声が辺りに響いてきた。 それを合図にしたかのように瀬見が「あのさ」と口を開いた。
「家に送り届けてから言うつもりだったんだけど」
「……なにを?」
「俺さ」
さっきまでうるさかった風の音が止む。 子どもたちの無邪気な声もいつの間にか聞こえなくなっていた。 海が穏やかに優しく凪ぐ音と、それと同じくらい優しい瀬見の声だけが私の耳には聴こえている。
「高校のときからずっと」
そんなこと、あるわけない。 瀬見とは仲が良かったけど本当にそれだけだった。 話しやすくて気が合って、からかいやすくて、ちょっかいをかけやすくて。 そういう相手だった。 瀬見にとって私もきっと同じようなものだった、と、思うのだけど。

「英太くん、な〜んで卒業式のとき、ちゃんに告白しなかったの?」
ぶっ、と思わず口に含んでいたビールを拭いてしまった。 それが直撃したらしい山形が「おい」と笑顔で俺を軽く殴ってきたが、それどころじゃなかった。 天童の言葉をもう一度頭の中で再生し直す。 そうして軽く咳払いをしてから「え、なんのこと?」ととぼけてみた。
「いやいや、とぼけても無駄だから。 みんな知ってるから」
「マジかよ」
「瀬見分かりやすすぎだったし」
「マジかよ!」
「気付いてないのってちゃんと工だけじゃない?」
衝撃的な事実に頭を抱えてしまう。 天童が俺の背中をばしばし叩きながら大笑いする。 山形もそれに続いて大笑いしながら「ばかだな〜」と言って唐揚げをつまんだ。
俺としては完璧に隠し通していたつもりだったのに。 いつの間にか部員全員(工は除く)に知れ渡っていたらしい。 今思い出せば妙にタイミングよくと二人きりになったり、移動のバスや合宿所での飯の席が隣になったりしていたっけか。 あれは単に運が良いからだと思って勝手に喜んでいたのだが、どうやら周りの協力あってのことだったらしい。
「卒業式で告白するだろうな〜って思ってたのにサ」
「英太くん、まさかの未行動なんだもん」と天童が頬杖をつく。 「びっくりしたよね〜?!」と山形に同意を求める。 山形もそれに頷いてから、俺の肩をかなり強めにつかんで「それでもお前は男か!」と頭突きをかましてきた。 こいつ、もう出来上がってやがる。 若干アルコールが回っている俺もぐわんぐわんと頭が揺れつつ、「すみません」となぜか謝ってしまった。
「連絡取ってるの?」
「いや……、なんか忙しそうだし悪いなと思って」
「ないわ〜英太くんマジないわ〜〜」
「なんでだよ!」
「そういうときこそ、逆にしつこく連絡してあげたほうがいいんじゃないの?」
「嫌がられるだろ……」
苦笑い。 すると、天童と山形を顔を見合わせて「ばかだよね?」「ばかだな」と失礼な確認作業を目の前でしやがった。 それにツッコミを入れつつ唐揚げをつまんで口に放り込む。 山形が「う〜ん」と腕組みをして何かを考え、「なんつーかな」と一人で首を傾げる。
「瀬見って残業とかすんの?」
「え? いや、ほとんどないけど」
「羨ましいなクソ。 有休は?」
「取ってるだろ……お前らと飲み会するときも次の日午前休もらったりしてるし」
「じゃあそれ全部逆になったらどうする?」
「逃げ出したくて泣く」
「っていまそういう状況だと思うけど」
心配はしていた。 当たり前だけど。 山形主催の飲み会に一度も来てないし、その理由を山形に聞くといつだって「仕事で忙しいんだと」と説明されていたし。 大学のときもそうだ。 ゼミが忙しいとかバイトの人が足りなくて大変とか。 そういう話ばかり聞いていた。 高校のときだって、そうだった。 マネージャーとして雑務は全部自分でやらないと、と頑固な考えをしていたっけ。 そういうやつなのだ、というやつは。 自分より他人を優先するというか。 自分が我慢すればいいと思っているというか。 高校のときはそんなの無視して横から仕事を奪ったりなんやりできたけど。 そばにいない今だと、そうそうそんなことはできない。 別に彼氏でもなんでもない俺がお節介を焼くのもでしゃばりすぎかと思って、なかなか連絡を取れずにいたのだ。
「英太くんなかなか動かないからさ、俺らでちゃんに声かけてみよって話してるんだけど」
「えっ」
「英太くん、それでもいい?」
にこ、と天童が笑う。 答えが分かっている笑い方だ。 それにちょっと照れくささを覚えつつ、「よくないです」と天童の頭をぐいぐい押しつつ答える。 それを聞いた山形が勝手に俺のスマホを鞄から取り出すと、「ん」と渡してきた。 「は?」と首を傾げたら「電話しろ、今すぐここで」と俺の顔面にスマホを押し当ててくる。 スマホを手で受け取りつつ「マジかよ」と呟く。 天童と山形が「マジだよ」と見事にハモると、少し笑ってしまった。
高校以来かけたことがないの番号をタップする。 心臓が発信音と同じくらいの鼓動を刻みつつばくばくとうるさい。 けれど、緊張しているというよりは不安の方が大きかったかもしれない。 そこそこ遅い時間なので寝ているのを起こしたらどうしようとか、そもそも出なかったらどうしようとか。 そういう不安と戦っていると、5コール目くらいで「もしもし?」と久しぶりに聞くの声がした。 にやにやしながら見ている天童と山形を見ないようにしてと会話をする。 声だけで分かる。 なんだか疲れている、し、たぶんまだ会社にいるらしい。 の声の後ろで数人の人の話し声が聞こえている。 思った通りいろいろ話して約束を取り付けてから「ごめん、まだ会社なんだ」とが苦笑いした。 また仕事に戻るとが言うので再度約束の確認をしてから電話を切ると、天童と山形はにやにや顔をやめて「仕事中だった?」と聞いてくる。 頷くと二人とも困ったような顔をして「なんだかな〜」とやりきれないような顔をする。
「英太くんさ〜」
「おう?」
「早くちゃんと結婚してよ」
「すげー話飛んでんだけど?!」
「うざいくらい新居行くね」
「俺もついてくわ」
「いや話がぶっ飛び過ぎだから!」

ぴたりと、まるで波が止まったかのようだった。 瀬見が言葉に迷っているのが分かってしまう。 瀬見の声が聞こえなくなった途端に波の音すら私の耳はとらえなくなった。 ただただ自分の心臓の音だけが内側から聴こえるだけ。 そんな時間を行ったり来たりしてさまよっているうちに、気付けば瀬見の瞳をまっすぐ見つめ返していた。 髪が風に揺れて邪魔をしてくるけれど決して風の音は聴こえない。 世界で瀬見と二人ぼっちになってしまったみたいな、そんな錯覚を覚えた。
瀬見といるのが楽しかった。 それは本当にそうだった。 今も変わらない。 たぶんバレー部の中で誰よりも瀬見といるのが楽しかっただろうと思う。 みんな楽しかったけど、その中でも瀬見といるのは一等楽しかったのだ。 気を遣わなくていいし、気を遣われなくて気が楽だし。 そんな日々に戻りたいと仕事中にふと、瀬見の顔を思い出すこともあったほど。 でも、決して連絡はしなかった。 きっと瀬見の声を聞いたら、固めるように溜めていたものが一気に流れ出ていってしまう気がして。 飲み会に行かなかったのだって正直なところ、それが原因だった。 ゼミとかバイトとか仕事とか。 そういうのが忙しいという理由も確かにあったけれど、行こうと思えば行けたのに。 瀬見の声を聞いてしまったら、ようやく慣れてきた瀬見のいない空間が、また、寂しくなってしまうのが怖くて。
自分の思っていたことをはじめてちゃんと整理してようやく気付いてしまった。 ああ、私、瀬見のことが。
「のことが」
瀬見からの電話を取ったとき、きっと私が一生懸命固めてきた何かは崩れ去っていたのだろう。 もうたぶん、瀬見のいない空間が、耐えられないものになっているのだろう。 そんな世界が待ち受ける明日の海を、私は、一人ぼっちで眺める自信はなかった。
私、瀬見のこと、好きだったんだ。 友達としてじゃなくて異性として。 知らない間に瀬見という存在を心の支えみたいなものにして、私の脚は立ち続けていたんだ。
だから今、こんなにも、心臓がうるさいのだろうか。
「ずっと」
瀬見の声が途絶える。 真っ赤になった瀬見の顔が少しずつ下を向いていくと、瀬見のつむじが見えた。 右手で頭をかいた瀬見は押し黙って言葉を探しているのか、言おうか迷っているのか、とにかく何かを考え始めてしまう。 私は高校時代よりもきれいになった指を見つめながら黙って待つしかできない。
ちょっと高いヒールの靴を履いてきたのも。 あまり着ないワンピースを着てきたのも。 ぜんぶ、瀬見を知らない間に意識していたからなんだ。 だから瀬見に「きれい」って言われて、あんなにも、照れてしまったんだ。 高校生のときなら照れつつももっと軽く返せていただろうに。 瀬見だってそうだ。 高校生のときだったらあんなふうに照れずに言っていただろうに。 私も、そして瀬見も、何一つ変わっていないけど、ぜんぶ変わっていたんだ。
黙りこくった瀬見のつむじ。 見たことがないほど真っ赤になっている瀬見を改めて認識したら、少しだけ笑えてしまった。 くすりと小さく笑ったのが聞こえたらしい瀬見ががばっと顔を上げると、真っ赤な顔のまま「なんで笑う?!」と声をひっくり返しながら言った。 それがまた面白くて、というか、照れくささが振り切ってしまって、余計に笑いが止まらなくなった。 「ごめん」と笑いながら謝ると、瀬見は真っ赤なまま「なんだよ」と拗ねたような顔をする。 ようやく海が凪ぐ音が聴こえた。 風が吹く音も、鳥が鳴く声も。 それに紛れた心臓の音も、ちゃんとぜんぶ聴こえる。 瀬見と二人きりの世界は、恐ろしいほど美しい音で溢れていた。
「瀬見」
「……なんだよ」
「最後まで言わないの」
履き忘れたままだった靴を履きつつ言う。 自然と視線が瀬見から逸れたけれど、視界の隅っこに驚いた顔をした瀬見が映っていた。 靴を履いて立ち上がる。 「え」と瀬見が私を見上げたけど構わずそのまま堤防を上を歩いていく。 駐車場のほうまでまっすぐ続いている堤防を歩く私の後ろを瀬見が少し早歩きで追いかけてきた。 私の腕をつかむと少し赤いけれど真面目な顔をして「あぶねーだろ」と言った。 それに大笑いしてしまう。
「あーあーもう笑ってくれていいから、本当にあぶねーし降りるぞ」
真面目な顔で心配してくれるから仕方なく階段に引き返そうとする。 けれど、瀬見がほんの少し高い堤防から道路に飛び降りるので驚いてしまった。 え、私も飛び降りろと? 困惑していると瀬見が私に手を伸ばす。 「ん」とだけ言ったその手を握ると瀬見が段差に足をかけてから、いとも簡単に私の体を抱き寄せた。 一瞬だけふわりと体が浮いたけれど、しっかりと瀬見の腕が捕まえてくれる。 すぐに降ろしてくれるかと思いきや瀬見はそのまま道路を歩いて駐車場に向かい始めた。
「瀬見、降ろしてよ」
「」
「うん?」
「ずっと、お前のこと好きだった」
不意打ちだった。 瀬見は私の背中をぽんぽん撫でながら、もう一度なぞるように「好きだ」と繰り返した。 私が言葉を探している間もずっと「が好きだ」「ずっと好きだった」と繰り返し続けるので、恥ずかしくて背中を思いっきり叩いてやった。 それに笑いながら「いてー」と呟いたけど、すぐにまた「好き」と繰り返し始める。 ずっと溜め込んでいたものを一気に外に出すように言い続ける瀬見は、もう赤い顔はしていなかった。
「のこと、今もすっげー好きなんだけど、俺」
きらきらと海が光って見える。 眩しいほどに光が反射する海が延々と続いていく水平線の果てを見たような気になる。 それくらい、自分で自分が恥ずかしくなるほど、心が叫んでいた。 ぎゅうっと瀬見の首をしめるくらいの勢いで抱き着くと、やっぱり瀬見と二人きりの世界が続いていた。
「私も瀬見のこと、すっげー好きだよ」
真似してやった。 瀬見は私の背中をぽんぽん叩いて「ちょっと苦しいですさん」と言うので余計にぎゅううっと力を入れてやる。 それに瀬見はけらけら笑いながら「苦しいって」とやり返すように私をきつく抱きしめた。
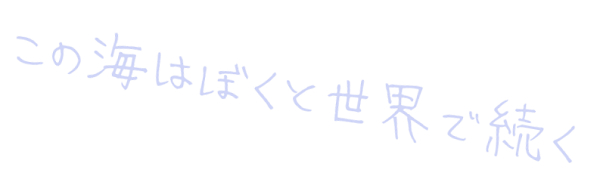
▼title by sprinklamp,