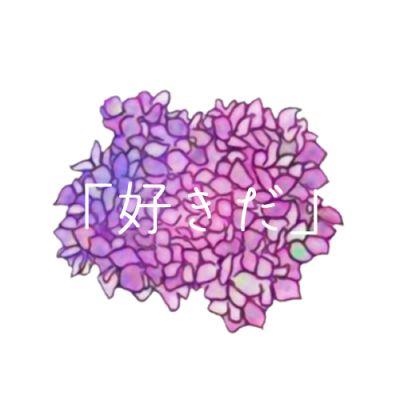二年生のときにクラスが離れてしまってちょっとがっかりした。なんだ、もうあの背中を見られないんだ。学校に来る楽しみが減っちゃった。ろくに会話をしたこともない男子なのに、変なの。そんなふうに不思議に思っていたけど、クラスが離れてから姿もあまり見られなくなっていたその男子を、たまたま昇降口で見かけた。ちょうど靴箱を開けようとしているところだった。可哀想なことに靴箱の位置が下のほうになったらしい。その男子は背中を丸めて靴をしまおうとしていた。
背中が丸い。じっと見つめてて、うっかり声をかけそうになったけど慌てて言葉を飲み込む。一年生のときに同じクラスだったとはいえ、本当にちゃんと話したこともないのに何をしようとしてるんだわたしは。話しかけてどうするつもりだったんだろう。本当、自分のことなのに不思議でたまらない。なんでだろう。ただ背筋がピンとしているだけなのに、なんでこんなに気になるんだろうな、わたし。あの男子のこと。名前を口にしたこともない。それなのになあ。
そして今年、三年生になったわたしはクラス発表の張り紙を見て、目を丸くした。あの背筋がピンとしている男子、北くんが同じクラスだったのだ。「一緒のクラスなれへんかった!」「今年もあんたとか〜!」といろいろな声が聞こえてくる廊下で、一人、きゅっと両手を握って「やった」と小さく呟いた。
その瞬間、これは恋なのだと、自覚してしまった。
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
わたしの席の右隣の列。二つ前に進んだところに座っている北くんを、授業中にこっそり観察するのが何よりも楽しみになった。一年生のときから変わらないまっすぐ伸びた背筋。やっぱり微動だにしない。ただの一瞬もだれることはない。じっと黒板を見つめる瞳がほんの少しだけ見える位置にいるのだけど、背筋だけじゃなくて視線もまっすぐな人なのだと気付いた。何にも気を取られずに先生の言葉だけに耳を傾けて、恐らく頭の中は授業の内容のことしかない。不真面目に授業を聞かずに北くんを観察しているわたしとは大違いだ。
北くんはどんなときに気を抜いてしまうのだろう。どんなことで笑うんだろう。どんなことを楽しいと思うのだろう。どんな顔で笑うのかな、どんな声で友達と話すのかな。知りたいことがたくさんある、のに、わたしは北くんとまだ話したことがない。たまに休み時間に話しかけている女の子をじっと見て何を話しているのかを観察するだけ。女子バレー部に所属している子が話しかけていることが多い。体育館の割り振りがどうだとかなんとか。北くんってバレー部なんだ。そんなこともわたしは三年生になるまで知らなかった。
北くんは授業が終わるとまず机の隅に集めた消しゴムのカスをごみ箱に捨てに行く。手をぱんぱん払ってそれを捨ててから席に戻って、ノートと教科書を鞄にしまって、出した文房具をきっちりペンケースにしまう。ペンケースは一年生のときから変わっていないシンプルで小さいもの。中身はたぶんあんまり入っていない。色ペンも赤色くらいしか使っているところは見たことがない。消しゴムはどんなに小さくなっても最後まで使い切りたいらしくて、今の消しゴムはもうどこを掴んで消してるんだろうってくらい小さい。物を大事にするタイプ。そう頭の中に書き留めた。
いつもきっちり結ばれているネクタイが見えた。珍しい。後ろの席に座っている子と会話をしている。体を横向きにして何やらノートを指差して話している。その様子からしてどうやら後ろの席の子に授業のことを聞かれたのだと分かる。北くんの顔を正面からちゃんと見たのは久しぶりだ。笑わないかな。そうじいっと見ていたけど、柔らかい表情をしたくらいで笑いはしなかった。
お昼になると北くんは必ず教室から出て行く。同じバレー部らしい大耳くんと一緒に。さすがに後をついていったりはしないけど、いつもどこでご飯を食べているのかな、と気にはなる。まあ後をつけたらただのストーカーになる。いつも観察しているだけで不審人物なのだからそこはちゃんと弁えているつもりだ。
はあ。ため息がこぼれる。たった一度でいいからお話ししてみたい。あわよくば笑ってほしい。男子に自分から話しかける明るい女子じゃないし、そもそも特定の仲が良い友達としかうまく話ができない。夢のまた夢。もう来年の今頃は北くんを観察することもできなくなっているんだな。恋なんて言うのもおこがましいほどささやかな想いだ。またため息がこぼれてしまった。
お昼ご飯を食べに行こう。そう財布とスマホだけ持って席を立つ。今日は友達が軒並み彼氏と食べる、と楽しそうに言ってきたので一人ご飯だ。悲しい。彼氏かあ。いいなあ。そう思いつつ教室を出て購買へ。ちょっと出遅れたくらいのほうがゆっくり見られるからいつも購買に行くときは時間をずらすようにしている。三年生の教室からだと一つ下の階に下りてすぐのところだ。まだ少し賑やかな購買にそろそろと一人で参戦して、適当におにぎりを取ってそそくさとレジへ。せっかくの一人ご飯だから教室じゃなくて、普段あまり行かないところで食べようかなあ。そんなことを考えながら、なんとなく外へ出てみることにした。たしか座れるところがあったよなあ。お昼のときに行ったことはないけど。そんな曖昧な記憶でふらふら歩いていると、男子の笑い声が聞こえてきた。渡り廊下からだ。わたしが通過しようとしているところなのでちょっと怖気付く。嫌だな、明るいタイプの男子のたまり場なのかもしれない。避けて通りたいけど遠回りになるなあ。そうっと様子を窺うと数人の男子が校舎に続く階段に座っているらしい。よし、あの位置なら通り過ぎても距離がある。何か言われてもダッシュで逃げられる! 被害妄想も甚だしいけど、危険察知能力は高ければ高いほどいい。
そそくさと渡り廊下を通過しようとして、何気なく視線が横を向いた瞬間。あ、と思った。北くん。大耳くんと他の男子数人と一緒にご飯を食べている。階段に座り込んで食べるタイプだとは思わなかったけど、意外と普通の男子高校生っぽくてそれはそれでいいなあ。いつもここでご飯、食べてたんだ。ここ通ってよかったあ、ラッキーだ! ささやかな幸せ。それを噛みしめながら何でもないフリをして通り過ぎ、ようとした。
「」
ビク、と肩が震えたけど足は止まらない。え、何、今呼び止められた気がする。知っているようで知らない、知らないようで知っている声に。気のせいかな。そうだ、気のせいだな! そのまま足を止めずに通過、しようとしたわたしを再び「」と凜とした声が呼び止めてきた。さすがに、足を止めざるを得ない。変な体勢で止まって、ぎこちなく振り返る。階段に座ったままの北くんと目が合った。
「え、あ、はい」
「スカート」
「えっ」
「なんか折れとんで。直したほうがええんとちゃうか」
すんなり頭に入ってこない。え、わたし、今、北くんと喋ってる? 三年間ただの一度も話せたことがないのに? そんな馬鹿な。夢か。そうだ、そんなわけないし、夢なんだこれ。完全に思考停止している頭が弾き出した答えに、内心「そんなわけあるか!」とツッコむ。どう見ても現実だ。これが夢ならわたしは事故に遭って長く意識不明の重体だったとかじゃないとおかしい。絶対に現実、なのに、現実ではありえないことが起こっている。なんで?
いや、ちょっと待て。北くんは今なんて言った? わたしの苗字を呼んだあと、「スカート」と言った。制服のスカート。ギリギリ校則に従っているくらいの長さのそれは、まあ、たぶんダサい部類に入ると思う。そんなスカートをなんと言ったか。「なんか折れとんで」。折れている、とは? そのあとには「直したほうがええんとちゃうか」と言った。直す。つまり、わたしのスカートは今正常な状態ではないということを北くんは言っている。正常な状態ではなく、折れているスカート、とは?
バッとお尻に手を当てる。なんとなく違和感。恐る恐る手を動かすと、どうやらパンツに巻き込まれていたらしいスカートが少し折れていることが分かった。
間。教えてくれた北くんは真顔のままわたしを見ていて、北くんの周りにいる男子数人は気まずそうに目をそらしている。わたしはというと、真顔のままスカートを手で直してから、一瞬で顔が熱くなった。
「……み、見やんかった、ことに」
「何がや」
「なっなんでもええから! 見やんかったことにして!」
死にたい。なんで好きな人とやっと話せたのにパンツ見られてるの。しかも興味なさそうだし。どうせならちょっと、こう、パンツ見られてラッキーくらいに思ってくれたほうが、よかった。どんどん熱くなっていく顔が恥ずかしくて俯いてしまう。そんなわたしの様子を知ってか知らずか、北くんがまたわたしの苗字を呼んだ。
「どこ行くんや? そっち何もないで」
「……す、座れるとこ、あったかなって」
「向こうにあったベンチならもう撤去されてないで」
「そ、そうですか……」
わたしの記憶は一年生のころのものだったらしい。なんとなくぼんやり覚えていたスポットは諦めて別のところへ行くしかない。北くんと一緒にいる男子数人が気まずそうにまだ目をそらしている。恥ずかしい。本当に恥ずかしいけど、指摘してくれて、助かったかもしれない。もし知らないままだったら絶対気付かず一日過ごしていた。電車にもこのまま乗っていただろうし、校内をうろうろしていたに違いない。教えてくれたんだからお礼、言わないと。好きな人にパンツを見られたショックは消えないけど。
ろくに会話をしたこともないのに、普通なら見て見ぬふりをしてしまうシチュエーションだっただろうに。北くんはただ親切心のみで声をかけてくれたのだ。恥ずかしいけど、きゅんとしてしまう。優しい。真面目な人なんだな、やっぱり。そう思ったら好きなぴんと伸びた背筋がより凛々しく見えてしまった。
「き、北くん」
「なんや」
「……教えてくれて、ありがとう」
たぶん顔は真っ赤だけど、ちゃんとお礼言えて良かった。そうほっとしながらそそくさとまた渡り廊下を通過しようとした。すると、北くんが立ち上がってこちらに歩いて来る。思わず足を止めてしまうと北くんはわたしの前で立ち止まって「顔赤いやん、大丈夫か?」とほんの少しだけ背中を丸めた。
「だ、大丈夫! 何でもない!」
「そうは言うても真っ赤やで。体調悪いんか?」
「ちゃう! ちゃうから!」
顔を近付けないで! そう思うのだけどこんなに近くで北くんの顔を見られる機会なんてそうない。そっぽを向いたり北くんを見たり忙しすぎて、なぜだか余計に顔が熱くなる。北くんはただただ心配してくれているだけなのに、わたしは。北くんって目が大きいんだな、意外と背が高いんだな、とか、そんなことばかり考えてしまう。下心しかない。それが何よりも恥ずかしかった。
北くんの手が伸びてきた。びっくりする間もなく、右手がぴとっとわたしの額にくっつく。「熱はないみたいやな?」と不思議そうに首を傾げられた。右手が離れてから少し乱れた前髪をちょいちょいと直してくれる。「しんどいなら保健室行ったほうがええで」と言って、ようやく北くんの右手が元の位置に戻っていった。
「?」
ずっと見ているだけだった好きな人に、はじめて声をかけられて、苗字を呼ばれて、恥ずかしいところを見られて、顔を覗き込まれて、おでこに触られて、って、たった数分の間に盛りだくさんすぎて。完全に思考が停止してしまう。だって、こんなの想像してなかった。こうなればいいなって妄想したことさえなかった。ちょっとお話しできればいいなって思っていたくらいなのに。ちょっと、いやかなり、キャパオーバーで。
「すっ、好きな人にパンツ見られたら恥ずかしくて顔も赤なるっちゅーねん!!!」
わーっと走り去ってしまう。最悪。最悪すぎる、いろいろ、いやもう全部! 明日からもう北くんの顔、見られない!
▽ ▲ ▽ ▲ ▽
走り去ったの背中を見送りつつ、首を傾げてしまう。よく分からないまま元々座っていたところに戻ると、アランがぼそりと「青春やなあ」と呟いた。何が。そう視線を向けると、赤木が「それよりお前、さすがに指摘するタイミング考えようや」と苦笑いをこぼす。何が。さらに首を傾げていると大耳が「それにしても知らへんかったな」と笑った。何が? ああ、不思議と言えば。
「、誰のことが好きなんやろうな」
「は?」
「は?」
「は?」
「なんやねん」
好きな人に、と言っていたからこの場にいた誰かのことなのだろう。パンツがどうとかとも言っていたけど、それはギリギリ見えていなかったから大丈夫だと教えたほうがよかっただろうか。そう少し後悔しているとアランが俺の肩を掴んだ。
「嘘やん、え、ほんまに言うとる?」
「何がやねん」
「いやどう考えても、お前のことやろ」
「何が?」
「あの子の好きな人が、やわ!」
「…………そうなん?」
「そうやろうがどう見ても!」
一年生のときに同じクラスだったことは覚えている。たしか一学期の間は前後の席だった。それでも話したことはなかったし、二年ではクラスが離れた。三年生でまた同じクラスになったけど、ただの一度も話をしたことはないはずだ。そんな俺のことをがそんなふうに思っているとは到底思えなくて。また首を傾げてしまう。俺ちゃうやろ。そう視線でアランに訴えたら「お前やねん!」と念を押されてしまった。