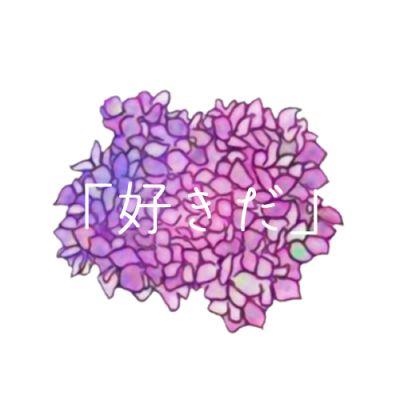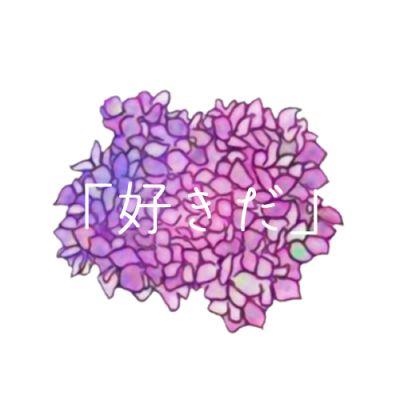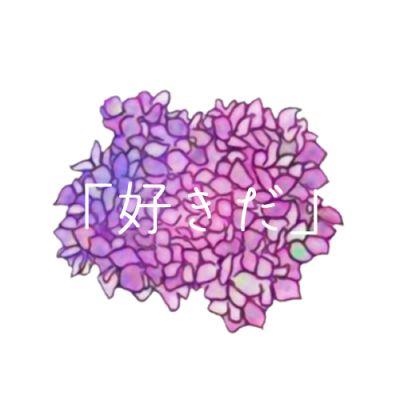 サーブ練習終了後、五分間の休憩時間が取られた。部員たちが次々コート外に座り込んで息を吐いている。準備したばかりのボトルを渡して回りつつ、それとなく声をかけていく。頑張り屋が多いからちょっと心配になるけど、自分が納得するまでとことんやってほしい気持ちもある。いつもその加減が難しくて。何もできないわたしはちょっと悔しい思いをするばかりだ。
サーブ練習終了後、五分間の休憩時間が取られた。部員たちが次々コート外に座り込んで息を吐いている。準備したばかりのボトルを渡して回りつつ、それとなく声をかけていく。頑張り屋が多いからちょっと心配になるけど、自分が納得するまでとことんやってほしい気持ちもある。いつもその加減が難しくて。何もできないわたしはちょっと悔しい思いをするばかりだ。
同輩部員といくつか言葉を交わしてから部員に代わってコートにモップでもかけるか、と顔を上げたときだった。「さん」と珍しい人に声をかけられた。佐久早の声。普通に会話をする後輩ではあるけれど、あまり佐久早のほうから声をかけてくることはない。ちょっと驚いて振り返る、けど姿が見えない。あれ、気のせいだったかな。そう不思議に思っていると「下」と言われた。下。恐る恐る視線を下に向けると、壁際に座っている佐久早と目が合った。
「どうしたの?」
「……あー」
「うん?」
いつも思ったことを割とズバッと言うのに、珍しく口ごもっている。今日は珍しいこと尽くしだ。普段あまり佐久早と部活以外の会話をしたことがないし、ちょっと調子に乗っても良いだろうか。そんなふうに小さく笑いつつ、佐久早の前にしゃがんでみる。「何?」と笑顔を向けると、佐久早は「あー」と視線をそらした。これは本格的にどうしたのだろうか。何かまずいことでもあったのかもしれない。そんなふうな心配に変わっていく。そんなわたしをよそ目に佐久早は、ようやく視線をこちらに戻してくれた。
「……肩」
「肩?」
「マッサージ、して、ほしいんですけど」
「いいよ。痛いの?」
これは、ものすごく貴重だ。佐久早は基本的にあまり人に触られることが好きではない。マッサージとなれば余計にだ。素人にやられたくない、というタイプ。部活ならさせても古森くらいなのに、どうしてわたしに声をかけてきたのだろうか。
痛いわけではないと言った。ちょっとだるい感じがあるくらいで、別に問題はない。そう聞いて安心した。選手の体をマッサージすることなんて滅多にない。痛んでいるのなら下手に触るのが怖かったし。そう安心しつつ佐久早の肩に触れようとして、手を止める。
「手洗ってくるから待ってて」
「……いや、別に良いですけど」
「だって嫌でしょ?
何触ったか分かんないよ?」
笑ってわたしの手を見せる。若干潔癖の気がある佐久早だ。先輩だから、女子だから、と気を遣って別に良いと言ったのかもしれない。いや、そういう気遣いをするタイプの後輩ではないのだけど。
じゃあ洗ってきて、と言いやすい環境にしてあげた先輩の優しさを身にしみてね。そんなふうに思いながら待っているのに、佐久早はじっとわたしの手を見たまま黙った。おや、今日は本当に様子がおかしい。いつもズバッと思ったことはそのまま言うのに。そんなふうに思っていると、佐久早が左手を伸ばした。広げて見せているわたしの手の中央、つん、と佐久早の人差し指が当たる。びっくりして言葉を失ってしまう。そのうち指が離れていって、手の平の中央に少し熱が残るだけになってしまった。
「さっき外でボトル洗ってからそれ以外何も触ってないの見てたんで。そのままでいいです」
くるりと背中をわたしに向ける。佐久早はまだ使っていないらしいタオルを自分の肩にかけると「ゆるめでお願いします」と言った。なんか、野良猫が懐いたみたいな。そんな小さな幸せを感じる。小さく笑ってから「はいはい」と返事をして佐久早の肩を掴む。見た目より大きく感じるその肩を慎重にぐっと揉みつつ、佐久早がわたしに声をかけた理由が分かった。そうか、部員だと力加減を間違えられたら痛くなるかもしれないからだ。わたしは元々の力が弱いから万が一強めにやられても大丈夫という判断なのだろう。さすが佐久早、そういうところも先回りして読んでるんだなあ。答えを聞いたわけでもないのに感心してしまった。
「これくらいでいい?」
「はい」
「にしても大きい肩だね。一年のときはもうちょっと小さく見えたのに。わたしなんかすぐ捻り潰されそう」
「そっすね」
「そっすねって!」
捻り潰す気あるのかよ!
なんてちょっと調子に乗って佐久早の肩をぺしんと叩く。さすがに怒るかな。ちょっとどきどきしていたけど、佐久早は特に何も言わなかった。
「でも好きだよ」
「……は?」
「だって頑張ってる証拠でしょ。佐久早がどんどん強くなってどんどん遠くに行くのが嬉しいよ、先輩として」
自慢の後輩だよ、なんて笑ってみる。でも本当にそうだ。佐久早は自慢の後輩。三年生全員が思っていることだ。手がかかるし面倒なことを言うときもあるけど。でも、バレーに対する姿勢は誰もが尊敬している。だから、わたしは佐久早の大きな肩や手、そのほか全部が好き。肩を揉みながら素直にそう言ってみた。佐久早とこんな話をする機会なんて滅多にないし言うなら今だと思って。
「……どうも」
「あ、照れた」
「照れてません」
「耳赤いよ」
ちょん、と指先で耳を触ってやる。びくっと震えた佐久早が耳を押さえながらこちらを振り返った。信じられないものを見るような目でわたしを睨むので、さすがに調子に乗りすぎたと反省する。「ごめんて」ともう何もしないポーズを取る。佐久早は耳を押さえたままちょっと顔を赤らめて、まだわたしを睨み付けたままだ。そんなに怒らなくても。苦笑いで「もうしないから。許して」と手を合わせる。せっかく懐いた野良猫がまた威嚇してくる。そんな寂しさに暮れてしまう。
佐久早が耳を押さえていた手を離した。じいっとわたしを睨んだまま、その手をこちらに伸ばしてくる。そのずいぶん長く思える腕をぽけっと見ていると、佐久早の指がわたしの髪に触れた。さらりと何本か滑り落ちた髪は放っておいて、佐久早は緩く指の腹でわたしの髪を撫でる。そのままその先にあるわたしの耳たぶに、ちょん、と指先を当てた。
「なに、どうしたの?」
「ムカつくんですけど」
「えっなんで?」
ぱっと手が離れる。佐久早がわたしから視線をそらした瞬間、休憩時間終了の声がかかった。佐久早はさっさとコートに戻っていってしまう。結局肩、あんまりマッサージしてあげられなかったけど大丈夫かな。大きな肩を見つめていると、佐久早の耳が真っ赤になっていることに気が付いた。本当に大丈夫かな、とわたしが思っていると古森が佐久早に声をかけた。「なんか赤くない?
大丈夫?」という古森の気遣いに佐久早は「うるさい黙れ」とだけ言って、それ以上聞く耳は持たない様子だった。