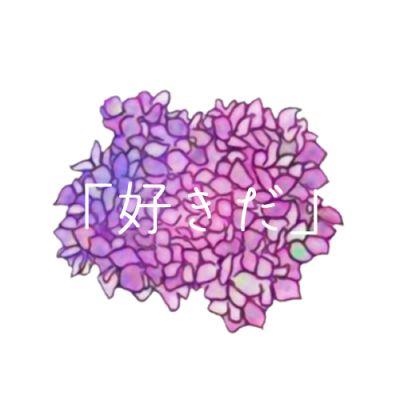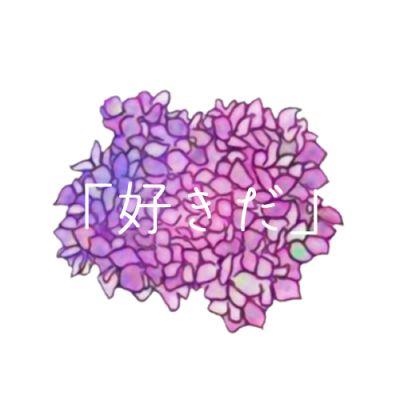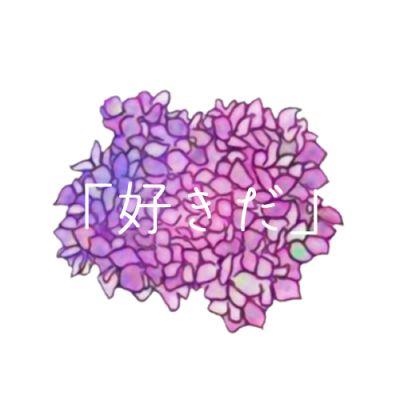 「こ、孤爪くん、好きです!
付き合ってください!」
「こ、孤爪くん、好きです!
付き合ってください!」
勇気を振り絞って、あの手この手で呼び出した孤爪くんに、告白した。孤爪くんは大人しくて口数が少なくて、正直あまり人付き合いが得意じゃないタイプの人だ。いつも大体一人でいて俯いている。ある日突然髪を金色に染めてきたときは学年が少しざわついたのを覚えている。
でも、孤爪くんは、本当はとても優しい人だと思うのだ。同じクラスだった一年生のとき、廊下を歩いていたら前方に孤爪くんを見つけた。特に気にせず歩いていたのだけど、ふと、孤爪くんが立ち止まってじっと動かなくなったことに気が付いて。どうしたんだろう。そんなふうにわたしも立ち止まって様子を窺ってみると、孤爪くんの足下に何かが落ちていた。よく見てみたらどうやら学生証のようだった。拾ってあげればいいのに。きっと孤爪くんの前を歩いている女の子のだよ。そんなふうに思った。なかなか拾わない孤爪くんを見ていて、ああそっか、声をかけるのが苦手なんだもんね、と気が付く。なら代わりにわたしが拾って届けてあげましょう。そんなふうに近寄ろうとしたら、緩やかに体を曲げて孤爪くんが学生証を拾い上げた。それからとても気まずそうにあっちを見たりこっちを見たりしながら、振り絞った声で女の子に声をかけたのだ。
孤爪くんって、そういうの、見なかったふりをする人だと思っていた。意外。そんなふうに思った瞬間から、わたしは孤爪くんのことがちょっと気になるようになって。毎日孤爪くんの観察をこっそりしては、意外な一面を見つけられて嬉しかった。イメージ通りの一面も同じく。そんなふうに勝手に孤爪くんを見ている内に、好きになってしまった。一度も話したことなんかないのに。
「…………え、お、おれ……?」
思っていたとおりの反応だった。だから全然動じない。孤爪くんはわたしから視線をそうっと外して「え、なんか、間違い……」と言ったあとにちょっと眉間にしわを寄せて「罰ゲーム……?」と言った。そこまで言われるとは思っていなかったけど、予想の範囲内だ。そういう反応をされる確率はほぼ百パーセントだと思っていた。だから、慌てることも傷付くこともない。
「間違いじゃないし罰ゲームでもないです」
「あ、そう……」
反応が薄いけどそれも想定の範囲内。全然驚かない。なんとなく気まずそうな孤爪くんに好きなところとか気になっていた理由とか、いろいろ一生懸命話した。二年生に上がってクラスが離れてしまったけれど、それでもよく見ていたよ。そんなふうに。孤爪くんはわたしの話をじっと聞いて、なんだか信じられないものを見る目でこちらを見ていた。ストーカーみたいって思われていたらどうしよう。そんなふうに不安に思ったけど、止められなかった。一度口から出ていった〝好き〟が止まらない。一方的に孤爪くんに投げつけているだけみたいになっていて、壊れたピッチングマシーンみたいに次から次へと〝好き〟が飛んでいった。
体育祭のときは日陰を見つけるのと存在感を消すのが上手かった、という話をしはじめたとき、孤爪くんが「あの、もう、分かったから……」とちょっと恥ずかしそうに止めてきた。ついに遮られてしまって、ようやく正気に戻ってくる。ちょっと顔が熱くなりつつも「他にもいっぱいあるけど、あの、好きです」と最後にもう一回言った。
孤爪くんは少し俯いて、じっと黙り込む。さらりと流れた長い前髪が孤爪くんの顔をちょっと隠してしまった。でも、その髪の隙間から見える瞳が好きだ。一度好きだと思ったらなんでも好きになってしまって困る。惚れっぽいと笑う人もいるだろう。それでも、恋をするというのは毎日を彩ってくれる、とても素敵なことだと知ることができた。孤爪くんのことを好きになってから毎日学校に来ることが楽しみになった。それは変えようのない事実なのだ。
「ご、ごめん、おれ、さんのこと、よく知らないし……」
そりゃそうだ。わたしが一人で盛り上がって告白をするなんて暴走をしているだけなのだから。最後まで話を聞いてくれた孤爪くんにお礼を言う。孤爪くんはちらりと視線を持ち上げて「あ、うん……」と気まずそうに言葉を返してくれた。
これ以上は迷惑になってしまう。突然呼び出したことを謝ってからまたお礼を言う。孤爪くんはそれで去って行くかと思ったのだけど、なかなか立ち去ろうとしなかった。わたしから「どうぞ帰ってください」なんて言うのは変だし、どうしようかな。ちょっと戸惑っていると、孤爪くんがブレザーのポケットに手を入れてスマホを取り出した。その仕草をぼんやり見ていると、孤爪くんが「あの」ととても言いづらそうに口を開く。
「……ライン、交換する?」
「…………えっ?!
いいの?!」
「う、うん」
「する!
お願いします!」
どういう風の吹き回しだろうか。孤爪くんからそんなことを言ってくれるなんて予想していなかった。驚きを隠せないままちょっと震えている手でスマホをポケットから出した。孤爪くんは手慣れた様子でアプリを操作して、QRコードを出してくれた。恐る恐るそれを読み取ると、わたしの友達一覧に孤爪くんの名前がピコンと現れた。
孤爪くんはわたしを友達登録してからスマホをポケットにしまう。「じゃあ」と言って去ろうとするので、「なんで連絡先教えてくれたの」と思わず聞いてしまった。だって、フラれたのに。孤爪くんの考えていることがよく分からない。そんなふうに困惑したままでいるわたしを孤爪くんがそっと振り返ると、ちょっと恥ずかしそうにすぐ目をそらした。
「よく知らないままなのは、なんか、嫌だなって思ったから……」
ぼそりと呟いてから、孤爪くんはピュッと予想外の素早い動きで去って行った。
孤爪くん、好きだなあ。そんなふうにスマホを握りしめる。拾った学生証を渡すために声をかけるだけであんなに躊躇っていたのだ。自惚れていいのなら、わたしに連絡先の交換を提案するの、すごく勇気を出して言ってくれたんだろう。そう思うと舞い上がりそうになる。孤爪くんがわたしのために勇気を出してくれた、かもしれない。それだけでもうとてもじゃないけど、胸がいっぱいでどうにかなりそうだった。