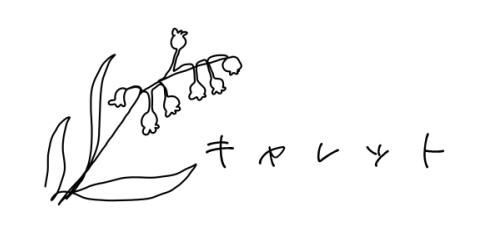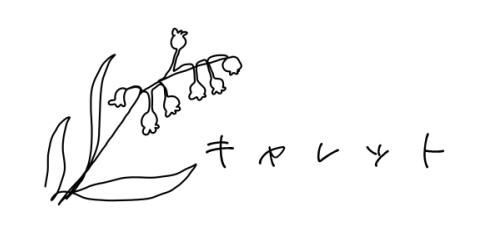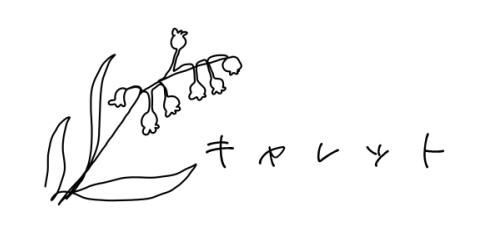 佐久早くんの家はいつもきれいで、とても緊張することが未だに多い。でも、前よりは、ずいぶんと慣れたと思う。玄関で靴を脱いで佐久早くんの後ろを歩けるし、ソファに座っていいか迷わなくなったし、花柄のスカートが浮いているんじゃないかって心配にもならない。普通のことなのだろうけれど、わたしにとっては大きな一歩だった。
佐久早くんの家はいつもきれいで、とても緊張することが未だに多い。でも、前よりは、ずいぶんと慣れたと思う。玄関で靴を脱いで佐久早くんの後ろを歩けるし、ソファに座っていいか迷わなくなったし、花柄のスカートが浮いているんじゃないかって心配にもならない。普通のことなのだろうけれど、わたしにとっては大きな一歩だった。
佐久早くんがスマホを操作しながら「何がいい?」と画面を見せてくる。覗き込んで見ると、佐久早くんが調べた履歴が動物系の映画で埋まっていて、ちょっと笑ってしまった。それに気付いた佐久早くんが「何?」と不思議そうに首を傾げる。
「ごめんね、佐久早くん、動物好きなんだなあって」
「……いや、別に嫌いでも好きでもない」
「そうなの?
履歴が動物の映画ばかりだから」
「が好きだから、動物」
きょとん、としてしまう。動物は好きだけど、そこまで好きだとアピールをした覚えはない、けどなあ。今度はわたしが首を傾げる番だった。そんなわたしを見て佐久早くんはほんの少しだけ怪訝そうな顔をした。
「前に犬を見てかわいいって撫でさせてもらってただろ」
「う、うん……動物は好きだけど、そんなに動物好きに見えたかな、と思って」
「それはこっちの台詞。俺、別にかわいいとか言ったことないだろ。かわいいとは思うけど」
「え?
言ってたよ?」
「いつ?」
「わたしが犬を撫でさせてもらってたときも、この前観た映画のときも」
佐久早くんが余計に首を傾げた。記憶を辿るように視線を斜め上に向けて「言ったっけ……」と独り言を呟く。言ったよ、はっきりと。そうくすくす笑ってしまった。なおも佐久早くんは怪訝そうにしていて、全く記憶に残っていない様子だった。わたしがかわいいと言った後に、佐久早くんもかわいいと言ったのに。はっきり覚えているよ。そんなふうに説明したら「ああ」と思い至ったらしい。
「あれ、のこと。だから、犬とか猫には言ったことない」
何でもないふうにそう言って「で、何観るの」と話を映画に戻してしまう。そんな、さらりと、戻れないよ。一人で照れてしまって返事に困ってしまった。佐久早くんはスマホを操作して、少し前に話題になった動物ものの映画で指を止める。「これとか?」と言われて、もう、「うん」と言うので精一杯だった。
映画の再生がはじまると、佐久早くんがスマホを机に置いた。それから前髪を少し払って、左手をソファに置く。力を抜いてリラックスしているのが分かる様子だった。いつも通り。佐久早くんは何も変わらない。それがちょっとだけ、悔しく思うようになっていた。
映画の冒頭。かわいい動物たちがたくさん出てきた。かわいい、けど。正直それどころじゃない。意識がすべて佐久早くんに向いてしまっている。だって、あんなこと言われたら、そりゃあ。
おかしいと言われるかもしれない。それでも、わたしは、わたしのために汚いものを触って、嫌そうに手を洗う佐久早くんに正真正銘の恋をした。汚れた水と汚れた雑巾。それを嫌そうに見ていたのに、それでも助けようと思ってくれたことが、嬉しかった。そこからはじまった恋だった。
汚いものが人一倍嫌いなはずなのに、佐久早くんの鍵を拾って汚れたわたしを、好きになってくれた。どうしてなのかは未だによく分かっていない。それでも、それは変えようない事実だし、目の前に佐久早くんがいることが何よりも証明になっている。未だに分からないことばかり。それでも、佐久早くんがここにいることは、いつまで経っても変わらなかった。
ちらりと佐久早くんがこっちを見た。それからしばらくじっと見ていたかと思えば、口元だけで小さく笑う。「かわいくないの」と、明らかにからかうように言ってくるものだから。恥ずかしくなってしまった。
「か、かわいいよ、動物」
「かわいいな」
「動物がね?」
「はいはい」
こんなふうな、恋人みたいな会話ができてしまう。それが未だに、分からない、けど。嬉しくて。
佐久早くんとの恋には、たくさんの〝はじまり〟があった。そうぼんやり思う。好きになった瞬間。好きになってもらえた瞬間。両思いになれた瞬間。自覚した瞬間。打ち解けた瞬間。たくさんの〝はじまり〟があって、今もこうして物語が続いていくように、ずっと止むことなく好きだと思う。そして、きっとこれからも変わらないのだろう。
するりと佐久早くんの爪が、わたしの右手を撫でた。びっくりして引っ込めそうになった手を佐久早くんが握ると「そういえば、何か飲む?」と聞いてきた。忘れてた、と小さく笑って。握られた手をちょっとだけ握り返して「じゃあ、お水で」と答えたら「ん」と返事をくれつつ、ゆっくりと手が離れた。
あの日の汚いわたしはどこにもいない。いなくなったわけじゃなくて、元からいなかったのだと佐久早くんが教えてくれた。わたしが佐久早くんに嫌な思いをさせたくないと強く思うあまり、佐久早くんの目にあの日のわたしが汚いと映っていたのではないか、と思っていたのだ。佐久早くんはそんな目で見ていなかったのに。汚い、と思って見ていたのは雑巾であり、こぼれた水であり、わたしではなかった。そう、思えるようになった。
戻ってきた佐久早くんがコップを机に置いてくれた。それにお礼を言うと、小さく笑いつつまた隣に座る。それからもう一度わたしの手を握ると、背もたれに体を預けた。
「映画、いつも暇潰しで流してるだけだから、大抵は内容なんか覚えてないけど」
「う、うん?」
「と観たやつはちゃんと全部覚えてる」
不思議だよな、と笑った。本当に、それはとても、不思議な話だ。佐久早くんの手を握り返しながら「不思議だね」と笑ったら、また手を握り返してくれる。あのシーンでこんな顔をしていたとか、こんな話をしたとか。そういうのを覚えているから内容も一緒に覚えている、と佐久早くんが言う。言われてみればわたしも、映画を観ているときに佐久早くんがこんな顔をしていたとか、佐久早くんとこんな話をしたとか、そういうことは覚えている。一緒だ。そんなふうに思っていると「どんなくだらない映画でも面白く思える」と佐久早くんが言った。
佐久早くんが買ってきてくれたケーキ。普通に食べてもおいしかっただろうけど、佐久早くんがわたしのために買ってきてくれたのだと思うと余計においしく思えた。もしかして、それと似たようなことなのだろうか。それなら嬉しい、な。浮かれているのかもしれないけどこっそりそう思った。
映画は話の大元である目的に向かってみんなが協力しはじめたところだ。佐久早くんに手を握られたまま、じっと画面を観ている。かわいい、と口に出すとまた恥ずかしいことになるから黙っておく。一人で勝手に照れていると、佐久早くんが指でわたしの手を撫でたりつついたりしはじめる。意外とじっとしていられないタイプなのかもしれない。微笑ましく思えてしまった。
しばらくしてから、佐久早くんが突然わたしの顔を覗き込んできた。びっくりして「どうしたの」と聞くと、佐久早くんは「いや」と小さな声で呟く。それから言葉に迷いながら一旦視線を逸らした。それからまたわたしをまっすぐ見つめると、きゅっと手を握り直す。
「映画の邪魔してもいい?」
きょとんとしてしまう。映画の邪魔、とは。よく分からないまま「うん?」と答えておく。何か手伝うことがあれば、という意味だった、の、だけど。その瞬間に佐久早くんの顔が近付いてきて、あっという間に唇を奪われた。時間にすればほんの数秒のことだった。唇が離れてから、佐久早くんは悪戯が成功した子どもみたいな顔で笑った。繋いでいない右手でわたしの髪を軽く撫でてから、また背もたれに体を預けてしまう。何事もなかったように。何でもないことをしたように。
一瞬で映画の内容が飛んでしまった。知らんふりして映画を観ている佐久早くんの横顔を見つめたまま、何も言えずに固まってしまう。確かにれっきとした〝映画の邪魔〟だった。でも、邪魔というには些か、かわいらしい悪戯だったけれど。
悔しかった、から、佐久早くんの手をまた握り返して、名前を呼ぶ。楽しそうにこっちを見た佐久早くんが「何?」と首を傾げた。
「あの」
「うん」
「……も、もう一回、して」
たぶん顔が真っ赤だと思う。そう分かるくらいに暑いから。手汗もかいているだろうし、化粧も崩れているかもしれない。それでも、わたしの言葉に固まって、ちょっと驚いている佐久早くんの顔を見たら、笑ってしまった。悪戯が成功した。そんなふうに。
佐久早くんがそんな顔をしてくれたのは一瞬だけ。すぐに「ん」と優しく笑って、右手をわたしの頬に添える。すぐに形勢逆転。やっぱり悔しい。でも、その手の温かさが何より嬉しくて。そっと目を閉じる。もう顔は熱くない。緊張はしているし、まだまだ照れるけれど。でも、もう、不安になることはこれっぽっちもなくて。心地よい心臓の音を聴きながら、美しい時の流れを肌で感じる。そんな、愛しい時間だと思う自分がいた。
戻る
/
FIN.